ザンクトガレン2009から術後の薬物治療を読み解く 個人に最適な治療を見極める! 乳がんはより個別化の時代へ
過剰な治療になるのを防ぐ効果もある

多遺伝子発現解析としては、「オンコタイプDX」と「マンマプリント」という2種類の検査が普及している。ただ、日本では健康保険の対象とならないので、費用はかなり高額だ。オンコタイプDXが45万円、マンマプリントが38万円である。
オンコタイプDXはアメリカで開発された検査。21種類の遺伝子の発現を調べることで、再発のリスクを算定する。再発スコアが18未満を低リスク、18~30を中リスク、30を超える場合を高リスクとしている。
「臨床試験の結果、高リスク群に化学療法を加えると上乗せメリットが出るというデータや、低リスク群に化学療法を加えても上乗せメリットが少ないというデータが出ています」
マンマプリントはオランダで開発された検査法だ。70種類の遺伝子を調べ、その発現パターンによって、高リスクと低リスクに分けている。
「判定した後の生存率を調べた臨床試験が行われていますが、高リスク群は予後不良、低リスク群は予後良好と、きれいに分かれたとされています」
オンコタイプDXもマンマプリントも高額だという欠点はあるが、日本でも受けることは可能だ。検査を受けたい人は、主治医に相談するのがよいだろう。
「こうした多遺伝子発現解析を導入することで、無駄な治療を省くという効果も期待できます。たとえば、化学療法を加えるかどうかで迷った場合、決め手がないと、どうしても“加えておいたほうがいい”という結論になりがちです。こうして過剰治療気味になってしまうのですが、遺伝子を調べて再発リスクが低いとわかれば、無駄な化学療法をしなくてすみますからね」
必要な治療を見極める――。多遺伝子発現解析は、そのツールの1つと考えればいいようだ。
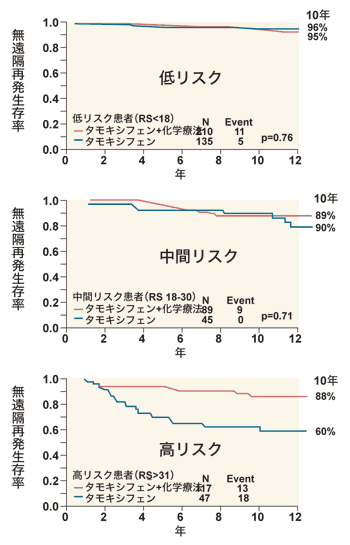
RS=再発スコア
閉経後のホルモン療法にはアロマターゼ阻害剤
ホルモン感受性陽性の場合、ホルモン療法が行われるわけだが、手術後のホルモン療法で使われているホルモン剤は、大きく2つに分類することができる。1つは抗エストロゲン薬、もう1つがアロマターゼ阻害剤だ。
ホルモン感受性陽性の乳がんは、エストロゲン(女性ホルモン)を利用して増殖する。そこで、がんがエストロゲンを利用できないようにすることで、がんを弱らせるのが抗エストロゲン薬である。タモキシフェン(商品名ノルバデックス等)という薬が広く使われている。
アロマターゼ阻害剤は、閉経後の患者さんを対象にした薬だ。閉経すると、卵巣からのエストロゲンの分泌はストップする。しかし、副腎から分泌されるアンドロゲン(男性ホルモン)を材料にして、アロマターゼという酵素の働きにより、エストロゲンを作り出しているのである。アロマターゼ阻害剤は、酵素の働きを抑えることで、エストロゲンが作られないようにする働きを持っている。
現在使用されているアロマターゼ阻害剤には、フェマーラ(一般名レトロゾール)、アリミデックス(一般名アナストロゾール)、アロマシン(一般名エキセメスタン)の3種類がある。 「手術後のホルモン療法は、先に承認されたタモキシフェンで始まったのですが、その後、閉経後の患者さんには、アロマターゼ阻害剤のほうが優れていることが臨床試験で明らかになってきました。現在ではアロマターゼ阻害剤での治療が標準治療になっています」
タモキシフェンとアロマターゼ阻害剤を比較する臨床試験はいろいろあるが、「BIG1-98」という臨床試験では、タモキシフェンとフェマーラの比較が行われている。1998年にスタートした試験で、試験開始から10年が経過した時点(観察期間中央値は76カ月)での解析が行われ、その結果が報告された。
下図に示したのがそれである。無病生存、全生存、遠隔再発までの期間について解析したものだが、いずれもフェマーラが優位という結果になっている。
「閉経後のホルモン療法には、アロマターゼ阻害剤が優れていることが明らかですが、閉経を迎える時期の患者さんをどうするかは難しい問題です。たとえば、50歳で生理がなくなっていたとしても、それが一時的なもので生理が再開したら、アロマターゼ阻害剤は効果がありません。本当に閉経後なのかという見きわめは、血液中の女性ホルモンを測るなど、慎重に行う必要があります」
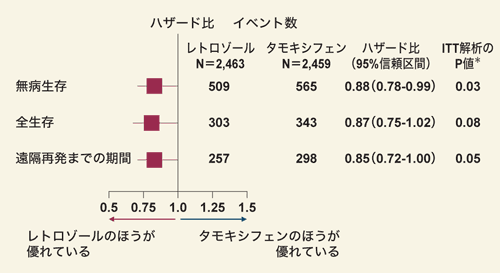
関節痛や骨の健康に注意する必要がある
手術後のホルモン療法は期間が長いのが特徴で、5年、あるいはそれ以上の期間、服用を続けることが必要になる。当然、副作用に注意しなければならない。
「アロマターゼ阻害剤の代表的な副作用は、骨粗鬆症などの骨の障害、それに関節痛です。うまく管理していかないと、大きな問題を引き起こすこともあります」
服用している間はエストロゲンが減るため、骨に影響が表れてくる。骨粗鬆症になると骨折が起きやすいが、骨折から寝たきりになってしまうこともあり、十分に注意しなければならない。
「定期的に骨塩量を測定して、骨の障害がどの程度現れているか確認する必要があります。程度が軽ければ、カルシウムとビタミンDを摂取することで対処できます。もう少し進んでいたら、早めにビスホスホネート製剤を飲むようにすべきですね」
ビスホスホネート製剤は、骨粗鬆症の治療に広く使われている薬である。
「関節痛はアロマターゼ阻害剤を飲む人の約4割に出るというデータもあります。がまんせず、主治医に話してNSAIDs(非ステロイド性抗炎症薬)などを処方してもらいましょう」
長い期間服用し続けることで効果が表れる治療なので、副作用に対しては積極的にケアしていくことが大切である。
(構成/柄川昭彦)
同じカテゴリーの最新記事
- 高濃度乳房の多い日本人女性には マンモグラフィとエコーの「公正」な乳がん検診を!
- がん情報を理解できるパートナーを見つけて最良の治療選択を! がん・薬剤情報を得るためのリテラシー
- 〝切らない乳がん治療〟がついに現実! 早期乳がんのラジオ波焼灼療法が来春、保険適用へ
- 新規薬剤の登場でこれまでのサブタイプ別治療が劇的変化! 乳がん薬物療法の最新基礎知識
- 心臓を避ける照射DIBH、体表を光でスキャンし正確に照射SGRT 乳がんの放射線治療の最新技術!
- 術前、術後治療も転移・再発治療も新薬の登場で激変中! 新薬が起こす乳がん治療のパラダイムシフト
- 主な改訂ポイントを押さえておこう! 「乳癌診療ガイドライン」4年ぶりの改訂
- ステージⅣ乳がん原発巣を手術したほうがいい人としないほうがいい人 日本の臨床試験「JCOG1017試験」に世界が注目!
- 乳がん手術の最新情報 乳房温存手術、乳房再建手術から予防的切除手術まで
- もっとガイドラインを上手に使いこなそう! 『患者さんのための乳がん診療ガイドライン』はより患者目線に


