不快な後遺症を生み出す、無駄なリンパ節の切除を回避できる センチネルリンパ節生検を上手く利用して、リンパ浮腫を防ごう
多くの患者さんが無駄なリンパ節郭清を回避した
日赤長崎原爆病院における乳がん手術症例のデータを見てみよう。5年半ほどの集計だが、乳がんの手術を受けた患者さんは590人。このうち、センチネルリンパ節生検を行わずに腋窩リンパ節郭清を受けた患者さんが、187人いたことになる。
「わきの下の触診でリンパ節が腫れているのがわかるとか、腫瘍が非常に大きいとか、明らかにリンパ節転移があると思われる患者さんには、センチネルリンパ節生検はやりません。それ以外は、だいたい実施する対象になりますね」
センチネルリンパ節生検を受けた患者さんは、590人中403人だった。その結果が陽性で、手術中に腋窩リンパ節郭清に移行したのは89人。陰性で、腋窩リンパ節郭清をしなくてすんだ人が314人だった。
見落としはないのかと気になるが、それはごくわずかだという。迅速病理検査で陰性だった314人のリンパ節を永久標本にして詳しく調べたところ、7例に微小転移が見つかっている。迅速診断は2ミリメートル幅のスライスで調べるのでその間にがん細胞があったケースだ。
「ごく小さな転移なので、改めて腋窩リンパ節郭清を行う必要はありません。ただし、その後の治療は転移が1個見つかった場合と同様にする、ということで学会のコンセンサス(合意)が得られています」
永久標本で調べたところ、3例で転移しているリンパ節が見つかった。センチネルリンパ節以外にがん細胞が行ってしまっていた例だ。
「この場合には、患者さんと相談して、腋窩リンパ節郭清を行うかどうか決めています」
例外的にこうしたことも起こるが、304人の患者さんは、リンパ節郭清を受けずにすみ、永久標本にしても転移は見つからなかった。少なくともこの人たちにとって、センチネルリンパ節生検は大きな価値があったことになる。
現在、センチネルリンパ節生検には健康保険が適用されていないため、どこでも受けられる状況���はない。ただ、先進医療に認定されているので、認定を受けている医療機関では、保険診療と組み合わせてこの検査だけ自由診療で受けることが可能だ。ちなみに日赤長崎原爆病院での費用は5万円。谷口さんによると、来年春ごろにはこのセンチネルリンパ節生検が保険適用になる見込みだという。
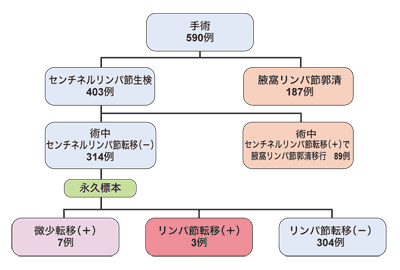
再発を防ぐためには適切な術後治療が必要
乳がんの手術後には、再発を防ぐための術後治療が行われる。手術で局所のがんを取り除くことができたとしても、画像検査で見つからないほど小さながんが、体のどこかに転移していることがあるからだ。センチネルリンパ節生検が陰性でも、その可能性は否定できない。がん細胞がすでに遠くの臓器に運ばれている可能性も考えなければならない。
術後に行われる薬物療法では、抗がん剤やホルモン剤が使用される。ここでは、ホルモン剤による術後治療について解説しよう。
ホルモン療法は、ホルモンレセプター陽性の乳がんに対して行われる。このような乳がんは、エストロゲン(女性ホルモン)を利用して増殖するので、エストロゲンを利用できないようにして、がんを弱らせるのである。
「術後のホルモン療法として広く使われてきたのは、抗エストロゲン薬のタモキシフェン(商品名ノルバデックス等)でした。手術後に5年間服用することで、再発を防ぎ、生存期間を延ばす効果が臨床試験で確認されています」
抗エストロゲン薬は、エストロゲンの分泌を抑える薬ではなく、エストロゲンが乳がんに作用するのを抑える薬だ。これに対し、近年、アロマターゼ阻害剤という薬が注目されている。閉経後の患者さんを対象にした薬で、タモキシフェン以上の効果があるのではと、さまざまな臨床試験が続けられてきた。
現在使われているアロマターゼ阻害剤には、フェマーラ(一般名レトロゾール)、アリミデックス(一般名アナストロゾール)、アロマシン(一般名エキセメスタン)の3種類がある。
レトロゾールの臨床試験で生存率が改善された
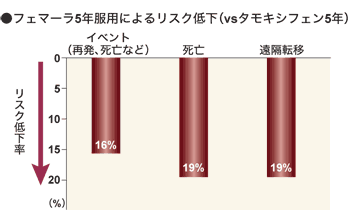
前述したように、閉経後の患者さんの術後ホルモン療法として、タモキシフェンとアロマターゼ阻害剤を比較する臨床試験が行われてきた。たとえば、「BIG1-98」という臨床試験では、タモキシフェンとフェマーラを比較しているが、1998年の試験開始から10年が経過した時点(追跡期間中央値は76カ月)での解析が行われ、興味深い結果が報告されている。
「タモキシフェンとフェマーラを術後治療に用いた比較試験で、タモキシフェンよりフェマーラが優れているというはっきりした結果が出ているのが驚きですね。再発を抑え、生存にも良い結果が出ています。これは患者さんにとって大きな意味を持つと思います」
この「BIG1-98」が、タモキシフェンとフェマーラの比較試験だという点も忘れてはいけないだろう。タモキシフェンによる術後治療は、優れた治療成績が評価されて標準治療として実施されてきた治療である。それに差をつけて上回るということは、そう簡単なことではない。
「これまではアリミデックスの長期データしかなかったのですが、フェマーラでも出たので、閉経後の術後治療には最初からアロマターゼ阻害剤を使うのが一般的になるでしょう。これから明らかにしてほしいのは、5年でいいのか、10年のほうがいいのかという治療期間の問題ですね」
タモキシフェンを5年飲んだ後、さらにアロマターゼ阻害剤を飲むことで、上乗せ効果があることはすでに明らかになっている。アロマターゼ阻害剤を5年飲んだ人が、その後も飲み続けることで、同じように上乗せ効果が期待できるのかどうか。この臨床試験は現在進行中だ。
「患者さんには、最低5年というお話をして、アロマターゼ阻害剤を服用してもらっています。5年後に臨床試験の結果が出ていれば、それに従ってその後の治療を決めましょうということです」
術後治療を継続して受けることが大切
アロマターゼ阻害剤の効果は明らかになりつつあるが、治療を長期継続するためには、注意しなければならない点もある。エストロゲンが減るため、骨粗鬆症が起きたり、また関節痛に悩まされる患者さんもいる。
「定期的に骨塩量を測定し、必要に応じて適切な治療を行う必要があります。関節痛は多くの場合、薬で抑えられますが、アロマターゼ阻害剤の種類を変えるのも1つの方法でしょう」
こうした工夫をすることで、とにかく術後治療を継続することが大切と谷口さんは強調する。
「いったん再発が起きてしまうと、根治はなかなか難しいのが現実です。つまり、再発は命に関わるイベントだということ。それを忘れずに、術後治療に取り組んでほしいと思います」
命を守るためにどうすればいいかは、臨床試験によって明らかになりつつある。これから出てくる結果にも期待したい。
(構成/柄川昭彦)
同じカテゴリーの最新記事
- 高濃度乳房の多い日本人女性には マンモグラフィとエコーの「公正」な乳がん検診を!
- がん情報を理解できるパートナーを見つけて最良の治療選択を! がん・薬剤情報を得るためのリテラシー
- 〝切らない乳がん治療〟がついに現実! 早期乳がんのラジオ波焼灼療法が来春、保険適用へ
- 新規薬剤の登場でこれまでのサブタイプ別治療が劇的変化! 乳がん薬物療法の最新基礎知識
- 心臓を避ける照射DIBH、体表を光でスキャンし正確に照射SGRT 乳がんの放射線治療の最新技術!
- 術前、術後治療も転移・再発治療も新薬の登場で激変中! 新薬が起こす乳がん治療のパラダイムシフト
- 主な改訂ポイントを押さえておこう! 「乳癌診療ガイドライン」4年ぶりの改訂
- ステージⅣ乳がん原発巣を手術したほうがいい人としないほうがいい人 日本の臨床試験「JCOG1017試験」に世界が注目!
- 乳がん手術の最新情報 乳房温存手術、乳房再建手術から予防的切除手術まで
- もっとガイドラインを上手に使いこなそう! 『患者さんのための乳がん診療ガイドライン』はより患者目線に


