ホルモン療法の最新動向 サンアントニオ乳がんシンポジウム2008より 個別化治療の実現へ着実に前進する乳がんのホルモン療法
タモキシフェンとアロマターゼ阻害剤とでは副作用が異なる
では、アロマターゼ阻害剤とタモキシフェンには、こうした効果の差以外に、どのような違いがあるのでしょうか。
女性ホルモンが結合することのできる部分であるホルモン受容体を持っている「ホルモン感受性」と呼ばれる乳がんは、エストロゲンが結合すると分裂や増殖が促進されることがわかっています。タモキシフェンは、自らがホルモン受容体に結合することによって、エストロゲンがホルモン受容体に結合するのを防ぐ薬剤です。
エストロゲンは、閉経前女性においてはおもに卵巣で作られますが、閉経後は脂肪組織などでアロマターゼという酵素の働きによって合成されます。そして、乳がんになると乳がんの組織でもアロマターゼが働いてエストロゲンが合成されていることがわかっています。このアロマターゼの働きを抑制して、エストロゲンの合成自体を抑える薬剤がアロマターゼ阻害剤です。働き方が違う薬剤ですから、副作用などにも違いが起こってきます。
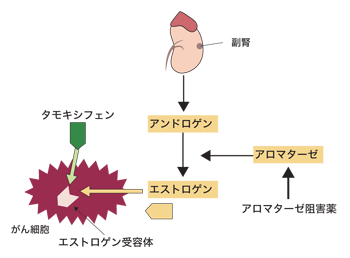
| タモキシフェン | アロマシン | |||
|---|---|---|---|---|
| 骨折 (椎骨・手根骨・大腿骨) | 26 | 0.5% | 28 | 0.6% |
| その他の部位の骨折 | 86 | 1.8% | 112 | 2.3% |
増田さんによればTEAM試験において、心血管系の副作用として、タモキシフェンを服用した患者さんでは血栓症やほてり、アロマシンを服用した患者さんでは高血圧が多く認められました。また従来から言われているとおり、婦人科系の副作用はタモキシフェンのほうが多く、筋骨格系の副作用はアロマシンのほうが多いという結果でした。これらの副作用の頻度や両群での違いは、これまでのアロマターゼ阻害剤やタモキシフェンで見られているものとほとんど変わらないものでした。ただし骨折率については、タモキシフェンとアロマシンで差がないことが示されました。
最初にアロマターゼ阻害剤を使い、その後タモキシフェンに替えることも可能
副作用の現れ方は、人によって異なります。またどのような副作用であれば我慢しやすいのかも、患者さんそれぞれです。「再発を効果的に防ぐためには、手術後のホルモン療法としてアロマターゼ阻害剤を使うことが重要であることがわかってきたわけですが、副作用などでどうしても服用を続けられない患者さんは、タモキシフェンに替えることも可能です。そのことは、今回やはり大きな注目を集めたBIG1-98という試験の結果で確認されました」(増田さん)。
BIG1-98試験ではすでに、手術後の初期治療としてフェマーラがタモキシフェンよりも優れていることが報告されています。今回新たに、フェマーラを5年間服用、タモキシフェンを2年間、その後にフェマーラを3年間服用、フェマーラを2年間、その後にタモキシフェンを3年間服用という3グループを比較した結果についても報告されました。無病生存期間(再発や転移なしに生存している期間)、生存期間、遠隔転移までの期間は、タモキシフェンからフェマーラに変更したグループより、フェマーラを続けて服用したグループのほうが長い傾向がありました。一方、フェマーラからタモキシフェンに変更したグループでは、フェマーラを継続的に服用していたグループと差がありませんでした。
したがって今後の術後のホルモン療法は、「初期治療はアロマターゼ阻害剤で開始し、副作用などの何らかの事情で続けることが難しい患者さんは、我慢してアロマターゼ阻害剤を継続するよりは、再発の危険性のピークが最も高い2~3年を乗り越えれば、その後、タモキシフェンに変更するという方法もベストな治療法の1つになるでしょう」(増田さん)。
(観察期間の中央値71カ月)
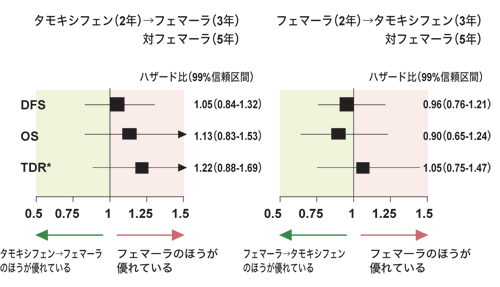
増える治療選択肢と個別化治療のための情報
今回、TEAM試験やメタ解析の結果から、閉経後女性の術後の初期治療ではアロマターゼ阻害剤が有用であることが確認されました。最近ではどのような患者さんにどのような薬剤が適しているのか、どのような患者さんで副作用が出やすいのかといった情報も、次々と明らかになってきています。「自分にはどんな治療がもっとも適しているのか、主治医とよく話し合い、体の状態に合わせて治療法を選ぶといいでしょう」(増田さん)。
たとえばTEAM試験では、アロマシンがリンパ節転移のある患者さんや化学療法を受けた患者さんなど、どのような患者さんであっても乳がん再発を抑制できることが示されました。また先ほども触れたように、アロマシンはほかのアロマターゼ阻害剤と比較して骨に優しい可能性もあります。一方、BIG 1-98試験では、フェマーラが再発リスクの高い患者さんでとくに効果が高いことがわかってきました。
今回のシンポジウムではほかに、タモキシフェンのほうがアリミデックスよりもQOL(生活の質)を高く保てるという報告や、遺伝的にタモキシフェンの効果が認められない患者さんがいるという報告などもありました。また「最近では、タモキシフェンによる治療を行った場合の再発リスクと、再発リスクを減少させるために、抗がん剤の追加効果がどの程度あるかを予測することのできるオンコタイプDXという遺伝子検査も開発されています。今回のシンポジウムでは、タモキシフェンではなくアロマターゼ阻害剤による治療を行った場合にも、この検査とその解釈を応用できるという報告がありました」(増田さん)。
ホルモン療法の継続期間や組み立て、耐性克服など課題も
ホルモン受容体と同じように、HER2(ヒト上皮細胞増殖因子受容体)と呼ばれるタンパク分子も、乳がんの進行に大きく関与していることがわかってきています。HER2遺伝子が活性化したり、それによってHER2タンパク質が過剰に産生されている、いわゆる「HER2陽性」の患者さんに対しては、HER2の働きを抑えるハーセプチン(一般名トラスツズマブ)が治療に取り入れられ、大きな効果を発揮しています。
ハーセプチンのように、そのがんの特徴となっている分子を狙った薬剤を分子標的治療薬といいます。日本ではまだ使うことができませんが、HER2だけでなく、別のタイプの増殖因子受容体(HER1/EGFR)の働きも同時に抑えることのできるラパチニブという分子標的治療薬も開発されています。今回のシンポジウムでは、世界の212の施設から閉経後ホルモン感受性転移性乳がん患者1286名が参加して、レトロゾールだけによる治療と、レトロゾールとラパチニブを併用する治療とを比較したEGF30008試験の結果も報告されました。ホルモン感受性でHER2陽性だった219人の患者さんでは、フェマーラとラパチニブを併用することによって、無増悪生存期間(病状が悪化することなく生存している期間)がフェマーラ単独群よりも、5カ月以上長くなることがわかりました。増田さんは、「このことは、ホルモン感受性でHER2陽性の転移性乳がんでは、その両者による増殖シグナルが働いていることが予想され、ラパチニブをアロマターゼ阻害剤に併用することにより、さらにその治療効果を改善することを示しています」と述べています。
このように、乳がん治療では、閉経の状態や遺伝子といった患者さんの特徴と、ホルモン感受性やHER2の状態といった乳がんの特徴を考慮して、1人ひとりの患者さんにもっとも適した治療(個別化治療)を行うべく、盛んに研究が進められています。またホルモン療法は、現在は術後5年間続けることが標準的となっていますが、さらに継続して10年間治療すべきとの議論もあります。同じ薬剤を継続的に服用していると効果がなくなってくる、いわゆる「耐性」も、克服していかねばなりません。その長い期間、治療をどのように組み立てていくべきかを、さらに明らかにしていくことが今後の課題の1つです。
同じカテゴリーの最新記事
- 高濃度乳房の多い日本人女性には マンモグラフィとエコーの「公正」な乳がん検診を!
- がん情報を理解できるパートナーを見つけて最良の治療選択を! がん・薬剤情報を得るためのリテラシー
- 〝切らない乳がん治療〟がついに現実! 早期乳がんのラジオ波焼灼療法が来春、保険適用へ
- 新規薬剤の登場でこれまでのサブタイプ別治療が劇的変化! 乳がん薬物療法の最新基礎知識
- 心臓を避ける照射DIBH、体表を光でスキャンし正確に照射SGRT 乳がんの放射線治療の最新技術!
- 術前、術後治療も転移・再発治療も新薬の登場で激変中! 新薬が起こす乳がん治療のパラダイムシフト
- 主な改訂ポイントを押さえておこう! 「乳癌診療ガイドライン」4年ぶりの改訂
- ステージⅣ乳がん原発巣を手術したほうがいい人としないほうがいい人 日本の臨床試験「JCOG1017試験」に世界が注目!
- 乳がん手術の最新情報 乳房温存手術、乳房再建手術から予防的切除手術まで
- もっとガイドラインを上手に使いこなそう! 『患者さんのための乳がん診療ガイドライン』はより患者目線に


