術後のホルモン療法はアロマターゼ阻害剤を、そしてより長期に 早期のうちに微小転移を抑える乳がんの術後治療
術後2年目に再発のピーク最初からアロマターゼ阻害剤を
閉経後の人で、タモキシフェンを途中でアロマターゼ阻害剤に変えたら治療成績はどうなるか、という臨床試験も行われている。
タモキシフェンを2~3年使ってからアロマシンに変えた場合と、タモキシフェンを継続した場合を比較しているのだ。その結果、アロマシンに切り替えたほうが、再発リスクは25パーセント減少した。アナストロゾールに切り替える臨床試験では、再発リスクが45パーセント減少することがわかっている。
「閉経後であれば、たとえ最初にタモキシフェンによる治療が行われていても、アロマターゼ阻害剤に変えたほうがいい、ということが明らかになったわけです」
厳密に言えば、最初からアロマターゼ阻害剤を使った場合と、初めにタモキシフェンを使ってアロマターゼ阻害剤に切り替えた場合を比較した臨床試験の結果は、まだ出ていないという。ただ、閉経後のホルモン療法としてはアロマターゼ阻害剤が推奨されているので、一般的には最初から使われているそうだ。
「乳がんの再発は術後2年目にピークがあって、早い段階で再発することがわかります。そこで、再発の危険性の高い時期に、より再発を抑える効果の高い薬を用いたほうがおそらく効果的だろうと推測できます」(図4)
この面から考えても、最初からアロマターゼ阻害剤を使ったほうがいいようだ。
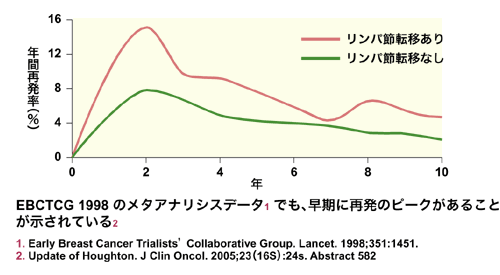
タモキシフェン5年投与終了後に再発がみられることもある
治療期間に関する臨床試験も行われている。従来はタモキシフェンの5年間投与が一般的だったが、治療後に再発するケースもあり、5年以降も何らかの治療が必要ではないかと考えられていた。そこで、タモキシフェン5年間の後で、フェマーラによる5年間のエクステンディド・アジュバント(継続術後治療)を行う大規模な臨床試験が行われた。その結果、タモキシフェン5年間だけの場合に比べ、再発のリスクが42パーセント減少した。
「タモキシフ��ン5年間だけでは、必ずしも十分でないことが明らかになりました。ただ、エクステンディド・アジュバントがすべての人に必要とは限りません。ザンクトガレンの推奨治療では、リンパ節転移のあった人には、積極的にエクステンディド・アジュバントを行ったほうがいいとされています」 実際、5年間のタモキシフェン治療の終了後、すぐに再発してくるケースが少なくないそうだ。次のような例があった。
50代の患者さんで、腫瘍径は2~5センチメートル、脇の下のリンパ節に転移があり、病期は2B期。ホルモン受容体は陽性。リンパ節転移があったので、まず化学療法が行われ、それからタモキシフェンによるホルモン療法が5年間続けられた。
閉経後の患者さんだったが、当時はアロマターゼ阻害剤がなかったため、タモキシフェンによる治療となった。終了した時点では、アロマターゼ阻害剤が使えるようになっていたが、その患者さんはエクステンディド・アジュバントを受けなかった。再発が発見されたのは、約半年後。腫瘍マーカーが上昇し、詳しく検査したところ、肝臓と骨への転移が見つかった。
「こういう例を見ると、ぜひ続けてほしかったと思います。患者さんにすれば、5年以降も治療を続けるのは大変ですが、タモキシフェン終了時点で閉経しているのであれば、アロマターゼ阻害剤によるエクステンディド・アジュバントが勧められます」
タモキシフェンを5年間終了してから、アロマターゼ阻害剤の治療を続けるのがエクステンディド・アジュバントだが、タモキシフェン終了後、無治療期間を経てアロマターゼ阻害剤の投与を開始する治療を、レイト・エクステンディド・アジュバントと呼んでいる。
フェマーラによるエクステンディッド・アジュバントの臨床試験では、その効果が明らかになったため、試験の途中で、プラセボ群(偽薬を服用した無治療群)の希望者にはフェマーラが投与されることになった。それにより、5年間のタモキシフェン治療後、無治療期間(平均2.8年)をおいてフェマーラを投与した群と、無治療のままの群の再発を比較することができた。その結果、間隔を空けても、フェマーラを投与された群のほうが再発が抑えられることが明らかになった。
「現在では、タモキシフェン終了時点で再発リスクの高い人にはアロマターゼ阻害剤によるエクステンディド・アジュバントを行っています。ただし、タモキシフェン終了時点では閉経前で、アロマターゼ阻害剤を使えなかったが、その後数年で閉経したというケースの場合は、無治療期間が数年あっても、レイト・エクステンディド・アジュバントが行われるようになるでしょう」
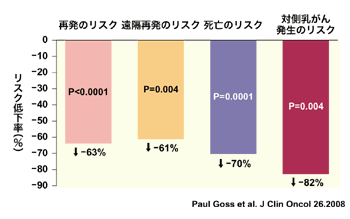
治療を開始する前に骨密度を測定する
アロマターゼ阻害剤の治療を行う場合、副作用で最も注意しなければならないのは骨の健康である。副作用として骨粗鬆症になったり、骨折のリスクが高まったりすることが明らかになっているからだ。
「ただし、治療開始時点で骨密度が正常であれば、骨粗鬆症になることはほとんどありません。もともと骨密度が低い人が危ないので、アロマターゼ阻害剤の治療を始める前に、骨密度を測定しておくことは大切です。骨密度が低い人に対しては、ビスホスホネート製剤を使ったり、ビタミン剤やカルシウムを投与したりして、有害事象を防ぎます」
副作用として関節痛や筋肉痛が起こることもある。これも患者にとっては辛いが、数カ月で消失することが多い。
「有害事象の問題はありますが、閉経後の術後治療はアロマターゼ阻害剤が中心になっていくでしょう。治療期間に関しては、現在も臨床試験が行われていますが、より長期になっていく可能性があると思います」
乳がんの術後ホルモン療法は、ここ数年で大きく変わってきた。臨床試験の結果が出そろうまでに、まだ数年かかりそうだという。
(構成/柄川昭彦)
同じカテゴリーの最新記事
- 高濃度乳房の多い日本人女性には マンモグラフィとエコーの「公正」な乳がん検診を!
- がん情報を理解できるパートナーを見つけて最良の治療選択を! がん・薬剤情報を得るためのリテラシー
- 〝切らない乳がん治療〟がついに現実! 早期乳がんのラジオ波焼灼療法が来春、保険適用へ
- 新規薬剤の登場でこれまでのサブタイプ別治療が劇的変化! 乳がん薬物療法の最新基礎知識
- 心臓を避ける照射DIBH、体表を光でスキャンし正確に照射SGRT 乳がんの放射線治療の最新技術!
- 術前、術後治療も転移・再発治療も新薬の登場で激変中! 新薬が起こす乳がん治療のパラダイムシフト
- 主な改訂ポイントを押さえておこう! 「乳癌診療ガイドライン」4年ぶりの改訂
- ステージⅣ乳がん原発巣を手術したほうがいい人としないほうがいい人 日本の臨床試験「JCOG1017試験」に世界が注目!
- 乳がん手術の最新情報 乳房温存手術、乳房再建手術から予防的切除手術まで
- もっとガイドラインを上手に使いこなそう! 『患者さんのための乳がん診療ガイドライン』はより患者目線に


