世界の乳がん治療の最新動向を追う 乳がんの治療は、1人ひとりの患者に合った個別化医療の時代に入った
重要な治療エデュケーションの組み立て
そうして化学療法の役割が縮小するなかでハーセプチンなどの分子標的薬と並んで、今まで以上に、今後の乳がん治療の中核となると見られるのがホルモン療法だ。
もっとも、ホルモン療法の場合も、化学療法ほどではないにせよ関節痛、骨量低下、さらにはうつ病の発症など、患者にとっては深刻な副作用がつきまとうのも事実だ。そうした副作用対策も含めて、これからのホルモン療法はどう変わっていくのだろうか。
その点について、中村さんは治療当初のエデュケーションが重要な意味を持つという。
「ホルモン療法は1度始めたら、たとえば5年なら5年と一定期間は使用を継続しなければなりません。それだけに副作用の問題もきちんと考えなければなりません。と、すれば最初にまず治療についてきちっとしたエデュケーションを行い、それを患者さんにしっかりと理解してもらう必要があるでしょうね。これはホルモン療法に限りませんが、これからは個々の患者さんに対する薬剤の効果を、使用前に把握して、治療をエデュケーションすることが重要になってくるでしょうね」
たとえばホルモン療法の副作用に関節痛や骨粗鬆症があるが、最近ではその原因の1つにエストロゲンの不足があることがわかっており、それらの副作用を抑えるには、ある程度はエストロゲンも必要であることがわかってきた。
もっとも最近では、同じホルモン剤でも治療効果の高さからタモキシフェンという抗エストロゲン剤から、エストロゲンをより強力に抑えるアロマターゼ阻害薬に薬剤を切り替える患者が急増している。そうした患者に関節炎などが起こった場合は、薬剤を元に戻すことも考えなければならないが、そこで患者に納得して治療の変更を受け入れてもらうには、あらかじめしっかりとしたエデュケーションを組み立てておく必要があるわけだ。
さらに、ホルモン療法に関していえば、これからは、術前治療という形で治療に導入される可能性も高いと中村さんはいう。
前にあげた遺伝子検査システムの導入に伴って、治療も化学療法からホルモン療法、ハーセプチンに重点が置き換わり、治療エデュケーションの内容も様変わりつつある。乳がん治療全体の改革に先駆けるように、治療現場では、治療エデュケーションの導入により個々の治療に対する見直しが行われ始めているわけだ。
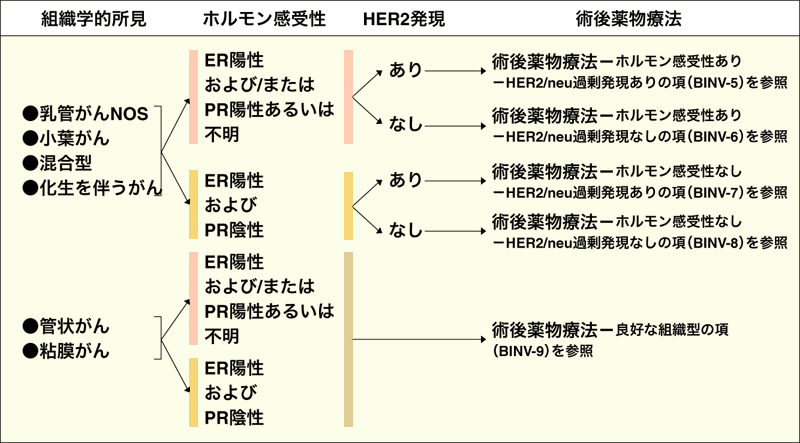
がんそのものを見直す幹細胞の研究
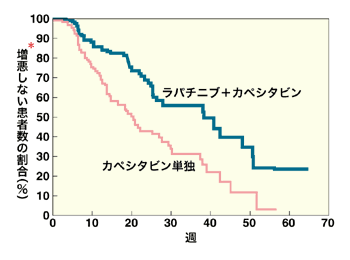
さて、ここまで見てきた治療面の知見とは別に、がんそのものの発生メカニズムを見直すことで、これからのがん治療の方向性を指し示す研究も最近になって活発に行われている。それはステムセル(幹細胞)についての研究だ。
私たちの体内では、骨髄にある造血幹細胞がその時々の体の状況に応じて、さまざまな白血球に分化を続けている。同じようにがん組織の中にも、幹細胞が存在し、さまざまながんとその周りを取り巻く細胞に分化しているのではないか、というのが基本的な考え方だ。では、乳がんの場合には、この幹細胞に関してどんな知見が報告されているのだろうか。
「乳がんの発達過程をみると、乳管内で発生したがん細胞だけでなく、その間にある間質細胞、さらにがん細胞に酸素や栄養を運ぶ新生血管の細胞も互いに連携しあって増殖しています。これまでは乳がんとは、がん化した乳管細胞のこととされてきましたが、そうした増殖過程を考えると、これらは一体の組織と見るべきではないかとする見方も出てきているのです。そう考えると、発がんとともに増殖している間質細胞や新生血管細胞は、ある特定の細胞が分化してつくられているとも考えられる。その元になる細胞が幹細胞と考えられているのです」
と、中村さんは解説する。
もっとも現段階では、幹細胞はまだ完全に特定されてはいない。昨年末に行われたサンアントニオ乳がんシンポジウムでも、CD44抗原に陽性反応を示し、CD24と呼ばれる抗原に陰性反応を示す細胞が幹細胞で、分子標的薬の1つであるタイケルブ(一般名ラパチニブ)にその作用が含まれていることが報告されている。けれども、まだこの報告も仮説の域を出ていないと中村さんは指摘する。
幹細胞を撃退する治療法の開発へ
とはいえ、幹細胞の存在が明らかになれば、従来の乳がん治療が一新される可能性も高い。
「幹細胞が分化してできた細胞を叩いても、元になる細胞を抑えなければがんは縮小しない。当然のこととして、幹細胞を撃退する治療が中核になっていくでしょう」
これまでの研究報告では、幹細胞はそれが分化してつくられた細胞に比べると、分裂が遅く、低酸素でも生き延びられる特徴を持っているため、それ以外のがん細胞とは異なる特性を持っており、撃退するには従来のがん治療とは異なる手法が求められる。
そこで現在、乳がん治療研究を行っている一部の研究者の間では、幹細胞の特定とともに、この細胞を抑えるための薬剤の研究が行われているという。これは見方によってはがんの本質に迫る研究ともいえるだろう。
世界の乳がん治療の最前線では、このように、従来の治療を一新するようないくつもの画期的な研究が行われている。これら最新の研究が少しでも早く、臨床の場に反映することを望みたい。
同じカテゴリーの最新記事
- 高濃度乳房の多い日本人女性には マンモグラフィとエコーの「公正」な乳がん検診を!
- がん情報を理解できるパートナーを見つけて最良の治療選択を! がん・薬剤情報を得るためのリテラシー
- 〝切らない乳がん治療〟がついに現実! 早期乳がんのラジオ波焼灼療法が来春、保険適用へ
- 新規薬剤の登場でこれまでのサブタイプ別治療が劇的変化! 乳がん薬物療法の最新基礎知識
- 心臓を避ける照射DIBH、体表を光でスキャンし正確に照射SGRT 乳がんの放射線治療の最新技術!
- 術前、術後治療も転移・再発治療も新薬の登場で激変中! 新薬が起こす乳がん治療のパラダイムシフト
- 主な改訂ポイントを押さえておこう! 「乳癌診療ガイドライン」4年ぶりの改訂
- ステージⅣ乳がん原発巣を手術したほうがいい人としないほうがいい人 日本の臨床試験「JCOG1017試験」に世界が注目!
- 乳がん手術の最新情報 乳房温存手術、乳房再建手術から予防的切除手術まで
- もっとガイドラインを上手に使いこなそう! 『患者さんのための乳がん診療ガイドライン』はより患者目線に


