旬の味覚をおいしく食べて、元気に過ごそう! 乳がん予防・治療中・治療後の「元気が出る」食事法
乳がんの予防には野菜や果物、大豆製品、魚類を
「乳がんの予防には、活性酸素を抑制する抗酸化物質の豊富な野菜や果物、エストロゲン抑制に働く可能性のある大豆製品などの食材を十分に摂れるメニューを工夫します」
抗酸化物質
がんは、細胞の中の遺伝子に傷がつき、細胞が突然変異を起こして増殖していく病気です。発がんに関わる原因の1つが体内で生じる活性酸素だといわれています。呼吸で取り入れた酸素の2~4パーセントが活性酸素になり、強い酸化力によって細胞膜や遺伝子を損傷するため、がんのほか、老化や動脈硬化、心筋梗塞などの原因にもなります。体内ではSOD(スーパー・オキシド・ディスムターゼ)という酵素が活性酸素を消去していますが、年齢とともにSODの働きが弱まり、活性酸素による弊害が増加します。遺伝子が何度も傷つき、細胞分裂を繰り返す過程でミスマッチが起こり、異型細胞ががん細胞になり(発がん=イニシエーション)、がん細胞の増殖(プロモーション、プログレッション)へと進むといわれています。
活性酸素の害を防ぐのが、ビタミンCやビタミンE、ベータカロテンなどのカロテノイド、ポリフェノール、フラボノイドなどの抗酸化物質です。これらの成分の豊富な野菜や果物等(モロヘイヤ、春菊、カボチャ、ニンジン、トマト、イチゴ、キウイ、バナナ、全粒粉、ゴマ、ナッツ類など)は、発がん予防に役立つと考えられます。
大豆イソフラボン
「発がんおよびがん細胞の増殖にエストロゲンが関係するのが乳がんの特徴ですから、エストロゲンを抑えることも有用です」
乳がんは母乳が作られる乳管の内側の上皮細胞から発生します。乳管の上皮はエストロゲンの刺激によって増殖したり、抑制されたりするため、エストロゲンががんの発生と増殖に大きく関わります。
日本の乳がんの約65パーセントは「エストロゲン依存性(ER陽性)」の乳がんで、エストロゲンの刺激によって、がん細胞の増殖が高まるタイプです。がんの芽ができていたとしても、エストロゲン刺激の少ない環境にしておけば、臨床的ながんとして発症することなく一生を過ごすこともできる、と福田さんは説明します。
これに関連して、乳がんを予防する可能性のある食品・成分として注目されているのが、豆腐、納豆、豆乳、味噌、湯葉などの大豆製品に含まれるイソフラボンです。大豆イソフラボンの乳がん予防効果は、「大豆製品を毎日食べている人は乳がん発生率が低い」(厚生労働省研究班のコホート研究。40~59歳の女性2万人を10年間追跡)、「味噌汁とイソフラボンの摂取量が多いほど���がん発症が少なく、これらの食品が乳がん発症を抑える可能性がある」(Yamamoto S,J Natl Cancer Inst 95:2003)など複数の研究によって示されています。
「乳がんの予防には大豆イソフラボンが有効である可能性がありますが、治療中は、イソフラボンの大量摂取には注意が必要です。大豆イソフラボンは、体内のエストロゲンと似た作用をもつ植物エストロゲンで、抗エストロゲン作用とエストロゲン作用の二面性があり、どちらの作用をもつかは体内のエストロゲン量に関連すると考えられています。体内のエストロゲンが多い状態ではイソフラボンが拮抗して抗エストロゲン作用をもたらし、乳がん予防的に作用します。一方、乳がんの治療でホルモン療法や抗がん剤治療などを行っている場合、体内のエストロゲンが非常に少なくなると、逆にイソフラボンがエストロゲン様作用を発揮し、乳がんを促進させる可能性があります」
乳がん治療中のイソフラボンの働きは、動物実験等の実験結果に基づく仮説であり、ヒトで証明されているわけではありませんが、体内のホルモン環境や治療の状況によって、マイナスに作用することもあるので、注意が必要です。
脂肪
愛知県がんセンター研究所が1988年~90年に行った研究(調査対象は40~79歳の女性2万6291人)によると、総脂肪摂取量は乳がんリスクに無関係でしたが、魚を多く食べる人は乳がんにかかるリスクが4割以上低く、魚油に含まれるDHA(ドコサヘキサエン酸)やEPA(エイコサペンタエン酸)等のオメガ3系多価不飽和脂肪酸が乳がん予防に関与しているのではないかと考察されています。
一方、乳がん治療を受けた女性を対象に最近海外で行われた比較試験の結果、低脂肪食の食事指導をしたグループは、最低限の食事指導をしたグループに比べて再発リスクが約2割減少したと報告されています(注6)。
「これらの研究と、閉経後の肥満は乳がんリスクを高めることなどを考え合わせ、乳がん予防、治療中・治療後は、肥満につながる脂肪過多、肉類中心の食事は避け、オメガ3系の不飽和脂肪酸を多く含むサケ、マス、イワシなどの魚メニューを増やすことがよく、調理にはオレイン酸の豊富なオリーブ油、シソ油などを使い、オメガ3系多価不飽和脂肪酸の多いくるみや亜麻仁油も利用しましょう」
注6:Chlebowski RT,J Natl Cancer Inst 2006 およびCA Cancer J Clin2006米国対がん協会のガイドより
食物繊維
食物繊維は、腸内でのエストロゲンの再吸収を抑えて排泄させる可能性があり、乳がん予防につながる可能性が示唆されています(図4)。食物繊維を含む根菜類や寒天などもメニューに加えるとよいでしょう。乳がん治療中にも、食物繊維は有用だといえます。
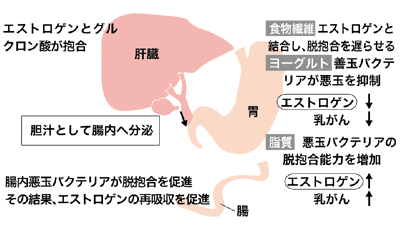
治療中は大豆イソフラボンの大量摂取に注意
- 毎日5皿以上の野菜・2皿以上の果物を
- 肉より魚類、特に青魚を十分に
- 大豆イソフラボンは適量を
- 食物繊維を多く食べる
- アルコールは控える
- 脂肪は摂取カロリーの2割以下に
- 低脂肪の乳製品を
- 閉経後の肥満に注意する
乳がんのホルモン治療、抗がん剤治療でエストロゲンレベルが低い場合や、エストロゲン陽性の方は、前述のようにイソフラボンのサプリメントや大豆製品の大量摂取は避けるのが賢明です。ただ、豆腐や納豆を通常の食事の範囲で食べる程度なら問題ありません。
また、抗がん剤の中には、酸化障害によってがん細胞を攻撃するタイプがあるので、治療効果を弱める可能性がある抗酸化ビタミンの大量摂取も控えたほうがよいというのが多くの専門医の見解です。「逆の意見もありますが、少なくとも抗がん剤治療開始後、血中濃度の高い1、2日目から1週間ほどは、ビタミンCのサプリメントを大量に摂るようなことは避けるほうがよいでしょう」
抗がん剤治療の副作用で吐き気がある場合、温かい食物のにおいが吐き気を誘発しやすいので、冬でも冷たいものを試してみます。また、口内炎で口の中が荒れ、飲み込みにくいときは、ゼリーやとろみのあるスープなら食べやすくなります。
一方、ホルモン療法中には、副作用としてホットフラッシュ(のぼせ)や発汗、イライラ、肥満など、更年期と同様のエストロゲン欠落症状が現れることが多く、高脂血症、骨粗鬆症などのリスクも高くなります。
「HRTや大豆イソフラボンのサプリメントはエストロゲンの欠落症状に有効ですが、乳がんに対しては悪影響がありますので、ホルモン療法中は使用を避けましょう。のぼせや発汗には桂枝茯苓丸、加味逍遥散、冷えには当帰芍薬散、イライラには自律神経調整薬、適度の運動などで対処します」
高脂血症の場合は、コレステロールの多い食品、脂肪、甘味、揚げ物、アルコールなどを控えて、摂取カロリーを抑え、余分な脂質を吸着・排出する水溶性食物繊維(海藻や果物に含まれる)の摂取を増やしましょう。2日に1回、30分以上の運動も効果的です。薬剤が必要な場合は、スタチン製剤などを処方してもらいます。
閉経後乳がん等に使われるホルモン治療薬のアロマターゼ阻害剤による骨粗鬆症には、カルシウムやビタミンDの多い食事を増やし、カルシウム阻害因子となる飲酒・喫煙・カフェインの過剰摂取は避け、適度な運動をするのがおすすめです。経口のビスフォスフォネート製剤も有効です。
「ホルモン療法や抗がん剤治療が終了した場合、新たな乳がんの発生を防ぐためには、予防の項と同様に考えます。ただ、エストロゲン受容体陽性の場合は、治療でいったん減弱していたがんの増殖を防ぐために、イソフラボンのサプリメントや大豆製品の大量摂取には引き続き注意しましょう。再発した場合は、治療中の項と同様に考えます。乳がん患者さんに役立つ食事・栄養の摂り方をまとめた8カ条と、僕も家庭で作ってみておいしかったレシピを参考に、楽しく食べて元気に過ごしていただきたいですね」
同じカテゴリーの最新記事
- 高濃度乳房の多い日本人女性には マンモグラフィとエコーの「公正」な乳がん検診を!
- がん情報を理解できるパートナーを見つけて最良の治療選択を! がん・薬剤情報を得るためのリテラシー
- 〝切らない乳がん治療〟がついに現実! 早期乳がんのラジオ波焼灼療法が来春、保険適用へ
- 新規薬剤の登場でこれまでのサブタイプ別治療が劇的変化! 乳がん薬物療法の最新基礎知識
- 心臓を避ける照射DIBH、体表を光でスキャンし正確に照射SGRT 乳がんの放射線治療の最新技術!
- 術前、術後治療も転移・再発治療も新薬の登場で激変中! 新薬が起こす乳がん治療のパラダイムシフト
- 主な改訂ポイントを押さえておこう! 「乳癌診療ガイドライン」4年ぶりの改訂
- ステージⅣ乳がん原発巣を手術したほうがいい人としないほうがいい人 日本の臨床試験「JCOG1017試験」に世界が注目!
- 乳がん手術の最新情報 乳房温存手術、乳房再建手術から予防的切除手術まで
- もっとガイドラインを上手に使いこなそう! 『患者さんのための乳がん診療ガイドライン』はより患者目線に


