渡辺亨チームが医療サポートする:若年性乳がん編
再発リスクの高い若年性乳がんは、長期の術後ホルモン治療が不可欠
| 倉田美樹さんの経過 | |
| 2005年 3月20日 | 左乳房、乳首の外側に小さなしこり |
| 9月20日 | 乳腺外科で乳がんの疑い |
| 10月3日 | F大学病院を受診 |
| 10月10日 | 大学病院を受診、乳がんの確定診断 |
| 10月27日 | 手術のために入院 |
| 11月7日 | 退院し、通院での放射線治療を開始 |
乳がんの疑いを告知された倉田美樹さん(32)は、大学病院を受診する。
乳房温存術が可能と聞き一安心するが、長期のホルモン治療により出産を諦めなければならないと知り、また治療へのためらいを覚える。
しかし、若年性乳がんは再発リスクが非常に高いことを考え、命を守るための選択へと踏み切った。
(ここに登場する人物は、実在ではなく仮想の人物です)
若い患者に強く出る否定的感情
乳がんの疑いが強いことから、一時は治療から逃げ出したい気持ちになっていた倉田美樹さん(32)は、友人の看護師からのサポートもあり、がんと向き合う気持ちになった(*1告知後の心理的サポート)。F大学病院の乳腺科を訪れた。
診察室に入ると、医長の松本医師は、自己紹介もそこそこに、ディスプレイに検査画像を示しながら話し始める。
「上島先生から画像が届きました。石灰化を見るカテゴリー分類(*2)では4に分類されるもので、悪性の疑いが強いです」
「がんではない可能性は?」 美樹さんは冷静に話す。 「確かに乳がんは、良性の疾患かどうか鑑別する必要があります(*3乳がんとの鑑別)。穿刺吸引細胞診を行い、本当にがんかどうか確かめます」と言って医師はピストルのような形をした注射器を示し、「よろしいですか?」とうながす。
美樹さんは看護師の手助けを受けながらブラウスの前を開き診察台に横たわった。
1週間後の10月10日、美樹さんは再び松本医長の前に座っていた。
「病理診断のレポートで、この部分にがん細胞が検出されたことが書かれています。細胞診の専門家の診断で、がんです。腫瘤の大きさはまだ2センチに達していないので、1期の乳がんと考えられます」
乳房温存術可能で、ひと安心
「先生、1期ならおっぱいは切らなくて済みますか?」
乳房温存術のことだ(*4乳房温存術の選択)。松本医長から話を聞いて、美樹さんは少しほっとする。
「確かに腫瘍の大きさやわきの下のリンパ節への転移もなさそうですから、温存術は可能です。ただ、乳房は切る必要はあります。部分切除といって、しこりの部分は取ります」
「ええ、知っています。放射線もするんですね」
「そうですね。薬物治療も行います。若い女性は術後の補助療法をしないと、再発リスクが高くなりますからね(*5腋窩リンパ節のない乳がんの予後因子)」
美樹さんがこの日不安だったのは、もっぱら医師から乳房全摘といわれるかどうかであった。美樹さんが高校3年生のとき、母が乳がんのため乳房を全摘した。以来、明るくて社交的だった母の性格が、すっかり暗くて閉じこもりがちになった。もし乳房を失っていなければ、現在60歳を超えた母はもっと若々しく行動的だったのではないかと思う。だから、「舞のためにも、おっぱいを守ることができてよかった」と、うれしささえ覚えていた。
「2週後の10月17日にベッドが空く予定でので、入院していただけますか?」
と松本医長が聞くと、美樹さんはすぐに「わかりました」と返事をした。
赤ちゃんを選ぶか、命を選ぶか
6月27日の午後2時、美樹さんは夫が運転する車に乗って大学病院に入院した。
病室に入って、車に積んできた着替えや洗面道具などを収納ボックスに整理していると、スピーカーから「倉田美樹さん、面談室へお越しください」と声がする。松本医師から手術の説明を受けることになっており、達也さんを伴って面談室に向かうと、松本医師のほか、麻酔医、放射線医、研修医や看護師が待っている。すぐに治療スケジュールを印刷したクリニカルパスと呼ばれる資料が手渡された。
「明日、午前中に乳房温存の手術を行います」
と松本医師は言いながら、ホワイトボードに「(1)手術(6月28日)」と書く。「そして、来週からは放射線治療です」
「5日間続け、7月10日に退院していただく予定です。その後の4週間は月曜日から金曜日まで通院していただきながら、放射線治療を受けてください」
美樹さんは、「1カ月間のがんとの戦いだな」と思った。
「そのあとで、薬物治療を始めます。倉田さんの状況ではリンパ節転移がないといっても、再発のリスクが25~30パーセントほどありますから。ホルモン感受性陽性なので、最低5年間、場合によっては閉経までホルモン治療を続ける必要があります(*6乳がんの術後ホルモン治療)。ホルモン受容体の働きを抑えるノルバデックス(一般名タモキシフェン)という薬と、エストロゲンの生産そのものを抑えるゾラデックス(一般名酢酸ゴセレリン)(*7)という薬を併用します」
すぐに美樹さんの表情がこわばった。
「えっ、5年間も……」
乳房温存療法についてはいろいろ勉強したつもりだったが、術後のホルモン治療については十分理解していなかったのだ。
「あの~、5年間もホルモン治療を続けると、その間は赤ちゃんを作ることはできないということになるのでしょうか?」
今度は医師のほうが困った顔をしながら答えた。
「うーん。それは無理ですね。倉田さんのような若い患者さんは、ホルモン治療をしっかり続けることがとても大切なのです。5年経ってホルモン治療を止めることができたとしても、赤ちゃんはまず難しいでしょうねえ。ある意味で命を選ぶか、赤ちゃんを選ぶかの問題ですから」
「私、治療を受けるの、いや。舞にはどうしても弟か妹が欲しいわ。もう家へ帰る」
突然叫び出した美樹さんの動揺に達也さんは驚く。
「何を言っているんだ。今はがんを治すことがいちばん大事なんだ」
医師は困り果てたような顔になっている。そのとき、同席した看護師が言った。
「私がこのあと倉田さんとお話しします。先生たちは、次の患者さんが待っていますから」
この言葉で医師たちは席を立った。看護師は達也さんにも席を離れるよううながす。2人だけになると、看護師はこう名乗った。
「私は乳がんの患者さんを専門にケアする認定看護師の浅川といいます(*8乳がん看護認定看護師)。初めてがんになるとわからないことだらけでお困りですよね。何でも聞いてくださいね」
美樹さんは、浅川看護師がとても話しやすそうな人に思えた。夫には何でも話しているつもりだったが、やはり自分とあまり年齢の変わらない同性に胸の内を聞いてもらいたいところがあった。しかも、相手は乳がんの専門知識を持っているという。
「ホルモン治療はそんなに効くものなの?」
美樹さんは少し冷静になってきた。
「先生は再発リスクが25~30パーセントとおっしゃっていましたが、ホルモン治療をしっかりやればそのリスクはだいたい半分になります」
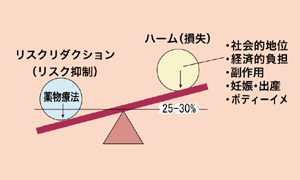
そう言って、浅川看護師は紙にシーソーのような絵を書き始める。
「若い方の乳がんは失うものが大きいですね。シーソーのこちら側をハーム(損失)としましょう。赤ちゃんもあきらめなければならないし、お金もたくさんかかるし、副作用もあります。ボディイメージが大きく損なわれる場合もあるでしょう。シーソーのもう一方の側はリスクリダクション(リスク抑制)です。これはホルモン治療ですね。多くのものを犠牲にしてようやく再発リスクを下げることができるというわけです」(図3)
浅川看護師は、少しずつ美樹さんにホルモン治療の大切さを説明していった。達也さんが1人で待つ病室に戻ったのは2時間近くあとのことだった。美樹さんは達也さんに微小んでこう言った。
「私はあなたと舞のそばにずっといたいわ。そのためには松本先生の言うとおり、ちゃんと治療を受けたほうがいいことがわかったわ」
同じカテゴリーの最新記事
- 高濃度乳房の多い日本人女性には マンモグラフィとエコーの「公正」な乳がん検診を!
- がん情報を理解できるパートナーを見つけて最良の治療選択を! がん・薬剤情報を得るためのリテラシー
- 〝切らない乳がん治療〟がついに現実! 早期乳がんのラジオ波焼灼療法が来春、保険適用へ
- 新規薬剤の登場でこれまでのサブタイプ別治療が劇的変化! 乳がん薬物療法の最新基礎知識
- 心臓を避ける照射DIBH、体表を光でスキャンし正確に照射SGRT 乳がんの放射線治療の最新技術!
- 術前、術後治療も転移・再発治療も新薬の登場で激変中! 新薬が起こす乳がん治療のパラダイムシフト
- 主な改訂ポイントを押さえておこう! 「乳癌診療ガイドライン」4年ぶりの改訂
- ステージⅣ乳がん原発巣を手術したほうがいい人としないほうがいい人 日本の臨床試験「JCOG1017試験」に世界が注目!
- 乳がん手術の最新情報 乳房温存手術、乳房再建手術から予防的切除手術まで
- もっとガイドラインを上手に使いこなそう! 『患者さんのための乳がん診療ガイドライン』はより患者目線に


