渡辺亨チームが医療サポートする:若年性乳がん編
看護師の精神的サポートにより、前向きな気持ちで闘病に取り組む
渡辺亨さんのお話
*1 乳房のしこり
乳房に現れるしこりには、乳繊維腫などによる良性のものと悪性のものとがあります。乳がんの初発症状の8割以上はしこりで、このしこりは良性のものと比べると、一般に硬くて境界がはっきりせず、指で押しても移動しないのが特徴です。患者さんの9割は自分でこのしこりを見つけます。しこりが大きくなるほど治癒率は低下しますから、早いうちに発見したいものです。月に1度、たとえば生理が終わったころなどに、自分で胸をさわってみる習慣をつけましょう。
*2 日本人の乳がん
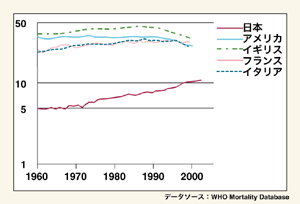
乳がんはもともと欧米には多いけれど、日本人など東洋人には少ないがんでした。かつて日本では欧米の7分の1くらいの発症率しかなく、「なぜ日本人には乳がんが少ないのか」ということが注目されていたほどだったのです。
ところがここ20~30年の間に日本でも乳がんが急増し、1年間におよそ3万5000人の女性が乳がんと診断されるようになりました。乳がんで死亡する女性は1年間に約1万人で、40~50歳代の女性におけるがん死亡の4分の1を占めており、この年代の女性にとって最も多いがん死亡原因となっています(図1)。
現在、アメリカでは乳がんの発生率は女性の8人に1人ですが、日本は20人に1人とアメリカの3分の1以上の頻度になっているのです(図2)。日本人の乳がん発生のピークは閉経前の40歳代後半ですが、欧米では閉経後の60歳以上にピークがあります。また、20歳代の発生例も稀ではありません。
| 年齢層 | 0~39歳 | 40~59歳 | 60~79歳 | 生涯(0~89歳) |
|---|---|---|---|---|
| 日本人女性の罹患リスク | 301人に1人 | 49人に1人 | 54人に1人 | 20人に1人 |
| 米国人女性の罹患リスク | 235人に1人 | 25人に1人 | 15人に1人 | 8人に1人 |
| 相対リスク(米国/日本) | 0.78 | 0.51 | 0.28 | 0.40 |
*3 家族性乳がん
遺伝による乳がんを家族性乳がんといい、乳がん全体の5~10パーセントくらいを占めるだろうといわれています。がんは遺伝子の変異によって起こる病気です。家族性乳がんの原因になるものとして、BRCA1、BRCA2という2つの遺伝子が見つけられました。アメリカで家族性乳がんと思われる人を調べたところ、BRCA1陽性の人が52パーセント、BRCA2陽性の��が32パーセント、残りの16パーセントの人は原因遺伝子が何かはわかりませんでした。BRCA1、BRCA2を持っている人全員が発症するわけではありませんが、これらの遺伝子を持つことによって乳がんになりやすいといえます(図3)。
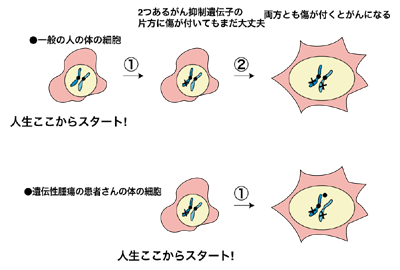
家族性乳がんの特徴は若くして発症することです。日本人の場合、欧米の家族性乳がんに比べれば発症年齢が遅いといわれますが、詳しいことはまだわかっていません。さらに家族性乳がんの特徴として、片側の乳房に発症すると、もう片側にも発症する可能性が高いもいわれています。
阿部恭子さんのお話
*4 若年性の乳がん検診
若い女性の乳がんを発見する機会として、以前は市町村の集団検診で30歳から視診触診が行われていましたが、ここ1、2年で集団検診から外れてしまいました。現在20~30代の女性の乳がんの検査は、自費で受けることになります。
乳がんが見つかるケースの1つは、もともと乳腺症などのため乳房が痛いとかしこりがあり、定期的に受診しているような場合です。また、メディアからの情報や、同じ職場に乳がんを発症する人がいるなどで、気になって受診したり、妊娠した女性への乳腺の検査で見つかる場合もあります。しかし、一般には、若い女性の乳がんはなかなか見つかりにくく、確定診断まで時間がかかることも少なくありません。
乳がんは他のがんに比べて身体の表面近くにできるため、自己検診を心がけることで、早期発見しやすくなります。毎月生理が終わった4~5日後に、鏡の前で乳房の形をチェックしたり、指でしこりがないかどうかを調べることを習慣にしてください。
*5 若年女性の乳がん
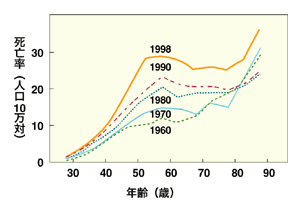
乳がんになる女性は年々増加していますが、20~30代の若い患者さんの割合が増えているというわけではなく、患者さんの中心は更年期前後から上です。ただ、それだけに乳がんに関する情報は、そうした年齢の患者さんを対象にしたものが大半です。若い乳がんの患者さんには、若さゆえの特有の悩みがいろいろあるのに、それに応えられる情報があまりありません。たとえまわりに乳がんの患者さんはいても、同じような世代の人であることはあまりなく、情報や悩みを交換できずに孤立してしまいがちになるのです。
若い人たちはインターネットなどで、自分でたくさん情報を集める能力はあります。ところが、集めた情報をどう判断するか、どう取捨選択するかで混乱に陥りやすい点も特徴です。
日本のがん医療の弱点の1つとして、患者さんへの精神的なサポートをする環境が整っていないことも挙げられます。とくに若年性乳がんの患者さんには、こうした日本のがん医療の弱点が集約して現れがちです(図4)。
*6 マンモグラフィと超音波診断
マンモグラフィは乳房を上下、左右にはさんで、X線を照射する画像診断装置で、腫瘍の有無や、広がり具合、どんな性質の腫瘍かといったことがわかります。触診ではわからない、非常に早期の乳がんも画像にとらえることができます。
また、乳房が大きくて超音波(エコー)検査が難しい人や、閉経後で乳腺が萎縮している人の乳がんの早期発見などにも有効です。
欧米ではマンモグラフィを使った乳がん検診は、乳がん死亡率を減らすことが証明されました。そしてアメリカやイギリスでは40~50歳代の女性の70パーセント以上が2~3年に1回はマンモグラフィ検査を受診しています。
これに対して日本では、マンモグラフィ検診の普及が遅れていて、受診率はわずか数~10数パーセントにすぎない状態です。国内にはまだマンモグラフィ検査が乳がん死を減らすという科学的データはありません。
また、マンモグラフィは年齢によっては、がんを見つけにくい場合もあります。千葉県民保健予防財団総合健診センター乳腺科部長の橋本秀行さんによれば、「40歳代以下の若い女性の乳房には乳汁を作る乳腺組織が多く、この組織もがんと同じようにX線をさえぎるため、画像の上では白く映ってがんと見分けがつけにくくなる。一方、閉経後には女性ホルモンが減るため乳腺組織の密度は薄くなってマンモグラフィでがんの診断がしやすくなる」とのことです。
超音波検査は、乳腺の密度に影響されず、また放射線被曝がありません。この検査もマンモグラフィと同様に乳がんの早期診断に用いられます。橋本さんによれば、「超音波検査は、妊娠中の女性や、乳腺密度の高い閉経前のとくに40歳代以下の若い女性、頻繁に検査する必要のある女性、またマンモグラフィで乳房をはさむ検査が『痛くていやだ』という人などに向いている」そうです。
超音波を使った乳がん検診も行われていますが、乳がん死を減らす有効性までは証明されていません。
同じカテゴリーの最新記事
- 高濃度乳房の多い日本人女性には マンモグラフィとエコーの「公正」な乳がん検診を!
- がん情報を理解できるパートナーを見つけて最良の治療選択を! がん・薬剤情報を得るためのリテラシー
- 〝切らない乳がん治療〟がついに現実! 早期乳がんのラジオ波焼灼療法が来春、保険適用へ
- 新規薬剤の登場でこれまでのサブタイプ別治療が劇的変化! 乳がん薬物療法の最新基礎知識
- 心臓を避ける照射DIBH、体表を光でスキャンし正確に照射SGRT 乳がんの放射線治療の最新技術!
- 術前、術後治療も転移・再発治療も新薬の登場で激変中! 新薬が起こす乳がん治療のパラダイムシフト
- 主な改訂ポイントを押さえておこう! 「乳癌診療ガイドライン」4年ぶりの改訂
- ステージⅣ乳がん原発巣を手術したほうがいい人としないほうがいい人 日本の臨床試験「JCOG1017試験」に世界が注目!
- 乳がん手術の最新情報 乳房温存手術、乳房再建手術から予防的切除手術まで
- もっとガイドラインを上手に使いこなそう! 『患者さんのための乳がん診療ガイドライン』はより患者目線に


