渡辺亨チームが医療サポートする:若年性乳がん編
再発リスクの高い若年性乳がんは、長期の術後ホルモン治療が不可欠
阿部恭子さんのお話
*1 告知後の心理的サポート
若い患者さんに限ったことではありませんが、初めてがん告知を受けた患者さんのなかには、著しく落ち込んだり、混乱してしまい、時には治療の一切を拒むという反応を引き起こす人さえいます。とくに若い患者さんは、同年代のがん患者さんが少なく「どうして私が?」と否定する気持ちが強いため、そうした反応を起こしがちです。
アメリカで、乳がん患者さんの「つらさ」に注目した研究が行れました。「つらさ」に影響する事柄として、年齢が若い、経済的に問題がある、うつや適応障害の既往歴がある、周囲のサポートが不十分、感情を抑えやすい傾向などが指摘されています。
治療を受ける病院が決まっている患者さんで、その病院のなかにサイコオンコロジー(精神腫瘍学)の専門医やリエゾンナース(精神的なケアを専門に行う看護師)、臨床心理士などの精神医学的サポートの専門家がいる場合には、つらさや不安に対するサポートを受ける機会もあります。しかし、治療する病院が決まっていない患者さんや、その病院に精神医学の専門家がいない場合には専門的なサポートが受けられません。現在のがん医療では、精神医学的な側面への支援体制は十分に整えられていない問題があります。
イギリスでは、35年前に、乳がん患者さんに精神的な症状が多いことが社会問題となり、乳がん患者への専門的な看護と心理的支援を行う「ブレストケアナース」の教育と資格認定が導入され、現在400名のブレストケアナースが活躍しています。さらに、外来診療においては、告知直後の患者さんへの乳がん体験者による心理的サポートもシステム化されています。
日本でも外来での相談に応じる施設が増えてきています。また、乳がん患者さんの不安や悩みに対し、乳がん体験者がボランティアで相談に応じる施設もあります。がん患者さんの不安な気持ちに注目したホームページもできています。がん患者さんのQOL(生活の質)が重要視されてきていますが、今後さらにがん告知後の心理的サポートの充実が切望されています。
渡辺亨さんのお話
*2 カテゴリー分類
乳腺のなかにカルシウムの固まりができることを石灰化といいますが、石灰化には良性のものから乳がんによるものまで、様々なものがあります。マンモグラフィでとらえられる石灰化の様子で、5段階にカテゴリー分類します。1~2は良性、3は良性だが悪性を否定できない、4は悪性の疑い、5は悪性と考えられる病変です(図1)。
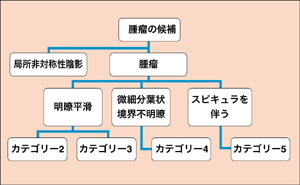
*3 乳がんとの鑑別
女性ホルモンなどの影響で、乳腺組織が腫れたり、しこりやのう胞ができたりする乳腺の変化を乳腺症と言い、線維のう胞性変化ともいいます。乳房の痛みを伴うこともありますが、通常治療の必要はありません。乳腺症からがんへの移行もないと考えられていますが、乳腺症のためにがんが見つけにくい場合があります。定期的に超音波検査、マンモグラフィ検査を受けるようにしてください。
*4 乳房温存術の選択
乳がんの治療として、かつて手術はがん細胞を1度にまとめて取り除くことができるので、最も成功率の高い方法と考えられていました。しかし、最近は抗がん剤治療やホルモン治療、放射線治療が進歩したことから、患者さんの病態に応じて、これらの治療法を組み合わせてそれぞれの特長をうまく生かす治療を行うことが普通になってきています。どれをどう組み合わせるかは、しこりの大きさや拡がり、悪性度、リンパ節への転移の数、患者さんの年齢などによって判断していきます。
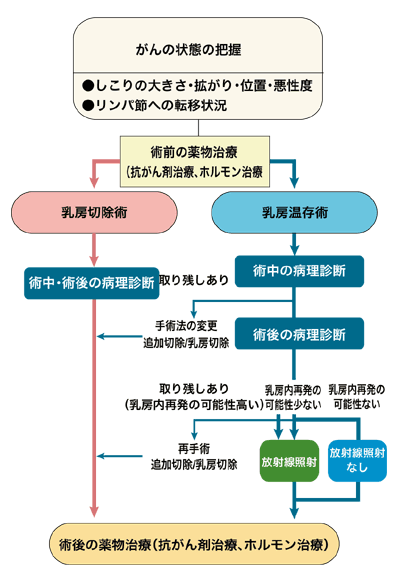
しこりの大きさが3センチ以下の乳がんで、乳房を切り取らないでがんを切除する手術法が乳房温存術(療法)です。がんのある部分を、周りを取り囲む正常細胞を含めてくり抜き、さらに残した乳房に放射線照射をして残っているかもしれないがんを叩きます。この治療を受けた人と乳房を全摘手術をした人とでは、遠隔転移率も生存率も変わらないことがわかっています。
*5 腋窩リンパ節のない乳がんの予後因子
乳がんは転移しやすい腋窩のリンパ節へ転移しているか、何個転移しているかが、がんの克服を判断する最も大きな材料になると考えられています。
しかし、腋窩リンパ節転移がなくとも、10パーセント前後の方が再発するので、ほかにどのような因子が関係しているかを調べる研究も数多く行われています。その結果、ホルモン感受性(女性ホルモンの影響で大きくなるタイプ)、腫瘍の大きさ(2センチ以上か否か)、年齢(35歳未満か否か)、核異型度(がん細胞の顔つきを表し、活発に増殖するタイプを3とし、1~3に分ける)などが、予後因子として浮かび上がりました。
*6 乳がんの術後ホルモン治療
乳がんの60~70パーセントは、エストロゲン、プロゲステロンという女性ホルモンを受け入れる窓口(受容体:レセプター)を持っていて、女性ホルモンの刺激で活発に増殖します。このタイプの乳がんは、その窓口をふさぐ働きをする抗女性ホルモン剤(タモキシフェン)を再発予防薬として用います。
また、閉経後の女性では、コレステロールを材料として、アロマターゼと呼ばれる変換酵素の働きにより、女性ホルモンが産生される経路があり、アロマターゼを阻害する薬も使います。一方、閉経前の女性は、卵巣から大量に出る女性ホルモンそのものを抑える薬も合わせて用います。
*7 ゾラデックス
ゾラデックスは女性ホルモンの産生指令を妨害するホルモンを放出することによって、卵巣のホルモン産生を抑制し、血中エストロゲン値を低下させる働きを持っています。タモキシフェンとゾラデックスの併用療法は、どちらか一方の薬を使った場合よりも効果的にエストロゲンを遮断することがわかっています。1期または2期の手術可能な乳がんを対象として行われた臨床試験では、タモキシフェン単剤を投与したグループに対してゾラデックスをあわせて投与したグループのほうが、明らかに無再発生存率が高いことがわかっています。
阿部恭子さんのお話
*8 乳がん看護認定看護師
乳がんの集学的治療のなかでも、薬物療法の占める割合は年々大きくなり、患者さんの増加とともに、薬物治療に関連する看護に求められるものが大きくなっています。
また、縮小手術が行われることが多くなり、入院期間が短縮している現在、外来看護が重視されるようになってきました。こうしたなかで乳がんの患者さんの看護として、診断(がん告知)後の心理的サポート、治療選択(意思決定)のサポート、様々な治療に伴う看護、ボディイメージの変容へのサポート、リンパ浮腫の予防など、患者や家族に対して行うほか、看護スタッフの指導や相談、さらに他職種との連携によってチーム医療を推進する役割が望まれています。こうした乳がん看護のための特定のスキルを身につけるため、2005年10月から千葉大学看護学部付属看護実践研究指導センターでは日本で初めて「乳がん看護認定看護師」の教育課程を誕生させました。
この過程を修了し、日本看護協会の認定審査(筆記試験)に合格すると、認定看護師として認定されます。
同じカテゴリーの最新記事
- 高濃度乳房の多い日本人女性には マンモグラフィとエコーの「公正」な乳がん検診を!
- がん情報を理解できるパートナーを見つけて最良の治療選択を! がん・薬剤情報を得るためのリテラシー
- 〝切らない乳がん治療〟がついに現実! 早期乳がんのラジオ波焼灼療法が来春、保険適用へ
- 新規薬剤の登場でこれまでのサブタイプ別治療が劇的変化! 乳がん薬物療法の最新基礎知識
- 心臓を避ける照射DIBH、体表を光でスキャンし正確に照射SGRT 乳がんの放射線治療の最新技術!
- 術前、術後治療も転移・再発治療も新薬の登場で激変中! 新薬が起こす乳がん治療のパラダイムシフト
- 主な改訂ポイントを押さえておこう! 「乳癌診療ガイドライン」4年ぶりの改訂
- ステージⅣ乳がん原発巣を手術したほうがいい人としないほうがいい人 日本の臨床試験「JCOG1017試験」に世界が注目!
- 乳がん手術の最新情報 乳房温存手術、乳房再建手術から予防的切除手術まで
- もっとガイドラインを上手に使いこなそう! 『患者さんのための乳がん診療ガイドライン』はより患者目線に


