乳がんホルモン療法最新レポート アロマターゼ阻害剤の臨床での使い方、3種類の使い分け方を学ぶ
臨床試験で明らかになっていること
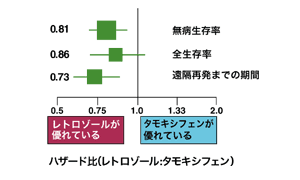
アロマターゼ阻害剤を使うのは、閉経後の乳がんで、ホルモンレセプター陽性の場合。これに該当するのは、乳がん患者の6~7割。このような人の術後補助療法として、タモキシフェンを使ったほうがいいのか、それともアロマターゼ阻害剤を使ったほうがいいのか、という問題がある。
「これに関しては、すでに臨床試験の結果が出ています。最初からタモキシフェンを投与する場合と、最初からアロマターゼ阻害剤を投与する場合で比較すると、アロマターゼ阻害剤を投与したほうが再発が減り、再発予防効果が優れているという結果が出ているのです。大きな臨床試験としては、アリミデックスを使った『ATAC試験』や、フェマーラを使った『BIG1-98試験』があります。どちらの試験も、最初から5年間アロマターゼ阻害剤を投与したグループのほうが、タモキシフェンを投与したグループより、再発が減ったことが確認されています」(図2)
ただ、BIG1-98試験の結果が発表される少し前に、途中で薬を変えるとどうなるかを調べた臨床試験の結果が発表されている。
タモキシフェンを2~3年投与して再発のなかった患者を2つに分け、一方にはアロマターゼ阻害剤を投与し、もう一方はタモキシフェンを続けたのだ。その臨床試験では、途中で薬をスイッチすると、大幅に再発が減るという結果が出ている。
「このスイッチングの臨床試験の結果と、最初からアロマターゼ阻害剤を投与した臨床試験の結果を、直接比較するのは難しいのですが、スイッチングしたほうが再発を抑える率が高かったのです。
もっとも、スイッチングしたほうは、タモキシフェンを2~3年飲んで再発のなかった人にアロマターゼ阻害剤を投与しているので、統計的な問題はあり、スイッチングのほうがいいというのも仮説にすぎません。今年のザンクトガレン乳がん国際会議(乳がん��期治療に関する国際会議)でも、現在行われている臨床試験の結果を待とうということになっていました。スイッチングがいいか、最初からアロマターゼ阻害剤がいいかに関しては、まだ結論が出ていません」
結果が期待されているのは、フェマーラを使ったBIG1-98試験だという。来年には解析が行われ、最初からフェマーラを使うのがいいのか、タモキシフェンを2年やってからフェマーラを3年投与するのがいいのか、あるいはその逆の順番でスイッチするのがいいのか、この3つを比較した結果が出ることになっているのだ。
「ザンクトガレン国際会議では、エキスパートパネルといって、乳がん治療の世界的なエキスパートたちが質問に答え、その結果を割合で表示することが行われます。アロマターゼ阻害剤の使い方に関しては、最初にタモキシフェンを投与し、それからアロマターゼ阻害剤にスイッチすると答えた人が多かったので驚きました。これは、スイッチしたほうがいいという仮説があることに加え、薬の価格が大きく関係していたようです」
紅林さんによれば、ヨーロッパにおけるアロマターゼ阻害剤の価格は、タモキシフェンの約20倍なのだという。この価格のために、最初からアロマターゼ阻害剤を使わず、タモキシフェンからスイッチする患者が多くなるらしいのだ。
日本では皆保険制度なので、どちらの薬でも経済的負担はあまり変わらない。そのため、より良いほうを最初から使おうということで、アロマターゼ阻害剤を最初から使っているケースが圧倒的に多いそうだ。
遠隔再発を抑制する効果が確認された
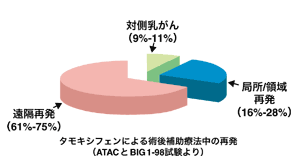
[図4 遠隔再発の死亡リスク]
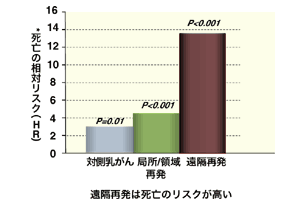
アロマターゼ阻害剤に関しては、これまでにもさまざまな臨床試験が行われている。それらのデータを分析すると、3種類のアロマターゼ阻害剤のなかで、フェマーラは、手術後に遠隔再発を起こさずに生存する期間を長くし、その率を上げることが報告されているのだそうだ。
乳がんの再発は、局所再発、領域再発、遠隔再発の3つに分けられる。(図3)
温存手術で残した乳房内にがんが出てきたり、切除手術による傷の近くに出てきたりするのが局所再発。鎖骨の上のリンパ節や胸骨の裏側のリンパ節など、領域リンパ節に再発するのが領域再発。血液を介して、肺、骨、肝臓など、離れた臓器に再発するのが遠隔再発(転移)だ。
「遠隔再発が起きてしまうと、その患者さんは、5年、あるいは10年以内に、再発のために亡くなるリスクが高くなると言われています。そういう意味では、遠隔再発をより強く低下させるというのは、魅力的な効果だといえます。遠隔再発が減れば、当然、生存率は向上すると考えられますが、これまでの臨床試験では、有意に生存率が向上するという結果は出ていません。そこまでつながっていくかどうか、見守っていく必要がありますね」(図4)
この点でも、今後の臨床試験の結果が待たれている。
定期的に骨塩量を測定しながら使用する
アロマターゼ阻害剤もタモキシフェンも、比較的副作用の少ない薬だ。それでも注意しなければならないポイントはある。
「副作用で最も多いのは関節痛や筋肉痛。多くは3~4カ月程度痛みがあり、徐々に軽快していきます。痛み止めの薬を出す必要のないケースがほとんどです。アロマターゼ阻害剤では、骨粗鬆症が進行することがあり、この点には十分な注意が必要です」
骨粗鬆症対策として必要なのは、アロマターゼ阻害剤の投与を始める前に、必ず骨塩量を測ることだという。その結果、骨粗鬆症と診断される人が、岡山では3~4割程度いるという。このような患者に、副作用対策をせずにアロマターゼ阻害剤を投与してしまえば、骨粗鬆症はどんどん進行してしまう。その結果、乳がんの再発は防げても、骨折して寝たきりになってしまうようなことも考えられるわけだ。
「骨塩量は*DXA法で測定しています。その結果、骨粗鬆症の手前の状態である骨減少症であることがわかったら、積極的にビタミンDを投与しています。カルシウムに関しては、処方薬は非常に服用しにくいので、サプリメントを利用して補給するように話しています。骨減少症でも検査値が下がり傾向の人や、すでに骨粗鬆症の人には、治療のためビスフォスフォネート製剤を処方します」
アロマターゼ阻害剤の服用が続いている間は、定期的に骨塩量を測る必要がある。正常の人でも年に1回、骨減少症や骨粗鬆症の人は半年に1回の測定が目安になるという。
*DXA法=Dual Energy X-ray Absorptiometry(二重エネルギーX線吸収法)。2つの異なるエネルギーのX線ビームを使い、パルス高の解析によって、骨と軟部組織を区別して、骨塩量を測定する。その正確さ、簡便さから広く普及している
フェマーラの長期処方が2007年5月から始まった
これまで、フェマーラは1回に2週間分しか処方できなかったのだが、2007年の5月から、他のホルモン療法剤と同じように長期処方ができるようになる。2週間おきの通院が、ほぼ3カ月に1度でよくなるのだから、患者にとっては大きな変化といえるだろう。
「2週間おきの通院に抵抗があって、フェマーラによる治療をためらっていた患者さんもいるでしょう。長期処方ができるようになって、患者さんの負担が軽減されることは間違いありませんね」
現在も臨床試験が進められているアロマターゼ阻害剤。すでに乳がんホルモン療法の主役となっているが、臨床試験の結果が出れば、どのように使えばもっとも効果的なのかが、明らかになるだろう。
同じカテゴリーの最新記事
- 高濃度乳房の多い日本人女性には マンモグラフィとエコーの「公正」な乳がん検診を!
- がん情報を理解できるパートナーを見つけて最良の治療選択を! がん・薬剤情報を得るためのリテラシー
- 〝切らない乳がん治療〟がついに現実! 早期乳がんのラジオ波焼灼療法が来春、保険適用へ
- 新規薬剤の登場でこれまでのサブタイプ別治療が劇的変化! 乳がん薬物療法の最新基礎知識
- 心臓を避ける照射DIBH、体表を光でスキャンし正確に照射SGRT 乳がんの放射線治療の最新技術!
- 術前、術後治療も転移・再発治療も新薬の登場で激変中! 新薬が起こす乳がん治療のパラダイムシフト
- 主な改訂ポイントを押さえておこう! 「乳癌診療ガイドライン」4年ぶりの改訂
- ステージⅣ乳がん原発巣を手術したほうがいい人としないほうがいい人 日本の臨床試験「JCOG1017試験」に世界が注目!
- 乳がん手術の最新情報 乳房温存手術、乳房再建手術から予防的切除手術まで
- もっとガイドラインを上手に使いこなそう! 『患者さんのための乳がん診療ガイドライン』はより患者目線に


