明確になった乳がんの「個別」治療の方向性 同じ乳がんでもタイプ別で異なる病気。治療法もそれぞれ異なる
効く薬がなかった脳転移にも有効か
| ラパチニブ+カペシタビン (n=160) | カペシタビン (n=161) | |
|---|---|---|
| 中枢系への転移 | 2 | 2 |
| 中枢系への再発 | 4 | 11 |
| 1部位だけの 中枢系への再発 | 3 | 10 |
さらに、このラパチニブは、乳がんの脳転移にも有効であるという可能性も示されていた。ハーセプチンは、血液脳関門という脳を守るためのしくみのために脳内に入り込めず脳転移には効かないとされていたが、ラパチニブは小分子の分子標的薬剤なので関門を通り抜けることができ、脳転移にも効くだろうと予想されている。
「もっともラパチニブは、脳転移を縮小する効果(奏効率)は5パーセントしかありません。それでも、8割の患者さんは症状がとれて楽になるという報告もあり、これは腫瘍による脳圧亢進が抑えられるためと見ることもできます。ですから、ラパチニブが本当に効くのかどうかは、脳転移全体にどういう治療がいいのかということも含めて、もう少しきちんと評価していく必要があります。ラパチニブに対する期待は大きいけれど、まだそれに対して確かにいいという手ごたえは十分とはいえない段階です」
HER2ディジーズの乳がんについての2番目の話題は、早期の乳がんに標準的な抗がん剤治療の後にハーセプチン治療を行うアジュバント(補助)療法により、生存期間が延長するというデータが示されたことだ。39カ国48施設で約5100人を対象に行われているHERA試験という大規模な臨床試験の結果による。23カ月目の段階で死亡のリスクが34パーセント低減することが明らかとなり、がんが再発するリスクも36パーセント低減することもわかった。
「ハーセプチンをできるだけ早期から使うことによって、死ななくてもすむ人がたくさん出ることがわかったわけです。いままでのデータだとただたんに再発を先送りしているだけではないかという批判もありました。けれどもそうではなく、そこでちゃんと病気を治癒できるのではないかという可能性も出てきたわけで、これは画期的な報告です」
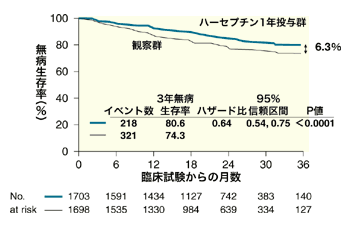
[ハーセプチン1年投与の全生存率]
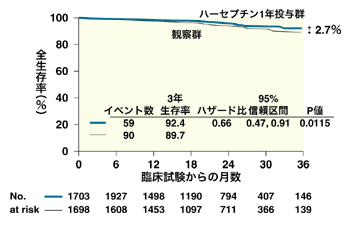
ホルモン療法の革新で生存期間延長
ホルモン剤がよく効くルミナルタイプの乳がんに対する治療においても、大規模臨床試験による画期的なデータが示された。このタイプには従来、一般的にタモキシフェンというホルモン剤を長期間投与する方法がとられてきたが、途中で同じホルモン剤でも作用機序の異なるアロマターゼ阻害剤という薬に切り替える療法によって、生存期間が延長するということが示されたのだ。
この臨床試験では初期の閉経後乳がん患者4724人を対象に行われ、ホルモン療法を5年間行った。タモキシフェンを2年から3年投薬してから、アロマターゼ阻害剤の1種であるアロマシン(一般名エキセメスタン)に切り替えたグループ2352人、タモキシフェンを5年間継続投与したグループ2372人を比較している。その結果、アロマシンに切り替えたグループは、タモキシフェンを継続投与したグループに比べて、死亡のリスクが15パーセント低減した。アロマシンに切り替えたグループでは、転移のリスクが17パーセント減少し、反対側の乳房にがんが発生するリスクも44パーセント減少している。
「これまでホルモン療法では、たんにがんの進行を遅らせたり再発を予防する作用しかなく、治療をやめればまた悪くなるのではないかというイメージがありました。これに対して、ホルモン治療のメニューを変えると生存期間が延長するというデータが今回初めて示されたわけで、このインパクトはとても大きいといえます」
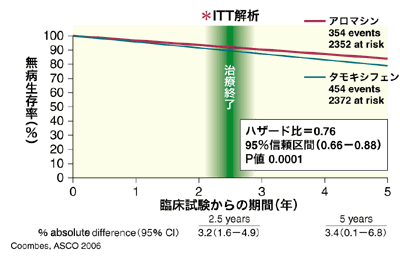
[タモキシフェンと途中からアロマシンに切り替えた群の比較(全生存率)]
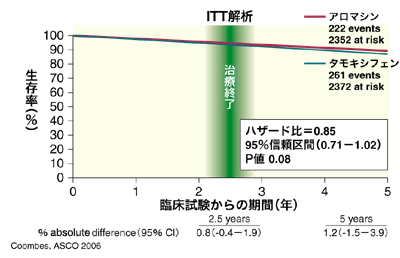
*ITT解析=臨床試験に割り付けられた患者から脱落者も含めて解析する
乳がん患者の骨のケアは腫瘍内科医の使命
今後乳がんのホルモン療法でアロマターゼ阻害剤が治療の主流になる可能性が大きい。が、一方アロマターゼ阻害剤は骨粗鬆症という副作用の懸念が大きい薬としても知られる。また、乳がんのため抗がん剤治療を受けていた人は、早く閉経を迎えて骨粗鬆症になりやすいこともわかっている。今年のASCOでは、乳がん治療における骨のケアということも焦点の1つとなっていて、治療による骨塩量の変化を評価した報告が多かった。
「アリミデックス(一般名アナストロゾール)というアロマターゼ阻害剤を使ってタモキシフェンに対する優位性を証明したATACという臨床試験でも、アリミデックスによる骨塩量の減少が報告されています。最初骨塩量が正常範囲だった人も、アリミデックスを5年間飲むと、骨粗鬆症や骨折まではいかないにしても、骨塩量がかなり減少することが示されました。すると乳がん治療に当たっては、担当医が骨塩量に対して、経験と知識を備え、十分な注意を払って臨むことが求められます。実際に米国のガイドラインでも、『オンコロジスト(腫瘍内科医)の重要な責務として、ボーンヘルス(骨の健康)というものを考えることが重大な任務である』というふうにしっかりうたわれています」
一方、乳がんと骨粗鬆症を同時に予防できる薬の可能性についても、ASCOで報告された。この薬は閉経後の女性の骨粗鬆症治療に使われているラロキシフェンという薬で、タモキシフェンとラロキシフェンを比較したSTAR試験という大規模臨床試験の結果、両者に同じくらい乳がん発症の予防効果があることがわかったのである。ラロキシフェンは日本でも骨粗鬆症の治療薬(商品名エビスタ)として市販されており、閉経後の女性はこの薬を乳がん予防と骨粗鬆症予防の保健薬として利用することができるかもしれないことになる。
「乳がんの骨転移や高カルシウム血症の治療薬として、日本でもビスフォスフォネートという治療薬が認められています。この薬の利用も含めた乳がんの患者さんの骨のケアは、我々腫瘍内科医が取り組むべき大きなテーマとなってきました。一方では、アロマターゼ阻害剤とラロキシフェンを一緒に使うことは慎むべきとされるなど、乳がん治療における薬物利用はいっそう複雑になっています。我々は片手間でがんの薬物治療に取り組む外科医にはますます『任せてはおけない』という思いを強くすることになりました」
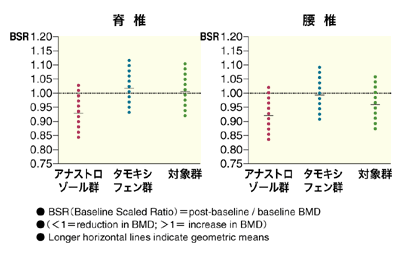
*骨密度=骨の中にあるカルシウムやマグネシウムなどのミネラル成分がどのくらいあるかの量
同じカテゴリーの最新記事
- 高濃度乳房の多い日本人女性には マンモグラフィとエコーの「公正」な乳がん検診を!
- がん情報を理解できるパートナーを見つけて最良の治療選択を! がん・薬剤情報を得るためのリテラシー
- 〝切らない乳がん治療〟がついに現実! 早期乳がんのラジオ波焼灼療法が来春、保険適用へ
- 新規薬剤の登場でこれまでのサブタイプ別治療が劇的変化! 乳がん薬物療法の最新基礎知識
- 心臓を避ける照射DIBH、体表を光でスキャンし正確に照射SGRT 乳がんの放射線治療の最新技術!
- 術前、術後治療も転移・再発治療も新薬の登場で激変中! 新薬が起こす乳がん治療のパラダイムシフト
- 主な改訂ポイントを押さえておこう! 「乳癌診療ガイドライン」4年ぶりの改訂
- ステージⅣ乳がん原発巣を手術したほうがいい人としないほうがいい人 日本の臨床試験「JCOG1017試験」に世界が注目!
- 乳がん手術の最新情報 乳房温存手術、乳房再建手術から予防的切除手術まで
- もっとガイドラインを上手に使いこなそう! 『患者さんのための乳がん診療ガイドライン』はより患者目線に


