世界最大のがん学会、ASCO2005レポート 今後のがん治療を大きく変えるハーセプチンの治療報告
血管新生阻害剤の効果

ハーセプチンとともに、もう1つ大きな注目を浴びたものがある。これまた従来の抗がん剤にはない、まったく新しい作用メカニズムを持つ血管新生阻害剤と呼ばれる薬のアバスチン(一般名ベバシツマブ)だ。この薬は、米国ではすでに転移性大腸がんの第1選択薬として、2004年2月に食品医薬品局(FDA)に承認されている。スイスの医薬品大手ロシュ社の子会社ジェネンテック社が製造している薬で、腫瘍に酸素と栄養分を供給する血管の造成を阻害することによって、腫瘍の成長を遅らせる効果を持つ。今回は、この大腸がんに次いで、乳がんと非小細胞肺がんに対して有効性を示す臨床試験結果が発表された。血管新生阻害剤が乳がんと肺がんの治療に有効であることが示されたのは、これが初めて。
まず、乳がんでは、治療を受けたことのない局所再発または転移性乳がんに対し、タキソールによる化学療法が標準的に行われてきたが、これにアバスチンを加えた治療をするとどうなるかを確かめる臨床試験が2001年から行われた。米国インディアナ大学のキャシー・ミラーさんがこの結果を発表した。無病生存期間の中央値がタキソール群で6.11カ月、アバスチン群で10.97カ月、有意に延長することが明らかにされた。奏効率も、タキソール群で14.2パーセントだったのに対し、アバスチン群では28.2パーセントと、およそ2倍に上った。
副作用については、アバスチン群で有意に高かったのは、高血圧やタンパク尿、神経障害など。もっとも、事前に定めた高血圧や出血、血栓塞栓性疾患に関する制限値には至らなかったという。
分子標的薬、初の延命効果
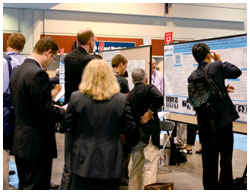
この乳がんでのアバスチン報告もさることながら、もっと話題を呼んだのは、肺がんでの報告だった。アバスチンの進行非小細胞肺がんに対する臨床試験結果の詳細は、学会のプレナリーセッションでバンダービルト大学医療センターのサンドラー准教授によって発表された。
その内容は、ステージ3Bまたは4の非小細胞肺がんに対して、標準的な化学療法にアバスチンを加える治療をしたところ、生存期間が延長する効果が出たというものだ。具体的にいうと、標準的な治療のみでは生存期間中央値が10.2カ月だったのに対して、アバスチンを加えると12.5カ月に、1年生存率は標準的治療が43.7パーセントだったのが、51.9パーセントへと有意に上がったという。進行非小細胞肺がんに対する抗がん剤治療では、これまで1年生存率は40パーセント程度に止まっていたが、今回の臨床試験で初めて50パーセントの壁を超えた。また、分子標的薬が進行非小細胞肺がんの治療で生存期間を延長させたのは今回が初めてである。
それだけではない。腫瘍増殖抑制期間や治療反応率、2年生存率なども、アバスチン併用群でそれぞれ有意に良好だったともいう。こうした結果に対して、早くも「非小細胞肺がんへの新たな標準的治療になった」という声も上がっている。
そんなこともあって、この発表に先立って米国立衛生研究所(NIH)がマスコミ向けに発表したところ、たちまち米株式市場が反応し、ジェネンテックの株価が急騰するという反響も起こっている。日本の医薬業界でも、このアバスチンは「抗がん剤史上初めて1000億円を超える市場の薬が誕生するのではないか」との話題でもちきりだ。これまでの最高記録はUFTで、700億円ほどであったから、その期待の大きさがうかがえる。
もっとも、これにはある程度の根拠があって、この薬の裾野、応用範囲の広さが影響している。現在、大腸がんでは転移がん治療から術後補助療法にも適応を広げていこうとしているが、そのほかにも、膵臓がん、卵巣がん、腎細胞がんなどでも適応が考えられている。血管阻害という作用メカニズムから見れば、あらゆるがんがその治療対象になり得、それだけ期待がかかっているわけだ。
しかし、いい話ばかりではない。まれではあったものの、深刻な副作用リスクも明らかになった。有害作用として、グレード3以上の出血、とくに肺からの致命的な出血が化学療法のみに比べてアバスチン群のほうに多く見られた。化学療法群では0.7パーセントだったのに対して、アバスチン群では4.5パーセントという多さだった。
それに、先のハーセプチン同様、このアバスチンも医療現場では使えない。保険適応どころか、承認すらされていないのが現状である。
胃がんの術後補助化学療法
最近は日本の臨床試験の発表も増えてきているが、その1つを紹介しておこう。
胃がんに対する術後補助化学療法の有効性を確かめる臨床試験についての報告で、発表者は、国立がん研究センター東病院消化器外科部長の木下平さん。
胃がんの術後補助療法では、これまで有効な治療法が確立されていなかった。そこで、木下さんらの臨床試験のグループでは、対象を絞り込み(しょう膜への浸潤がなく、リンパ節転移のあるT2の患者)、胃がんの手術後、UFTという5-FU系の経口抗がん剤を服用するとどうなるかを確かめる試験を1997年から開始した。2001年までに190例が集まり、その結果が発表されたのだ。
結果は、手術単独群の4年生存率が73.6パーセントだったのに対して、UFT群では86.3パーセントと有意に高かった。
ただし、サンプル数が少ないことから「これだけでは術後補助療法の有効性はまだ不明」と批判された。サンプル数が少ないのは、UFTをさらに改良したTS-1という抗がん剤が医療現場に出現したためで、これにより胃がんの術後補助化学療法への道が切り開かれたことは確かなようだ。
同じカテゴリーの最新記事
- 高濃度乳房の多い日本人女性には マンモグラフィとエコーの「公正」な乳がん検診を!
- がん情報を理解できるパートナーを見つけて最良の治療選択を! がん・薬剤情報を得るためのリテラシー
- 〝切らない乳がん治療〟がついに現実! 早期乳がんのラジオ波焼灼療法が来春、保険適用へ
- 新規薬剤の登場でこれまでのサブタイプ別治療が劇的変化! 乳がん薬物療法の最新基礎知識
- 心臓を避ける照射DIBH、体表を光でスキャンし正確に照射SGRT 乳がんの放射線治療の最新技術!
- 術前、術後治療も転移・再発治療も新薬の登場で激変中! 新薬が起こす乳がん治療のパラダイムシフト
- 主な改訂ポイントを押さえておこう! 「乳癌診療ガイドライン」4年ぶりの改訂
- ステージⅣ乳がん原発巣を手術したほうがいい人としないほうがいい人 日本の臨床試験「JCOG1017試験」に世界が注目!
- 乳がん手術の最新情報 乳房温存手術、乳房再建手術から予防的切除手術まで
- もっとガイドラインを上手に使いこなそう! 『患者さんのための乳がん診療ガイドライン』はより患者目線に


