渡辺亨のザンクト・ガレン乳がん国際会議レポート 4年ぶりの改定。大きく変わったリスク分類と治療方法
ホルモン感受性重視の再発リスク
今回の会議から、術後の患者がどの程度再発の危険性(リスク)があるかを分類したリスクカテゴリーについて、腋窩(わきの下)リンパ節転移陰性、陽性の別なく、すべての術後の患者を、低、中、高の、3つのカテゴリーに分類しています。
1998年の第6回会議のコンセンサスでは、腋窩リンパ節転移について陰性と陽性に大きく分けて、さらに陰性の患者について、腫瘍サイズ、ホルモン受容体の状態などに基づいて、3つのカテゴリーに分けていました。01年の第7回会議からは、腋窩リンパ節転移陰性の患者は、ホルモン受容体反応性ありと反応性なしの2つに大きくわけ、それぞれを低~高リスクに分類していました。これらを踏襲し、今回は次のような改訂が加えられました。
(1) 腋窩リンパ節転移の陰性、陽性に関わらず、低リスク・中リスク、高リスクの3つのカテゴリーを設定、それぞれをホルモン感受性あり、ホルモン感受性なしにわけ、計5つのリスクカテゴリーに分類した。
(2) ホルモン感受性陽性で、病理学的浸潤径が1センチ未満ならば、他の項目に関係なく低リスクに分類される。
(3) 低リスクと中リスクの区別には、従来の病理学的腫瘍浸潤径、ホルモン受容体、年齢、*グレードに加え、広汎な*脈管浸潤の有無、*HER2過剰発現/遺伝子増幅の有無の2項目が加えられ、計5項目となった。
(4) 中リスクには、腋窩リンパ節転移1~3個陽性で、広汎な脈管浸潤がなく、HER2過剰発現がない症例が含まれる。
(5) 高リスクも2つのカテゴリーが設けられた。1つは、腋窩リンパ節転移4個以上の患者、もう1つは腋窩リンパ節転移陽性(1個以上)で、広汎な脈管浸潤または、HER2の過剰発現のある患者が含まれる。
リスクカテゴリーについて、「ホルモン感受性が不明あるいは不確実という状態がありうるか」という質問に対して、ほとんどのパネリストが、「はい」と答えました。つまり、いままでは、ホルモン感受性(ホルモン療法が効きやすいというがんの性格)は、「あり・なし」の2つに分けられるような傾向がありました。
しかし、ホルモン感受性には、強弱があり、ホルモン感受性がすごく強い場合、ホルモン感受性が中くらい、さらに、陰性���はないが弱い、そして、ホルモン感受性は不確か、というような、段階的な考え方が確認されたわけです。
*グレード=核や組織の悪性度を示す *脈管浸潤=血管やリンパ管へがんが染み込むこと *HER2=乳がん細胞などの表面に出る受容体タンパク
| ホルモン療法反応別の治療方法 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| リスク カテゴリー | ホルモン療法反応性 | 反応性不明(含弱陽性) | ホルモン療法不反応性 | ||
| 閉経前 | 閉経後 | 閉経前 | 閉経後 | ||
| 低リスク | TAM or 無治療 | TAM, AI or 無治療 | TAM or 無治療 | TAM, AI or 無治療 | |
| 中リスク | TAM±OFS,OFS CT→TAM±OFS AI+OFS | TAM, AI CT→TAM CT→AI | CT→TAM(±OFS) CT→AI+OFS CT | CT→TAM CT→AI | AC, CEF or FEC±タキサン |
| CT : ACR±タキサン | CT : ACR±タキサン | CT : ACR±タキサン | CT : ACR±タキサン | ||
| 高リスク | CT→TAM±OFS CT→AI+OFS | CT→TAM CT→AI | CT→TAM(±OFS) CT→AI+OFS | CT→TAM CT→AI | AC, CEF or FEC+タキサン |
| CT : ACR+タキサン | CT : ACR±タキサン | CT : ACR+タキサン | CT : ACR+タキサン | ||
CEF : シクロホスファミド + エピルビシン + 5-FUの3剤併用
FEC : 5-FU + エピルビシン + シクロホスファミドの3剤併用
AI : アロタターゼ阻害剤 CT : 化学療法 ACR : アントラサイクリン系抗がん剤を含む化学療法
リスク別の治療方法も大きく変更になった
変わったタキサンとアロマターゼ阻害剤の位置づけ
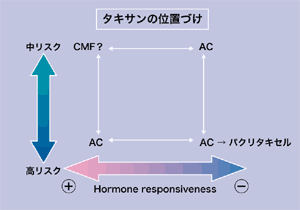
このように新しいコンセンサスのもとに設けられたリスクカテゴリーに対して、どのような治療が行われるかについても、今回、大幅な変化がありました。すなわち一方に低リスクでホルモン感受性ありの極があって、こちらはホルモン療法中心、もう一方に高リスクでホルモン感受性なしの極があってこちらは抗がん剤治療中心となり、それをつなぐ連続傾斜の上にホルモン療法と抗がん剤の組み合わせが分布されるという基本的な考え方が導入されたように思います。
こうしたなかで、パクリタキセル(商品名タキソール)やドセタキセル(商品名タキソテール)などタキサン系の薬剤の位置づけについてもコンセンサスが得られました。高リスク患者では、アントラサイクリン系薬剤に加え、タキサンの使用を推奨する意見が多くなってきました。また、中リスクでも、ホルモン感受性のない、あるいは不確実な場合や、腋窩リンパ節転移陽性の患者では、AC療法[ドキソルビシン(商品名アドリアシン)+シクロホスファミド(商品名エンドキサン)]に加えて、タキサンが必要になるのではないかと認識されるようになったのです。
日進月歩の乳がん薬物療法

もう1つ今回の重要な改訂点は、閉経後でホルモン感受性があるかあるいは不確実な症例に対して、タモキシフェンに代わってアロマターゼ阻害剤がほぼ標準的な治療として認識されるようになったことです。ホルモン感受性を有する閉経後患者では、術後にはかならずアロマターゼ阻害剤を使用するという考え方はもはや標準といっていいでしょう。
どの時点で、アロマターゼ阻害剤を使用するか、については、タモキシフェン(商品名ノルバデックス)を全く使用しないで、最初から使用する場合、2~3年のタモキシフェンの後に使用する場合、さらにタモキシフェンを5年使用した後で、5年間使用する、というような、3種類の考え方があります。このあたりは、まだ、整理がついていないようです。
このように今回のザンクト・ガレンでは、概してみると久々に大きな改訂がありましたが、残念なのは議事運営の上でまだ十分スムーズではない点が見られたことです。たとえば質問項目が示されアンサー・パッドが押されたあとで、パネリストから「こういう質問の仕方ならわかりやすいのに」といった発言があって、それにしたがって質問をし直すと、イエス・ノーの回答結果ががらっと変わったりしました。
その結果、参加者の中にも、「コンセンサスといいながら、けっこういい加減に決定されるものだ」という印象を持つ人もあったのです。ザンクト・ガレンの結果は、必ずしも金科玉条のように尊重すべきものとはいえませんが、少なくともこれから先2年間の乳がん治療における1つの方向性を示す羅針盤になるのは間違いありません。
もちろん患者さんの乳がん診療の受け止め方も、ザンクト・ガレンのコンセンサスによって、これまでとは違いが出てくると思います。
一番重要なことは、ホルモン感受性や再発リスクが、イエスかノーかではなく連続的傾斜の上にあるという考え方になり、これに対応して、ホルモン剤や抗がん剤の治療が展開されることになったことです。
また、ホルモン療法ではアロマターゼ阻害剤を積極的に推奨する動きが強くなったわけですが、この薬は再発抑制効果が強い一方、骨粗鬆症や虚血性心疾患の頻度がやや高いことが指摘されており、このプラスの面とマイナスの面のバランスを考える必要が出てきました。そして、高リスクの患者さんに対する抗がん剤治療では、基本的なAC療法にタキサンが加えられることが標準的になってきたことについても、効果と副作用のバランスをよく考える必要があります。
いずれにしても、時々刻々と進歩している乳がんの薬物療法については、担当医と患者さんとの十分なコミュニケーションが必要だということが、改めて確認されたように思います。
同じカテゴリーの最新記事
- 高濃度乳房の多い日本人女性には マンモグラフィとエコーの「公正」な乳がん検診を!
- がん情報を理解できるパートナーを見つけて最良の治療選択を! がん・薬剤情報を得るためのリテラシー
- 〝切らない乳がん治療〟がついに現実! 早期乳がんのラジオ波焼灼療法が来春、保険適用へ
- 新規薬剤の登場でこれまでのサブタイプ別治療が劇的変化! 乳がん薬物療法の最新基礎知識
- 心臓を避ける照射DIBH、体表を光でスキャンし正確に照射SGRT 乳がんの放射線治療の最新技術!
- 術前、術後治療も転移・再発治療も新薬の登場で激変中! 新薬が起こす乳がん治療のパラダイムシフト
- 主な改訂ポイントを押さえておこう! 「乳癌診療ガイドライン」4年ぶりの改訂
- ステージⅣ乳がん原発巣を手術したほうがいい人としないほうがいい人 日本の臨床試験「JCOG1017試験」に世界が注目!
- 乳がん手術の最新情報 乳房温存手術、乳房再建手術から予防的切除手術まで
- もっとガイドラインを上手に使いこなそう! 『患者さんのための乳がん診療ガイドライン』はより患者目線に


