進行再発乳がんのホルモン療法最新トピック 今後はアロマターゼ阻害剤と分子標的薬の組み合わせが鍵に
化学療法より楽な治療だが副作用はある
アロマターゼ阻害剤による治療は、化学療法に比べると、いろいろな面で優れていると言えそうだ。
「アロマターゼ阻害剤は内服剤で、1日1回服用するだけなので、飲みやすさの点で抗がん剤より優れています。施設によっては最大90日分を処方できるので、その場合、病院に来るのは3カ月に1回。抗がん剤の場合、外来で受けたとしても、通常は3週間に1回、場合によっては毎週、病院で点滴を受ける必要があります」
副作用も化学療法と、アロマターゼ阻害剤などのホルモン療法とでは大きく異なっていて、楽なのはやはりホルモン療法である。化学療法の場合、食欲低下、脱毛、倦怠感などの副作用が現れるので、どうしてもQOL(生活の質)が低下してしまうからだ。その点、ホルモン療法なら、QOLを維持したまま治療を続けることができる。だからこそ、ホルモン感受性が陽性の人は、可能な限りホルモン療法を続けるのである。
ただし、アロマターゼ阻害剤にも副作用はある。気をつけなければならない副作用は、関節痛や骨粗鬆症などだ。
「服用を始めてからしばらくして関節痛が出現しますが、多くの患者さんは身体がなれるのか、半年くらい使っているとよくなる人が大勢いらっしゃいます。また、NSAIDs(非ステロイド性抗炎症薬)を飲むことで症状がおさまる患者さんもいらっしゃり、痛みのためにアロマターゼ阻害剤の服用を中止するケースはあまり多くありません」
骨粗鬆症対策としては、カルシウム製剤やビタミンDを併用したり、ビスホスホネート製剤が使われたりするという。
「骨への転移があれば必ずビスホスホネート製剤を使っていますが、アロマターゼ阻害剤の副作用で起こる骨粗鬆症を防ぐのにも有効です。また、最近、ビスホスホネート製剤であるゾメタ(一般名ゾレドロン酸)に、転移再発の抑制効果があることを示唆するような臨床試験結果も出ています」と緒方さんは話している。
3剤の中で「どれがいいか」の明確な科学的根拠はまだない
アロマターゼ阻害剤は3種類あるが、その中でどれが最も有効性が高いかを示す臨床試験の結果は出ていない。現在のところ、臨床の現場では、3剤とも効果も副作用もほぼ同じという認識で使われているという。
ただ、タモキシフェン投与中に進行してしまった転移性乳がんの患者さんを対象に、フェマーラとアリミデックスを比較した臨床試験が行われている。
その結果、無増悪期間や全生存期間では有意な差は��かったが、奏効率(腫瘍縮小割合)ではフェマーラが優れていたという結果が出ている。
「フェマーラは3剤の中では、最もエストロゲンを下げることが基礎研究で明らかになっています。そういうことが奏効率に影響している可能性はあるでしょう。進行再発乳がんの患者さんにとって、無増悪期間や生存期間を延ばすことは重要です。ただし現在のところ、そこに差があるというエビデンスは出ていません」
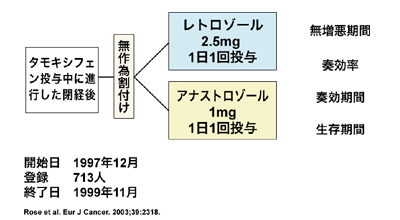
[図5 レトロゾールとアナストロゾールの効果の比較]
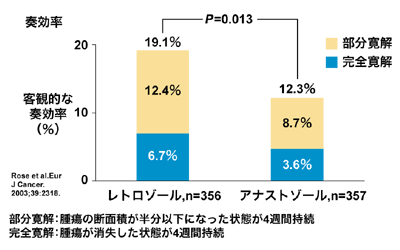
アロマターゼ阻害剤が3剤あることで患者の選択肢も増える
ただ、アロマターゼ阻害剤が3種類あるのは、患者さんにとってはいいことだと言える。ある薬を使っていて、その薬が効かなくなった場合に、第2、第3のアロマターゼ阻害剤を使って、治療を続けることができるからだ。
たとえば、こんな患者さんがいるという。
70代後半で乳がんの肝転移が発見された患者さん。肝転移はあったが、高齢のため抗がん剤は厳しいと判断され、ホルモン感受性が陽性だったので、アロマターゼ阻害剤による治療が行われることになった。
3年近く安定した状態が続いたが、腫瘍が少し大きくなり始め、腫瘍マーカーが上がり始めたので、2種類目のアロマターゼ阻害剤に変更。3年以上経過した現在も治療継続中だという。
また、現在では、手術後の再発予防にも、アロマターゼ阻害剤が使われるようになっている。そういう人が、数年後に再発した場合、術後治療で使ったアロマターゼ阻害剤は使うことができない。こんなケースでも、3剤そろっていることは意味があると言えそうだ。
期待されている分子標的薬との併用
アロマターゼ阻害剤によるホルモン療法は、今後どのように進歩していくのだろうか。
「ハーセプチンとの併用について、臨床試験が進められていることは前に話しましたが、実はハーセプチン以外の分子標的薬との間でも、併用したほうがいいのか、併用しないほうがいいのかを調べる比較試験(臨床試験)が行われています」
ハーセプチン以外の乳がん治療薬として認可が待たれているタイケルブ(一般名ラパチニブ)などの分子標的薬と、アロマターゼ阻害剤との併用による効果を調べた臨床試験が現在進行しているという。
今後分子標的薬は続々と登場してくると考えられる。それぞれに関して臨床試験が必要になるのだから、宿題は山積みといったところなのである。
「ホルモン療法を行っていると、治療抵抗性によって、いずれ薬が効かなくなってきます。この現象がなぜ起こるのか、はっきりしたことはわかっていません。ただ、ある種の分子標的薬には、いったん効かなくなったホルモン療法を、再び効くようにする働きがあるのではないかと期待されています」
いずれにしても、アロマターゼ阻害剤によるホルモン療法の今後は、分子標的薬とどう組み合わせていくかが重要な問題になっていくのだろう。
同じカテゴリーの最新記事
- 新薬の登場で選択肢が増える 乳がんの再発・転移の最新治療
- SONIA試験の結果でもCDK4/6阻害薬はやはり1次治療から ホルモン陽性HER2陰性の進行・再発乳がん
- 乳がんサバイバーの再発恐怖を軽減 スマホアプリの臨床試験で世界初の効果実証
- 術後のホルモン療法は10年ではなく7年 閉経後ホルモン受容体陽性乳がん試験結果
- より推奨の治療法が明確化した「ガイドライン」 HR陽性、HER2陰性の進行・再発乳がんの最新治療
- 原発巣切除による生存期間延長効果の比較試験が進行中 試験結果が待たれるステージIV乳がんの原発巣手術の是非
- 血管新生阻害薬アバスチンの位置づけと広がる可能性 アバスチンと免疫チェックポイント阻害薬の併用が未来を拓く
- ホルモン陽性HER2陰性の進行・再発乳がんに、イブランスに続きベージニオも承認間近
- 長期戦の覚悟と対策を持って生き抜くために ホルモン陽性HER2陰性の乳がんは、なぜ10年経っても再発するのか


