末梢血中のがん細胞の数で、転移性乳がんの治療効果を予測する 循環がん細胞(CTC)検査で無駄な治療をしなくてすむ
早く効果の有無がわかれば無駄な治療をしなくてすむ

CTC(循環がん細胞)検査装置(米国Veridex LLC提供)
このように、CTCの数は転移性乳がんの予後や治療効果を反映することがわかってきたのです。
こうした結果を受けて、すでにアメリカでは、FDA(米国医薬品局)がCTC検査を転移性乳がんの予後を予測する検査として承認しています。
この検査の利点について、中村さんはこう評価しています。ひとつはより早く、治療効果の有無をみることができることです。これまで、抗がん剤の効果は、画像診断によって評価されていました。がんの病巣を一方向で測定し、30パーセント以上縮小した状態が4週間以上続けばPR(部分寛解)で、効果ありと判定されるわけです。
といっても、「がんが治療によって30パーセント以上縮小するのは、抗がん剤を使って3~4カ月後」だそうです。ということは、効かない抗がん剤であっても、その間は使いつづけることになってしまうのです。これに対して、CTCは治療開始後3~4週後には効果の有無を判定できるのが大きな利点です。
「一般的には、化学療法は2コース行ってから効果の判定を行い、効果がなければ別の治療法に切り換えることになります。しかし、もし1コース行ったあと、2コース目の治療に入る前にCTC検査で効果を判定できれば、1コース無駄に行うのを防ぐことができるのです」と中村さんは話しています。早く効果の有無がわかれば、無駄な治療をしないですむし、より早く効果的な治療に変えることも可能になるのです。
医療経済的にもこれは大きなメリットです。CTC検査で必要な血液は、わずか7.5ccです。CTやMRIなどの画像診断を頻繁に行うより、血液を採取して検査をする方が、患者さんの体の負担も少なければ、経済的にもメリットは大。必要に応じていつでも検査が行えるのです。まして、使っている抗がん剤が分子標的治療薬のよ���に高価なものであれば、無駄に使う経済的損失も大きなものです。
「本当に効果のある人に使ってあげたい」と中村さん。今後は、CTC検査の医療経済的な評価も行われていくそうです。
CTC検査の臨床試験結果は米国乳がん学会で報告予定
こうしたメリットを踏まえて、日本でも聖路加国際病院や駒込病院などがんでCTC検査の臨床試験が2005年から行われました。現在、その結果がまとめられているところ。秋にはアメリカの乳がん学会で報告される予定です。
以前、発表された中間報告の結果をみると、転移性乳がんの人の半分に2個以上のCTCが見つかること、さらに5個以上と5個未満の人では生存率に大きな差があることが判明しています。ほぼ、アメリカと同様の結果が出ていると言えそうです。日本でも、まもなくCTC検査が承認され、自費で検査を受けることが可能になると見られています。
しかし、中村さんは「CTC検査は、まだこの種の検査の導入部か先駆けかもしれません」と話しています。中村さんが、今後期待しているのは術前化学療法や術前ホルモン療法の効果予測です。
最近は、3センチを超える少し大きな乳がんでも術前化学療法や術前ホルモン療法でがんを縮小させて乳房温存手術に持ち込むことが、一般的になってきました。こうした原発巣の乳がんに対する化学療法の効果をみるためには、「転移性乳がんの3倍ぐらい、つまり25~30ccの血液を採取し、その中に1~2個CTCがあるかどうかが、指標になると言われている」そうです。逆にいえば、この程度の感度がCTC検査の限界ともいえます。
転移性乳がんの場合も、偽陽性率(転移性ではないのに転移性と出てしまう率)は極めて低いものの、転移性乳がんに対する感度は50パーセント。つまり、陽性と出ればほぼ間違いなく転移性ですが、半分の人しか転移性と出ないのが現状です。
この感度をもっとあげるか、あるいは「今後はがん細胞以外の治療に由来する血液内の物質が指標になるかもしれません」と中村さんは話しています。
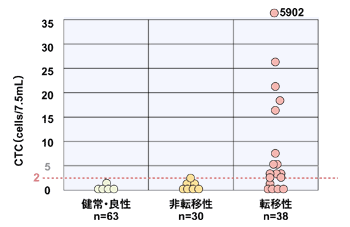
健常者でCTCが2個以上の人は1人もいない
どの分野で利用価値が高いかこれから調べていく必要がある
たとえば、その候補のひとつが血管内を循環する血管内皮細胞です。がんは旺盛に増殖するため必ず自らの周囲に新生血管を作り、酸素や栄養を補給します。この新生血管が抗がん剤や血管新生阻害剤などでダメージを受けると、破壊された血管から血管内皮細胞などが血中に出てきます。これを治療効果の指標にしようという研究も進んでいるそうです。細胞レベルではなく、破壊された細胞から血中に出てくるDNAの一部を指標にしようという研究も進んでいるそうです。こうしたレベルで治療効果をみれば、より微小な変化も捕らえられる可能性があるのではないかというのです。
したがって、CTC検査の実用化のためには、治療効果の予測という意味ではもっと感度をあげる、血液内の別の指標に注目するなどの研究が必要です。「どの分野で1番利用価値が高いかは、まだこれから調べていく必要があります」と中村さん。
最近では、遺伝子検査でDNAを調べて再発リスクや抗がん剤の効果を予測する検査も開発されています。治療効果の判定にもさまざまな手法が登場しているのです。
「分子標的治療薬などさまざまな抗がん剤が登場し、今では術前化学療法でがんが病理学的に完全に消失することもあります。そうなれば、予後はきわめて良好でほとんど乳がんでない人と変わりなくなります。そういう人は高価な薬を使う意味も十分にあるのです。今後は、化学療法によってがんの完全消失が得られそうな人をどれだけ検査で絞り込めるか、それが大きな問題になっていくと思います」と中村さんは治療効果予測の必要性を説明しています。
- 治療効果判定が早い(1カ月)
- 転移能をもつCTCを測定
- 的確に臨床経過を反映(リアルタイムに)
- (転移性)多種がんで測定可能
- 発展性がある(PCR/マイクロアレイ/プロテオーム解析)
同じカテゴリーの最新記事
- 新薬の登場で選択肢が増える 乳がんの再発・転移の最新治療
- SONIA試験の結果でもCDK4/6阻害薬はやはり1次治療から ホルモン陽性HER2陰性の進行・再発乳がん
- 乳がんサバイバーの再発恐怖を軽減 スマホアプリの臨床試験で世界初の効果実証
- 術後のホルモン療法は10年ではなく7年 閉経後ホルモン受容体陽性乳がん試験結果
- より推奨の治療法が明確化した「ガイドライン」 HR陽性、HER2陰性の進行・再発乳がんの最新治療
- 原発巣切除による生存期間延長効果の比較試験が進行中 試験結果が待たれるステージIV乳がんの原発巣手術の是非
- 血管新生阻害薬アバスチンの位置づけと広がる可能性 アバスチンと免疫チェックポイント阻害薬の併用が未来を拓く
- ホルモン陽性HER2陰性の進行・再発乳がんに、イブランスに続きベージニオも承認間近
- 長期戦の覚悟と対策を持って生き抜くために ホルモン陽性HER2陰性の乳がんは、なぜ10年経っても再発するのか


