症状や副作用を極力抑えながら、延命を目指す がん難民にならない転移・再発乳がんの考え方
ホルモン感受性がない、著しい進行の場合に抗がん剤

ホルモン感受性のない人や進行著しい人は、抗がん剤による治療を行います。1次療法(最初の療法)はアドリアシン(一般名塩酸ドキソルビシン)、ファルモルビシン(一般名塩酸エピルビシン)などのアントラサイクリン系またはタキソール(一般名パクリタキセル)、タキソテール(一般名ドセタキセル)などのタキサン系の薬剤が使われます。
これらが効かなくなったら、2~3次療法としてはナベルビン(ビノレルビン)、ゼローダ(カペシタビン)などたくさんの薬剤があって、それらを組み合わせる療法も検討されています。ただ薬剤は豊富なのですが、どのような順序が良いのか、あるいはどのように組み合わせれば良いのか、それはまだわかっておらず、医療施設や医師によって使い方はまちまちです。
治療薬のなかにはハーセプチンという分子標的薬もあります。
乳がん患者の20~25パーセントは、がん細胞の表面にHER2というタンパク質が過剰に発現しており、これががんの増殖に重要な役割を果たしているとされています。このタンパク質のみに作用して、がんを増殖させないようにする薬剤としてハーセプチンが開発されたのです。副作用が比較的少ない分子標的薬の先駆けで、2001年の発売時には一般紙でも取り上げられるほど注目を浴びました。
がんの組織を調べてHER2が過剰に発現していればハーセプチンが効きますので、これを単独で使うか、もしくは他の抗がん剤と組み合わせて使います。組み合わせることの効果はまだ確認されておらず、これも医師によって使用法はまちまちだと言います。
岩瀬さんの場合は、副作用を少なくするために次のように行っています。
「僕はハーセプチンを単独で使います。それも毎週投与だと大変ですから、3週に1度の投与法を採用しています。ハーセプチンだけでコントロールできなくなったらタキサン系を、その次はナベルビンを組み合わせています」
ただし、アントラサイクリン系の抗がん剤を使うのであればハ���セプチンは使えないので、エピルビシン単独で使ったりします」
保険適応の薬剤の範囲はこの付近までだそうです。
延命効果の高い治療法がベストとは限らない

「これらの薬剤を上手に使い分ければ、延命やQOL維持は充分に期待できるでしょう」
岩瀬さんはそう言いますが、冒頭で紹介したように治療目的がはっきりしないまま日常生活に支障の出るような療法を行うケースが少なくないようです。
その多くは「なるべく長生きしたい」という患者さんの願いをもとに行われているようですので、セカンドオピニオン医は何も口を挟めないと言います。
そのようなケースを何例も見て岩瀬さんは、転移・再発乳がんの治療において、がむしゃらに延命期間の延長を求める医師の価値観には懐疑的になっています。
「今度の新しい抗がん剤はこれまでの標準薬より3カ月の延命効果がある、と患者を誘導する医師にも疑問を感じます」
統計的に生存期間が延びたといっても、転移性乳がんに対する抗がん剤の延命効果は数カ月程度です。
転移性乳がんの治療では延命効果と同時にQOLの維持がどの程度できるかについても知りたいところですが、そこまで踏み込んだ評価はさほど多くはないようです。
「ですから延命期間だけを見て、こっちがすぐれていると飛びつくのはいかがなものかと思います」(岩瀬さん)
2~3カ月の延命でもその差が大きいと感じる患者さんがいる一方で、それくらいの差だったら副作用の少ない治療法のほうがよいという患者さんも多いのではないでしょうか。そもそも化学療法を受けた人が延命したかどうかは判定ができません。
最近はその点に配慮して、QOLを加味した評価法が見直されているといいます。たとえば副作用などの理由で治療を中止するまでの期間を表すTTF(time to failure)といった指標です。
そういう指標に計算しなおしたデータが乳がんの治療法の評価でも採用されつつありますが、まだ少ないのが実情です。
「転移・再発乳がんでは、体を痛めつけるだけの強力な療法をやるのはやはりおかしいと思います。医師と治療法を相談する前に、残りの限られた時間をどう過ごすかはっきりして臨まないと、こんなはずではなかったと後悔することになりかねません」と岩瀬さんは強調します。
倦怠感、痛み、便秘などの症状が出れば緩和ケアを
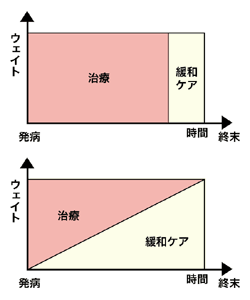
転移・再発乳がんの生存期間は、さきほど紹介したように薬物療法が効果的であれば長期生存も期待できるのですが、薬物はどれもがいずれは効果が薄れてきます。
つまり、いつかはがんが増殖してきます。原発巣から遠く離れた臓器への進展を止めるのも難しくなります。
このときに生じる痛みをはじめとする不具合の対策を、遅れることなくとれるようにしておくことが重要です。このときに頼りになるのが緩和ケア医です。
緩和ケア医は、終末期医療を担当する医師のように思われていますが、欧米では患者さんのQOLを維持する治療の専門医として見るのが一般的で、転移・再発が見つかれば自覚症状の有無に関わらず自動的に治療チームに加わります。その役目は次のようなものです。
がんが進んでいくと様々な症状がでてくるようになります。
たとえば全身倦怠感や食欲不振、痛み、胸水、腸閉塞、便秘、不眠、呼吸困難、うつ症状、混乱などで、どれもが患者さんのQOLを著しく損なうものです。
緩和ケア医は薬物や放射線、あるいは手術などの適応を考え、QOLを維持するようにするのです。
たとえば骨転移の痛みは放射線やビスフォスフォネートなどの薬を用いて鎮め、同時にがんの増殖を抑制して骨折に至らないように考えます。
「胸水がたびたび溜まって患者さんが苦しんでいる場合は、胸膜癒着術を行うこともあります。すると胸水が溜まりにくくなって、苦しさを緩和することが可能です」
抗がん剤の副作用で極度の食欲不振になり、体力の低下が懸念されるようなケースでは、薬剤を用いるなどして食欲を回復させ、治療に復帰できるように努めます。
「QOLを維持することは、日常生活をすこやかに送るうえでも重要ですし、予定した治療を完了するうえでも大事です。そのことは、ひいては延命にも貢献するのです」(岩瀬さん)
がん難民にならないためには早くから2人主治医制を
こういった緩和ケアの重要性をWHOでは重視し、その推進を強く訴えています。わが国では来年4月から施行される「がん対策基本法」に、早期のうちから緩和ケアを実施する必要性が明記されています。
にもかかわらず、わが国では、こういった本来の緩和ケアが軽んじられていて、いまだに終末期医療と見られがちなのが実態です。当の緩和ケア医もしくは施設も、抗がん剤などの治療を継続中の患者さんは、現状ではなかなか受け入れてくれないようです。
では、手立てがなくなった患者さんは、無条件で受け入れてくれるかというと、がん患者を受け入れるホスピスの絶対数はまだ少ないし、経済的な問題で入所できるとも限りません。がん患者さんの中でホスピスで生をまっとうすることができるのは全体の3~4パーセントに過ぎないという調査があります。
岩瀬さんはこう進言します。
「がん難民にならないためには、手立てがなくなってから緩和ケア医や施設を見つけるのでは遅すぎるのです。英国ではずっと早く、再発が判明したらすぐに緩和ケア医にもかかるのが普通です。つまりがん治療専門の医師と2人の主治医にかかりながら治療を続けるのです。
転移・再発した患者さんが残りの生をすこやかにまっとうするためには、こういった体制が必要ですが、まだわが国では整備されていませんので、そのような医療を受けたいという患者さんは、自発的にがん医療に理解のある緩和ケア医を探さなければなりません。
それはなかなか大変ですが、不可能ではありません。それが達成できれば、がん難民になる心配はなくなるのではないでしょうか」
同じカテゴリーの最新記事
- 新薬の登場で選択肢が増える 乳がんの再発・転移の最新治療
- SONIA試験の結果でもCDK4/6阻害薬はやはり1次治療から ホルモン陽性HER2陰性の進行・再発乳がん
- 乳がんサバイバーの再発恐怖を軽減 スマホアプリの臨床試験で世界初の効果実証
- 術後のホルモン療法は10年ではなく7年 閉経後ホルモン受容体陽性乳がん試験結果
- より推奨の治療法が明確化した「ガイドライン」 HR陽性、HER2陰性の進行・再発乳がんの最新治療
- 原発巣切除による生存期間延長効果の比較試験が進行中 試験結果が待たれるステージIV乳がんの原発巣手術の是非
- 血管新生阻害薬アバスチンの位置づけと広がる可能性 アバスチンと免疫チェックポイント阻害薬の併用が未来を拓く
- ホルモン陽性HER2陰性の進行・再発乳がんに、イブランスに続きベージニオも承認間近
- 長期戦の覚悟と対策を持って生き抜くために ホルモン陽性HER2陰性の乳がんは、なぜ10年経っても再発するのか


