渡辺亨チームが医療サポートする:乳がん骨転移編
12年前の手術で「治った」と思っていた乳がんに、骨転移の疑い
転移性乳がんに多い骨転移
渡辺 亨さんのお話
*1 腰痛
腰痛は様々な原因で起こります。若い人に多いのは主に腰を支える筋肉や靭帯など、慢性的な緊張や疲労から起こる筋膜性腰痛症ですが、中高年になると老化による変形性脊柱症、椎間板ヘルニア(いわゆるぎっくり腰)などが多くなりがちです。
女性の場合には、骨粗鬆症などの疾患が脊柱の骨の異常をもたらして起こる腰痛が少なくありません。骨のカルシウムの新陳代謝には、女性ホルモンが大きく関係していますが、閉経を控えて更年期に差し掛かると骨の量が減ってくるためにかかりやすくなるのが骨粗鬆症です。骨がもろくなっているために体重を支え切れずに圧迫骨折を起こす場合もあります。
一方、乳がんの既往のある人が、手術後何年経ってもけっして忘れてはいけないのは、骨転移によって起こる腰痛です。乳がんの転移臓器としては骨が最も多く、転移性乳がん患者の60~80パーセントには骨転移が認められ、いちばん多いのは脊椎への骨転移です。これにより骨破壊が進行すると痛みだけでなく、神経のまひ症状が出現したり、下半身不随になることもあります。乳がんにかかったことがある人は、原因不明の腰痛が長く続く場合、骨転移を疑う必要があります。
その他にも腰痛は、膵臓や腎臓などの内臓の病気、神経や血管の病気でもみられ、またストレスなどが引き金になった心因性のものもあります。痛みが長引くとき、安静にしていても痛みがとれないときなどには専門医の診察を受け原因を確かめることが必要です。
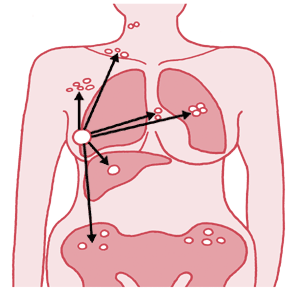
10年経っても再発する乳がん
*2 MRI

骨転移を示したMRI画像
磁場を使って体の成分である水素原子を運動させて、その運動の違いからいろいろな角度から輪切りにしながら連続的に撮影し、体内の詳細な画像をする検査です。放射線の被曝がなく、レントゲン検査では見分けの付きにくい部分もMRI検査で診断できる場合があります。
*3 乳がんの10年生存
がんが治ったかどうかは、一般に手術をしてから5年生存できたかどうかということを目安にしています。そのため「治る可能性」として、「5年生存率」を用いるのが普通です。
ところが、乳がんの治る割合は5年でなく10年生存率を用います。がんの性質は人間の性格が1人ひとり違うように、人によってやはり違いますが、乳が���はとくにそれが大きいのです。乳がんで再発する場合、70パーセントは手術から2~3年以内に起こりますが、あとの30パーセントの中には5年経っても10年経っても再発する例が含まれます。ですから、乳がんは手術後も長期にわたって根気よく観察する必要があります。そこで乳がんは10年経過したときを治った目安にしようと、10年生存率を用いることになったわけです。乳がん全体の10年生存率は75パーセントであり、比較的治りやすいがんといえます。しかし、しばしば10年を超えても再発することもあります。
血液の流れに乗って骨に転移する
渡辺亨さんのお話
*4 がんの骨転移
がん細胞が血液の流れに乗って骨に転移することを骨転移といいます。男性の場合、肺がんや前立腺がんの患者さんの4人に1人は骨転移を来たし、女性では乳がんの50~60パーセントに骨転移が認められます。このほか胃がん、子宮がん、肝がん、腎臓がん、膀胱がん、甲状腺がんなど、ほとんどのがんに骨転移が見られる場合があります。骨転移の転移先となるのは75パーセントが脊椎です。突然の腰痛から脊椎転移が先に発見され、原発巣が見つかるということも度々です。このほか骨転移は、大腿骨、骨盤、胸椎、腰椎など体を支える骨に目立ちます。
骨転移はまずこれらの骨の中心である骨髄にがんが転移し、外側の骨皮質に変性が生じて発症するのが一般的です。肺がんや乳がんなどでは骨が溶ける骨溶解性転移、前立腺がんなどでは骨が硬くなる骨形成性転移というタイプの転移を示すことが多くなります。
骨転移を生じると痛み、骨折、脊髄神経の圧迫、高カルシウム血症など来たし、患者さんのQOLを著しく悪くしてしまいます。同じ骨転移でも、肺がんの骨転移の患者さんの生存期間は平均6カ月以下ですが、乳がんや前立腺がんの場合は、ホルモン剤や多剤併用化学療法によって軽快することが少なくありません。
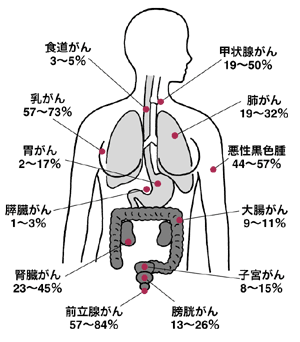
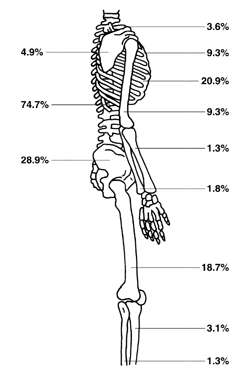
*5 術後補助療法
乳がんの手術で完全にがんが取り切れたと考えられる場合でも、目に見えないようながん細胞が全身に残っている可能性があります。そのために、がんの再発の可能性を低くするために手術を補う治療を行う場合があり、それを術後補助療法といいます。術後補助療法には、ホルモン剤を使うホルモン療法と抗がん剤療法、放射線治療があります。ホルモン療法や抗がん剤療法には、いろいろな薬剤の組み合わせがあり、患者の年齢、がんの性質、進行度合いに応じて、患者にとって最も適切な治療法が選ばれます。
乳がんの治療は「乳腺外科」で
渡辺亨さんのお話
*6 骨粗鬆症と骨転移の区別

骨シンチグラフ。ほぼ全身の骨に転移している
骨粗鬆症の症状と骨転移の症状は似ていて、また単純X線写真ではほとんど違いが現われず整形外科クリニックなどでは区別がつけられないこともしばしばあります。がんの骨転移が疑われる場合は、大きな病院を受診してMRIや骨シンチという検査などを受ける必要があります。
骨粗鬆症では骨量が減るだけでは痛みが現れることはなく、脊椎圧迫骨折などの骨折を来たして激痛を覚えることになります。この骨折による激痛は発症から1~2週間で徐々に軽快し、3週間でほぼ治まるのが普通です。これに対して、がんの骨転移では徐々に痛みが増悪することが多くなります。
*7 乳腺外科
乳がんの治療法には、乳房温存療法や切除手術、さらに抗がん剤、ホルモン療法と、様々ありますが、病院や医師によっても治療法は異なっています。最適な治療を受けるためには、乳がん治療の専門医がいる「乳腺外科」という診療科を受診してください。ただし、厚生労働省は医療機関が標ぼうできる38の診療科の中にはまだ「乳腺外科」を入れていません。このため、医療機関は誰でも目に触れる屋外看板には「乳腺外科」と掲示できないのが実情です。
*8 骨転移への放射線治療
骨転移の痛みを軽減する目的で放射線治療を行うことがあります。80~90パーセントの方で痛みが軽くなり、半分くらいの方がほとんど痛みを感じなくなります。
同じカテゴリーの最新記事
- 新薬の登場で選択肢が増える 乳がんの再発・転移の最新治療
- SONIA試験の結果でもCDK4/6阻害薬はやはり1次治療から ホルモン陽性HER2陰性の進行・再発乳がん
- 乳がんサバイバーの再発恐怖を軽減 スマホアプリの臨床試験で世界初の効果実証
- 術後のホルモン療法は10年ではなく7年 閉経後ホルモン受容体陽性乳がん試験結果
- より推奨の治療法が明確化した「ガイドライン」 HR陽性、HER2陰性の進行・再発乳がんの最新治療
- 原発巣切除による生存期間延長効果の比較試験が進行中 試験結果が待たれるステージIV乳がんの原発巣手術の是非
- 血管新生阻害薬アバスチンの位置づけと広がる可能性 アバスチンと免疫チェックポイント阻害薬の併用が未来を拓く
- ホルモン陽性HER2陰性の進行・再発乳がんに、イブランスに続きベージニオも承認間近
- 長期戦の覚悟と対策を持って生き抜くために ホルモン陽性HER2陰性の乳がんは、なぜ10年経っても再発するのか


