渡辺亨チームが医療サポートする:副作用対策編
脱毛、口内炎、更年期障害の苦しみは、こうして乗り越えた
渡辺亨さんのお話
*1 制吐剤の予防的投与
抗がん剤による悪心・嘔吐を1度経験すると、それが条件付けられて、次回からも抗がん剤投与の度に「また吐いてしまう」「苦しい思いをしなければならない」という思いに取り付かれて、それがさらに吐き気を引き起こすことになりがちです。逆に最初に悪心・嘔吐を起こらなかったり軽く抑えられれば、「自分は平気」という自信になります。
こうしたことを考えて、抗がん剤を投与するとき、より早期に制吐剤を投与して、きちんと悪心・嘔吐をコントロールするようにしてきました。
*2 発熱
抗がん剤治療を受けると白血球中の好中球が低下し、細菌感染から発熱することが少なくありません。これに対してシプロキサン(一般名塩酸シプロフロキサシン)という抗生物質などが予防的に処方されることがあります。
*3 脱毛
頭皮の毛根細胞は、造血器官、口の中や消化管の粘膜などとともに活発に細胞分裂をする部分なので、抗がん剤によりダメージを受けやすく、脱毛が起こりがちです。抗がん剤治療による脱毛は、いわゆる若はげのようにパラパラと髪が抜けていくのではなく、ごそっといっきに抜けていきます。ただし、薬剤の種類や投与量などにより、軽いものから、頭髪が完全に抜けてしまうものまでさまざまです。
| アルキル化剤 | シクロホスファミド イホスファミド |
|---|---|
| 抗がん性抗生物質 | アクチノマイシンD ドキソルビシン(アドリアマイシン) ダウノルビシン エピルビシン イダルビシン アムルビシン |
| ビンカアルカロイド | ビンクリスチン ビンデシン ビノレルビン |
| 植物由来 | エトポシド イリノテカン パクリタキセル ドセタキセル ノギテカン |
髪の毛の成長サイクルは成長期→退行期→休止期とあり、普通の脱毛は、髪が休止期に入って起こるものです。これに対して抗がん剤を使用した場合は、毛母細胞がダメージを受けて成長期の状態で抜ける頭髪も出てくると考えられます。この成長期に抜ける頭髪は、まるで動物の冬毛と夏毛が生え変わる時期のように、いっきに脱毛が進み、数日間で抜けきることもあります。
ただし、抗がん剤の毛母細胞への影響は一時的なので、まもなくまた細胞分裂が始まり、新しい髪の成長期に向かいます。3~6カ月のうちに再発毛が生えてきて、髪の毛はいっきに生え変わってくるのです。再発毛は最初は赤ちゃんのような細い産毛状ですが、必ず元通りの髪になっていきます。
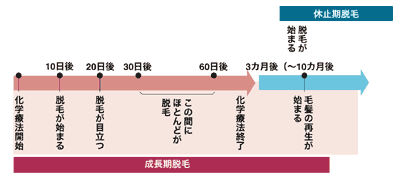
*4 脱毛のケア
抗がん剤による脱毛は、予想していても、実際に起こることはとてもショックです。しかし、いつ頃、どのように髪が抜けるか、また、必ず元に戻るということがわかっていると、脱毛時のショックはかなり和らげることができます。脱毛に備えてかつらやスカーフ、帽子など必要な物品を用意しておくことは、心の準備という面でも大切なことです。
かつらやスカーフなどは、頭皮を外傷や直射日光から保護する頭髪の代わりをする役割もあります。専用の医療用かつらというものもあり、とくに頭皮を保護する機能に優れています。
実際に脱毛が始まったら、寝ているうちに抜けた髪が散らばらないように、また頭皮を守る意味でもナイトキャップをします。毛が抜けるのを恐れてシャンプーを嫌がる人もいますが、それは必ず再生する髪なので抜けるのを恐れる心配は無用です。頭皮が不潔になると毛嚢炎という感染症などにかかりやすくなるため、髪が抜けているときほどきちんとシャンプーをしてください。
*5 口内炎
口の中にある粘膜の上皮細胞は細胞分裂が速く進み、細菌を除去して清潔さを保つバリヤーの役割を果たしています。ところが、抗がん剤は細胞分裂の速いがん細胞をターゲットにした薬であることから、口腔粘膜の細胞も攻撃を受けることになり、口内炎が現れやすいのです。とくにメソトレキセート(一般名メトトレキサート)、5-FU(一般名フルオロウラシル)などは、口内炎を起こしやすい抗がん剤として知られています。
口内炎の発生は、口腔粘膜上皮の細胞周期と関連しており、一般的には抗がん剤投与後5~10日で出現します。口腔粘膜は通常7~14日サイクルで再生しており、回復までに通常2~3週間を要します。
口内炎に対しては、まず痛みをとる治療を行い、消毒や消炎のうがい薬、クリームなどが処方されます。また、粘膜損傷のもとになる刺激物を取り除き、やわらかいナイロンブラシを使ってブラッシングを丁寧に行ったり、うがいをしたり、また飴や氷片などを用いて口の中が乾燥しないようなセルフケアが必要です。口内炎の痛みがあるとこうしたセルフケアを敬遠しがちになってしまうことから、さらに口内炎を悪化させてしまうことがあります。
*6 性機能障害
抗がん剤治療を受けると性機能障害を受けることが少なくありません。乳がんの薬物療法であるCEF療法で用いるエンドキサン(一般名シクロホスファミド)などのアルキル化剤には、卵巣毒性が数多く報告されています。
性機能障害は女性の場合は月経不順、過少月経、無月経などの症状を示します。多くの場合、抗がん剤治療による無月経は一過性のものですが、30代後半以降の患者さんでは性機能が回復せずにそのまま月経が停止することがあります。
もちろん男性が抗がん剤を受けた場合も、無精子症などの性機能障害が現れることが少なくありません。治療を始める前の十分なインフォームドコンセントが必要です。
| 治療法 | 年齢 | 危険性 |
|---|---|---|
| CMF,CEF,CAF×6コース(乳がん治療) (C:シクロホスファミド,M:メトトレキサート,F:フルオロウラシル,A:ドキソルビシン(アドリアマイシン),E:エピルビシン) | 40歳以上 | 高リスク(>80%) |
| 30-39歳以上 | 中等度リスク | |
| 30歳未満 | 低リスク(<20%) | |
| AC×4コース(乳がん治療) (A:ドキソルビシン(アドリアマイシン)/C:シクロホスファミド) | 40歳以上 | 中等度リスク |
| 40歳未満 | 低リスク(<20%) |
*7 更年期障害
ほてりや冷や汗、抑うつ感などの更年期障害と呼ばれる症状が出現します。また、女性ホルモンが低下する経過で骨塩量の低下から骨粗鬆症などを発症しやすくなり注意が必要です。
*8 2次がん
2次発がんは、抗がん剤や放射線治療後に発生するがんで、化学療法に伴う慢性毒性としては最も重篤なものです。がん治療の進歩により長期生存例や治癒症例が増加したことによって、2次発がんは増えています。2次発がんとして多いのは、白血病、膀胱がん、非ホジキンリンパ腫、骨肉腫などです。
2次発がん発症に注意をしなければならない薬物は、アルキル化剤、エトポシド、タモキシフェンなどです。ただし、第1のがんが発症したこと自体が2次発がんの危険因子になるので、2次発がんが治療の影響かどうかは断定できないという問題があります。
これまでの臨床経験から、抗がん剤治療ではできる限り2次がんの発生を抑えられる投与メニューを考えるようになってきました。
| 薬剤名 | 2次がん | |
|---|---|---|
| 抗がん剤(単独) | メルファラン(アルケラン) | 急性白血球 |
| シクロホスファミド(エンドキサン) | 膀胱がん、悪性リンパ腫、急性白血病 | |
| ブスルファン(マブリン) | 急性白血病、乳がん | |
| クロラムブシル※ | 肺がん、急性白血病 | |
| メトトレキサート(メソトレキセート) | 皮膚がん | |
| チオテバ(テスパミン) | 急性白血病 | |
| ロムスチン※ | 急性白血病 | |
| アザチオプリン(イムラン、アザニン) | 悪性リンパ腫、皮膚がん | |
| ホルモン剤 | ジエチルスチルベストロール※ | 腟がん(次世代)、子宮内膜がん |
| タモキシフェン(ノルバデックス) | 子宮体がん |


