「日本の治療になじんだガイドライン」は、はたして最良の治療か!? 卵巣がん、子宮体がんに遅れて、子宮頸がんに初の治療指針
欧米データを取り入れると現場は混乱する!?
こうした彼我の相違点が問題視され、日本にはエビデンスが少ないということで、本当に「外国のデータをそのまま日本人に適応できない」のだろうか。
先の宇田川さんが言う。
「日本の子宮頸がん治療は、かねてより先人たちによって開発された根治性の高い術式である広汎子宮全摘出術が行われてきました。一方、欧米では放射線を中心に治療が進歩してきました。したがって欧米の指針を踏襲するのは意味がなく、日本では日本の治療になじんだ指針でなければならないのです」
今回のガイドラインは、日本の医師をはじめ、医療界のみんなに認められ、受け入れられるものでなくてはいけないといい、その理由として、作成委員会は「欧米のデータをそのまま取り入れ、もし同時化学放射線療法を推奨するということになった場合、実際には手術を行う医師が多いわけで、それをがらっと変えていくと、現場ではかなり混乱するという事情がある」と弁解する。
しかし、この「事情」は、どこかおかしくないだろうか。
ガイドライン作成委員会は、ガイドラインの目的を「本来、国内外の科学的エビデンスに基づいて書き進めていくもので、それにより治療レベルの均霑化=恩恵や利益が等しく受け入れられること=が図られる」と述べている。
ところが、このガイドラインでは、エビデンスのある化学放射線療法よりも、エビデンスのない手術療法を推奨しており、この目的と矛盾している。しかも「医療界の混乱」を回避するために、そうしたのだとしたら、うがった見方をすると、あたかも婦人科医の職域を保持しようとするもので、それは、「医療者のための」ガイドラインであって、「患者のための」ガイドラインではないということになるのではなかろうか。
もう1つは、日本でも、ここ数年の間にいくつかの医療施設で手術に代わって放射線治療や化学放射線療法が採用され普及し始めていることだ。例えば1b期の治療では、2002年を境に海外の放射線治療を見習って日本でも行うようになり、2005年までの放射線治療は約1割程度。2b期にいたってはもっと多く、放射線治療が4割にもなっている。
今回のガイドラインは、この流れに逆行し、ブレーキをかけるのではないかと危惧する。
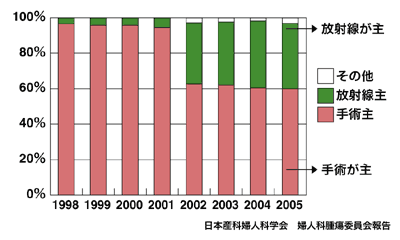
患者サイドに立ってみると疑問が……
現在、子宮頸がん患者の9割近くが手術で切除されている。放射線などで治療するのは、高齢者や糖尿病、高血圧などの合併症のために手術ができない患者に限られてきた。作成委員会は、手術療法と放射線治療とで、その後の副作用が異なってくることを指摘している。
たとえば若い人の場合、放射線を当てると卵巣の働きを失ってしまうが、手術では卵巣を残すことができ、働きも失わないで済む。また、腟の粘膜が少し固くなり、性交障害を起こしやすい、といった有害事象も考えなければいけない。
一方、手術療法では排尿障害といった副作用も考えられるが、神経温存術式に対する多くの工夫がされてきているので、有害事象は少しずつ減ってきている、というが、ここには明らかに放射線治療に不利な説明がなされている。
子宮頸がん治療で手術を施された患者の多くは、排尿・排便障害を始め、性機能障害、リンパ浮腫など、さまざまな副作用に苦しめられているのが実情で、施設によってはこれらの術後のケアもまだまだ行き届いていない。放射線を当てると卵巣の働きを失ってしまうという指摘も、現在は卵巣を吊上げて照射するなど、機能を失わない方法も可能になっている。放射線治療でも卵巣を残すことができるのに、ガイドラインでは、そうした放射線治療のメリットが隠されているのだ。
患者の立場に立った改訂版の発刊を早急に望む
今回のガイドラインは、本文構成をQ&A形式にして、各クエスチョンに対して推奨の文面があり、その推奨のグレード(推奨の強さ)をAからEまでの6段階で示している。
たとえば「上皮内がんに対して、至適な手術方法は何か?」という設問に対し、推奨:子宮頸部円錐切除術が推奨されるとして、グレードはBと示されている。
ちなみにAは「絶対的な自信あり」、Bは「まあ自信あり」、Cは「このへんが妥当か」、Dは「わかっていません」ということを意味する。別立ての説明としてA´、Eを挙げ、前者は「明確なエビデンスは見いだせないが、臨床腫瘍学の常識」であり、後者を「明確なエビデンスは見いだせないが、委員会のコンセンサス」であることを示している。
今回のガイドラインでは、化学放射線療法は推奨基準Bとしているのは前述の通り。数年前には子宮頸がんの治療はほとんど手術で、放射線治療や化学放射線療法が行われる余地がまったくなかったことを思えば、推奨度は少々低くても、治療選択の1つに取り上げられたことは一定程度評価はできる。が、患者の立場に立った医療を考えると、ガイドラインでは、エビデンスレベルから見れば、せめて手術と同等のグレードに近づけてほしいものである。
その意味で、今回の指針は、最良の治療法にはなっていないといえるかもしれない。
作成委員会は、本指針をあくまでも現時点でのコンセンサスであり、3年ごとに改訂し、グレードアップさせていくとしているが、3年とはいわず、患者の立場に立った改訂版を早急に発刊してほしいものだ。
同じカテゴリーの最新記事
- 1次、2次治療ともに免疫チェックポイント阻害薬が登場 進行・再発子宮頸がんの最新薬物療法
- AI支援のコルポスコピ―検査が登場! 子宮頸がん2次検診の精度向上を目指す
- 第75回日本産科婦人科学会 報告 ~慈しみの心とすぐれた手技をもって診療に努める(慈心妙手)が今年のテーマ~
- HPV9価ワクチンが定期接種に! 子宮頸がんはワクチン接種で予防する
- 自己採取HPV検査とHPVワクチンの持続感染予防効果を検討 〝子宮頸がん撲滅〟を目指す2つの臨床研究~福井大学
- 定位放射線療法を併用した臨床試験も進行中 子宮頸がんの化学放射線療法
- 受診率アップのためには若い世代への意識付けが肝要 大学生に対する子宮頸がん検診啓発活動を実施~福井県
- 世界80カ国以上でHPVワクチンは定期接種に 子宮頸がんは、検診とワクチンで予防できる!
- 子宮体がん、子宮頸がんにおけるダヴィンチ手術の現状と今後 子宮体がんがダヴィンチ手術の保険適用に


