妊娠・出産、治療後の合併症など、患者さんの立場を考えた治療選択を 子宮頸がんの治療は、手術だけでなく、放射線や化学療法も考慮
妊娠・分娩への影響がない光線力学的療法
患者さんが妊娠・分娩を希望している場合、0期なら、光線力学的療法という選択肢もある。標準治療ではないが、妊娠・分娩に及ぼす影響がほとんどないのが特徴だ。
この治療法では、まずフォトフィリンという光増感物質を注射する。この物質は、正常組織より、がんにたくさん取り込まれる性質がある。そこで、がんのできている部位にレーザーを照射すると、感受性の高まっているがん組織が、大きなダメージを受けることになるわけだ。
「食道がんなど、表在性のがんの治療にも使われている治療法です。がんの治癒率は円錐切除術を行ったときと同じですが、妊娠・分娩に与える影響に関しては、この治療法なら問題ないといわれています。」
ただし、この治療を行っている医療機関は、それほど多くない。静岡県立静岡がんセンターでも行っていないため、0期か1a1期で妊娠・分娩を希望している患者さんには、光線力学的療法を行っている施設を紹介することもあるという。
もっとも、光線力学的療法には欠点もある。治療後もしばらくは光増感物質が体内に残るため、1カ月ほど入院して、暗い部屋で過ごさなければならないのだ。
「光増感物質は正常組織にも多少は入るため、強い光に当たると、そこがやけどをしたような状態になってしまいます。それを避けるために、暗い部屋で過ごすのですが、1カ月ですからなかなか大変です」
2~3日の入院ですむ円錐切除術に比べると、1カ月の入院はさすがに長い。妊娠・分娩への影響では光線力学的療法が上だが、入院期間では円錐切除術に分がある。総合的に見れば、どちらにも一長一短があるということだろう。
やや進んだ1a期では、準広汎子宮全摘術が適応
1a1期の標準治療は単純子宮全摘術だが、それよりもやや進んだ1a2期になると、準広汎子宮全摘術と骨盤内リンパ節郭清が行われている。これが日本における標準治療となっているのだ。
「準広汎というのは、やや広く取るということ。子宮だけでなく、周囲に組織を少しつけて切除します。具体的にいうと、子宮の入口部分の組織をつけて、腟をちょっと長めに取ります」
この準広汎子宮全摘術を行い、骨盤内のリンパ節を郭清するのだが、卵巣は残すので、閉経前の女性であれば女性ホルモンは普通に分���されることになる。単純子宮全摘術に比べると、手術は少し大変になるが、この段階でも治療成績はきわめて高い。
さらに進行した1b1期~2b期では、日本では広汎子宮全摘術が最もよく行われている。子宮と周囲の組織、それに腟の一部も切除し、リンパ節郭清を行う手術だ。病状によっては卵巣の温存も行われている。
「もともと日本で開発された手術法ということもあって、日本では、1b1期~2b期の治療としては、この手術が行われるケースが多いですね。大部分の患者さんがこの手術を受け、合併症などがあって手術できない人が、放射線治療に回される、という流れになっている施設がほとんどです」
しかし、1b1期~2b期の場合、手術でも放射線治療でも治療成績は同等という臨床試験の結果が報告されているという。それなのに、日本では放射線治療を受ける人はごく一部でしかない。あくまで手術が主役で、放射線治療は脇役に回っている状況だ。
欧米の状況は、日本とはかなり異なっているようだ。
「同じ進行期の子宮頸がんでも、欧米では放射線治療を受ける人がもっと多く、特にアメリカでは、多くは放射線治療という状況になっています。いろいろな理由が考えられますが、手術と放射線治療の治療成績が同等だという臨床試験の結果も、重要な根拠になっていることは確かです。放射線治療と手術を直接比較した臨床試験は、実は1つしかありません。この成績を根拠として、日本はなぜそんなに手術にこだわるのだ、という意見も聞かれます。」
ただ、厳密にいうと、欧米で行われている子宮頸がんの手術と、日本で開発され日本で広く行われている広汎子宮全摘術とは、必ずしも同じものではないという。日本で行われている手術のほうが、欧米で行われている手術に比べ、優れた治療成績をあげる可能性もあるわけだ。しかし、残念なことに、日本では広汎子宮全摘術と放射線治療を直接比較した臨床試験を行ってこなかった。そのため、信頼できるエビデンスがないのが現状なのだ。
「欧米人と日本人の体型の違いも関係していると思います。太った人に大きな手術を行うと、血栓症などの合併症が増えます。そのため、肥満した人だと、放射線治療のほうが比較的安全かもしれません。欧米で放射線治療を受ける人が多く、日本では手術を受ける人が多いのには、そういった違いも関係していると思います」
患者さん自身が治療法を選択できるシステム
しかし、静岡県立静岡がんセンターでは、エビデンスに沿って治療が進められている。1b1期~2b期の患者に対しては、放射線治療科と婦人科から、放射線治療と手術の説明が行われる。その上で、患者さんがどちらかを選択するシステムになっているのだ。
「原則に従って治療法が選択できるようになっているわけですが、このような形をとっている病院は、日本でも数少ないと思います」
また、大きな腫瘍の場合や2b期では後で紹介する化学療法と放射線治療を併用した治療法が行われている。
治療法を選択するときには、治療成績だけでなく、治療による合併症というマイナス面にも目を向ける必要がある。
手術の場合、最大の問題は排尿障害。尿が出にくくなることがあるのだ。また、リンパ節郭清を行うため、リンパ浮腫で脚がむくみやすくなるという。
放射線治療では、晩期症状として、腸から出血したり、腸に穴が開いたりすることがある。晩期症状というのは、放射線治療後、半年から数年して現れる副作用だ。また、治療期間が6週間と長いのも、放射線治療の弱点といえるかもしれない。
放射線治療で卵巣機能を温存したケースもある
放射線治療の方法についても解説しておく必要があるだろう。子宮頸がんの放射線治療は、体の外から照射する外照射と、子宮の内部から照射する腔内照射を併用するのが基本だ。腔内照射は、子宮内のがんができている部位に小さな線源を挿入し、線源から照射される放射線で治療する方法。この治療を行うためには、特殊な治療室と設備が必要になる。その設備がなければ行えない治療法だ。
「外照射だけより、外照射と腔内照射を組み合わせたほうが、治療成績がよいというデータが出ています。放射線治療を受けるのであれば、腔内照射のできる施設を選ぶべきでしょうね」
広汎子宮全摘術では卵巣を切除するが、放射線治療でも卵巣に放射線がかかるため、卵巣機能は失われてしまう。ただ、卵巣機能を残すことも不可能ではないそうだ。
「これまでわずか2例ですが、卵巣を移動させる手術を行い、放射線の当たらない部位にずらしてから放射線治療を行ったケースがあります。若い患者さんだったのですが、卵巣をずらしたことで、放射線が当たらず、卵巣機能を温存することができました。女性ホルモンが分泌されるので、更年期症状のような合併症が起こらずにすみます。特殊な例ですが、若い人が放射線治療を受けるときには、このような治療も可能ではあります」
卵巣を移動させる手術は、技術的には簡単だという。若い患者さんが増えているだけに、今後はこのような治療が、広く行われるようになる可能性はあるだろう。
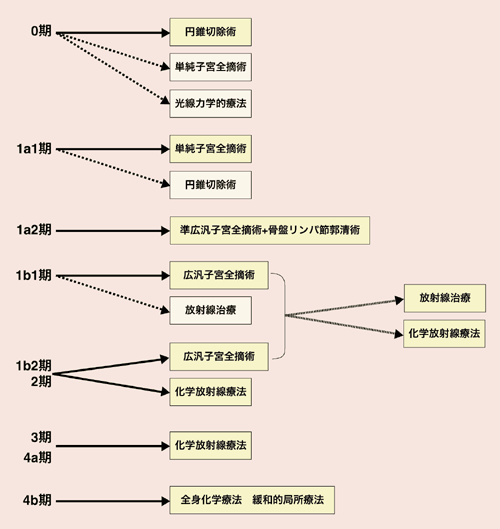
同じカテゴリーの最新記事
- 1次、2次治療ともに免疫チェックポイント阻害薬が登場 進行・再発子宮頸がんの最新薬物療法
- AI支援のコルポスコピ―検査が登場! 子宮頸がん2次検診の精度向上を目指す
- 第75回日本産科婦人科学会 報告 ~慈しみの心とすぐれた手技をもって診療に努める(慈心妙手)が今年のテーマ~
- HPV9価ワクチンが定期接種に! 子宮頸がんはワクチン接種で予防する
- 自己採取HPV検査とHPVワクチンの持続感染予防効果を検討 〝子宮頸がん撲滅〟を目指す2つの臨床研究~福井大学
- 定位放射線療法を併用した臨床試験も進行中 子宮頸がんの化学放射線療法
- 受診率アップのためには若い世代への意識付けが肝要 大学生に対する子宮頸がん検診啓発活動を実施~福井県
- 世界80カ国以上でHPVワクチンは定期接種に 子宮頸がんは、検診とワクチンで予防できる!
- 子宮体がん、子宮頸がんにおけるダヴィンチ手術の現状と今後 子宮体がんがダヴィンチ手術の保険適用に


