妊娠・出産、治療後の合併症など、患者さんの立場を考えた治療選択を 子宮頸がんの治療は、手術だけでなく、放射線や化学療法も考慮
3a期~4a期は化学放射線療法
3期まで進行した場合には、もう手術は行われない。3a期~4a期では、放射線治療と化学療法を同時に行う化学放射線療法が標準治療とされている。
「この進行期のがんには、かつては、日本でも欧米でも放射線治療が行われてきました。ところが、1999年に、放射線治療単独よりも、放射線治療に化学療法を併用したほうが治療成績が優れているとする論文がいくつも発表され、その治療法が世界標準になったわけです」
放射線治療は約6週間かかり、この間、週5回の治療が行われる。外照射だけで行われることもあるが、やはり外照射と腔内照射の併用が基本だ。
この放射線治療に、シスプラチン(商品名ブリプラチンもしくはランダ)の毎週投与を組み合わせるのが、日本で一般的に行われている方法である。
もともとの臨床試験では、「シスプラチンの毎週投与」だけでなく、「5-FU(一般名フルオロウラシル)+シスプラチンの3週に1回投与」でもよいことになっていた。両者の治療成績には差がないというデータが出ていたのだ。
「それなら、シスプラチンの毎週投与のほうが副作用も軽く、患者さんにとって楽だろうということで、こちらが一般的になってきました。アメリカでも、この方法に傾きつつあるようです」
シスプラチンは比較的強い副作用がある抗がん剤だ。しかし、この併用療法で使用される量は、通常の化学療法で使われる1回量に比べると、ほぼ半分程度ですむ。放射線治療と併用するので少なくていいのだが、使用量が少ないことにより、あまり強い副作用は出ないようだ。
「現在標準治療として行われている化学放射線療法ですが、この治療を放射線治療単独より有効とする臨床試験は、すべて欧米のものです。実は、日本と欧米では、放射線のかけ方も同じではありませんし、臨床試験における進行期の決め方も微妙に違います」
たとえば、進行期の決め方だが、報告されている臨床試験では、腹部のリンパ節は腹腔鏡を使ってリンパ節生検を行っているという。それに対し、日本の医療現場では、腹部のリンパ節はCTかMRIで評価するのが一般的。腹腔鏡まで使ってリンパ節生検をすることはまずない。
「報告されているのは、しっかりした臨床試験です。その試験で出た、化学放射線療法がいいという結果は信頼できます。問題は、それをそのまま日本の現状に当てはめてしまっていいのか、という点ですね。日本の3a期~4a期の患者さんの場合、シスプラチンを加えることで本当に治療成績が向上するかどうか、厳密に言えば、答えはまだ出ていません。日本の現状に合わせた臨床試験は行われていないので、現在の段階では、欧米のデータを無視できないという状況なのです」
これまで日本では、放射線治療と化学放射線療法とを比較する臨床試験が行われずにきた。今後は、日本で行われている化学放射線療法についての効果を確認する試験を行わなければならないだろう。
全身に転移した場合はQOLの維持も重要
全身に転移した状態が4b期だ。この段階では、全身治療としての化学療法が必要となる。シスプラチンを中心とした化学療法などが行われるが、治療成績はあまりよくない。
「子宮頸がんは、抗がん剤がさほどよく効くがんではありません。そのため、化学療法に大きな期待を寄せることはできないのです。また、再発例や4b期の平均生存期間は、現状では1年程度。完治する人がゼロというわけではありませんが、積極的に治しにいく治療だけが重要なわけでもありません。状況によっては、治すことではなく、QOL(生活の質)を低下させないことを目的とした治療も行われます」
たとえば、化学療法を行いながら、必要に応じて放射線治療を併用する治療が行われることがある。たとえば、性器出血がある場合、そのコントロール目的で放射線を利用するのだ。転移巣の痛みが強い場合には、その痛みを解消するための放射線治療が行われることもある。
同じように放射線と抗がん剤と使う治療でも、3a期~4a期の化学放射線療法とは、まったく異なる治療なのだ。4a期までは間違いなく治癒を目指す治療だが、4b期になると、症状をコントロールし、QOLを低下させないことが中心になっている。
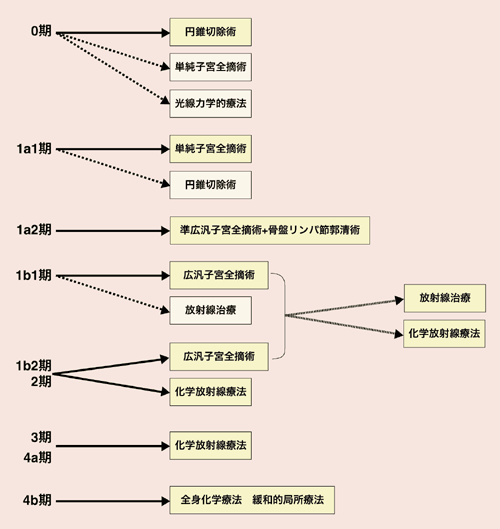
検診率の向上とワクチンに期待
子宮頸がんは、検診が普及することで早期発見されるケースが増え、それが治癒率の向上をもたらしてきた。しかし、検診の受診率は頭打ち状態で、早期発見される率も上がっていないという。
「検診が始まったのは1960年代。それからしばらくは、検診の受診率はどんどん上がっていき、それに伴って早い段階で発見される人が増えていきました。
しかし、1980年代後半から1990年代にかけて、受診率は伸びなくなり、その頭打ち状態が現在も続いています。検診の対象が、かつての30歳以上から20歳以上に引き下げられているのですが、検診受診率は上がっていません」
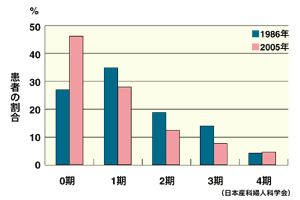
[子宮頸がんの5年生存率]
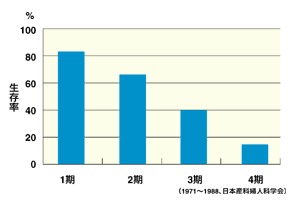
検診が進めば、確実に治療成績は向上することになる。受診率の向上が、子宮がん対策としては最も重要なことだという。
「現在、0期と1期で発見される患者さんが、全体のほぼ7割程度です。0期や1a期なら、ほとんど治りますし、1b期の5年生存率が、日本全体の集計でだいたい70パーセントくらい。がんを専門にしている病院なら、もう少し高くなるでしょう。つまり、1期までに発見していれば、まあまあ悪くない治療成績と言えます。検診の受診率を上げることで、この段階で発見される人を増やすことが重要ですね」
検診の受診率向上とともに、これからの子宮頸がん対策として期待されているのがワクチンだ。子宮頸がんの発症には、ヒューマン・パピローマ・ウイルス(HPV)の感染が深く関係している。このウイルスのワクチンの開発が進められており、現在、治験が行われている段階だという。
「HPVワクチンがいつ実用化されるか、はっきりしたことはわかりませんが、たぶんあと数年でしょう。このワクチンによって、子宮頸がんをとりまく状況は大きく変わると思います。将来的には、子宮頸がんの撲滅も夢ではないかもしれません」
将来の展望は明るいが、現時点での子宮頸がんの治療には、まだまだ問題が少なくない。まずは日本の実情に合わせた臨床試験が、国内で行われることを期待したい。
同じカテゴリーの最新記事
- 1次、2次治療ともに免疫チェックポイント阻害薬が登場 進行・再発子宮頸がんの最新薬物療法
- AI支援のコルポスコピ―検査が登場! 子宮頸がん2次検診の精度向上を目指す
- 第75回日本産科婦人科学会 報告 ~慈しみの心とすぐれた手技をもって診療に努める(慈心妙手)が今年のテーマ~
- HPV9価ワクチンが定期接種に! 子宮頸がんはワクチン接種で予防する
- 自己採取HPV検査とHPVワクチンの持続感染予防効果を検討 〝子宮頸がん撲滅〟を目指す2つの臨床研究~福井大学
- 定位放射線療法を併用した臨床試験も進行中 子宮頸がんの化学放射線療法
- 受診率アップのためには若い世代への意識付けが肝要 大学生に対する子宮頸がん検診啓発活動を実施~福井県
- 世界80カ国以上でHPVワクチンは定期接種に 子宮頸がんは、検診とワクチンで予防できる!
- 子宮体がん、子宮頸がんにおけるダヴィンチ手術の現状と今後 子宮体がんがダヴィンチ手術の保険適用に


