渡辺亨チームが医療サポートする:子宮頸がん編
ステージ2aの扁平上皮がん。子供はあきらめなければならないの?
10代、20代の女性に増えている
喜多川亮さんのお話
*1 子宮頸がんの好発年齢
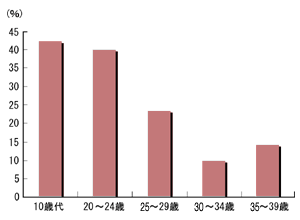
子宮頸がんはかつて子宮がんのうち90パーセントくらいを占めていましたが、子宮体がんが増えてきた今でも65パーセントくらいをしめています。罹患率は、減少してきているとはいえ、日本の婦人科がんの中では最も多い疾患です。
子宮頸がんが見つかる年齢は、かつては60歳以降が多かったのですが、最近は、若年者が増えており、30~40歳前後で見つかることも多く、20歳代での発症も珍しくありません。10歳代の女性からでも、子宮頸がんになる前の「前がん状態」と呼ばれる状態で見つかるケースも増えています。
子宮頸がんはヒト・パピローマウイルス(HPV)という、ウイルスが原因のひとつであることがわかってきました。これは、一種の性感染症と考えられており、初交年齢の若年化、多数のセックスパートナーなどが重要な原因になっていると考えられます。
| ●子供を多く産んだ女性 |
| ●セックスパートナーが複数の女性 |
| ●初めてのセックスが若い女性 |
| ●喫煙者 |
| ●ビタミンA、Cの少ない食事 |
| ●経口避妊薬(ピル)服用者 |
| ●免疫系の低下している女性 |
このため、現在、30歳以上を対象としている子宮頸がん検診が、20歳以上を対象とする方向性に進みつつあります。
子宮頸がん検診では、子宮頸がんの発生しやすい部位を綿棒やヘラで軽くこすって細胞を採取します。この細胞を、*パパニコロウ法という方法で染色し、顕微鏡で調べて、がんがあるかないかを調べる*細胞診を行います。
子宮頸がん細胞診は、*正診率は80パーセント程度ですが、本当は、がんであるのにがんでないという結果がでる、「偽陰性」の率は1パーセント未満とたいへん低く、少しでも疑いのある患者さんを見落とさない、という検診の目的に適した検査といえます。患者さんに負担が少なく、しかも見落としが少ないため、子宮頸がん検診は広く普及しています。
検診の普及、衛生環境の改善、性教育の普及により、日本を含めた先進国での子宮頸がんの発生頻度と死亡率はこの50年間でともに4分の1にまで減少したと言われています。なお、自己採取で検査する細胞診もあり��すが、正しく採取できていないこともあるので、お薦めできません。
しかし、女性は内診台へ上ることへの抵抗感が強く、とくに若い人は検診を敬遠しがちなので、がんの発見が遅れる要因になっています。実際に、先進国で浸潤子宮頸がんと診断される女性の約60パーセントは検診を受けたことがない、もしくは5年以上検診を受けていない女性であるという報告もあります。
今回の患者さんも、この10年近く検診を受けていない、ということが浸潤がんにまで至った要因の一つと考えられます。むしろ、50歳前後以降の年齢では、検診に抵抗感もなくなり積極的に受けるためか、20年前に比べると子宮頸がんの発症は少なくなっています。
*パパニコロウ法=子宮頸管から綿棒などでとった細胞を調べる際の染色法。1943年に開発された。
*細胞診=ある部分から細胞をとり、細胞が悪性かどうかを判定する。
*正診率=がんをがんと診断できる確率。
*2 不正性器出血
| ●妊娠関連の出血 |
| ●ホルモンの異常による出血 |
| ●良性の腫瘍による出血 |
| 子宮頸管ポリープ、子宮筋腫(特に子宮粘膜下筋腫)、 子宮内膜ポリープ、子宮内膜症などの原因 |
| ●がん関連の出血 |
| 接触出血(性交渉後の出血)があるときは、 子宮頸部の細胞診、組織診を行う 子宮体がんでは、ホルモンの異常による出血と紛らわしいことも |
| ●炎症や血液の異常(出血性要因、白血病など)による不正性器出血も |
子宮頸がんは早期なら無症状のことが多いので、検診で発見されるのが普通です。言い換えれば、無症状で発見される場合はまだ早期であることが多く、予後もいいことが多い、と言えます。無症状のまま妊娠して婦人科を受診したときに見つかるという場合もあります。そのため、妊婦健診時の検診が行われるようになってきてもいます。
自覚症状としていちばん多いのは不正性器出血です。しかし、ある程度進行しなければ起こりません。婦人科に「性交のたびに出血する」とか「おりものが茶色っぽい」という訴えで受診し、子宮頸がんが見つかるケースがよくあります。
出血は、月経と月経の中間にある排卵日にも起こることがあり、不正性器出血をこの出血だと思い込んでしまうことも少なくありません。
さらに、更年期が近づくと月経後もだらだらと出血が長引くことがあるため、不正性器出血なのに気づかないこともあります。こうして、症状を見過ごすうちに病気が進行するというパターンも少なくありません。
さらにがんが進行すると、子宮頸部だけにとどまっていないで、基靭帯や子宮体部に浸潤したり、足の付け根のリンパ節に転移していきます。また、尿管を圧迫すると、腎臓が腫れて腰痛を覚えたり、膀胱にがんが顔を出して血尿、腸に顔を出して血便、といった症状に結びつくこともあります。しかし、これらは、かなり進行した状況で現れる症状です。
子宮の機能を保つ円錐切除
喜多川亮さんのお話
*3 視診・内診の意義

診断の確定に使用する
コルポスコープ

子宮内部をコルポスコープで
観察した部分
子宮頸がんの視診・内診は、病気の進行度をみるために必要不可欠なものです。
腟を拡げて肉眼的に明らかにがんとわかればステージ1b以上になります。
がんの疑いが強い場合「コルポスコープ」と呼ばれる腟拡大鏡を使い腟内を拡大して詳しく診察し、がんの広がりを調べます。
この患者さんの場合、明らかにがんであったことに加え、腟への広がりも見て取れたためステージ2aと診断されたものと思われます。
視診に加え、検査の中心となるのは内診です。内診では医師が薄い手袋を着用して片方の手の指を腟や直腸に挿入し、他方の手をおなかの上にあて、両手で子宮などの骨盤内臓器をはさむようにして、しこりの大きさや骨盤内での広がりを調べます。
*4 体外受精の可能性
子宮頸がんが、子宮頸部の表面にとどまっているような、ごく早期の段階で見つかった場合は、レーザー蒸散術や*子宮頸部円錐切除術という方法でがんを焼却・切除できれば子宮の機能は保たれるので、自然分娩は可能です。また、広汎子宮全摘という子宮、卵巣など、妊娠に必要な臓器をすべて摘出する手術をした場合でも、赤ちゃんがほしい、という女性は多いと思います。
最近、マスコミでも、別の女性の子宮で育てる「代理母への体外受精」で子供をつくることが話題になりました。しかし、この方法は、倫理的な問題、などが十分な検討ができておらず、それを認める法律はなく、「どうしても赤ちゃんが欲しいときの選択肢」とはいえないのが現状です。
*子宮頸部円錐切除術=子宮頸部を円錐状に切除する手術。全身麻酔が必要。
診断の確定にはコルポスコープで
喜多川亮さんのお話
*5 細胞診のクラス分類
細胞診の結果は、クラス1から5で表されます(本誌では算用数字で表します。下表参照)。これは細胞の状態であって、がんの進行期とは無関係です。
クラス1と2は陰性、クラス3はaとbに分かれていて疑陽性です。3aは軽度の異形成の可能性があり、定期的な検診で様子をみますが、80~90パーセントは自然に消滅してしまいます。3bは高度の*異形成の可能性があるということで、10~20パーセントはがんに進行する可能性のある前がん状態です。クラス4は、がんの進行期でいう0期の上皮内がんの可能性があるということ、クラス5は、浸潤がんの可能性があるということです。
*異形成=正常な細胞から変化してがんになる前の状態。
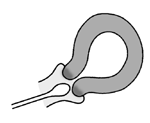
| クラス1 | 陰性 | 正常な細胞 |
|---|---|---|
| クラス2 | 陰性 | 良性の異型細胞あり |
| クラス3a クラス3b | 疑陽性 | 軽度異形成の可能性 高度異形成の可能性 |
| クラス4 | 陽性 | 上皮内のがんの可能性あり |
| クラス5 | 陽性 | 浸潤のがんの可能性あり |
*6 子宮頸がんの診断法
浸潤がんが進行するにつれ細胞診における検出力は低下していくといわれ、やはり症状がある場合の視診と内診は欠かせません。診断の確定はコルポスコープで疑わしい場所から組織を削り取る組織診で行います。
またあやしい場所が子宮頸管の奥のほうにあって直接見えないときの診断などには、*子宮頸管内膜掻爬による組織診のほか、子宮頸部円錐切除術を行うこともあります。要するに、細胞診は検診には使えますが、がんの確定には組織診が必要です。
病気の進行度を詳しくみるためには、前述の通り視診と内診を行いがんの広がりや大きさを調べます。
がんが進行していることが疑われる場合は、周囲の臓器や全身の他の臓器に広がっていないかどうか調べるために、腎盂尿管造影法(腎盂、尿管、膀胱を映す造影検査)、胸部X線検査、膀胱や大腸の内視鏡検査を行います。
さらにMRIやCTなどの画像検査を行うこともあります。MRIやCTでは病変の大きさ、子宮頸部周囲組織への浸潤の程度や骨盤リンパ節への転移の有無など、子宮頸がんの広がりをある程度診断することができます。しかし、CTやMRIは治療方針決定の補助として用いられ、国際規約上でもステージの決定には関与しません。というのは、発症頻度が高いアフリカや南米などの発展途上国でこれらの検査を一般的に行うことができないからです。よって、それらの国々で最低行えるであろう検査の範囲で進行度が決定できるように規定されています。
*子宮頸管内膜掻爬=子宮の入り口から少し奥をかきとってきて組織を調べる。
*7 子宮頸がんのステージ
子宮頸がんの進行度は、大きくは5期、細かく考えると11期に分れます。がんの大きさが4センチ以上になるかならないかでも、予後が大きく変わってきます。
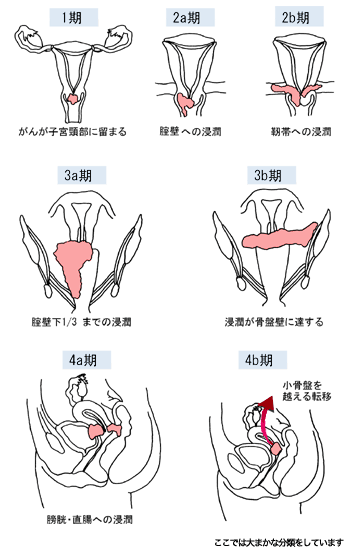
同じカテゴリーの最新記事
- 1次、2次治療ともに免疫チェックポイント阻害薬が登場 進行・再発子宮頸がんの最新薬物療法
- AI支援のコルポスコピ―検査が登場! 子宮頸がん2次検診の精度向上を目指す
- 第75回日本産科婦人科学会 報告 ~慈しみの心とすぐれた手技をもって診療に努める(慈心妙手)が今年のテーマ~
- HPV9価ワクチンが定期接種に! 子宮頸がんはワクチン接種で予防する
- 自己採取HPV検査とHPVワクチンの持続感染予防効果を検討 〝子宮頸がん撲滅〟を目指す2つの臨床研究~福井大学
- 定位放射線療法を併用した臨床試験も進行中 子宮頸がんの化学放射線療法
- 受診率アップのためには若い世代への意識付けが肝要 大学生に対する子宮頸がん検診啓発活動を実施~福井県
- 世界80カ国以上でHPVワクチンは定期接種に 子宮頸がんは、検診とワクチンで予防できる!
- 子宮体がん、子宮頸がんにおけるダヴィンチ手術の現状と今後 子宮体がんがダヴィンチ手術の保険適用に


