進行別 がん標準治療 放射線治療をするには抗がん剤も同時に行うのが欧米の標準治療
現在進められている臨床試験
一方、多くの論文を解析したメタアナリシスの成績では、術前化学療法を行ってから手術を行う場合と放射線治療単独では、術前化学療法+手術群の生存率のほうが明らかに高いのです。ただし「検討した症例数が800と少ないので、まだ科学的に優位性が証明されたとは言えない段階」なのだそうです。
そこで、JCOG(日本臨床腫瘍学グループ)では、現在手術前に術前化学療法を行ったほうが手術単独の成績を上回るのか、科学的に評価するために臨床試験を行っているところです。この試験では、1b期から2b期の4センチ以上の手術可能な子宮頸がんの患者さんが対象です。このうち、広汎子宮全摘術という標準治療を行った上で放射線治療を行った群と術前化学療法を行った上で手術を行い、術後に放射線治療を行った群を比較検討しています。
また、ヨーロッパでもヨーロッパの標準治療である放射線化学療法と術前化学療法+広汎子宮全摘術の比較臨床試験が進行中だそうです。
術前化学療法を導入した成果
進行期別5年生存率]
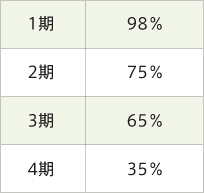
このように、術前化学療法の効果は、現在科学的な評価が行われている最中です。紀川さんは、現在がんが4センチ以上ある1b2期の段階から術前化学療法を導入しています。ここに示したのは鳥取大学での子宮頸がんの進行期別5年生存率です。これが全国平均の5年生存率よりかなりいいのも「化学療法を導入した新しいデータだからです」と紀川さんは語っています。
これまでのデータから「基本的に手術をできない症例に術前化学療法を行ってがんを縮小し、手術をできるようにするのはいいと思います。しかし、1b1期のような確実に手術ができる症例に術前化学療法を行うのが良いことなのか。化学療法が効かない3割の人はその間に進行してしまうわけですから、これは疑問です。さらにいけないのは、術前化学療法を行って、縮小手術を行うことです。どのデータをみても腫瘍の残存やリンパ節転移率が高いので、手術の縮小はやめるべきです」
縮小手術は、子宮だけを摘出してリンパ節郭清などを行わない方法(単純子宮全��術)です。上皮内がんや1a期の一部では行われていますが、術前化学療法で縮小させた子宮頸がんの場合は、リンパ節転移の可能性もあるので、縮小手術を行うことは危険だというのです。
卵巣の機能温存について
若い女性にとって、卵巣の機能を残せるかどうかは、早期閉経という点からも大きな問題です。放射線治療を行えば、卵巣の機能は失われてしまいます。手術に際して、卵巣を残す基準が明確ではありませんでした。
これまでの論拠をみるとごく少ない症例での検討がもとになっていたといいます。
そこで、紀川さんは複数の施設と協力して子宮頸がんで手術をして卵巣を摘出した人3300例を集めて改めて解析してみました。
すると、1期から2a期までの扁平上皮がんであれば、転移は1パーセント未満、1000人に2人程度で極めて少ないことがわかったのです。一方、腺がんだと卵巣転移が3パーセント近いことが判明しました。「ふつう、転移の率は1パーセントを境に残すか残さないかを考えます。これで言うと、扁平上皮がんならば2a期まで卵巣を残せることになるのです」
これまでより、かなり多くの人で卵巣を残せることが初めて明らかにされたのです。ただし、残しても術後に放射線をかければ卵巣の機能はダメになってしまいます。ですから、手術時に放射線のあたらない部位に、卵巣を移動することも必要と紀川さんは考えています。
3期~4期
放射線治療と化学療法の同時併用が中心
3期は、3a期ががんが腟壁の下3分の1を越えて下まで広がったもの。3b期ががんが骨盤まで食い込んだものです。「この場合、3期の一部は動注による術前化学療法を行って手術をするという選択肢もありますが、これはやはり限られた例です。基本的には放射線治療と化学療法の同時併用が中心になると思います」と紀川さん。アメリカに倣って、日本でも放射線化学療法が今後広まっていくと考えられるのです。
実際には、まだ施設によって差がありますが、紀川さんのところでも放射線治療と化学療法を同時に行っています。しかし、ここでも日本で独自のエビデンス(科学的根拠)を出す必要があることは前述のとおりです。
なぜするの?一時代前のBOMP療法
4期は、膀胱や直腸にがんが食い込んだものが4a期、肺や肝臓など遠隔臓器に転移したものが4b期です。この場合、膀胱や直腸に明らかにがんが限られていれば、放射線による局所治療の可能性もありますが、大多数は化学療法による全身療法の適応になります。
では、ここでどういう抗がん剤の組み合わせが標準的なのかというと、これはまだ探索している段階なのだそうです。「まだ、シスプラチン単剤の効果を上回る組み合わせがないのが実情です。卵巣がんならば、タキソール+カルボプラチンというゴールドスタンダードがありますが、こういう組み合わせがまだ子宮頸がんでは見つかっていないのです」と紀川さん。
以前から、日本ではBOMPという抗がん剤の併用療法が用いられてきました。これは、ブレオ(一般名ブレオマイシン)、オンコビン(一般名ビンクリスチン)、マイトマイシン、そしてシスプラチンという4種の抗がん剤を併用する治療法です。日本ではいまだにこの治療法が行われていますが、シスプラチンは単剤でも強い薬です。4種の組み合わせとなると患者さんにはかなりハードな治療です。紀川さんは「これはもう古典的な治療法です。副作用も強力だし、だからといってこの治療法がいいというデータもないのです」。
タキソールとシスプラチンの組み合わせがいいとの報告
ただ、それならばどういう組み合わせがいいのか、それを模索しているのが実情です。
実は、前述のJCOGが術前化学療法の効果を調べるために行っている臨床試験も、術前化学療法にBOMP療法を採用しているのです。
これに関して紀川さんは「本当は、まず最善の化学療法の組み合わせを探すほうが先決なのです」と語っています。
現在では、進行・再発頸がんを対象にタキソールとシスプラチンの組み合わせがいいという報告、あるいはカンプト(もしくはトポテシン、一般名塩酸イリノテカン)とシスプラチン、ジェムザール(一般名ゲムシタビン)とシスプラチンなど、さまざまな組み合わせで治療成績の研究が進んでいるところです。「子宮頸がんは歴史的に、手術と放射線で治療が行われてきたがん。そのため、抗がん剤の研究はまだ十分ではないのです」と紀川さん。
しかし、だからこそ今後従来の治療法に抗がん剤を組み入れることで、子宮頸がんの治療成績がさらに向上することが期待されているのです。
同じカテゴリーの最新記事
- 1次、2次治療ともに免疫チェックポイント阻害薬が登場 進行・再発子宮頸がんの最新薬物療法
- AI支援のコルポスコピ―検査が登場! 子宮頸がん2次検診の精度向上を目指す
- 第75回日本産科婦人科学会 報告 ~慈しみの心とすぐれた手技をもって診療に努める(慈心妙手)が今年のテーマ~
- HPV9価ワクチンが定期接種に! 子宮頸がんはワクチン接種で予防する
- 自己採取HPV検査とHPVワクチンの持続感染予防効果を検討 〝子宮頸がん撲滅〟を目指す2つの臨床研究~福井大学
- 定位放射線療法を併用した臨床試験も進行中 子宮頸がんの化学放射線療法
- 受診率アップのためには若い世代への意識付けが肝要 大学生に対する子宮頸がん検診啓発活動を実施~福井県
- 世界80カ国以上でHPVワクチンは定期接種に 子宮頸がんは、検診とワクチンで予防できる!
- 子宮体がん、子宮頸がんにおけるダヴィンチ手術の現状と今後 子宮体がんがダヴィンチ手術の保険適用に


