再発を防ぎ、QOLを高める、子宮頸がんの放射線化学療法 とくに1b~2b期の局所進行がん患者にお勧め
抗がん剤は十分な量を投与することが重要
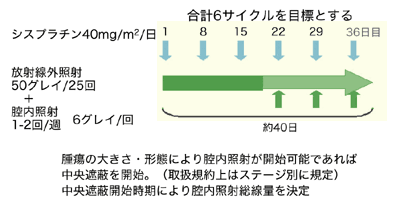
子宮頸がんに対する放射線化学療法のやり方にはいくつか方法がある。喜多川さんの前勤務地である国立がん研究センター中央病院では、放射線の照射期間中(6~7週間)に、抗がん剤を毎週1回ずつ計6回(6サイクル)投与する方法を指針とし、3年前の2001年から実施している。
「放射線は体外から骨盤内の子宮とその周辺にあてる外照射と、子宮や腟の中から病巣部にあてる*腔内照射を併用します」(喜多川さん)
外照射は1回2グレイ(1週5回10グレイ)ずつ、5週にわたって合計50グレイを病巣部にあてる。腔内照射の放射線量は進行具合や腫瘍の大きさによって異なるが、後半の2~3週間で1回5~6グレイずつ、計20~30グレイをあてる。
「抗がん剤はシスプラチンだけを用います。放射線の照射初日に40ミリグラム(患者の体表面積1平方メートル当たりの量、以下同)のシスプラチンを投与し、6サイクルを目標に1週間ごとに繰り返していきます」(喜多川さん)
放射線化学療法における抗がん剤治療の役割は、局所における放射線感受性を高めることもあるが、全身に微小転移していると考えられるがん細胞を叩き、再発を抑えることだ。そのためには十分な量の抗がん剤を投与しなければならないが、40ミリグラムのシスプラチンを週ごとに6サイクル投与するという方法は、先ほどのNCI提言が出る契機となった大規模無作為化比較試験の一つを参考にしたものである。
「当初は吐き気や食欲不振、下痢、脱水、腎機能障害などの副作用によって、同時併用の化学療法を中止した患者が少なくありませんでした。しかし、吐き気止め(セロトニン拮抗剤)や下痢止めなど脱水の早期予防を含めた副作用対策(化学療法の支持療法)を強化したことから、この投与法を完遂できる患者が増えていきました」(喜多川さん)
今年で治療後3年目を迎えるのが最長の患者なので、まだ治療成績について安易な評価は下せない。しかし、40ミリグラムのシスプラチンを5サイクル以上投与できた患者の場合、少なくとも従来の放射線単独の治療法などより優れた治療成績をあげられることは十分期待できる。
*腔内照射=放射線源を金属カプセルに��入し、それを子宮腔内などの体腔の中に投入してがんを治療する方法
シスプラチン40ミリグラムは最低限の投与量
問題は同時併用の化学療法で、40ミリグラムのシスプラチンをきちんと5サイクル以上投与できる割合が定かではないことだ。
「化学療法は一定の期間に十分な量の抗がん剤が投与されないと、その治療効果を得るのは難しいのです。中途半端な投与では抗がん剤の副作用によって患者はダメージのみを受ける可能性が大きくなりますが、放射線化学療法における抗がん剤治療にも同じことがいえるのです」(喜多川さん)
実は、シスプラチンを1回40ミリグラム、5サイクルで計200ミリグラム以上という量は、先の大規模無作為化比較試験の80パーセント以上の患者で達成されている最低限の投与量なのである。
「日本では子宮頸がんの放射線化学療法と称しながら、シスプラチンを30ミリグラム程度しか投与していない施設も少なくありませんが、それではきちんとした放射線化学療法といえません。抗がん剤の投与量が不十分であり、臨床試験の結果で得られた抗がん剤追加のメリットが保障できません」(喜多川さん)
国立がん研究センター中央病院の放射線化学療法の場合も、40ミリグラムのシスプラチンを5サイクル以上投与させるための副作用対策(支持療法)の充実が必要となったわけであり、より副作用の少ない抗がん剤の組み合わせの開発が次の課題として浮かびあがってきたのである。
シスプラチンに代わって登場してきたTP療法
一方、アメリカでは転移・再発子宮頸がんに対するより有効な化学療法としてこの間、タキソール+シスプラチンを組み合わせたTP療法が登場してきた。従来のシスプラチン単独の化学療法と比べ生存期間に有意差は見出されなかったものの、奏効率と無増悪期間で有意に優り、副作用も許容範囲内でQOLを損なうことが少なかったので、いまやTP療法は子宮頸がんに対する第一選択肢の化学療法と認められつつある。
その結果、米国臨床試験グループのGOGでは、1b期以上の進行子宮頸がんに対する放射線化学療法においてTP療法の適切な投与量と有効性を調べる臨床試験をスタートさせた。TP療法が放射線化学療法でも副作用を減少させ、より楽にそれを完遂させ得ることが立証され、TP療法はシスプラチンに代わる併用化学療法の主軸を担う可能性が出てくる。
しかし、残念なことに日本では子宮頸がんに対するタキソールの使用は保険でまだ認められていないのだ。
今後、日本で期待されるTJ療法
[カルボプラチン(シスプラチンとの比較)]
●カルボプラチンの利点
- 消化器毒性が軽く神経毒性もほとんどない
- QOL向上が目的のひとつである
- 緩和医療として有用
- 腎毒性が少ない
- 水腎症などをきたすことがある子宮頸がんへの一般化可能性が高い
- 水分の大量摂取の必要がなく入院期間とともに身体的負担も軽減
●カルボプラチンの欠点
全骨盤外照射を以前に行った人では血小板減少が顕著にみられるが、
▼
タキソールとの併用により減少する
シスプラチンに比べて有効性のデータが圧倒的に少ない
これに対して、日本では、放射線化学療法の新たな併用化学療法として、タキソール+カルボプラチン(商品名パラプラチン)を組み合わせたTJ療法が期待されている。喜多川さんが発案したものだ。
「たしかに子宮頸がんに対する単剤でのパワーはシスプラチンよりカルボプラチンのほうが弱いので、放射線と併用する場合もシスプラチン単剤、もしくはそれを中心とした抗がん剤の組み合わせが主流でした。
しかし、カルボプラチンは、シスプラチンよりも消化器毒性(吐き気や嘔吐等)や神経毒性(しびれや麻痺等)、腎毒性が軽いという点で患者にやさしい薬剤といえます。さらに、タキソールと組み合わせるとTJはTPに匹敵するパワーを発揮する可能性もあると期待できます。タキソールとの併用によりカルボプラチンに特徴的な血小板減少の頻度が減少することも有利です。TJ療法は子宮頸がんに対し有効性も高く副作用も軽い効率的な治療法である可能性があります。よって、シスプラチン単独やTP療法などのシスプラチンとの併用療法の場合より楽に(放射線化学療法の)併用化学療法が完遂できるようになる可能性も出てきます」(喜多川さん)
患者にやさしい併用化学療法を
[静岡がんセンターでの子宮頸がん放射線化学療法]
時期 2001年5月より
対象 未治療で1b2~2期の手術不適例と、3~4a期
適格基準 75才以下、臓器機能が保たれている、など
化学療法 シスプラチン:40mg/m2/日(1、8、15、22、29、36日目)
(原則として放射線治療開始日を第1日目とする)
放射線治療
外照射:計50グレイ(2グレイ×25回)
腔内照射:イリジウム192を線源とした高線量率照射による。線量は進行期別に変更。
日本で子宮頸がんの放射線化学療法を普及させるためには、より楽に完遂できる患者にやさしい併用化学療法の確立が不可欠といえる。明らかに副作用が少ないと予想されるTJ療法は、いまもっとも有望な併用化学療法の一つなのである。
すでに今年の夏を目途に再発子宮頸がんに対するTP療法とTJ療法の無作為化比較試験が全国規模でスタートする。カルボプラチンを用いた抗がん剤治療の子宮頸がんへの有用性を証明する世界初の臨床試験となる。その結果次第ではTJ療法が放射線化学療法へ速やかに導入される可能性は大きい。
現在、日本では1b~2b期までの子宮頸がんの患者のほとんど(9割近く)が手術で切除されている。放射線などで治療するのは、高齢や糖尿病、高血圧などの合併症のため手術のできない患者に限られてきた。国立がん研究センター中央病院婦人科や東大病院放射線科などで静岡がんセンターのような新たな試みが始まっているが、その恩恵を受けられる患者はまだ微々たるものでしかない。
がんの治癒と、QOLの維持を両立させることが可能な、患者にやさしい子宮頸がんの放射線化学療法は、もっと大きく広がってほしい治療法である。
同じカテゴリーの最新記事
- 1次、2次治療ともに免疫チェックポイント阻害薬が登場 進行・再発子宮頸がんの最新薬物療法
- AI支援のコルポスコピ―検査が登場! 子宮頸がん2次検診の精度向上を目指す
- 第75回日本産科婦人科学会 報告 ~慈しみの心とすぐれた手技をもって診療に努める(慈心妙手)が今年のテーマ~
- HPV9価ワクチンが定期接種に! 子宮頸がんはワクチン接種で予防する
- 自己採取HPV検査とHPVワクチンの持続感染予防効果を検討 〝子宮頸がん撲滅〟を目指す2つの臨床研究~福井大学
- 定位放射線療法を併用した臨床試験も進行中 子宮頸がんの化学放射線療法
- 受診率アップのためには若い世代への意識付けが肝要 大学生に対する子宮頸がん検診啓発活動を実施~福井県
- 世界80カ国以上でHPVワクチンは定期接種に 子宮頸がんは、検診とワクチンで予防できる!
- 子宮体がん、子宮頸がんにおけるダヴィンチ手術の現状と今後 子宮体がんがダヴィンチ手術の保険適用に


