2010年に臨床試験がスタート~治療の進歩に大きな可能性が~ 新薬の登場で変わる小児白血病の治療
アラノンジーの登場でT細胞性白血病の治療が変わる
従来、B前駆細胞性でもT細胞性でも同じ治療が行われていたが、T細胞性に効くアラノンジー(一般名ネララビン)という新しい抗がん剤が登場してきたことで、異なる治療が行われるようになってきた。
「アラノンジーは、T細胞性急性リンパ性白血病に親和性のある強力な薬です。それまではT細胞性によく効く薬、B前駆細胞性によく効く薬というのはありませんでした。ところが、いよいよ登場してきたということで、特に予後の悪そうなT細胞性急性リンパ性白血病に使ったほうがいいのではないか、ということになったのです」
T細胞性の場合、年齢には関係なく、プレドニゾロンに対する治療反応性がよければ予後がよく、治療反応性が悪ければ予後も悪いというデータがある。そこで、従来の化学療法では治せない予後不良群に対して、アラノンジーを使用するという治療が始められている。それによって、移植を避けられるケースが出てくるのではないかと期待されている。
「アラノンジーは中枢神経に届きやすいという特徴を持った薬です。そのため、脳での再発を防いでくれるという効果が期待できます。その反面、中枢神経に影響することで、けいれんや末梢神経障害などの副作用が出ることがあるとされていますが、昨年のASCO(米国臨床腫瘍学会)では、アラノンジーを加えた群と加えなかった群で、神経毒性の発現に差がなかったという報告も出ています」
神経毒性は、アラノンジーの使用を決定する要因になっているが、早期に適切に使用すれば、大きな問題にはならないことが多いようだ。
現在、アラノンジーを組み込んだ小児急性リンパ性白血病の全国統一臨床試験が準備されている。順調ならば、来年の春にはT細胞性急性リンパ性白血病の全国共通プロトコール(臨床試験計画書)による試験がスタートし、秋にはB前駆細胞性急性リンパ性白血病を対象にした試験がスタートする。
「急性リンパ性白血病の治療に使われている薬のほとんどは、古くから使われているもので、組み合わせを工夫したり���大量に投与したりする治療が行われてきました。新しくアラノンジーが登場してきたのは、非常に大きな出来事です。この薬が登場したから、T細胞性をB前駆細胞性と違うプロトコールにしたのですからね」
この臨床試験によって、急性リンパ性白血病の治療はさらに進歩することになるようだ。
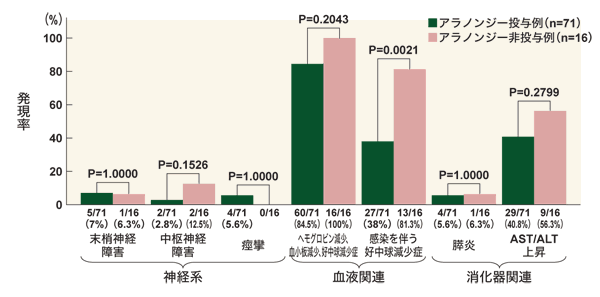
長期のフォローアップが欠かせない
小児の白血病治療では、長い時間が経過してから現れる晩期合併症にも注意を払う必要がある。新しく登場してきた薬は、治療を進歩させる大きな可能性を持っているわけだが、同時に新たな合併症を引き起こすリスクも内包している。
「アラノンジーは新薬ですからこれを使って治療してから、30年たった人はまだいないわけで、それをちゃんとフォローアップしていくことはとても重要です」
また、治療を行うときには、個々の患児の年齢に応じたインフォームド・アセント(自分なりに納得したうえで治療を選択するプロセス)が行われるが、成長に応じたインフォームド・アセントを行っていく必要があるという。たとえば、3歳で治療を受けた子どもが、4歳、5歳、6歳と成長したとき、あるいは中学生、高校生になったときに、「きみが3歳のときになったのはこのような病気で、こうして治したんだよ」ということを、説明していく必要があるというのだ。小児の白血病治療では、こうしたフォローが大切なのである。
同じカテゴリーの最新記事
- 小児がんに対する陽子線治療の全国4施設調査結果 2016年4月から保険診療に
- 活発な議論が出来るカンファレンス 診療科をつなぐ接着剤
- 小児がんの新薬開発で再発治療の充実を!
- 政府も動き出した希少がん対策
- 小児がん看護で先進的なトータルケアを実践する聖路加国際病院 ナースはあくまでも患者さんとその家族の側に
- 2010年に臨床試験がスタート~治療の進歩に大きな可能性が~ 新薬の登場で変わる小児白血病の治療
- 先見性を持った活動を展開し続ける「財団法人がんの子供を守る会」 がん医療とそのサポート体制を患者側から変えてきた40年の闘いの軌跡
- 小児がんで苦しむ子どもたちとその家族を救いたい ゴールドリボン運動のさらなる推進への熱き想い
- 多施設共同研究で進歩する小児血液がんの治療 リスク分類に基づいた「層別化治療」が進む小児白血病


