是非知っておきたいチャイルド・ライフの考え方や実践方法 子どもががんになったら!?――「チャイルド・ライフ・スペシャリスト」を探して下さい
嘘をつかず、子どもにわかる言葉できちんと説明する
以上がチャイルド・ライフの概要ですが、では、子どもががんになったとき、そのノウハウはどんなふうに役立てることができるのでしょうか。
たとえば、最初に医師からお子さんのがんについて聞くとき、チャイルド・ライフ・スペシャリストが同席することが理想です。
親御さんにとって子どものがんは「ありえないこと」であり、その事実は受け入れがたいものです。その一方、その事実を受け入れられないと、先に進めないという現実があります。
子どもにとっても、自分の病気を自分のこととして理解し、受け入れるのは大事なことです。それによって適切な治療が受けられるだけでなく、まさに「選べる人」として病気に立ち向かうことができ、成長することができるからです。
とはいえ、病気を受け入れて立ち向かうのは大変です。その「説明」はやはり一種の「プリパレイション」ですが、いちばんのポイントは嘘をつかないこと、そして、その子にわかる言葉で説明することです。嘘をつくと、それは必ず明るみに出ますから、親や医療者との信頼関係が損なわれてしまうのです。
たとえば、小さい子ならこんなふうに説明します。
「大丈夫よ。今から体を調べて、いちばんいいようにするのよ。ママも一緒にいるから大丈夫よ」
検査の待ち時間などに、セラピューティック・プレイをすることもあります。親御さんは「とても遊ぶ気分じゃない」と思いますが、子どもは遊びによって気を紛らわせることができます。とくに、7歳以下の小さな子の場合、ブロックやパズルなど、いつも親しんでいるおもちゃがあるだけで、リラックスすることができるのです。
大きなお子さんの場合は、まず「自分の病気のことを、どこまで知りたい?」と確認します。私が以前担当した中学3年生の女の子は、悪性リンパ腫と診断されましたが、彼女は「全部聞きたい」と答えました。実際には両親の強い希望もあり、「悪性」という言葉を省略して説明しましたが、こ��子は説明を受けて安心し、不安がらずに治療を受けるようになりました。気分のいい日は受験勉強もがんばり、志望校にも合格しました。今では大学生になっています。
手術の前に手術室ツアー大人も参加の人気行事に
本当のところ、「プリパレイション」は新しく出会うすべてについて必要だと、私は考えています。大人でもそうではありませんか? 何をされるか知らされず、いきなり手術室に放り込まれたら、気丈な人でもパニックになるでしょう。知らないことに対しては、人間は本来の力を発揮できないのです。ですから、私は子どもに「どんなことが起こるのか」を説明しています。
私が宮城県立こども病院にいたときは、術前に「手術室探検ツアー」をしました。行く先々でスタンプを押す「スタンプラリー」形式にして、全部のスタンプがそろったら、手術室へ行くパスポートができ上がります。それをもって手術に向かうのです。
このツアーは、小児科からそのまま20歳代、30歳代になった患者さんや、子どもの患者さんの親御さん、兄弟姉妹にまで人気がありました。毎日行っていましたが、参加者が20人くらいになってしまうほどでした。言葉を変えると、そのくらい、経験のないことに対して、人はプリパレイションを求めるのだと思います。 長期入院や治療のダメージについても、特別なケアが必要です。
たとえば、抗がん剤の副作用で髪が抜けることは、子どもにとって大きなショックです。小学生でも気にしますし、髪が抜けないよう、頭を動かさずに寝ていた4歳児もいました。
まして、「見た目命」の思春期の子にとっては、自己イメージの危機と言えます。そんなとき、心の支えにもなるのが、同年代の入院仲間です。同じ病気の子が笑ったり遊んだりしているのを見て、「髪が抜けても大丈夫だ」と少しだけ安心します。
チャイルド・ライフ・スペシャリストがいる病院では、私たちもこうした橋渡しのお手伝いができますが、もしいない病院でも、できれば同世代の友人をつくり、経験を分かち合えれば、その効果ははかりしれないと思います。
拒食症になった子が、「やっとママが私を見てくれた」
子どもががんになったとき、親御さんが最も悩むことの1つは、兄弟姉妹のケアでしょう。アメリカでは20年前から重要と考えられており、病児の兄弟姉妹のケアはチャイルド・ライフ・スペシャリストの大事な仕事の1つともされています。が、これも日本では十分ではありません。
がんになった子の兄弟姉妹は、大きな心の負担を受けています。病気の兄弟に嫉妬し、親に「かまって」と要求しますが、かまってもらうと今度は「親に負担をかけた」、「病気の兄弟に不当なことをした」と感じたりします。不登校や心身症、更に、20歳を過ぎてから拒食症になる子もいます。
拒食症になったある病児の姉は、体重30キロを切って病院に連れてこられ、「やっとおかあさんが私を見てくれた」と言いました。親御さんも切なかっただろうと思います。
大事なのは、最初から兄弟姉妹に介入させ、一緒に病気に立ち向かうことです。その一方、「あなたも同じように大事なのよ」と、できるだけ態度で表すことが大切です。
がんのお子さんを抱えた親御さんは本当に大変だと思いますが、どうか兄弟姉妹に心を向けることも忘れないでいただきたいと思います。
いかがでしょうか。まだまだ日本では馴染みの薄いチャイルド・ライフですが、その考え方をお子さんの闘病に生かしていただけましたら幸いです。もちろん、チャイルド・ライフ・スペシャリストのいる病院でしたら、積極的にチャイルド・ライフ・スペシャリストのサポートを求めていただきたいと思います。お子さんがよい闘病をされ、治癒されますよう、心からお祈りしています。
いのちにははじまりとおわりがあって、その間を“生きている”というブライアン・メロニー
藤井さんが1996年に出会い、感動して、98年に翻訳・出版したのが、絵本『いのちの時間~いのちの大切さをわかちあうために~』(新教出版社)だ。人間だけでなく、木やアリや魚の生の時間にふれ、
「長くても短くても
いのちの時間にかわりはない。
はじまりがあっておわりがあり、
その間には
“いのちの時間”がみちている」
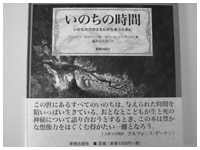
と結ぶこの絵本は、死を生きものに当たり前のものとして静かに位置づける視点で描かれており、癒しに満ちている。
「がんの場合、どうしても命や死の問題とは切り離せませんが、死は本来、生とともにあるべきもの。死を避けていては、生きることも肯定できません。世の中全体として、死をきらうのではなく、死も生の一部として受容することが必要だと思います。そうした社会なら、たとえ病気になり、命が短く終わることも、恐れる必要はないのではないかと思います」(藤井さん)
この本は今、中学校の総合学習の教科書としても使われている。
同じカテゴリーの最新記事
- 小児がんに対する陽子線治療の全国4施設調査結果 2016年4月から保険診療に
- 活発な議論が出来るカンファレンス 診療科をつなぐ接着剤
- 小児がんの新薬開発で再発治療の充実を!
- 政府も動き出した希少がん対策
- 小児がん看護で先進的なトータルケアを実践する聖路加国際病院 ナースはあくまでも患者さんとその家族の側に
- 2010年に臨床試験がスタート~治療の進歩に大きな可能性が~ 新薬の登場で変わる小児白血病の治療
- 先見性を持った活動を展開し続ける「財団法人がんの子供を守る会」 がん医療とそのサポート体制を患者側から変えてきた40年の闘いの軌跡
- 小児がんで苦しむ子どもたちとその家族を救いたい ゴールドリボン運動のさらなる推進への熱き想い
- 多施設共同研究で進歩する小児血液がんの治療 リスク分類に基づいた「層別化治療」が進む小児白血病


