多施設共同研究で進歩する小児血液がんの治療 リスク分類に基づいた「層別化治療」が進む小児白血病
治療法の進歩によって不治の病から治る病気へ
小児白血病は、かつては不治の病だった。急性リンパ性白血病を例にとると、1960年代には抗がん剤の併用療法により、いったんは良くなるようになった。しかし、治癒することはなかった。
「なぜ死亡してしまうのかを調べると、約半数は脳に再発が起きていることがわかりました。病気になった段階でがん細胞が脳に行っていて、そこには抗がん剤が届きにくいため、いずれ再発してくるのだと考えられました。そこで、当時は脳に放射線をかけたり、脳脊髄液に薬を注入したりする再発予防治療が行われるようになりました。これによって、半分近い患者さんが治るようになったのです」(堀部さん)
それ以降も治療の進歩は止まらなかった。どういう人が治り、どういう人が治らないのかを分析すると、治りにくいタイプがはっきりしてきた。そこで、治りにくいタイプには、治療を強化して行うようになったという。
「がん治療によって起こる症状に対する予防と治療を支持療法と言いますが、この支持療法が進歩したことで、より強力な化学療法が可能になりました。たとえば、成分輸血と言って、特定の血球だけを輸血することができるようになりました。抗がん剤には血液毒性があり、投与量を増やすと貧血や血小板減少が起こります。そんなときでも、成分輸血で赤血球や血小板を補充すれば、乗り越えられるわけです。また感染症の治療薬も多く開発されました。このような支持療法が登場したことで、多量の抗がん剤を使うことができるようになりました」(堀部さん)
こうして、1980年代に強力な化学療法が行われるようになり、再発せずに生存する人の率が上昇。また1990年代には、リスク分類に従って、適切な治療が行われるようになった。治りにくいタイプには強い治療、治りやすいタイプには弱い治療を行う「層別化治療」が行われるようになったのだ。
更に、より強力な治療として造血幹細胞移植も始まった。
「移植が治療として確立したのは1980年代で、骨髄バンクが登場したのは1990年代。治療成績の向上に移植が貢���していることは確かですが、小児の場合、治療の中心は化学療法です」(堀部さん)
このように治療法の進歩、リスク分類に基づいた層別化治療が進んだ結果、急性リンパ性白血病の5年無イベント生存率(化学療法で寛解が得られ、その後再発することなく5年生存する確率)は80パーセント程度にもなったのだ。
治療成績が向上し、長期生存者が増え、現在、多くの小児がん経験者が成人期を迎えている。しかし、5年生存した小児がん経験者たちを長期に観察した米国の調査研究によれば、小児がん経験者は25年後の生存率が84~85パーセントと、健常人の97~98パーセントに比べて有意に低いことが明らかとなった。その原因は再発や2次がんであり、また、さまざまな合併症による死亡も少なからず認められている。堀部さんは、「これらの問題を防ぐことが大事であり、日本でも長期フォローアップシステムの構築が急務です」と言う。早急な長期フォローアップ体制の整備が期待される。
急性リンパ性白血病の最新治療研究
日本における小児血液がんの治療研究は、東京小児がん研究グループ、小児癌白血病研究グループ、小児白血病研究会、九州山口小児がん研究グループという4つのグループを中心に行われてきた。
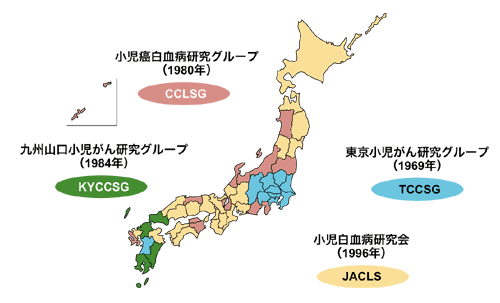
しかし、小児血液がんは、もともと希少疾患であるうえに少子化で患者数が減少。更には、治療の層別化が進んだため、臨床試験に必要な患者の確保が困難になっていた。
そこで、4つのグループが共同して症例の集積と質の高い研究を行う必要があることから、2003年に日本小児白血病リンパ腫研究グループ(JPLSG)が設立された。現在、全国183施設がJPLSGに参加している。この研究グループにより、日本の小児血液がんの研究、臨床試験が進められている。
また、これら臨床研究の運営・管理は、新たに設立されたNPO法人臨床研究支援機構(OSCR)によって支えられている。
現在、進められている研究、臨床試験に関して、JPLSG代表を務める堀部さんに、最新の治療研究についてうかがった。
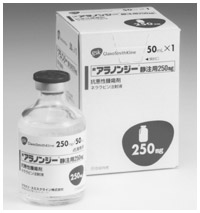
2007年12月に、「再発または難治性のT細胞急性リンパ性白血病(T-ALL)、T細胞リンパ芽球性リンパ腫(T-LBL)」の治療薬として認可されたアラノンジー(一般名ネララビン)について、早ければ2009年に新しい臨床試験がスタートする予定という。
「T-ALLは、従来はB前駆細胞性と同じ治療が行われてきました。薬に対する反応がやや悪いので高リスクに分類されますが、強い化学療法を行うことで、3分の2の患者さんはB前駆細胞性の場合と遜色のない治療成績が得られています。ただ、残りの3分の1は、化学療法だけでは不十分。そういう患者さんに対する有効な治療法が求められていたところに、アラノンジーが登場してきたわけです」(堀部さん)
アラノンジーは、従来の化学療法で効きが悪くなった人に対して、単剤で効果があることが確認されている。T-ALLもT-LBLも、患者数は決して多くないが、その必要性は高い。
「抗がん剤を使用した後に再発した患者さんに効く薬は、なかなかありません。それゆえにアラノンジーは期待が大きい薬です。これまでに使った人数は少ないのですが、その中に劇的に効く人がいて、単剤治療で寛解に入った例もあります。しかし、アラノンジーで治癒までいけるかは疑問です。ただ、いい状態にまで持ち込めれば、いい状態で移植を受けることができ、治癒へと導ける可能性が高まります」(堀部さん)
堀部さんが説明するように、アラノンジーは、再発または難治性の患者さんへの使用で、良い成績をあげてきた。そこで、T細胞急性リンパ性白血病で、薬の効きが悪そうなタイプには、最初からアラノンジーを使うことでもっと良い結果が得られるのではないか、という考えが生まれた。これを検証するための臨床試験で、この試験もリスク分類に基づいた「層別化治療」のための研究の一環である。
試験は、従来の化学療法にアラノンジーを加えるという併用療法で、25歳以下の患者さんを対象とする予定だ。
期待の大きな臨床試験であるが、対象患者数が少ないため、どうしても研究に時間がかかってしまう。研究結果について、堀部さんは、「この研究結果が見えてくるまでに、7~8年はかかるだろう」と見ている。
このほか、フィラデルフィア染色体陽性の急性リンパ性白血病に対する造血幹細胞移植を前提としたグリベック(一般名イマチニブ)の有用性を調べる臨床試験なども行われている。
現在、JPLSGでは、付随研究を合わせて11の臨床試験が進行中という。
小児白血病患者さんの80パーセント以上で長期生存が可能になった現在も、より安全な治療法の開発や難治症例に対する有効な治療法の開発が求められている。
| 臨床試験名 | 対象疾患 | 登録開始年月 | 登録数 | 予定症例数 | IRB承認施設数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. ALCL99(国際) | 未分化大細胞型リンパ腫 | 2002. 5~ | 81 | 454 | 130 |
| 2. MLL03 | 乳児急性リンパ性白血病 | 2004. 2~ | 56 | 70 | 151 |
| 3.Ph+ALL04 | フィラデルフィア染色体陽性急性 リンパ性白血病 | 2004.11~ | 39 | 56 | 137 |
| 4. B-NHL03 | 成熟B細胞性リンパ腫 | 2004.11~ | 178 | 308 | 167 |
| 5. B-NHL03G-CSF | 進行期成熟B細胞性リンパ腫 | 2004.11~ | 32 | 90 | 105 |
| 6. LLB-NHL03 | 限局型リンパ芽球型リンパ腫 | 2004.11~ | 7 | 48 | 168 |
| 7. ALB-NHL03 | 進行期リンパ芽球型リンパ腫 | 2004.11~ | 91 | 124 | 167 |
| 8. AML-P05 | 急性前骨髄球性白血病 | 2006. 2~ | 12 | 44 | 163 |
| 9. AML-05 | 急性骨髄性白血病 | 2006.11~ | 144 | 254 | 143 |
| 10. AML-D05 | ダウン症に伴う急性骨髄性白血病 | 2008. 1~ | 5 | 73 | 59 |
| 11. FM-05 | 骨髄性白血病の骨髄移植例 | 2006.12~ | 3 | 34 | 23 |
※IRB=機関審査委員会
同じカテゴリーの最新記事
- 小児がんに対する陽子線治療の全国4施設調査結果 2016年4月から保険診療に
- 活発な議論が出来るカンファレンス 診療科をつなぐ接着剤
- 小児がんの新薬開発で再発治療の充実を!
- 政府も動き出した希少がん対策
- 小児がん看護で先進的なトータルケアを実践する聖路加国際病院 ナースはあくまでも患者さんとその家族の側に
- 2010年に臨床試験がスタート~治療の進歩に大きな可能性が~ 新薬の登場で変わる小児白血病の治療
- 先見性を持った活動を展開し続ける「財団法人がんの子供を守る会」 がん医療とそのサポート体制を患者側から変えてきた40年の闘いの軌跡
- 小児がんで苦しむ子どもたちとその家族を救いたい ゴールドリボン運動のさらなる推進への熱き想い
- 多施設共同研究で進歩する小児血液がんの治療 リスク分類に基づいた「層別化治療」が進む小児白血病


