分子標的薬を含む新薬の登場で生存期間は2倍に よりよい生活を目指して進行大腸がんの分子標的治療
使えるのは遺伝子型が合う6割程度の人
利便性に関しては、ベクティビックスに分があると言えそうだ。それでも、欧米では先に開発されたアービタックスのシェアが圧倒的だという。それに対し、日本では両者が同じくらい使われている。日本では利便性が重視されやすいのかもしれない。
副作用も両者はよく似ている。最も問題となるのは、皮疹と爪周囲炎だ。とくに爪周囲炎は痛みを伴い、患者さんにとってはつらい症状だという。
アービタックスとベクティビックスは、大腸がんなら誰にでも使えるわけではない。がん細胞のKRAS遺伝子を調べる検査が行われ、この遺伝子に変異がない「KRAS野生型」の場合にだけ使うことになる。変異がある「KRAS変異型」には、どちらの薬も効かないことがわかっているからだ。
KRAS野生型の割合は大腸がん全体の6割程度。少なく見積もっても、半分以上の患者さんは、アービタックスやベクティビックスの治療を受けることができる。
| 比較的多く見られる副作用 | 頻度は高くないが重篤な副作用 | |
| ベバシズマブ | 高血圧 たんぱく尿(尿にたんぱくが出る) | 血栓症 (動脈や静脈の中に血のかたまりができる〔脳梗塞、心筋梗塞、肺梗塞、血栓塞栓症〕) 消化管穿孔(胃や腸に穴があく) 出血 |
| アービタックス べクティビックス | 皮疹(にきび、発疹、皮膚乾燥など) 爪周囲炎 | 重度で急性のアレルギー症状 (気管支痙攣、浮腫、低血圧、意識消失など) 間質性肺炎 |
2タイプの分子標的薬を順次使うこともできる
大腸がん治療における分子標的薬は、手術できない進行がんが対象になる。『大腸癌治療ガイドライン』では、次頁に示した治療法が推奨されている。選択肢が多く、分子標的薬はいろいろな組み合わせで使われている。
「分子標的���は3種類ありますが、作用で分類すれば2タイプになります。どちらも使える患者さんなら、2つのタイプの薬をどこかで使うのが基本です」
KRAS変異型の場合、アービタックスとベクティビックスは使えない。
これに対しKRAS野生型の場合には、1次治療はアバスチンの併用でもいいし、アービタックスやベクティビックスの併用でもよい。1次治療でアバスチンを使えば、2次治療か3次治療でアービタックスまたはベクティビックス。1次治療でアービタックスかベクティビックスを使った場合には、2次治療でアバスチンを使うことになる。
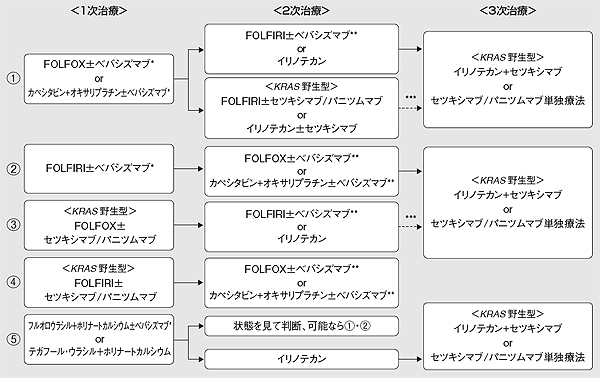
** 1次治療においてベバシズマブを投与していない場合、および1次治療の効果が持続しているがイリノテカンやオキサリプラチンの毒性のために投与を中止した場合は、2次治療でベバシズマブの投与が推奨される
*** 2次治療までに抗EGFR抗体薬を未使用の場合
新しい分子標的薬の注目される試験結果
現在使用されている分子標的薬に加え、アフリバセプト(一般名)という新たな分子標的薬が登場してきそうである。11年夏に海外の第3相臨床試験の結果が発表され、注目を集めた。この薬は血管新生阻害薬で、血管内皮細胞増殖因子に働きかけて効果を発揮する点はアバスチンと同じ。現れる副作用もよく似ている。
臨床試験は、2次治療において、FOLFIRI+アフリバセプトとFOLFIRI+プラセボ(偽薬)で比較を行った。その結果、アフリバセプトを併用することで、生存期間が延びることが証明された。
「この結果が出たことで、欧米では承認作業に入りますが、日本では国内の臨床試験が行われることになっています。日本での承認は、海外より少し遅れると思います」
新しい薬の登場は、治療の選択肢が増えることにつながる。アバスチンが効かなくなった人にもある程度の効果が期待できるが、最適な使用方法については今後の臨床試験結果を待たなければならない。そうした使い方ができると、この薬の存在価値が高まりそうだ。
人生の最後の時間をよりよく過ごすために
大腸がんで分子標的薬治療を受けるほとんどの患者さんは、手術できない進行がんの患者さんである。この状態になると、なかなか治癒は難しい。5-FUしかなかった時代には、治癒する例は極めてまれであると言ってよかった。薬物療法が進歩し、分子標的薬が使えるようになった現在、がんが縮小して手術可能になる例が一部あり、その中から治癒する例も現れてきた。とはいえ、それは5~10パーセント程度で、例外的なケースといえるだろう。
「基本的には、人生の最後の時間を、よりよく過ごすための治療ということになります。患者さんのとって大事なのは、がんの治療ではなく、治療以外の生活です。その点を大切にして、治療に取り組むようにしています」
現在、生存期間中央値は24カ月。この時間が得られたことで、患者さんは残された人生を、かなり計画的に過ごせるようになった。
「生存期間が延びると、その間に孫が生まれたり、娘さんが嫁いだり、子どもが卒業して就職したり、といったことが可能になる場合があります。生存期間が3年になれば、高校生だった子どもが大学生になりますからね」
朴さんはこう語る。生存期間が延長することで、患者さんの人生最後の時間は、ずいぶん違ったものになってくるのである。
同じカテゴリーの最新記事
- 切除可能な直腸がん試験結果に世界が注目も 日本の標準治療は「手術」で変わりなし
- ビタミンDの驚くべき効果がわかってきた 消化管がん手術後の再発・死亡リスクを大幅に減少
- 世界最大規模の画期的研究の一部解析結果が発表 大腸がんの術後補助療法の必要性をctDNAで判断する
- 初めての前向き試験で抗EGFR抗体薬の信頼性が確実に! 進化を続ける切除不能・進行再発大腸がんの薬物療法
- 遺伝子変異と左右どちら側にがんがあるかが、薬剤選択の鍵を握る! 大腸がん薬物療法最前線
- 化学放射線と全身化学療法を術前に行うTNT療法が話題 進行下部直腸がん 手術しないで完治の可能性も!
- 肛門温存の期待高まる最新手術 下部直腸がんTaTME(経肛門的直腸間膜切除術)とは
- 大腸のAI内視鏡画像診断が進化中! 大腸がん診断がより確実に
- 患者さんによりやさしいロボット手術も登場 新しくなった大腸がんの手術と薬物療法


