患者さんのライフスタイルに合わせた治療法が選択可能に XELOX療法の登場で、大腸がん再発予防にもう1つ武器が増える!
新たな武器XELOX療法
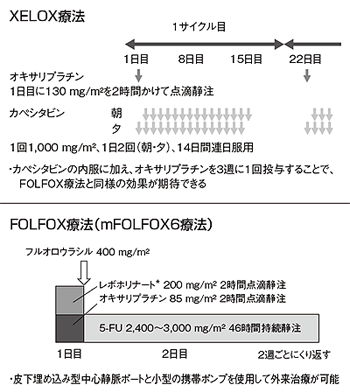
mFOLFOX6療法は2週間ごとに点滴、さらにフルオロウラシルを46時間持続静注する
術後補助化学療法の新たな選択肢として、XELOX療法が期待されている。XELOX療法はゼローダとエルプラットの併用療法であり、進行再発大腸がんの治療では、すでに実績を上げている治療法である。XELOX療法の大きな特徴は、ゼローダは経口薬なので5-FU持続静注のようなわずらわしさがないことだろう。また、1サイクルが3週間。ゼローダは2週間連日服用して1週間休薬、エルプラットは3週間ごとに点滴で投与する。2週間ごとの治療となるFOLFOX療法より簡便な治療といわれている。
「XELOX療法を使った術後補助化学療法の臨床試験が海外で行われました。3期の患者さんに、XELOX療法の有効性が認められ、XELOX療法が術後補助化学療法の新たな選択肢として期待されているのです」
海外29カ国、1886人を対象に実施されたこの臨床試験はNO16968試験と呼ばれ、3期の患者さんにXELOX療法または5-FU+ロイコボリン療法がそれぞれ実施された。その結果、3年無病生存率(3年後に再発せずに生存している患者さんの割合)は、XELOX療法で70.9パーセント、5-FU+ロイコボリン療法で66.5パーセントであり、ハザード比(5-FU+ロイコボリン療法を受けて再発するリスクを1としたときの、XELOX療法を受けて再発するリスクの大きさ)は0.80であった。
「再発のハザード比が0.80ということは、XELOX療法で再発リスクが20パーセント低減されることを意味します」
| XELOX療法 | FOLFOX療法 | |
| 有効性 | フルオロウラシル/ホリナートカルシウムに対して優越性を示した | フルオロウラシル/ホリナートカルシウムに対し���優越性を示した |
|---|---|---|
| 主な有害事象 | 手足症候群, 下痢, 血管痛, 末梢神経症状 | 好中球減少, 末梢神経症状 |
| 投与方法 | 静注+経口 | (急速+持続) 静注 |
| 服薬指導 | 必要 | 不要 |
| 薬剤費 | 約152万円/6ヵ月約 | 146万円/6ヵ月(mFOLFOX6療法) |
| 通院間隔 | 3週間ごと | 2週間ごと |
| 皮下埋め込み型中心静脈ポートの設置 | 原則、不要 | 必要 |
| ポート/ポンプの自己管理 | 不要 | 必要 |
| ポンプの2日間携帯 | 不要 | 必要 |
それでは、FOLFOX療法とXELOX療法、効果の面でどちらがより優れた治療法なのだろうか。
「術後補助化学療法におけるXELOX療法とFOLFOX療法の有効性の違いは、直接比較した臨床試験がないので、厳密に言うとわかりません。ただ、それぞれ術後補助化学療法として5-FU+ロイコボリン療法と比較する臨床試験が実施されており、いずれも5-FU+ロイコボリン療法を同じくらい上回る効果を有することが示されています。さらに進行再発大腸がんに対してXELOX療法とFOLFOX療法は同等の効果を発揮することがわかっているので、術後補助化学療法でもほぼ同等と考えてよいでしょう」
XELOX療法では副作用の手足症候群に注意
| 手足症候群 | |
| ⇒ | 適切な減量/休薬、保湿クリームによる小まめなケア |
| 下痢 | |
| ⇒ | 適切な減量/休薬、処置(止瀉薬、脱水症状を避けるための水分補給など) |
| 血管痛 | |
| ⇒ | 処置(患部を温める、輸液にステロイドを混ぜるなど) |
| ⇒ | 中心静脈ポートの設置により回避可能 |
| 末梢神経症状(XELOX療法/FOLFOX療法 共通) | |
| ⇒ | 適切な減量/休薬、処置(カルシウム/マグネシウム投与、漢方薬など) |
XELOX療法が術後補助化学療法として承認されると(2011年10月28日現在未承認)、患者さんはFOLFOX療法とXELOX療法を提示され、どちらかを選択することになる。そこで、さまざまな点から2つの治療法を比較してみよう。
有効性については、前述したとおり同等と考えられ、選択のポイントにはならない。治療に伴う副作用は、それぞれに特徴がある。FOLFOX療法でとくによく現れるのが好中球減少だ。これに対し、XELOX療法では手足症候群が現れやすい。
「手足症候群は、ゼローダを使用する患者さんの80パーセント程度に現れます。手、足、爪に紅斑や色素沈着が出て、進行すると痛みや手足の機能障害を伴います。箸が持てないなどの機能障害を伴うグレード3以上の症状は、ゼローダの単剤療法では10パーセント以上の患者さんに現れます。しかし、XELOX療法ではゼローダの服用量が少ないため、グレード3以上の症状が現れる頻度は5パーセント程度です」
XELOX療法でもう1つ問題なのが、皮下に埋め込むポートを使わずエルプラットを腕の静脈から点滴するときに現れる血管痛である。血管痛は半分以上の人に現れるといわれている。その原因は定かではないが、患部を温めたり、エルプラットの点滴溶液にステロイドを混ぜるなどで症状が改善するとの報告がある。
注意すべき副作用には末梢神経症状もあるが、これはFOLFOX療法でもXELOX療法でも同じように現れ、大きな差はないという。
患者さんのライフスタイルに合わせやすいXELOX療法
| カペシタビンの服薬遵守(1日2回(朝・夕)14日間連日服用) | |
| ⇒ | 医師より指示された量を正しく服用してください。多く飲みすぎると思わぬ副作用が出たり、重症化します。逆に、飲み忘れると効果が弱まります |
| 3週ごとの通院 | |
| ⇒ | 副作用の重症化を見逃さないよう、気になることがあったらすぐに医療者へ連絡してください |
| 他人の目には見えない症状(足の裏に現れる手足症候群、末梢神経症状など)は患者さんの訴えが大切です | |
| ⇒ | 処置の開始が遅れると回復も遅れ、治療継続を困難にさせる可能性があります。我慢せずに医療者へ相談してください |
通院回数は、3週間ごとのXELOX療法のほうが少ない。
「XELOX療法は、家が病院から遠い、仕事をしているなど通院が大変だと考える人に適していて、患者さんのライフスタイルに合わせやすい治療法。ただ、最初から3週間に1回の通院ですむのではなく、2~3サイクル目で落ち着くまでは、どちらの治療でも、何回か病院に来てもらうことになります」
FOLFOX療法に伴うポートの埋め込みやポンプの管理などが、経口薬を使うXELOX療法では不要となる。ただ、経口薬にも問題がないわけではない。患者さん自身がきちんと薬を飲まなければ、狙い通りの効果は期待できない。経口薬であることは、XELOX療法の強みであると同時に、患者さん自身での服薬管理が求められる。
副作用をコントロールして治療を完遂することが大切
術後補助化学療法で大切なのは、6カ月間の治療を完遂すること。治療をやり遂げるためには、副作用をうまくコントロールしていくことが重要で、副作用の症状に合わせて適切に薬を減量するなどの対応が必要だ。
XELOX療法では、手足症候群などで治療の中断を余儀なくされることがある。
「グレード3では治療は中止となります。大切なのは、痛みが出たらすぐ医療者に相談し、減量など適切な処置を受けること。減量すれば症状は改善します」
ゼローダは経口薬なので、減量は行いやすい。ただ、自分で勝手に服用量を変えるのではなく、医療者に相談し、医師の指示で減量することが大切である。
「手足症候群などの副作用を見ながら、ゼローダを減量していきます。減量しても、再発のリスクが上がらないことが、臨床試験で確かめられています。当初の投与量にこだわって治療中止になってしまうより、減量してでも、6カ月間の治療を完遂することのほうが重要です」
XELOX療法で狙い通りの効果を得るためには、経口薬を正しく服用すること、副作用を我慢せずすぐに医療者へ伝えることなど、患者さんにも気を付けるべきことがありそうだが、「外来化学療法の発達により、医師、看護師および薬剤師が一体となって患者さんをサポートする体制の強化に取り組む病院が増えてきています。患者さんが安心してXELOX療法を受けられるような環境は整ってきています」と松本さんは語る。医療者によるこのような努力の積み重ねにより、術後補助化学療法はさらに進歩していくのかもしれない。
(構成/柄川昭彦)
同じカテゴリーの最新記事
- 切除可能な直腸がん試験結果に世界が注目も 日本の標準治療は「手術」で変わりなし
- ビタミンDの驚くべき効果がわかってきた 消化管がん手術後の再発・死亡リスクを大幅に減少
- 世界最大規模の画期的研究の一部解析結果が発表 大腸がんの術後補助療法の必要性をctDNAで判断する
- 初めての前向き試験で抗EGFR抗体薬の信頼性が確実に! 進化を続ける切除不能・進行再発大腸がんの薬物療法
- 遺伝子変異と左右どちら側にがんがあるかが、薬剤選択の鍵を握る! 大腸がん薬物療法最前線
- 化学放射線と全身化学療法を術前に行うTNT療法が話題 進行下部直腸がん 手術しないで完治の可能性も!
- 肛門温存の期待高まる最新手術 下部直腸がんTaTME(経肛門的直腸間膜切除術)とは
- 大腸のAI内視鏡画像診断が進化中! 大腸がん診断がより確実に
- 患者さんによりやさしいロボット手術も登場 新しくなった大腸がんの手術と薬物療法


