局所再発を抑えるだけでなく、排便・排尿障害や性機能障害など重い術後障害を回避できる可能性も! 人工肛門よ、さよなら! 直腸がんの術前化学放射線療法
術後化学療法も行うと生存率が高まる可能性も
ヨーロッパでは化学放射線療法と放射線単独療法の別の比較試験が行われている。この試験では、直腸がんの患者を4群に分け、A群とC群には術前に放射線照射だけを行い、B群とD群には放射線療法と化学療法を実施。C群、D群には術後に補助化学療法も行った。
手術により十分にがんを切除できたと思っても、肉眼では確認できない微小ながん細胞が残っていて再発が起こる。そのため、手術では取りきれなかった微小ながんを叩くため、術後6カ月程度、補助的に化学療法が行われることがある。こうした補助化学療法の有効性も確認するための試験だ。
その結果、術前の放射線照射のみを行ったA群だけが局所再発率が高く、他の3群には有意な差は認められなかった。また、生存率については4群とも差は認められなかったが、放射線の感受性が高い患者では、術後化学療法を行わなかった群(A群、B群)に比べて行った群(C群、D群)のほうが、生存率が高かった。
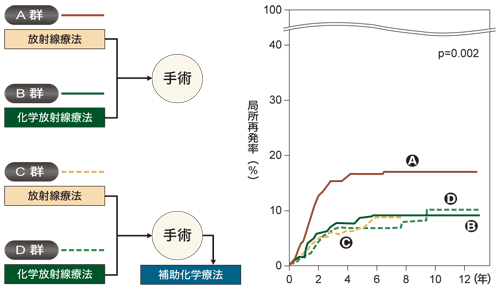
「化学放射線療法を術前に行った場合と術後に行った場合を比べる臨床研究も、ドイツで実施されています。その結果、術前に行ったほうが局所再発率は下がることも証明されました。こうした結果から、少なくとも直腸がんの局所再発率については、術前の化学放射線療法が有効と言えるでしょう。さらに、術後の補助化学療法も加えたほうが、生存率が高まる可能性は示唆されたと考えます」
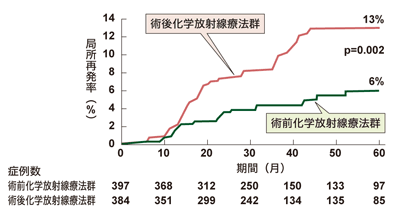
ステージ2でも補助化学療法を行う
ただし、どのような患者が術後化学療法の適応になるかは難しい選択だという。
「放射線療法を実施しない化学療法単独に限った話ですが、結腸がんについては、リンパ節への転移が認められるステージ(病期)3以上の患者さんには、術後化学療法が推奨されています。ステージ2以下の患者さんについても、病理診断で悪性度が高いと判断された一部のハイリスク群では術後化学療法を行うのが一般的ですが、術前化学放射線療法を行った直腸がんに関しては、こうした基準はありません」
しかも、術前に放射線療法を実施すると、放射線の作用でリンパ節に転移したがん細胞が殺され、リンパ節の転移が確認できず、放射線照射前にはステージ3であった患者をリンパ節転移のないステージ2と過小評価してしまう可能性もある。そのため、どの患者に補助化学療法を行うかどうかの判断は難しいのだが、「現実にはステージ2の患者さんにも、予防的に補助化学療法が実施されていることが多い」と渡邉さんは指摘する。
術前の放射線照射で切除範囲が小さくなる
ところで、放射線照射を術後に実施するという選択はないのだろうか。
「術前か、術後かと問われれば、術前のほうが良いでしょうね。というのも、術前の照射は手術で切除する部分に放射線を照射するので問題は少ないのですが、術後だと体に残る部分に照射することになるので、放射線の副作用が強く出やすいのです。それに、術前に照射しておくと、がんが小さくなるので、切除範囲が小さくなるという利点もあります」
がん病巣を中心に直腸を切除する場合でも、微細ながんの広がりを考慮して、がんの下縁から2センチ程度のセーフティマージン(*)をとって切除する必要があるが、大きく切除すればするほど、直腸の機能低下が心配される。肛門機能まで維持できないとなると、人工肛門を造設しなければならないが、術前に照射を行っておけば、セーフティマージンを1センチ程度に小さくできるとする報告もあります。
しかし、術前照射にもデメリットはあって、照射部位が水ぶくれのようになり、がんを切除する際の剥離作業が難しくなることがある。また、隣接する正常な膀胱に放射線を照射すれば、排尿障害が起こりうるため、現在では可能な限り放射線をがんに集中させ、周囲の正常組織に照射しないための工夫も行われている。従来では2方向から放射線を当てる方法(2門照射)だったが、4方向から当てる方法(4門照射)が推奨され、周辺組織への副作用を抑えられるようになっている。
*セーフティマージン=がんの手術では安全策としてがん組織に隣接する正常組織も切除するが、その範囲のこと
化学放射線療法はQOLの維持に役立つ
最後に、化学放射線療法が側方郭清にとって代われるかについても触れておきたいところだが、残念ながら両者を比較した信頼に足るデータはないという。
過去、直腸がんについて側方郭清と化学放射線療法の治療効果を比べるため、日韓共同での比較試験研究が行われたことがある。日本で側方郭清を、韓国で術後化学放射線療法を行い、その治療効果を比べたところ、局所再発については化学放射線療法のほうが有効で、遠隔転移については側方郭清のほうが有効であるとの結果が報告されている。しかし、この試験では、対象となる下部直腸がんの定義が日本と韓国では異なっていたことで、正当に両者を比較することになってはいないという批判もある。
前述のように患者によって放射線の感受性が異なる以上、放射線療法が効きにくい患者に対しても、化学放射線療法を実施するのは適切な選択だとは言い難い。そこで、渡邉さんは、遺伝子を調べることで放射線に対する感受性を予測する技術の開発を進めている。将来的には、放射線がよく効く直腸がん患者には手術と化学放射線療法を組み合わせ、放射線が効きにくい患者には側方郭清を実施することも考えられる。
こうした個別化医療の実現にはもう少し時間がかかるが、これまでに紹介したいくつかの研究でも、化学放射線療法によって直腸がんの局所再発を抑制する可能性が示されており、術前の補助療法でがんを小さくすれば、人工肛門の造設の回避も期待できる。
「側方郭清と化学放射線療法のどちらが有効かについては、結論ははっきりとは出ていません。とはいえ、患者さんのQOLという点から見ると、側方郭清は、排尿障害や性機能障害といった生涯にわたる不利益を蒙る可能性があるのです。それを考慮すれば、体への負担が比較的少ない化学放射線療法の利点は高く評価できるしょう。私は術前化学放射線療法が、わが国でももっと普及していくと考えています」 渡邉さんは、力強くこう語った。
同じカテゴリーの最新記事
- 切除可能な直腸がん試験結果に世界が注目も 日本の標準治療は「手術」で変わりなし
- ビタミンDの驚くべき効果がわかってきた 消化管がん手術後の再発・死亡リスクを大幅に減少
- 世界最大規模の画期的研究の一部解析結果が発表 大腸がんの術後補助療法の必要性をctDNAで判断する
- 初めての前向き試験で抗EGFR抗体薬の信頼性が確実に! 進化を続ける切除不能・進行再発大腸がんの薬物療法
- 遺伝子変異と左右どちら側にがんがあるかが、薬剤選択の鍵を握る! 大腸がん薬物療法最前線
- 化学放射線と全身化学療法を術前に行うTNT療法が話題 進行下部直腸がん 手術しないで完治の可能性も!
- 肛門温存の期待高まる最新手術 下部直腸がんTaTME(経肛門的直腸間膜切除術)とは
- 大腸のAI内視鏡画像診断が進化中! 大腸がん診断がより確実に
- 患者さんによりやさしいロボット手術も登場 新しくなった大腸がんの手術と薬物療法


