延命効果に加え、副作用やQOLを考慮してキードラッグを選ぶのがポイント 新分子標的薬の登場で、大腸がん治療の選択肢がさらに増えた
10年版ガイドラインが示す最新の大腸がん化学療法
『大腸癌治療ガイドライン』は化学療法の内容が改訂され、10年7月に最新の2010年版が刊行された。そこに手術できない進行大腸がんの化学療法として、図2のような治療法が推奨されている。選択肢が多いのが特徴のようだ。
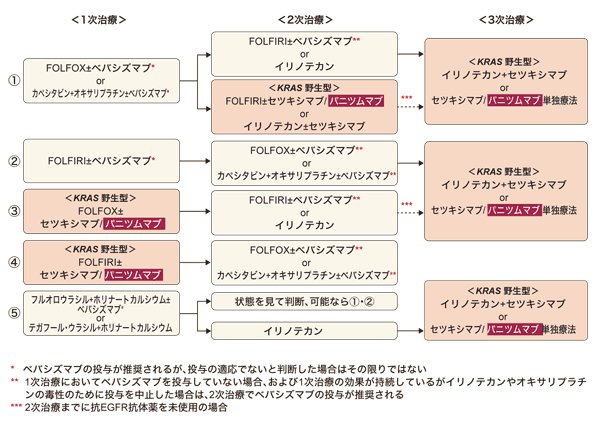
選択肢が増えた理由として、ベクティビックスが加わったことがあげられる。それも、新登場でありながら、1次治療でも、2次治療でも、3次治療でも推奨されている。
また、それまで2次治療以降で使うとされていたアービタックスが、適応を広げ、1次治療から推奨されているのもポイントだろう。
「新しく登場してきたベクティビックスが、最初から1次治療でも、2次治療でも、3次治療でも推奨されているのは、それぞれの臨床試験が行われているからです。大規模臨床試験は1つずつしかないのですが、それが認められたわけですね」
1次治療の臨床試験では、「FOLFOX単独」と「FOLFOX+ベクティビックス」の比較試験が行われている。結果は図3に示したとおりで、KRAS変異型ではまったく効果が見られなかったが、KRAS野生型では効果が現れていた。無増悪生存期間(がんが悪化しなかった期間)中央値は、FOLFOX群の8.0カ月に対し、併用群は9.6カ月だった。
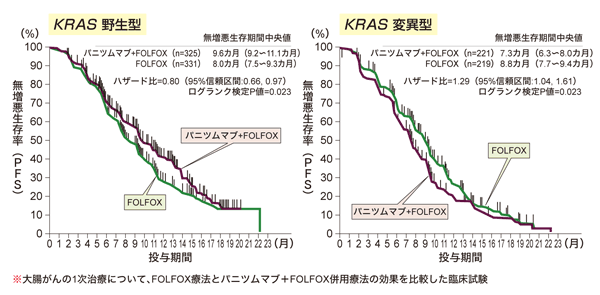
KRASの変異型と野生型について説明してもらった。
「ベクティビックスなどの抗EGFR抗体薬は、受容体をブロックすることで、増殖などを命じるシグナルが出ないようにします。ところが、KRAS遺伝子に変異があると、シグナルが出続けてしまいます。そのため、受容体をブロックしても増殖などを抑えられないのです。KRAS遺伝子に変異がないのが野生型で、このタイプであれば効果が期待できます」
効く人と効かない人がはっきりしているのが、抗EGFR抗体薬の特徴と言えそうだ。
2次治療の臨床試験では、「FOLFIRI単独」と「FOLFIRI+ベクティビックス」で比較している。やはりKRAS野生型だけに効果が確認され、無増悪生存期間中央値は3.9カ月対5.9カ月だった。
3次治療の臨床試験は、「無治療」と「ベクティビックス単独」の比較。KRAS野生型だけ効果があり、無増悪生存期間中央値は7.3週対12.3週だった。
KRAS検査で医療費を節約できる
臨床試験の結果からも明らかなように、ベクティビックスなどの抗EGFR抗体薬が効果を発揮するのは、KRAS野生型の大腸がんである。そこで、抗EGFR抗体薬を使う場合には、KRAS検査を受け、変異型か野生型かを調べる必要がある。KRAS検査は、手術や生検で取ったがん組織の遺伝子を調べる検査で、10年4月からは保険適応となっている。
「日本でも欧米でも、KRAS変異型の人が40パーセントほどいます。つまり、KRAS検査を受けずに治療すると、40パーセントの人は、効果がないのに副作用に苦しめられるわけです。また、効かない人に高価な薬を使うのですから、医療費も無駄になります。抗EGFR抗体薬を使う前にKRAS検査を受けることで、年間約40億円の医療費削減になると試算されています」
患者さんを無駄に苦しめないためにも、医療費を無駄にしないためにも、KRAS検査が保険で受けられるようになった意義は大きいようだ。
副作用が強い人ほど治療効果が高かった
インフュージョンリアクションについては前述したが、抗EGFR抗体薬のその他の副作用についても解説してもらった。
ベクティビックスとアービタックスは、副作用もほぼ共通している。抗EGFR抗体薬に特徴的な副作用は皮膚障害だ。
「にきび様の吹き出物が出る、皮膚が乾燥する、顔が赤くなる、爪が割れるといった症状が現れることがあります。患者さんにとってはつらい症状ですが、副作用が出た人のほうが、薬がよく効くことがわかっています」
それを示したのが図4である。副作用の程度はグレード1~4で示されるが、グレード2~4の重い皮膚障害が出た人のほうが、治療成績が優れていることが明らかにされたのだ。
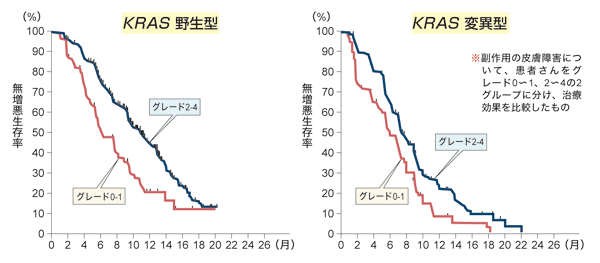
間質性肺炎(*)に対する注意も必要だという。放置すると死亡することもあるので、甘く考えてはいけない。息苦しさ、咳、発熱などの症状があったら、すぐに医師に伝えるようにしたい。
*間質性肺炎=肺胞や肺胞壁(間質)に起こり、治療が難しく致死率も高い肺炎
副作用やQOLも考慮し治療法を選択する
キードラッグが出そろい、治療法の選択肢が増えたために、大腸がんの化学療法は複雑さを増している。ガイドラインには、臨床試験結果に基づき、有効と認められた治療法が推奨されている。しかし、その数が多く、どれを選べばいいのか迷うほどなのだ。
「臨床試験では生存期間が重要な評価基準になっていて、少しでも長く生きられる治療法が優れた治療として推奨されています。しかし、実際の治療では、副作用の種類や頻度、程度、さらには患者さんのライフスタイルも考慮して、治療を選択していくことが大切です」
たとえば、同じ抗EGFR抗体薬でも、ベクティビックスが2週毎の投与なのに対し、アービタックスは1週毎の投与である。通院が大変な患者さんや仕事を持っている患者さんにとっては、ベクティビックスのほうが負担は少ないだろう。
「日本と欧米の違いも考えるべきでしょう。手術後、日本では定期的な検査が行われ、再発の多くは無症状の小さな腫瘍として見つかります。これに対し、欧米では症状が出てから検査するので、再発が見つかった時点の腫瘍は大きいのが普通です。日本の患者さんは再発診断時のQOL(生活の質)が高いので、これを維持できる治療法を選択することも考えるべきだと思います」
臨床試験では生存期間を評価するが、患者さんにとっては、QOLの高い期間を延ばすことこそが重要なのかもしれない。
同じカテゴリーの最新記事
- 切除可能な直腸がん試験結果に世界が注目も 日本の標準治療は「手術」で変わりなし
- ビタミンDの驚くべき効果がわかってきた 消化管がん手術後の再発・死亡リスクを大幅に減少
- 世界最大規模の画期的研究の一部解析結果が発表 大腸がんの術後補助療法の必要性をctDNAで判断する
- 初めての前向き試験で抗EGFR抗体薬の信頼性が確実に! 進化を続ける切除不能・進行再発大腸がんの薬物療法
- 遺伝子変異と左右どちら側にがんがあるかが、薬剤選択の鍵を握る! 大腸がん薬物療法最前線
- 化学放射線と全身化学療法を術前に行うTNT療法が話題 進行下部直腸がん 手術しないで完治の可能性も!
- 肛門温存の期待高まる最新手術 下部直腸がんTaTME(経肛門的直腸間膜切除術)とは
- 大腸のAI内視鏡画像診断が進化中! 大腸がん診断がより確実に
- 患者さんによりやさしいロボット手術も登場 新しくなった大腸がんの手術と薬物療法


