FOLFOX療法による術後補助化学療法は、日本でも標準治療となる 大腸がんの再発予防の決め手はこれだ
FOLFOX療法が選択肢となる患者さんは?
術後のFOLFOX療法は、どのような患者さんが対象になるのだろうか。MOSAIC試験では、2期と3期を合わせたデータで、有効性が明らかになっている。だが、病期ごとの解析では、3期では効果が明らかだが、2期では有意な差は出ていない。
「どういう患者さんにFOLFOX療法を行うか、明確な決まりはありません。いろいろな意見の最大公約数的なところを述べれば、3期ならFOLFOX療法が選択肢の中心になります。2期は、基本的に術後補助化学療法は不要ですが、再発の確率が高いと考えられるハイリスク群(多臓器浸潤、穿孔、閉塞、静脈浸潤、組織型が低分化型などのうち1つ以上に適合)なら、やはりFOLFOX療法が選択肢の1つになります」
3期は、進行度によって3a期と3b期に分けられるが、わが国の手術成績における手術後の再発率は、3a期が24.1パーセント、3b期が40.8パーセントとなっている。
「3b期であれば、基本的にFOLFOX療法を行うべき、というのが私の考えです」
厚生労働省が承認している適応では、2期でも3期でも、術後補助化学療法としてFOLFOX療法が行えるようになっている。ところが、術後補助化学療法としてのFOLFOX療法は、十分に行われているとは言えない状況だという。進行再発大腸がんの治療では広く普及したFOLFOX療法だが、術後の治療としてはあまり使われていない。
理由はいくつかある。外来治療室がパンク状態の病院が多いし、副作用が強いからと使いたがらない医師もいる。また、日本の手術成績は欧米に比べて優れているので、FOLFOX療法のような強い術後補助化学療法は不要だという意見もある。
「ただ、FOLFOXという治療法が承認されていて、従来の治療法を上回る成績をあげているということが、患者さんに提示されないまま、FOLFOXが使われていないとしたら、それは問題ですね」
| 病期 | 再発率 | 5年生存率 | |
|---|---|---|---|
| 1期 | 3.7% | 90.6% | 術後補助化学療法は必要なし |
| 2期 | 13.3% | 81.2% | 術後補助化学療���が必要? |
| 3a期 | 30.8% | 71.4% | 術後補助化学療法が必要 |
| 3b期 | 56.0% |
FOLFOX療法で再発を防ぎ「完治」を目指す
患者さんが理解しておきたいのは、術後のFOLFOX療法で、どのような利益が得られるかということだ。たとえがんを切除する手術を受けても、検査で見つからないほど小さながんの転移が、すでに起きている可能性は否定できない。それが増殖して再発してしまうと、治療によって延命はできても治癒の可能性はほぼなくなってしまう。FOLFOX療法を用いた術後補助化学療法がうまくいけば、小さな転移が起きていても、そのうちの何人かは治癒に導くことができるのである。
「進行がんでは、FOLFOX療法は生存期間を延ばしますが、必ずしも治る人が増えるわけではありません。ところが術後補助化学療法では、FOLFOX療法で再発せずに治る人が増えます。3期の場合、術後補助化学療法なしだと100人中30人が再発しますが、FOLFOX療法を行えば、これを22~23人に減らせます。つまり、放置すれば大腸がんが再発したであろう7~8人の命を救うことにつながるのです」
完治する人が増える。――このことにどれほどの価値があるかを考えてほしい。
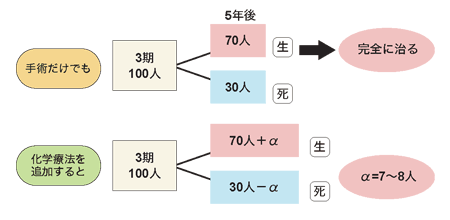
16週目以降に起こるしびれに注意する
FOLFOX療法では副作用に注意する必要がある。
「治療開始後、早期の段階から問題となるのは白血球の減少。とくに注意しなければならないのは、手術後の体力の回復が不十分なケースです」
2週毎の治療を12コース行うが、後半には、神経毒性によるしびれに注意が必要だ。
「神経毒性の現われ方は2つあります。1つは、冷たいものを触ったときにピリッとくるような急性の末梢神経障害。これはさほど問題になりません。問題なのは蓄積性の神経障害で、多くは8コース以降に現れます。指先がジーンとしびれる、といった症状から始まることが多く、悪化すると、歩きにくい、字を書きにくい、ボタンの着脱が困難になる、といった症状になります。ひどくなると生活に支障をきたすので、十分に注意しなければなりません」
しびれの程度は、〈ピリピリするが日常生活に支障なし〉がグレード1。〈日常生活に支障はないがかなり気になる〉がグレード2。グレード3は〈日常生活に支障をきたす〉レベルである。
「副作用を我慢しすぎるのはよくありません。再発を防ぐことで結果的に生活をよくする目的で治療を行うわけですから、グレード3になってはいけないというのが基本。グレード2になったら注意して、ひどくなりそうなら、しびれの原因であるエルプラットを減量したり、休薬したりします。たとえば、最後の2コースが5-FU+ロイコボリンになったとしても、術後補助化学療法を12コース最後まで(半年間)やることには意味があると思います」
しびれという症状は、見てもわからないし、数値化することもできないので、患者さんは自分の症状を的確に医療者に伝えることが大切だ。外見ではわからないからこそ医師、看護師、薬剤師などにきちんと伝えてほしい、と室さんは言う。
「近年、大腸がんの薬物療法ではさまざまな薬剤が登場し、大きく進歩しました。世界から遅れていた日本も、ようやくその承認が追いついたと言えます。しかし、ここから先10年ほどは、新しい薬の登場はあまり期待できません。ですからこれからやるべきことは、FOLFOXなど、今ある薬剤を使った治療法の中で患者さんに合ったものを的確に選択していくこと。例えば術後補助化学療法であれば、患者さんが高いクオリティで、長く生存できることを目指して、副作用をきめ細かく管理しながらきっちりと行っていくことがとても大切です」
術後のFOLFOX療法を必要とする患者さんに、きちんと治療が行われるようになってほしいものである。
同じカテゴリーの最新記事
- 切除可能な直腸がん試験結果に世界が注目も 日本の標準治療は「手術」で変わりなし
- ビタミンDの驚くべき効果がわかってきた 消化管がん手術後の再発・死亡リスクを大幅に減少
- 世界最大規模の画期的研究の一部解析結果が発表 大腸がんの術後補助療法の必要性をctDNAで判断する
- 初めての前向き試験で抗EGFR抗体薬の信頼性が確実に! 進化を続ける切除不能・進行再発大腸がんの薬物療法
- 遺伝子変異と左右どちら側にがんがあるかが、薬剤選択の鍵を握る! 大腸がん薬物療法最前線
- 化学放射線と全身化学療法を術前に行うTNT療法が話題 進行下部直腸がん 手術しないで完治の可能性も!
- 肛門温存の期待高まる最新手術 下部直腸がんTaTME(経肛門的直腸間膜切除術)とは
- 大腸のAI内視鏡画像診断が進化中! 大腸がん診断がより確実に
- 患者さんによりやさしいロボット手術も登場 新しくなった大腸がんの手術と薬物療法


