腹腔鏡下手術が普及し、新しい化学療法も登場。進行度に応じた治療法の選択を 『大腸癌治療ガイドライン』を、今後の展望を踏まえ読み解こう!
日本の手術成績がいいのは、リンパ節郭清技術のため
リンパ節に転移がある可能性が高いとき、あるいは、がんの深達度が固有筋層以上であるとき、治療の原則は外科手術です。
その場合、ステージ2以上のがんでは、D3と呼ばれるリンパ節郭清を行うことが基本で、ステージ1でも、がんが固有筋層に達している場合にはD3を行うことがあります。これが欧米と最も違う点です。
がんはリンパ管を通って転移します。そのため、転移が認められるリンパ節までをとり除くリンパ節郭清を行うわけです。D3とは、がんに近い場所から数えて、3番目の領域のリンパ節までをとるという意味です。
「欧米では、一般的にはこのような徹底したリンパ節郭清は行わず、そこまでがん細胞が広がっている場合は化学療法や放射線に委ねるという考え方が主流です。ですから、D3を薦めるようなガイドラインもありません。しかし、日本の大腸がん手術の成績がいい理由は、間違いなくこのD3という系統的な郭清にあると、多くの日本の外科医は考えています。
また、腹腔鏡下手術が進行がんに行われるようになった背景にも、腹腔鏡下手術で開腹手術と同様にD3ができるようになったことがあげられます。日本ではそのくらい、大腸がんにおけるリンパ節郭清が重視されています」(固武さん)
現に、がんが固有筋層より深く浸潤しているステージ2のがんでも、5年生存率は約80パーセントにまで達しています。
直腸がん、とくに肛門に近い部位の直腸がんでは、がんを完全に取り除き、リンパ節郭清を徹底的に行うためには骨盤内の神経を切除する必要があることがありますが、神経を切除すると、性機能障害や排尿障害といった機能障害が起こります。しかし、日本では神経を残しながらリンパ節郭清を行う技術(骨盤神経温存術)も普及しており、できるだけ機能障害を軽くするように配慮した手術が行われています。


直腸がん治療化学療法との併用
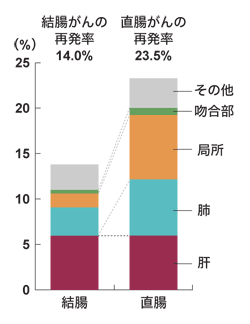
『ガイドラインサポートハンドブック 大腸癌 改訂版』より
結腸がんは、術後に機能障害が問題になることは多くありませんが、直腸がんの術後にはいろいろな機能障害がおこります。また、肛門に近い部位の直腸のがんでは、直腸とともに肛門も切除して、人工肛門にしなければならないことがあります。さらに、直腸がんは、結腸がんよりも局所再発(初めにがんができた近くの場所に起こる再発のこと)が起こりやすいという特性があります。
日本では歴史的に『直腸がんは手術で徹底的にとる』というのが基本方針で、化学療法や放射線の効果にあまり期待していませんでした。しかし、最近、結腸がんに対する化学療法の有効性を示すエビデンスが出てきたため、直腸がんでも化学療法の併用が見直されています。
2009年版では、従来、結腸がんのステージ3に薦められていた術後補助化学療法が直腸がんにも推奨されるようです。
また、放射線については、従来と同様にオプションとして掲載するにとどまるものと思われますが、がん組織にだけ集中的に放射線を当てる精度の高い治療が確立されてきている今日、たとえば肛門付近にできたがんを放射線であらかじめ小さくし、人工肛門を回避して肛門を温存する手術を行うといった治療法も可能になってきているようです。
栃木県立がんセンター
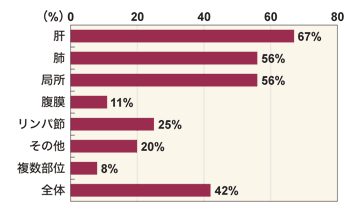
[再発がんの切除成績]
栃木県立がんセンター
| 再発部位 | 5年生存率 |
|---|---|
| 肝 | 48.00% |
| 肺 | 57.90% |
| 局所 | 19.00% |
| その他 | 26.80% |
| 全体 | 44.00% |
「直腸がんの局所再発は、再手術をしても治りにくく、患者さんのQOL(生活の質)もいちじるしく低下します。局所再発を防ぐために、欧米では手術の前に放射線治療と化学療法を行う『術前化学放射線治療』が標準治療として確立され、局所再発は少なくなってきています。腫瘍を小さくすることで人工肛門を回避することも大きなメリットですが、よいことばかりではありません。生存率を高める効果は十分に確認されていないこと、放射線の副作用による機能障害がかなり発生することなどがあり、日本の手術の補助療法としては標準治療とする段階ではないと考えています」(固武さん)
「人工肛門については、日本では70年代から肛門温存手術が徐々に普及しはじめ、その後の発展は飛躍的です。70年代には直腸がんでは4人に3人が人工肛門になりましたが、今や4人に1人以下と数字が逆転しているのです。
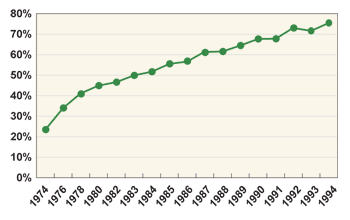
肛門は一部でも切除すると、形は残っても機能が著しく悪くなるといわれ、かつては肛門にメスを入れてはいけないとされていました。しかし、現在は肛門内の筋肉にまで切り込んで、がんをとり除くISR(内肛門括約筋切除)という手術も行われるようになりました。人工肛門にするのと、どちらがQOLがいいか、現在、比較検討が行われているところです」(固武さん)
患者さんにとっても治療の選択肢は増えそうですが、手術を検討するときにも症例数などは確認したほうがよい、と固武さんは語ります。
「開腹手術の技術はほぼ全国的に統一されてきていますが、やはり症例数や治療成績をきちんと把握して公開している病院は、優れた成績をおさめている場合が多いといえます。
もう1つ、直腸がんの場合は、機能を残せるか、肛門を残せるかを確認し、残せないといわれたときは十分納得できる説明を受けることです。納得できないときは、セカンドオピニオンを聞くことをお勧めします。そして、どうしても機能が損なわれてしまう場合は、どんな機能障害が起きてくるか、それに対してどんな対応があるかについても、手術の前にきちんと聞いておくことが大切です」
同じカテゴリーの最新記事
- 切除可能な直腸がん試験結果に世界が注目も 日本の標準治療は「手術」で変わりなし
- ビタミンDの驚くべき効果がわかってきた 消化管がん手術後の再発・死亡リスクを大幅に減少
- 世界最大規模の画期的研究の一部解析結果が発表 大腸がんの術後補助療法の必要性をctDNAで判断する
- 初めての前向き試験で抗EGFR抗体薬の信頼性が確実に! 進化を続ける切除不能・進行再発大腸がんの薬物療法
- 遺伝子変異と左右どちら側にがんがあるかが、薬剤選択の鍵を握る! 大腸がん薬物療法最前線
- 化学放射線と全身化学療法を術前に行うTNT療法が話題 進行下部直腸がん 手術しないで完治の可能性も!
- 肛門温存の期待高まる最新手術 下部直腸がんTaTME(経肛門的直腸間膜切除術)とは
- 大腸のAI内視鏡画像診断が進化中! 大腸がん診断がより確実に
- 患者さんによりやさしいロボット手術も登場 新しくなった大腸がんの手術と薬物療法


