本来のがん種の性格が治療法を左右する あくまでも大腸がんとの闘い! 大腸がん肝転移の治療法
術死、ほぼゼロの安全性
原発性肝がんは、慢性肝炎から肝硬変を経て出てくるケースが約90パーセントを占めるので、かなり肝機能が悪くなったところに発生する。一方、転移性の肝がんは正常な肝臓の中に出てくる。これが手術の安全性の上でも、成績にも、大きな差となって現れるのだ。
「転移性肝がんの手術死亡は日本ではほとんどゼロです。手術の翌日には水やお茶が飲め、その翌日から三分粥、翌日が五分粥、翌日に全粥、手術から5日目くらいにはご飯が食べられます。それほど大きくない手術の場合、1週間から10日で退院が可能です。以前私がいた病院で、転移性肝がんの手術の統計をとりましたが、なんらかのトラブルでクリニカルパス(診療計画書)の通りに行かずに再手術になった例はわずか4パーセントほどでした。そこで私は患者さんには『100人手術したら96人は2週間以内に退院できます』と説明します。この病院に来てから、予定通りに退院まで行かなかった人はいません」
ただ肝臓の手術はどうしても傷が大きくなりがちだ。だからたとえ1週間くらいで退院できても2週間目の外来で「傷が痛い」と訴える人はいる。
「最近、うちの科で96歳の男性が転移性肝がんの手術を受けられました。半年前に大腸がんの手術を受けており、肝臓に1個だけ腫瘍が見つかったということで紹介されてみえたケースです。『ラジオ波焼灼療法という選択もある』とお伝えしましたが、本人が手術を希望されました。術後、1週間程度で退院されています。もちろん手術の適応は慎重に考えなければなりませんが、年齢的にも許容範囲が広いことを示す1例です」
また肝切除の方法として、腹腔鏡を使った手術法もある。当然、腹腔鏡なら開腹手術より傷ははるかに小さくできる。
「ただ、肝臓は大きくて厚みのある臓器なので、10センチくらい傷口を作らないと摘出した腫瘍が取り出せません。また切除している時の出血をどうコントロールするかも難しい問題です。転移巣が肝臓の端っこにある場合や表面にある場合に、主に適用されています。現状の器械だと肝切除例の半分以上のケースでは腹腔鏡で行うということにはならないでしょう」
| 報告者(年) | 症例数 | 再肝切除率 | 生存率(%) | 50%生存期間(月) | 術死率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3年 | 5年 | |||||
| Bozzetti(1992) | 10 | 9.2 | 36 | - | 25 | 9 |
| Vaillant(1993) | 16 | 8.4 | 57 | 30 | 33 | 6.2 |
| Fong(1994) | 25 | 5 | - | - | 30 | 0 |
| Nordlinger(1994) | 116* | 6.4 | 33 | - | 24 | 0.9 |
| Fernandez-Trigo(1995) | 170* | - | 45 | 32 | 34 | - |
| Adam(1997) | 64 | 26 | 60 | 41 | 46 | 0 |
| Yamamoto(1999) | 75 | 21 | 48 | 31 | 31 | 0 |
| Suzuki(2001) | 26 | 27 | 62 | 32 | 31 | 0 |
| Petrowsky(2002) | 126* | 8.5 | 51 | 34 | 37 | 1.6 |
転移性肝がんの性格
(ラジオ波焼灼療法を行う場合)
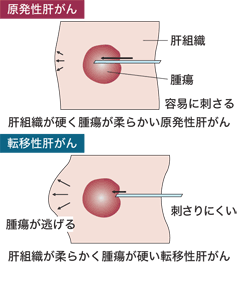
肝細胞がんの細胞は、たんぱくを合成したり胆汁を作ったりする肝臓の機能を受け継いでいる。これに対して、転移性肝がんの細胞は肝臓の中にあっても、原発の大腸の細胞の性格をそのまま持っている。すなわち、消化管の粘膜を覆ったり粘液を造ったりする機能があるのだ。
「肝細胞がんの治療法としてラジオ波焼灼療法は広く行われていますが、大腸がんの肝転移に対してはあまりメジャーではありません。理由の1つは、がん組織の違いにあります。丸くて羊羹のような形をした肝細胞がんは柔らかく、それを支える肝臓が肝硬変で硬くなっているので、外から針をブスッと突き刺しやすいのです。一方、転移性肝がんは硬いのに、柔らかい健康な肝臓の中にあるので、針を刺すときにがん巣が逃げてしまい、正確に穿刺するのに技術を要します」
もう1つ、肝細胞がんと転移性肝がんの大きな違いは、治療効果が余命に与える影響。肝細胞がんは肝硬変の肝臓にできるため、1カ所から出てきた腫瘍を根こそぎ治療しても、肝臓の他の場所から別の腫瘍が出てくるなど5年以内の再発率が80~90パーセントもあることがわかってきた。これに対し、切除の対象となるような大腸がんの肝転移は、肝細胞がんのように次々出てくることはそれほど多くない。転移性肝がんの1カ所をきちんと治療するメリットは、肝細胞がんに比べてはるかに大きいというわけだ。
また肝細胞がんにおいて、ラジオ波治療が外科治療に対して有利な点として、侵襲が少ないために、1回の治療が不完全でも繰り返して治療できることがある。肝硬変の肝臓を何度も手術するのは困難だからだ。しかし転移性肝がんでは、再肝切除も繰り返し安全に可能なので、この点でのラジオ波治療のアドバンテージもない。
切除できないときの化学療法
大腸がん肝転移でも、肝切除ができない例に対しては、抗がん剤治療が行われる。もちろん大腸がんの肝転移には、大腸がんに有効な抗がん剤が用いられる。この分野では、日本でも2000年代になってFOLFOX(フルオロウラシル、ロイコボリン、オキサリプラチンの併用)やFOLFIRI(フルオロウラシル、ロイコボリン、イリノテカンの併用)という抗がん剤のメニューが普及し、成績が向上した。さらにこれらの抗がん剤治療の効果を高める抗血管内皮増殖因子抗体アバスチン(一般名ベバシズマブ)が併用されることもある。こうした抗がん剤治療を行うことによって、がんが小さくなって肝切除が可能になる場合もある。
しかし、これらはかなり強力な薬物療法なので、このために肝臓を傷めてしまうこともあり、どんなケースで抗がん剤治療を導入するかが問題になる。
「切除できない場合は抗がん剤をまず使い、もし切除できるようになったら切除するという用い方なら異論ありません。これに対してよく議論されるのは、もともと切除できるのに抗がん剤を使ってがんを小さくしたり効果を確認してから切除しようという考え方です。確かにそうしたほうがわずかに治療成績がよくなるという海外の報告もありますが、日本ではまだ有効だという証拠がありません。現状での私のスタンスは外科切除できる人はまず切除して、そのあと抗がん剤を希望する人には臨床試験で行っています」
同じカテゴリーの最新記事
- 切除可能な直腸がん試験結果に世界が注目も 日本の標準治療は「手術」で変わりなし
- ビタミンDの驚くべき効果がわかってきた 消化管がん手術後の再発・死亡リスクを大幅に減少
- 世界最大規模の画期的研究の一部解析結果が発表 大腸がんの術後補助療法の必要性をctDNAで判断する
- 初めての前向き試験で抗EGFR抗体薬の信頼性が確実に! 進化を続ける切除不能・進行再発大腸がんの薬物療法
- 遺伝子変異と左右どちら側にがんがあるかが、薬剤選択の鍵を握る! 大腸がん薬物療法最前線
- 化学放射線と全身化学療法を術前に行うTNT療法が話題 進行下部直腸がん 手術しないで完治の可能性も!
- 肛門温存の期待高まる最新手術 下部直腸がんTaTME(経肛門的直腸間膜切除術)とは
- 大腸のAI内視鏡画像診断が進化中! 大腸がん診断がより確実に
- 患者さんによりやさしいロボット手術も登場 新しくなった大腸がんの手術と薬物療法


