大腸がん治療薬5剤を用いて30カ月の生存期間延長が可能になった 目覚ましい進歩をとげる大腸がんの分子標的治療
承認が待たれるアービタックス
- EGFR阻害剤
- モノクローナル抗体
- 投与量は初回400mg/kg、以降250mg/kg
- 単剤でも有効、化学療法に上乗せもする
- 奏効率は単剤では10%
- 副作用は皮疹
- 重篤な副作用は少ない
- 第2、第3次治療で用いる
アービタックスもモノクローナル抗体の一種だが、こちらは、がん細胞が増殖するために必要なシグナルを受け取るEGFR(上皮成長因子受容体)というタンパク質を標的としている。アービタックスがEGFRと結合すると、がん細胞の表面に顔を出してアンテナの役割をしているEGFRは働けなくなり、その結果、シグナル伝達が遮断され、がん細胞は増殖できなくなってしまう。
ただし、アービタックスは欧米では承認されているが、日本では未承認。07年2月に申請が行われ、08年中の承認が期待されている。
アービタックスについての臨床試験は04年に発表された「BOND試験」が有名だ。イリノテカンで進行を止められなかった転移性・進行性の大腸がん患者218人に対して、イリノテカンとアービタックスの併用療法を行ったところ、半数の患者で進行を4カ月以上遅らせることができ、20パーセントの患者では50パーセント以上の縮小がみられた。
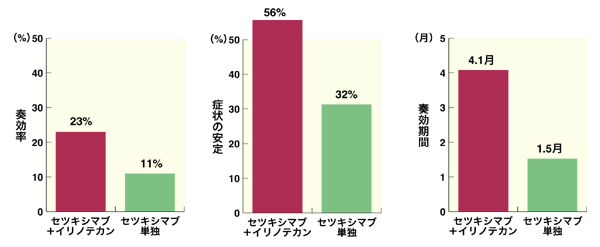
その後に行われたほかの臨床試験でも高い奏効率と生存期間の延長が認められており、日本でも同様の成績が得られているという。
併用療法で生じた副作用には軽微なものが多く、イリノテカンの副作用をアービタックスが増強することはなかったという。
「アービタックスに特有の副作用としては、海外の臨床試験では皮膚障害、とくににきび様の発疹が報告されています。しかし、アバスチンの血栓などに比べれば、皮膚の発疹は美容的には問題があるものの、感染を起こさなければコントロールが可能なので、扱いやすい副作用だとはいえます」
アービタックスと同じようにEGFRをターゲットにする分子標的薬として、イレッサやタルセバという薬がある。とくにイレッサは間質性肺炎など重篤な副作用が相次いで社会問題になるほどだったが、アービタックスはイレッサなどと”親戚”の薬ではあっても作用メカニズムはまるで違うという。
抗体であるアービタックスは大分子化合物なので細胞膜を通過することはできず、細胞の表面にある受容体に作用する。一方、イレッサ、タルセバは、細胞膜を通過できる小分子化合物。がん細胞の中に入り込み、異常な増殖シグナル伝達を断ち切る役割を果たす。
分子標的薬が意外に使われない理由
アービタックスはどのような使われ方をするのだろうか?
「最新の試験の結果では、アービタックスは第1、第2治療ではなく、第3治療での効果が1番注目されています。しかし、第1、第2治療での臨床試験の結果も出つつあり、1~2年後には第1治療でもアービタックスを使うようになっているかもしれません」
日本での承認はまだ先だが、第1治療でFOLFOX+アバスチンが勧められているので、第2治療としてFOLFIRI+アービタックスが予想されるという。
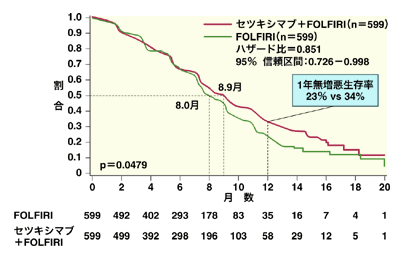
また、「ファイブドラッグセオリー」という考え方があり、FOLFOX、FOLFIRIに使う5-FU、カンプト(トポテシン)、エルプラットに加えて、アバスチン、アービタックスの5剤が入っていれば、どちらが先でもいいし、どの組み合わせでもいい、という意見もある。
たしかに、この5剤を用いると生存期間は有意にのびている。臨床試験によって幅はあるものの、平均して30カ月ぐらいまでの生存期間の延長が可能になっているという。
しかし、これほど期待の大きい分子標的薬にもかかわらず、アバスチンの使用は予想よりはるかに少ない、と水沼さんは指摘する。
理由の1つとして、イレッサによる副作用の問題が尾を引いていることがあげられていて、「イレッサの二の舞を避けて、しばらくは様子をみたほうがいい」と慎重になっている医療関係者が多いのでは、といわれている。
だが、毎年、10万人近くが罹患し、約4万人もの人が亡くなっているのが大腸がん。アバスチンを待ち望んでいた患者さんは少なくないはず。エビデンス(科学的根拠)があるなら、新しい治療により積極的に取り組むべきではないのか。
なお、アバスチン、アービタックスに続く分子標的薬として、パニツムマブ、マツズマブが開発され、臨床試験が行われている。
このうちパニツムマブはアービタックス同様、EGFRをターゲットにする薬で、欧米ではすでに承認されている。副作用は比較的少ないものの、効果はアービタックスより落ちる可能性がある。
一方、マツズマブは、第2相臨床試験で期待したほどの効果が得られず、開発が中止されている。
同じカテゴリーの最新記事
- 切除可能な直腸がん試験結果に世界が注目も 日本の標準治療は「手術」で変わりなし
- ビタミンDの驚くべき効果がわかってきた 消化管がん手術後の再発・死亡リスクを大幅に減少
- 世界最大規模の画期的研究の一部解析結果が発表 大腸がんの術後補助療法の必要性をctDNAで判断する
- 初めての前向き試験で抗EGFR抗体薬の信頼性が確実に! 進化を続ける切除不能・進行再発大腸がんの薬物療法
- 遺伝子変異と左右どちら側にがんがあるかが、薬剤選択の鍵を握る! 大腸がん薬物療法最前線
- 化学放射線と全身化学療法を術前に行うTNT療法が話題 進行下部直腸がん 手術しないで完治の可能性も!
- 肛門温存の期待高まる最新手術 下部直腸がんTaTME(経肛門的直腸間膜切除術)とは
- 大腸のAI内視鏡画像診断が進化中! 大腸がん診断がより確実に
- 患者さんによりやさしいロボット手術も登場 新しくなった大腸がんの手術と薬物療法


