アバスチンの恩恵を最大限に受けるために アバスチン登場で大腸がん治療はどう変わる?
3次治療以降では使えない
アバスチンは、治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸がんであっても適応とならない場合がある。その1つは、1次治療、2次治療とすでに2種類以上の化学療法が行われ、効果がみられなくなった場合だ。なぜなら、海外において、このような患者さんを対象にアバスチンを加えた治療の臨床試験を行った結果、効果が得られたのはたった1パーセントで、重篤な副作用などのリスクのパーセンテージが高くなってしまったのだ。
「1パーセントでもいいからアバスチンを加えた治療を希望される患者さんがいらっしゃる。しかし、消化管に穴があく、出血するなどの重篤な副作用が起こるリスクが効果(ベネフィット)を上回ることを説明すると、投与できないことを納得していただける。治療はリスクとベネフィットを勘案して選択すべき。アバスチンを加える治療は、ベネフィットがリスクを上回る1次治療または2次治療での選択が重要となります」
また、この他にも、注意が必要な場合があり、胃潰瘍の方、大きな手術を受けてから1カ月以内の方、血が止まりにくい体質の方、3カ月以内に血栓症(脳梗塞、心筋梗塞、深部静脈血栓症、肺塞栓症)にかかった方、血圧のコントロールができていない方、腸閉塞の方などが該当する。
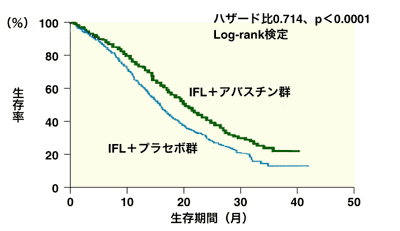
| IFL+プラセボ群 | IFL+アバスチン群 | p値 | |
|---|---|---|---|
| 生存期間 | 15.80ヵ月 | 20.37ヵ月 | <0.0001 |
| 奏 効 率 | 34.8% | 45.0% | 0.0029 |
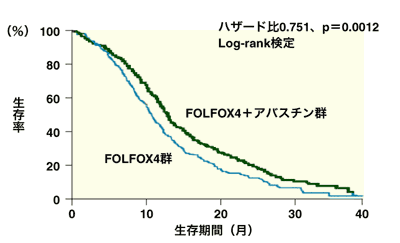
| FOLFOX4+プラセボ群 | FOLFOX4 +アバスチン群 | p値 | |
|---|---|---|---|
| 生存期間 | 10.8ヵ月 | 13.0ヵ月 | 0.0012 |
| 奏 効 率 | 8.6% | 22.2% | <0.0001 |
リスクを最小限に抑え、治療の継続を
従来の抗がん剤は、がん組織だけでなく正常な組織まで攻撃してしまうため、さまざまな副作用があらわれる。一方、アバスチンは、正常な組織にはほとんど作用しないものの、正常な血管の仕組みに影響することがあり、従来の抗がん剤とは異なる特徴的な副作用があらわれることがある。アバスチンを一緒に使用することにより、抗がん剤だけの治療を受けた場合に比べ多くみられる副作用としては、高血圧、たんぱく尿、鼻血などの粘膜からの出血、白血球の減少。また、頻度が高くないものの、あらわれれば重篤になる副作用として、消化管に穴があく(消化管穿孔)、傷口が治りにくい、がん組織からの出血、血栓ができるなどがある。「アバスチンの副作用を過剰に恐れることはない。これらの副作用については早期対応が重要で、病院でも血圧測定、尿検査、血液検査など定期的にチェックが行われます。さらに患者さん自身が、どんな副作用(症状)があらわれる可能性があるかをあらかじめ理解し、腹痛、出血がとまらない、発熱、めまいがするなどの症状がでた場合には、すぐに医師や看護師に連絡するなどの対応策を知っておくことが大切です」
また、アバスチンによる治療中は出血しやすくなるため、歯周病の方は口腔内ケア、痔の方はそのケアを治療開始前に行っておくことも肝要だ。
一方、アバスチンは他の抗がん剤と一緒に投与されるため、他の抗がん剤の副作用にも注意することが必要だ。主なものとしては、白血球減少、吐き気などがあげられるが、特徴的なものとしてFOLFOXに用いるエルプラットは手足のしびれが高頻度にあらわれ、FOLFIRIに用いるカンプトは下痢、倦怠感の発現が高い。ただし、副作用の発現は個人差が大きく、白血球減少などの血液毒性がでやすい方もあれば、吐き気、下痢などの非血液毒性が強くでる方もいる。
「副作用が生活に支障をきたす程度というのは患者さん1人ひとりで異なる。たとえば、しびれが出た場合に、ある方は問題なくても、手先を使う仕事をされている方には非常に問題になってしまうこともある。また、脱毛が大きな問題となる方には脱毛の発現頻度が高いFOLFIRIではなく、比較的低いFOLFOXを選択するということもできるし、全身状態などを考慮して、最初から3剤併用療法ではなく、5-FU+アイソボリンという治療を選択することもできる。FOLFOXあるいはFOLFIRIのどちらを先に選択してもよいという意見もあるが、1次治療の期間がもっとも長いことを考えると、患者さんの体質、価値観、生活を考慮して治療を選択するということが大切です」
FOLFOXでは副作用による治療の変更は6割を占め、がんの進行による変更よりも多い。
「しびれというエルプラット特有の副作用のために、その他の併用薬剤すべてを中止にするのではなく、エルプラットのみを中止すべき。副作用には対症療法あるいは当該薬剤の減量・中止にて対応し、可能な限り治療を継続することが良好な結果につながる」という。こうした背景には、化学療法を継続している方が、中止するよりも生存期間の延長につながることが示されているからだ。
施設を限定した使用に
アバスチンは、厚生労働省の優先審査によって、海外で行われた臨床試験成績を基に、国内での臨床試験を簡略化し、必要最低限の臨床試験成績のみで認可された。そのため、国内での患者さんのデータが極めて少ない。こうした状況を踏まえ、承認時の条件として、「製造販売後、一定数の症例に係わるデータが集積されるまでは、全症例を対象に使用成績調査を実施することにより、使用患者の背景情報を把握するとともに、安全性および有効性に関するデータを早期に収集し、適正使用に必要な措置を講ずること」ということが課せられた。これを受けて販売元の中外製薬株式会社は、2500人を目処に調査を行うこととし、発売後一定期間は使用できる施設を副作用への緊急対応が可能で、全例調査に協力可能な施設に限定した。
「国内での症例数が少ない現状を踏まえれば、当然の措置といえます。ただ、一部の患者さんが、アバスチンの治療を受けられないという事態は避けるべきと考えます」
ただ、先にも記載したとおり、すべての患者さんでアバスチンの効果が期待できるというわけではないため、アバスチンが使える病院を探す前に、主治医とよく相談することが大切だ。
日常生活での制限はほとんどない
アバスチンを含む併用療法は、基本的に外来で行うことができる。日常での留意点は、CVポート(FOLFOXやFOLFIRIを行う場合に、薬を静脈に送り込むために皮下に埋め込む医療機器)による周囲の傷や炎症に注意が必要なぐらいで、それ以外にほとんど制限はなく、普通の生活が送れ、仕事も続けられる。
「入院でなく外来で治療ができるということは、家族や友人と食事をしたり、仕事をしたりという社会との接点を持っていられるということ。患者さんには、病院に来たときのみ、がんを思いだしてもらい、それ以外の日常生活では忘れていて欲しい」と吉野さん。患者さんの生活スタイルの違いはあるだろうが、治療に専念しすぎないほうが、メンタル的にもよりよく治療を進めていくことにつながる。
「アバスチンを追加する最大のメリットは、これまで切除不能だった患者さんの10~15パーセントで手術が可能となり、治癒を望める治療に移行できること。言い換えれば、治癒する希望を持てるということ」
これまでの抗がん剤にはない、重篤な副作用の発現というリスクに留意しなければならないが、治癒する希望が持てるというのは大きな治療の励みになるのではないだろうか。
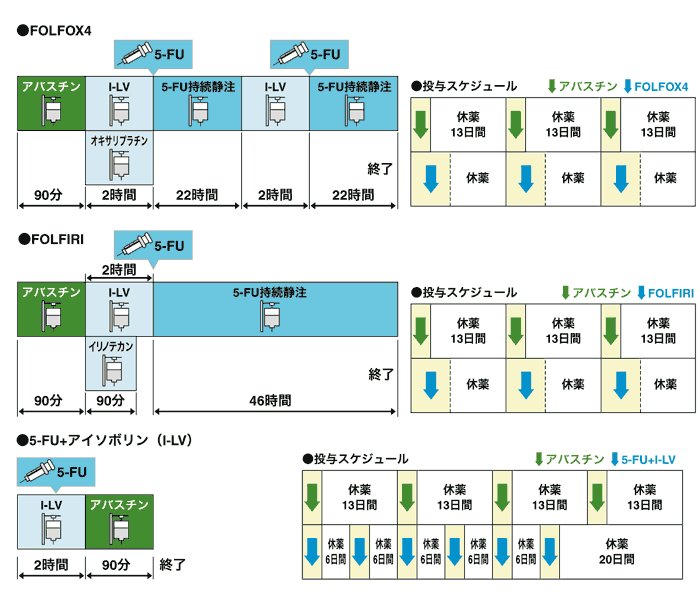
同じカテゴリーの最新記事
- 切除可能な直腸がん試験結果に世界が注目も 日本の標準治療は「手術」で変わりなし
- ビタミンDの驚くべき効果がわかってきた 消化管がん手術後の再発・死亡リスクを大幅に減少
- 世界最大規模の画期的研究の一部解析結果が発表 大腸がんの術後補助療法の必要性をctDNAで判断する
- 初めての前向き試験で抗EGFR抗体薬の信頼性が確実に! 進化を続ける切除不能・進行再発大腸がんの薬物療法
- 遺伝子変異と左右どちら側にがんがあるかが、薬剤選択の鍵を握る! 大腸がん薬物療法最前線
- 化学放射線と全身化学療法を術前に行うTNT療法が話題 進行下部直腸がん 手術しないで完治の可能性も!
- 肛門温存の期待高まる最新手術 下部直腸がんTaTME(経肛門的直腸間膜切除術)とは
- 大腸のAI内視鏡画像診断が進化中! 大腸がん診断がより確実に
- 患者さんによりやさしいロボット手術も登場 新しくなった大腸がんの手術と薬物療法


