大腸(結腸)がんの診断から治療まで 「大腸癌治療ガイドライン」をやさしく読み解くために
リンパ節郭清をどこまやるか
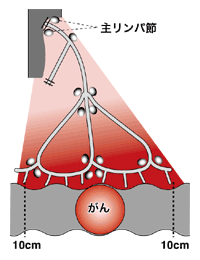
手術の場合に問題となるのは、リンパ節郭清をどこまでやるかだ。リンパ節郭清は、腸管の近くにあるリンパ節(1群)の郭清にとどめるのか、血管の根元まではいかないがその手前ぐらいまでの部分(2群)を郭清するか、血管の根元まで(3群)広く郭清するか、に分けられていて、がんの進行度によって決められる。
「通常、一般的に行われているステージ2以上の手術に関していえば、血管の根元まで含めるリンパ節郭清(D3郭清)が行われます。このとき、よく患者さんに説明するのは、血管の根元はちょうど扇子の要の部分にあたり、がんは必ずこの要の部分に集まるということです。がんを取るとき、病気の場所だけ取ってもダメで、正常な部分であっても、そのなかにがんを閉じ込めるような形で取ってこないといけないんですよ、というと『よくわかりました』と納得してくれます」
ステージ1であれば、腸管近くのリンパ節を取るだけのD1郭清で終わる可能性が高い。
「しかし、SMがんであったり、粘膜下層あるいはそれより進んで筋肉まで入ってくるような場合には、D3郭清が一般的に行われます。ガイドラインにもとづいて手術を行っていることが多いと思います」
腹腔鏡と開腹の違いは?
手術では、腹腔鏡手術と開腹手術のどちらを選択するかが問題となる。これについて高橋さんはこう語る。
「腹腔鏡手術の技術はどんどん進歩しています。直腸は細かい操作が必要となるので、まだ開腹のほうがいいような気がしますが、結腸に関しては、技術的には開腹と比べて遜色ないといえます。ただ、開腹手術なら、全国的にみて技術的な差はほとんどありませんが、腹腔鏡は施設によって差があるというのが問題点としてあげられます。早期がんに対しては腹腔鏡でいいですが、進行がんに関しては、どの程度までやっていいかは施設の技量によって違ってきます。あまり腹腔鏡手術に慣れていないと���ろだと、がんを取り残す恐れがあるので要注意です」
腹腔鏡の手術の場合、侵襲が少ないので回復が早い、退院までの日数が短い、などのメリットがある。しかし、開腹手術の技術も進んでおり、退院までの日数はだいたい10日以内と、腹腔鏡と比べてあまり差がなくなっているという。
また、手術時間は開腹のほうが短くてすみ、結腸がんの場合、腹腔鏡手術の6~7割の時間で手術できる。この点は逆に開腹手術のメリットといえる。
「手術室も手術時間も限られていて、でも手術のクオリティを下げないことを考えれば、腹腔鏡の手術より開腹の手術をせざるを得ない。結局のところ、メリット、デメリットの差はあまりなく、治療成績の差もありません。施設ごとにどちらを専門にしているかで選択されればよいと思います」
手術の合併症としては、縫合不全、腸閉塞、創感染などがあげられる。しかし、縫合不全は結腸に関してはほとんどない、と高橋さん。
「そもそも、傷が治るときに癒着は必ず起きるものです。癒着がなければ傷は治りません。たとえば、腸と腸を糸で縫った直後に糸を切れば外れてしまいますが、1週間そのままにしておけば、糸を切ってもはずれません。どうしてかというと、癒着の力で治しているからです。腸をちゃんと並べ替えたり、癒着しても腸の流れが障害されないように、外科医はちゃんと気をつかっており、腸閉塞もたいていは大丈夫です。もちろん、それでも癒着しやすい人はいるので万全の対策が欠かせませんが」
補助化学療法の標準治療
手術後は補助化学療法が考慮される。しかし、どんな抗がん剤を使うかについては決定打がない、という。
「手術で治癒切除したという場合、補助化学療法が必要になるのかならないのかですが、一般的には、ステージ2までは補助化学療法は必要ないのではないかと、日本では一定のコンセンサスが得られています。ただ、ステージ2でも再発の高危険群というのがあって、その人たちに対しては補助化学療法が必要といわれていますが、これについてもまだそうと決まったわけではありません」
ステージ3の患者に対しては術後補助化学療法が行われ、5-FU(一般名フルオロウラシル)とロイコボリン(一般名ホリナートカルシウム)の注射薬または内服薬を投与するのが一般的だ。
内服薬で一般的に使用されているのは、UFT(一般名 テガフール・ウラシル)/ユーゼルもしくはロイコボリン、TS-1(一般名 テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム)であるが、エビデンスがあるのはUFT/ユーゼルもしくはロイコボリンで、TS-1は胃がんについてはエビデンス(根拠)があるが、大腸がんについてはまだ示されていない。
それ以外にも、欧米ではFOLFOX療法と呼ばれる治療法が標準治療となっている。これは、エルプラット(一般名オキサリプラチン)を含む多剤併用療法のことだが、日本では補助化学療法でFOLFOX療法を行うことは認められていない。
日本は欧米と比べて手術成績が優れている
世界標準の治療法がなぜできないのか。高橋さんはこう解説する。
「日本では、ステージ2で治癒切除ができれば、平均すると手術単独で80パーセント以上の5年生存率が得られます。補助化学療法を使えば5パーセント上乗せして5年生存率を85パーセントにすることができるかもしれません。ところが、欧米の治療成績は、手術単独だと60パーセントからよくて70パーセントです。そこで補助化学療法としてFOLFOX療法をやって、ようやく80パーセントになっている。このため、FOLFOX療法がスタンダードの治療法になっているんです。このように、欧米の治療成績と日本の治療成績には違いがあるので、欧米のトライアル(大規模比較試験)をそのまま日本に当てはめることはできないんです。」
FOLFOX療法は、効果が大きいかわりに副作用も強い。それよりは、手術後の患者のQOL(生活の質)を考慮し、なおかつ予防にも効果のある薬というので、パワーは落ちるけれども、現在行われている化学療法で十分なのでは――というのが今のところの日本のコンセンサスということなのだろう。
同じカテゴリーの最新記事
- 切除可能な直腸がん試験結果に世界が注目も 日本の標準治療は「手術」で変わりなし
- ビタミンDの驚くべき効果がわかってきた 消化管がん手術後の再発・死亡リスクを大幅に減少
- 世界最大規模の画期的研究の一部解析結果が発表 大腸がんの術後補助療法の必要性をctDNAで判断する
- 初めての前向き試験で抗EGFR抗体薬の信頼性が確実に! 進化を続ける切除不能・進行再発大腸がんの薬物療法
- 遺伝子変異と左右どちら側にがんがあるかが、薬剤選択の鍵を握る! 大腸がん薬物療法最前線
- 化学放射線と全身化学療法を術前に行うTNT療法が話題 進行下部直腸がん 手術しないで完治の可能性も!
- 肛門温存の期待高まる最新手術 下部直腸がんTaTME(経肛門的直腸間膜切除術)とは
- 大腸のAI内視鏡画像診断が進化中! 大腸がん診断がより確実に
- 患者さんによりやさしいロボット手術も登場 新しくなった大腸がんの手術と薬物療法


