ASCO2006 大腸がん編 次々に出てくる新しい大腸がんの化学療法。が、副作用や経済的問題点も
新しい治療法、FOLFOXIRI療法
ASCOにおけるもう1つの大きな話題は、進行・再発大腸がんに対するFOLFOXIRI療法という新しい治療法が登場したことだ。いわば5-FU+ロイコボリンにカンプト(またはトポテシン)を加えたFOLFIRI療法に、さらにもう1つエルプラットを加えた多剤併用療法である。
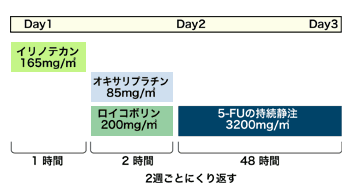
FOLFOXIRI療法の治療成績は、転移を有する進行大腸がんの患者244人を2つのグループ(122人ずつ)に分け、一方にFOLFOXIRI療法、もう一方にFOLFIRI療法を行った無作為化比較試験の結果によって立証された。
「その結果は、FOLFOXIRI療法の奏効率が60パーセントにのぼるという劇的なもので、34パーセントだったFOLFIRI療法の奏効率の2倍近くに達したのです。これはFOLFOX療法にアービタックスを加えた多剤併用療法と同じくらい高い奏効率だといえます」(久保田さん)
加えて、FOLFIRI療法で転移巣が消失し、手術を受けられるようになった患者は6人にとどまったのに対して、FOLFOXIRI療法で手術が受けられるようになったのは2倍以上の15人にのぼったのである。
「通常、進行大腸がんに対する1番手の治療法としてFOLFIRI療法を行った場合、それが効かなくなったらFOLFOX療法に切り替えます。実際、この無作為化比較試験でFOLFIRI療法のほうに割り付けられた患者のうち、その後、約7割がFOLFOX療法に切り替えられました。『それなら最初からFOLFOXIRI療法を行ったほうがよいのではないか』という主張も明らかにされていました」(久保田さん)
いずれにしても、これまでは進行・再発大腸がんに対して約50パーセントの奏効率をあげるFOLFOX療法とFOLFIRI療法が第1選択肢の治療法とされてきた。
しかし、今後は約60パーセントの奏効率をあげたFOLFOXIRI療法や、FOLFOX療法にアービタックスなどの抗体医薬を加えた治療法がゴールドスタンダードになるだろうというのが今年のASCOで確認されたことである。
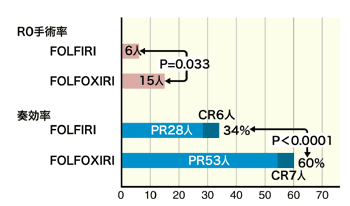
これまでにない副作用に注意
しかし、アービタックスなどの抗体医薬を加えた新たな治療法は、2つの点で大きな問題を有していることも明らかにされた。
1つは、抗体医薬による新たな副作用が加わる可能性が大きいため、��者の生活の質(QOL)が低下しかねず、医師による厳格な管理が求められることだ。アービタックスには発熱や悪寒、発疹、呼吸苦、鼻粘膜の異常、日光過敏症、下痢、痛みなどの副作用がある。
「アバスチンの副作用としては出血傾向や高血圧、消化管穿孔などがあげられます。血管が破れたり腫瘍が壊れたりして、大量出血する副作用も報告されています」(久保田さん)
FOLFOX療法やFOLFIRI療法とは異なった副作用が、新たに生じて付け加わる可能性は大きいといえる。
もう1つは、アービタックスやアバスチンは非常に高価な薬なので、医療費を賄う保険財政が大きく圧迫されてしまうことだ。
「事実、FOLFOX療法は1カ月に40万円近くかかりますが、それにアービタックスやアバスチンを加えると1カ月に要する費用は90万円前後と、2倍以上に跳ねあがると予想されています」(久保田さん)
一般のサラリーマン家庭ではとても出せるような費用でないことは言うまでもない。
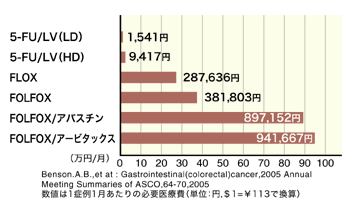
医療経済上の新しい問題点
ちなみに現在のNCCNガイドラインでは、再発予防のための大腸がんの術後補助化学療法として、ステージ2と3の患者にFOLFOX療法が推奨されている。そのきっかけは、昨年のASCOで発表された大規模無作為化比較試験の中間報告だった。
「その大規模無作為化比較試験というのは手術を受けた大腸がん患者2246人を対象にして、従来の5-FU+ロイコボリン併用療法と、FOLFOX療法を比べたものです。前者より後者の4年生存率のほうが、約5パーセント上回っていたことが明らかにされていたのです」(久保田さん)
しかし、術後補助化学療法としてのFOLFOX療法は半年間続ける必要がある。アメリカでは年間約5万5000人が大腸がんの手術を受けるから、そのうちのステージ2、3の患者すべてにFOLFOX療法を行うとなると軽く数千億円に達し、いかにアメリカでもその負担に耐えられない。
「もちろん日本も同様で、無作為化比較試験の積み重ねによって急速に発展してきた大腸がんの化学療法が、医療経済上、大きな壁に突き当たっていることが判明したのも近年のASCOの大きな特徴です」(久保田さん)
進行・再発大腸がんに対する抗体医薬を加えた新たな多剤併用療法も同じ事情を抱えており、確実な治療効果が得られる患者に絞って投与するなどの工夫が求められている。そのうえで費用対効果の面からも大腸がんの化学療法について、改めて社会的コンセンサスを形成することが求められているといえる。
リンパ節の拡大郭清をしても延命しない
今回のASCOでは、国立がん研究センター中央病院副院長の笹子三津留さんから、進行胃がんの手術に関して貴重な報告がなされたことも目を引いた。
「ステージ2以上の進行胃がんは、腹部大動脈周囲リンパ節にがん細胞が転移している可能性が存在します。そのため、胃がんの標準手術とされている第2群までのリンパ節(胃に接するリンパ節と胃に流れこむ血管に沿って存在するリンパ節)を郭清(D2郭清)することに加え、大動脈周囲リンパ節も郭清する拡大郭清(D2+大動脈周囲リンパ節郭清)が行われることもありました」(久保田さん)
しかし、拡大郭清は患者の肉体的負担を増大させ、かえって治療成績を落としているのではないかという批判もあった。そこで全国の標準的なD2郭清を受けた患者260人と拡大郭清を受けた患者263人の生存率を比べて見たところ、3年生存率(どちらも76パーセント)も5年生存率(69パーセントと70パーセント)も、いずれも有意差が認められなかった。
「拡大郭清に延命上の利点がなく、進行胃がんに対するリンパ節郭清は、D2郭清が標準治療であると発表したのです」(久保田さん)
この報告は、無作為化比較試験が難しい手術に関してそれをきちんと行い、科学的な裏付けをとったところに大きな意義がある。
胃がんに関しては、進行胃がんに対するFOLFOXIRI療法の有効性を確かめる臨床試験の結果も発表された。14.8カ月という生存期間中央値は優れた治療成績といえる。
膵臓がんの治療に関する報告もいくつか発表されたが、とくに目新しい報告はなかった。現在、膵臓がんの第1選択肢の抗がん剤はジェムザール(一般名ゲムシタビン)だが、5-FUも有効なのでそれにシスプラチンやエルプラットを加えて治療効果の増強をはかる臨床試験の結果が発表された。
「しかし、ジェムザール単独の治療成績を上回ることはなかなかできません。多数の臨床試験の結果を統計学的に解析するメタアナリシスで、5-FUとプラチナ製剤との併用療法のほうが治療成績は少しよいかもしれないという結果を報じた発表もあったが、インパクトを与えるほどのものではありませんでした」(久保田さん)
総じて今回のASCOで発表された消化器がんの報告は、大腸がんの化学療法に集中した。それだけ大腸がんの化学療法はめざましい発展を遂げていることが浮き彫りになったが、その行く手に新たな問題も明らかにされたのであった。
同じカテゴリーの最新記事
- 切除可能な直腸がん試験結果に世界が注目も 日本の標準治療は「手術」で変わりなし
- ビタミンDの驚くべき効果がわかってきた 消化管がん手術後の再発・死亡リスクを大幅に減少
- 世界最大規模の画期的研究の一部解析結果が発表 大腸がんの術後補助療法の必要性をctDNAで判断する
- 初めての前向き試験で抗EGFR抗体薬の信頼性が確実に! 進化を続ける切除不能・進行再発大腸がんの薬物療法
- 遺伝子変異と左右どちら側にがんがあるかが、薬剤選択の鍵を握る! 大腸がん薬物療法最前線
- 化学放射線と全身化学療法を術前に行うTNT療法が話題 進行下部直腸がん 手術しないで完治の可能性も!
- 肛門温存の期待高まる最新手術 下部直腸がんTaTME(経肛門的直腸間膜切除術)とは
- 大腸のAI内視鏡画像診断が進化中! 大腸がん診断がより確実に
- 患者さんによりやさしいロボット手術も登場 新しくなった大腸がんの手術と薬物療法


