大腸がんの基礎知識 手術が第1選択。が、取りきれなくても、あきらめることはない
治療はまず第1に手術。再発・転移後に手術で治癒も
大腸がんの病期を表わす分類には、国際的に広く使われているデュークス分類と、日本で使われているステージ分類(TNM分類)があります。2つの分類にはあまり差がなく、デュークスAは0~1期、デュークスBは2期、デュークスCは3期、デュークスDは4期に相当します。
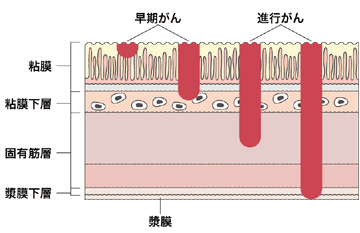
[デュークス分類]
| A | がんが大腸壁内にとどまっているもの |
| B | がんが大腸壁を越えているが、リンパ節転移のないもの |
| C | リンパ節転移のあるもの |
| D | 腹膜、肝臓、肺など遠くの臓器への転移があるもの |
[ステージ分類]
| 0期 | がんが粘膜にとどまっているもの |
| 1期 | がんが大腸壁内にとどまっているもの |
| 2期 | がんが大腸壁を越えているが、大腸の周りの臓器には及んでいないもの |
| 3期 | がんが大腸の周りの臓器に広がっているか、リンパ節転移のあるもの |
| 4期 | がんが腹膜、肝臓、肺など遠くの臓器に転移しているもの |

手術の様子
病期、つまりがんの広がりの程度に応じて、治療法は異なりますが、大ざっぱにいうと、「大腸がん治療の第1選択は全病期を通じて、可能な限り手術」ということになると思います。
その理由は主に2つです。ひとつは、病巣を切除することで、腸閉塞を回避し、結果として、根治する症例が決して少なくないため。もうひとつは、一般にゆっくりと進行する大腸がんには、抗がん剤が効かないことが多かったからです。
抗がん剤に関しては近年、大きな方向転換があり、世界標準の抗がん剤療法も確立されつつあります。それについては後述しますが、しかし、そうした抗がん剤治療事情を考慮しても、大腸がんの第1選択は、手術による病巣の切除といっていいでしょう。
リンパ節やほかの臓器への転移がない1期~2期の場合、病巣がすべて切除できたら、かなり高率で根治を期待することができます。転移のある3期でも、病巣を切除し、補助療法として抗がん剤を投与することで、5年生存率は約50パーセント以上とされています。
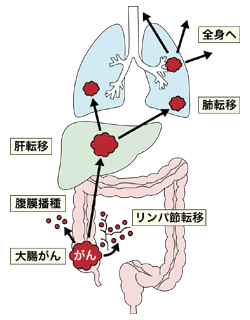
しかし、手術に関して大腸がんが最も特徴的なのは、遠くの臓器へ転移がある4期でも手術を行い、なおかつ完治の可能性がある、ということでしょう。
大腸がんの場合、まず、腸閉塞の予防のため、がんの原発巣を切除することが一般的に行われています。が、それ以外に、肝臓や肺に転移した病巣を切除する手術も、積極的に行われます。大腸がんからの転移で最も多いのは肝臓で、次いで肺、腹膜となっていますが、肝転移や肺転移は、その転移病巣を切除することで、根治する可能性があるのです。 ですから、最初の手術でがんを切除できた患者さんに対しても、術後5年間くらいは3~6カ月に1度の割合で、外来で定期的な検査を受けることをおすすめしています。事実、胸部X線検査、肝臓のCT、超音波検査、腫瘍マーカーなどの検査を継続して行えば、再発の8割を2年以内に発見できるとしている病院もあるのです。
つまり、大腸がん治療の原則は、「取れるものは、とにかく取る。再発も2回目、3回目でも、肝転移も肺転移も取れれば取る。そして、切除が不可能な場合には、ラジオ波焼灼法などを用いて、モグラ叩きのようにがんを叩く」といったところでしょうか。それによって生存期間を延ばすことは、やはり可能だと思います。
複数の抗がん剤による補助療法が世界標準に
そこで抗がん剤治療ですが、前述したように、大腸がん手術の補助療法としての抗がん剤治療は、ここ10年ほどで大きく変わりました。従来、大腸がんに用いられる抗がん剤は5-FU(一般名フルオロウラシル)が一般的でしたが、奏効率は20~25パーセントと、ごく限られたものでした。ところが、90年代後半、世界的に有名なアメリカのメイヨー・クリニックで、大腸がん手術後の患者さんに対して、5-FUとその効果増強剤(レバミゾール)を同時投与する療法が行われ、生存率の改善が得られたのです。
| 1993年 | 化学療法以前 | |
| 2000年 | 5-FUのみ | |
| 2000年 ソルツ、デグラモント | 5-FU + 抗がん剤1剤 イリノテカン or オキサリプラチン | |
| 2004年 ゴールドバーグ、ハーウィツ | 5-FU + イリノテカン + オキサリプラチン併用抗がん剤 + 分子標的薬 | |
以来、いろいろな組み合わせの抗がん剤治療が試みられ、今日では世界標準治療も確立されつつあります。欧米ではそうした標準治療の情報が「ガイドライン」として公開され、だれもがその時点で最も成績のいい治療を受けることができるようになっています。
日本ではなかなかそこまでいきませんが、昨年にはそのガイドラインの日本語解説も、有志の医師らによって作られ、出版されました。大腸がんで抗がん剤治療をすすめられたら、こうした資料もぜひ参考にしていただきたいと思います。
大腸がんに対して抗がん剤療法が行われるのは、主に2つの場合です。ひとつは、進行がんの手術後に再発予防を目的に行う補助療法として、もうひとつは、根治を目的とした手術ができない進行がんや再発がんに対して、生存期間を延ばしたり、不快な症状を抑えたりするために行うケースです。
同じカテゴリーの最新記事
- 切除可能な直腸がん試験結果に世界が注目も 日本の標準治療は「手術」で変わりなし
- ビタミンDの驚くべき効果がわかってきた 消化管がん手術後の再発・死亡リスクを大幅に減少
- 世界最大規模の画期的研究の一部解析結果が発表 大腸がんの術後補助療法の必要性をctDNAで判断する
- 初めての前向き試験で抗EGFR抗体薬の信頼性が確実に! 進化を続ける切除不能・進行再発大腸がんの薬物療法
- 遺伝子変異と左右どちら側にがんがあるかが、薬剤選択の鍵を握る! 大腸がん薬物療法最前線
- 化学放射線と全身化学療法を術前に行うTNT療法が話題 進行下部直腸がん 手術しないで完治の可能性も!
- 肛門温存の期待高まる最新手術 下部直腸がんTaTME(経肛門的直腸間膜切除術)とは
- 大腸のAI内視鏡画像診断が進化中! 大腸がん診断がより確実に
- 患者さんによりやさしいロボット手術も登場 新しくなった大腸がんの手術と薬物療法


