大腸がんの最新標準治療 最良の医療が提供され、最良の治療が受けられる『ガイドライン』が出そろった
パンフレットを用いて患者さんの疑問を解消するシステム
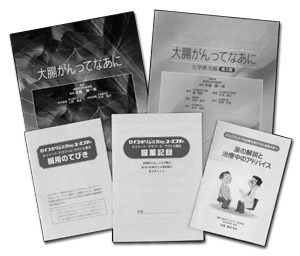
水沼さんは、化学療法を患者さんに理解してもらうためにいくつかのパンフレットを用いる。最初に『大腸がんってなあに』と『同(化学療法編)』を患者さんに手渡して読んでもらう。1週間後、患者さんの質問や疑問に回答し、話し合ったうえで、治療法を決定する。
化学療法が決まったら、実際に処方する抗がん剤の作用や副作用、治療中のアドバイスを解説したパンフレットを手渡す。治療する薬を理解してもらうためだ。「標準治療を行うためには、患者さん自身が自分の受ける治療法、薬を理解することが大切です」と水沼さんは言う。
「転移・再発した大腸がんの標準的な化学療法は、2005年4月、オキサリプラチンが使用できるようになって大きく変わりました。これに5-FU、抗がん剤の効果を高める薬剤のアイソボリンの3剤を併用するFOLFOXと呼ばれる化学療法が始まったからです」(水沼さん)
がん研有明病院ではFOLFOX、FOLFIRIが化学療法の中心
「FOLFOXの奏効率は約50パーセントです。これまでの化学療法の奏効率は20~30パーセントでしたから飛躍的な向上です。FOLFOXは5つの化学療法の中で最も優れた治療成績を持ち、第1選択の治療法です。この1年間で、全国で約5000人がこの治療法を受けていると言われています。当院では200人ほどに行っています。FOLFOXの実施数は全国で最も多いと思います」(水沼さん)
また、オキサリプラチンの代わりにイリノテカンを用いるFOLFIRIという治療法(前出(2))もFOLFOXに近い治療効果が報告されている。ただし、脱毛、下痢等の副作用があり、第2選択になる。FOLFOXが行えない場合は第1選択となる。
がん研有明病院化学療法科では、前出の5つの化学療法のうちFOLFOXを受ける患者さんが一番多い。FOLFOXが効かなくなった場合、次の化学療法としてFOLFIRIに取り組むケースもある。FOLFOXとFOLFIRIができない場合には、(4)または(5)の治療法を選ぶ。
「標準的な化学療法の中で、どの化学療法が患者さんにとって最適かは、患者さんが術後補助化学療法を受けたかどうかなど、それまでに受けてきた化学療法の治療経験や患者さんの状態によって変わってきます。FOLFOXやFOLFIRIが行えない場合もあります。5-FUとオキサリプラチン、イリノテカンを使った治療を行うことが大切なので、患者さんの状態が悪くな��場合は最初の化学療法からFOLFOXやFOLFIRIを行うようにしています」(水沼さん)
医師・薬剤師・看護師による厳しいチェックのもとに

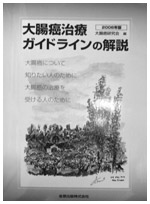
標準的な化学療法を行うには化学療法に精通した医師、抗がん剤専門の薬剤師、抗がん剤の作用と副作用に対応できる看護師との連携が大切である。がん研有明病院では30人の腫瘍内科医、20人の薬剤師、看護師によるチーム医療で大腸がんの化学療法に取り組んでいる。
抗がん剤の処方・投薬ミスがないように、医師同士のチェック、薬剤師のチェック、さらに看護師によるチェックという厳しいシステムが確立されているのだ。
「FOLFOXを含めて抗がん剤治療では、決められた投与量と投与期間をきちんと守ることが大切です。そうでなければ標準治療として認められた効果を期待できなくなる可能性があるからです。副作用を恐れて、投与量を減らしてしまうケースが少なくないようですが、抗がん剤の効果を落としてしまうことになりかねません。当院では、副作用についても患者さんによく理解してもらい、投与量を減らさず治療を続けることを検討したり、逆に投与量を減らす場合も、納得していただいた上で行うようにしています」(水沼さん)
大腸癌治療ガイドラインが発表されて、全国で大腸がんの標準治療が行われていくであろう。
「標準治療は、科学的な根拠に基づいて、その時点で最も優れた治療成績が認められた治療法です。どこでも、誰でも、同じ方法で、ほぼ同様の治療効果が得られる治療法です。ですから、患者さんが高齢だとか、肝臓や腎臓などが弱い場合などを除いて、標準治療は守るべきですし、守らなければいけないと思います」と水沼さんは語る。
患者さんは患者さん向けのガイドライン、医師は医師向けのガイドラインを読んで、標準治療の理解を深めることは、患者さんと医師との信頼関係を生み出す。納得した治療を受けるためにも『大腸癌治療ガイドラインの解説』のご一読を、是非お奨めしたい。
がん研有明病院で化学療法を受けたケース
Aさん(60代・男性)は4年ほど前に、別の病院で直腸がんの手術を受けた。2002年夏頃、定期検査で再発が見つかり、がん研有明病院を訪れ当時の標準治療である5-FUとアイソボリンを併用する化学療法を受けた。さらに、04年5月頃、再発したがんの進行がわかり、今度はIFL療法(5-FU+アイソボリン+カンプト/トポテシン)を受けて、しばらくの間、がんの進行を抑えることができた。
しかし、05年春頃、肺転移のため、承認・販売されたばかりのエルプラットと5-FU、アイソボリンを併用するFOLFOX療法を始めた。この治療のために、Aさんの右鎖骨下に中心静脈リザーバーの埋め込みが行われた。48時間にも及ぶFOLFOX4療法を確実に施行するための準備である。最初のサイクルは入院で行い、2サイクル目からは入院せず、外来治療センターで治療を行った。治療1日目、エルプラットとアイソボリンが同時に2時間で静脈内投与され、続いて5-FUの静脈内注射を行った。その後、5-FUが詰め込まれた携帯ポンプを中心静脈リザーバーに接続して、持続点滴治療(22時間)を開始した。
2日目は、2時間のアイソボリンのみの点滴治療を受けた後に、同様に5-FU静脈内注射、5-FU持続投与(22時間)を続けた。がん研有明病院では3日目は来院せず、患者さんが自宅で注射針を抜くようにしており、その方法や注意点を指導している。これを2週間ごとに繰り返し、2カ月後、腫瘍は治療前と比較して60パーセントもの縮小が見られた。
「Aさんのように第3選択としてFOLFOXを受けた場合、欧米ではその奏効率は10~20パーセントですから、その効果は劇的と言えます」と化学療法科の末永光邦さんは語る。ただし、治療を始めて4カ月後、手足のしびれなどのエルプラットに代表される慢性期神経障害のため、治療を休んでいる。
Bさん(60代・女性)は、05年春、結腸がんで手術。術後補助化学療法の対象となる3期だった。同病院を紹介され、UFTとロイコボリンの併用療法を始めた。2剤とも経口薬なので自宅で服用。2週間ごとに外来を受診し、血液検査、副作用のチェックを受ける。6月から12月まで6カ月間服用。経過は順調だ。「UFTによる軽い色素沈着、軽い味覚異常、軽度の肝機能異常などがありましたが、CT検査で無再発を確認しています」(末永さん)
同じカテゴリーの最新記事
- 切除可能な直腸がん試験結果に世界が注目も 日本の標準治療は「手術」で変わりなし
- ビタミンDの驚くべき効果がわかってきた 消化管がん手術後の再発・死亡リスクを大幅に減少
- 世界最大規模の画期的研究の一部解析結果が発表 大腸がんの術後補助療法の必要性をctDNAで判断する
- 初めての前向き試験で抗EGFR抗体薬の信頼性が確実に! 進化を続ける切除不能・進行再発大腸がんの薬物療法
- 遺伝子変異と左右どちら側にがんがあるかが、薬剤選択の鍵を握る! 大腸がん薬物療法最前線
- 化学放射線と全身化学療法を術前に行うTNT療法が話題 進行下部直腸がん 手術しないで完治の可能性も!
- 肛門温存の期待高まる最新手術 下部直腸がんTaTME(経肛門的直腸間膜切除術)とは
- 大腸のAI内視鏡画像診断が進化中! 大腸がん診断がより確実に
- 患者さんによりやさしいロボット手術も登場 新しくなった大腸がんの手術と薬物療法


