渡辺亨チームが医療サポートする:再発大腸がん編
術後3年で肺転移。補助療法の抗がん剤治療を受けなかったから?
白尾國昭さんのお話
*1 大腸がんと腫瘍マーカー
腫瘍マーカーは血液のなかに含まれる特定のタンパク質の量を調べる検査により、身体のどこかに潜んでいるがんを診断する方法です。大腸がんの検査に使われるのは、CEA(正常値2.5以下)、とCA19-9(糖鎖抗原、正常値37以下)と呼ばれるマーカーが一般的で、原則として進行がんの判定に用いられます。
ただし、進行大腸がんであっても陽性を示すのは約半数に過ぎません。つまり、転移・再発した場合でも必ずしも異常値を示すわけではなく、逆に喫煙者や糖尿病の人は転移・再発していない場合でも異常値を示すときもあります。とくに早期がんでは陽性を示す率が低く、腫瘍マーカーは早期発見にはあまり役立ちません。しかし、大腸がんの切除をしたあと再発を予測したり、抗がん剤の効果を予測することには、比較的役立つ検査と考えられています。
*2 大腸がんの術後の検査
大腸がんは手術を受けた後に再発することもあるので、手術後も定期的に検査することが必要です。手術時にどの程度進行していたかによって異なりますが、手術後3年間は3~6カ月に1度通院し、胸部X線検査、肝臓のCT、超音波検査、腫瘍マーカーなどの検査を行います。通常、再発の8割は2年以内に発見されます。成長の遅い大腸がんもあるので5年間またはそれ以上の追跡も必要ですが、年が経つにつれ検査間隔を延ばして行くのが一般的です。
*3 大腸がんの種類・進行度
大腸は、盲腸、結腸、直腸、肛門管に分かれます。入り口側から盲腸、それに続いて、最初に上のほうに向かう部分が上行結腸、その次に水平方向に続いている部分が横行結腸、次に下に向かう部分が下行結腸、さらにS字状に曲がっている部分がS状結腸、約15センチの真っすぐな部分が直腸です。これに続いて肛門管があります。
国立がん研究センター中央病院で1990年~1995年の間に切除された1409例の大腸がんの発生部位と頻度は、直腸534例(37.9パーセント)、S状結腸483例(34.3パーセント)、上行結腸146例(10.4パーセント)、横行結腸99例(7パーセント)、盲腸83例(5.9パーセント)次いで下行結腸64例(4.5パーセント)となっています。
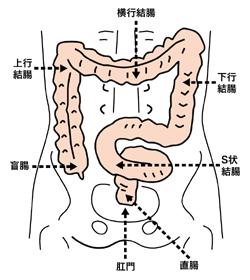
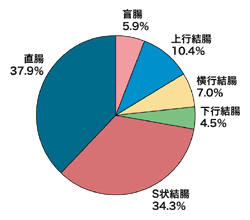
腸の表面は内側から、粘膜、粘膜筋板、粘膜下層、筋層、漿膜下層という5つの層に分かれていますが、このうち、がんが粘膜内もしくは粘膜下層にとどまっているものを「��期がん」、筋層以下にまで進んでいるものを「進行がん」といいます。
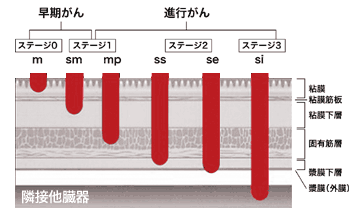
大腸がんの進行度を示すためには、国内では主に大腸癌研究会の『大腸がん取り扱い規約』による病期分類が、国際的にはデュークス分類がよく使われます。これらの分類はがんの大きさではなく、大腸の壁の中にがんがどの程度深く入っているか、またリンパ節転移や遠隔転移があるかないかによって規定されるものです。2つの分類にはわずかな違いがあるのみで、臨床的病期の0.1期はデュークスA、2期はデュークスB、3期はデュークスC、4期はデュークスDに相当するものと考えて差しつかえありません。
| 「大腸がん取り扱い規約」 による病期分類 | デュークス分類 | 5年生存率 (結腸がん) |
|---|---|---|
| 0期 | デュークス A | 95.7% |
| がんが粘膜にとどまるもの | がんが大腸壁内にとどまるもの | |
| 1期 | ||
| がんが大腸壁にとどまるもの | ||
| 2期 | デュークス B | 91.6% |
| がんが大腸壁を越えているが、隣接臓器におよんでいないもの | がんが大腸壁を貫いているが、リンパ節転移のないもの | |
| 3期 | デュークス C | 78.7% |
| がんが周囲の臓器に広がっているか、リンパ節転移のあるもの | リンパ節転移のあるもの | |
| 4期 | デュークス D | 18.6% |
| 腹膜、肝、肺などへの遠隔転移のあるもの | 腹膜、肝、肺などへの遠隔転移のあるもの |
*4 大腸がんの術後化学療法
大腸がんは手術で取りきれたと思っても、実はその時点で目に見えない転移がすでに他の臓器に飛び火していることもあります。これを微小転移と呼びます。この微小転移を根絶するために術後、一定期間にわたり抗がん剤治療を行うことを術後化学療法といいます。ステージ3以上に進行した大腸がんには、5-FU+ロイコボリン、UFT+ロイコボリンという抗がん剤を用いる方法が補助療法として標準治療と考えられてきました。ただし、ステージ2より早期の大腸がんには、これらの薬剤が再発予防に有効であるかどうかという科学的な裏づけはまだはっきりわかっていません。
これに対して2005年に、再発予防のため、手術後FOLFOX4(5-FU+ロイコボリン+オキサリプラチン)という治療を隔週に12サイクル行うことにより、ステージ2で再発率を約15パーセント、ステージ3では30パーセント低下させることが報告されました。抗がん剤治療はどんどん進歩しており、現段階で確定したわけではありませんが、今後標準治療はFOLFOX4に変わっていく可能性があります。
*5 TS-1
TS-1は、UFTの改良型として開発された抗がん剤です。がん細胞内で5-FUという抗がん剤成分に変換されてから効力を発揮するプロドラッグと呼ばれる薬で、その特性により優れた抗腫瘍作用と副作用の軽減がはかられています。保険承認されており、経口薬で利用しやすいことから、大腸がんの治療薬としてもしばしば用いられますが、この薬が大腸がんの患者の延命に結びつくというデータはまだありません。
*6 再発・転移巣に対する治療
一般的にがんが再発した場合には、抗がん剤治療が行われます。抗がん剤治療の目的は、(1)がんに伴う症状が出現するのを遅らせる (2)がんの症状を和らげ、QOLを高める (3)延命などです。これに対して大腸がんが、肝臓や肺、骨盤内に転移・再発し、他の臓器に転移・再発していない場合には手術を行う場合があります。
すなわち、再発が肝転移だけに限られていて、なおかつ肝転移の個数や場所(大きな血管のすぐわきなどは切除不可能)などの条件がある一定の基準を満たせば、手術が第1選択となります。肝切除が適応であった場合、切除後の5年生存率は約40パーセントと報告されています。
肝転移についで多いのは肺転移ですが、転移先が片肺だけに限られていて、転移の数などいくつかの規準を満たせば、転移巣の切除手術が行われます。ただし肺転移を切除しても、治癒、延命効果は明らかではありません。
同じカテゴリーの最新記事
- 切除可能な直腸がん試験結果に世界が注目も 日本の標準治療は「手術」で変わりなし
- ビタミンDの驚くべき効果がわかってきた 消化管がん手術後の再発・死亡リスクを大幅に減少
- 世界最大規模の画期的研究の一部解析結果が発表 大腸がんの術後補助療法の必要性をctDNAで判断する
- 初めての前向き試験で抗EGFR抗体薬の信頼性が確実に! 進化を続ける切除不能・進行再発大腸がんの薬物療法
- 遺伝子変異と左右どちら側にがんがあるかが、薬剤選択の鍵を握る! 大腸がん薬物療法最前線
- 化学放射線と全身化学療法を術前に行うTNT療法が話題 進行下部直腸がん 手術しないで完治の可能性も!
- 肛門温存の期待高まる最新手術 下部直腸がんTaTME(経肛門的直腸間膜切除術)とは
- 大腸のAI内視鏡画像診断が進化中! 大腸がん診断がより確実に
- 患者さんによりやさしいロボット手術も登場 新しくなった大腸がんの手術と薬物療法


