渡辺亨チームが医療サポートする:再発大腸がん編
セカンドオピニオンにより、承認されたばかりの新薬を使って治療開始
白尾國昭さんのお話
*1 エルプラット
エルプラット(一般名オキサリプラチン)は「切除不能の進行・再発の結腸・直腸がん」を対象にした抗がん剤で、標準治療薬として世界約70カ国で承認されている抗がん剤です。もともと日本で開発されたものですが、日本では承認が遅れ、2005年4月に大腸がんの治療薬として承認されました。シスプラチン(商品名ランダ、 ブリプラチン)やカルボプラチン(商品名パラプラチン、 カルボメルク)など、白金を材料にしたプラチナ系と呼ばれる抗がん剤のグループの1種です。このグループの中でもとくに大腸がんに対してよく働くことが示されています。
ただし、理解しておかなければならないのは、オキサリプラチンはこれまでの薬に比べて劇的な効果をもたらすわけではありません。平均数カ月延命効果も上乗せが期待できることは事実ですが、これまで治らなかったものが治るわけではないのです。
オキサリプラチンは、大腸がんの患者さんたちから健康保険の早期適用を求める声があがったことから、名前はすっかり有名になりました。そのためにマスコミなどでも「夢の新薬」として伝えられた部分もあります。患者さんもこうした情報に惑わされないよう、新薬の適応と限界、メリットとデメリットを十分知った上で治療を選択してください。もちろんこの抗がん剤の適応のある患者さんにとっては、今後積極的に使用される薬剤となるでしょう。
*2 新薬の採用
エルプラットは今年の4月6日に薬価収載になりましたが、全国一斉に大腸がんの治療薬ががらりと変わったわけではありません。実際には施設の体制が整うまで数カ月はかかっているようです。「新薬は使い慣れていないので、すぐには使わない」という医師も確かにいます。従来の薬がすべて悪いというわけではありません。抗がん剤は致死的な副作用が出る可能性もあるので、「使い慣れている薬で」という考え方も否定はできないでしょう。
もちろん新しい治療法は今までの治療よりも良いということは理解される必要があります。ですから、目の前に患者さんがいれば、新薬を使うことのできる施設を紹介するという手もあるかもしれません。
エルプラットは市販後厚生労働省から、「半年間の全例調査」が義務付けられていました。患者さんの症状を正しく把握して、治験で見つからなかった副作用がないかを調べ、安全性を把握するための措置です。この期間が経過したことから、より多くの施設でエルプラットが使えるようになり、今後さらに利用が広がっていくでしょう。
*3 再発がんの確定診断
腫瘍が見つかった場合、それががんか否か、がんならどの程度の悪性度か、原発か転移してできたものかによって���療法が違うので、普通は体に負担がかかりますが組織を1部採ってきて細胞を顕微鏡で調べる病理学的生検というものを行います。しかし、再発・転移したがんは生検を必要としない場合があります。大腸がんの肺転移などは、転移巣が種を播いたようにポツポツと現れるのが普通です。ですから、もともと大腸がんの既往があって、画像検査(CTなど)でそうした所見があれば、明らかに転移したがんと診断することができるので、わざわざ細胞を検査する必要がありません。ところが、1個だけポツンと肺に丸い影が出て、これが原発の肺がんか転移した病巣なのか、肉芽腫と呼ばれる良性の腫瘍かわからないといった場合は、やはり生検が必要になります。
*4 肺転移巣の切除
大腸がんの肺への転移は、切除しても予後がよくならないというのが最近の考え方です。切除する部分がある程度以上広がると治療成績はよくありません。ですから、切除しきれるかどうかではなく、治療成績がよりよいと考えられる方法を選択する(手術か抗がん剤治療か)必要があります。そのために、次のような再発巣切除の適応基準があるのです。
大腸がんの肺転移切除の適応基準の原則
- 肺転移巣が完全切除可能であること
- 手術に耐えられる全身状態であること
- 肺以外に転移がないこと
- 肺転移巣が1側肺に限局していること
*5 再発大腸がんの治療
がんは一般に再発・転移が見られた時点で、完治を望むことは難しくなります。ただ、大腸がんは他のがんに比べて再発した場合も、かなり延命される方が少なくありません。
再発大腸がんの治療には、症状の緩和や延命のために抗がん剤が使用されます。2000年に報告された海外の臨床試験の結果によると、抗がん剤治療を行わないグループの生存期間中央値(MST)は約8カ月であるのに対して、抗がん剤治療をしたグループは約12カ月と、抗がん剤治療が有効であることが示されています。ただしこのデータは、以前採用されていた標準治療のもとでの効果であり、最近目覚しい進歩を遂げた抗がん剤を用いた治療のもとでは生存期間はかなり延長しています。
大腸がんは以前は「抗がん剤の効きにくいがん」と考えられてきました。1957年に開発された5-FUが唯一の大腸がん治療薬とされていましたが、あまり生存に寄与するとは考えられなかったのです。これに対して欧米では1990年代後半に5-FU/ロイコボリンとカンプト(一般名イリノテカン)や、エルプラットなどの薬を組み合わせた併用療法が開発されました。この結果、全生存期間を目標にした欧米の第3相比較試験では、5-FU系の薬剤のみでは12カ月前後であった生存期間中央値が、最近は20カ月を超える結果があちこちで見られるようになっています。
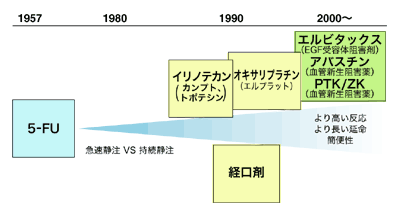
*6 FOLFOX4療法
エルプラットを使って再発大腸がんを治療する場合、世界的に標準とされている投与法がFOLFOX4です。これは、ロイコボリン を100ミリグラム(体表面積1平方メートル当り)およびエルプラット85ミリグラム(同)を2時間かけて点滴静注し、その後5-FU400ミリグラム(同)を急速静注します。さらに、5-FU600ミリグラム(同)を22時間かけて持続点滴して1日目を終わりますが、2日目も同様の治療を行い、これを2週間毎に繰り返すという方法です。
| FOLFOX4 | |||
|---|---|---|---|
| オキサリプラチン | 85mg/m2 | 点滴静注 | 1日目、2日目 |
| ロイコボリン | 100mg/m2 | 点滴静注 | 1日目、2日目 |
| 5-FU | 400mg/m2 | 急速静注 | 1日目、2日目 |
| 600mg/m2 | 22時間かけて 持続点滴 | 1日目、2日目 2週間毎 | |
*7 急速静注と持続静注
5-FUの投与法は、従来わが国では急速静注しか保険が適用されていませんでしたが、欧米のデータで持続点滴がより効果が高く、毒性の低いことがわかってきたことから、FOLFOX4ではこちらで行われます。この方法を通院で行うためには、肩からの点滴を行うことが必要となります。そのためまず右の鎖骨の下側に穴を開けてリザーバーシステムというものが取り付けられます。
| 5-FUの投与法 | 奏効率(%) | 生存期間(月) |
|---|---|---|
| 急速静注 | 14 | 11.3 |
| 持続静注 | 22 | 12.1 |
[急速静注5-FUと持続静注5-FUとの毒性の比較(メタアナリシス)]
| グレード3/4の毒性の頻度(%) | ||
|---|---|---|
| 毒性 | 持続静注5-FU n=607 | 急速静注5-FU n=612 |
| 血液毒性 | 4 | 31 |
| 非血液毒性 | 13 | 14 |
| 下痢 | 4 | 6 |
| 悪心・嘔吐 | 3 | 4 |
| 粘膜炎 | 9 | 7 |
| 手足皮膚反応 | 34 | 13 |
同じカテゴリーの最新記事
- 切除可能な直腸がん試験結果に世界が注目も 日本の標準治療は「手術」で変わりなし
- ビタミンDの驚くべき効果がわかってきた 消化管がん手術後の再発・死亡リスクを大幅に減少
- 世界最大規模の画期的研究の一部解析結果が発表 大腸がんの術後補助療法の必要性をctDNAで判断する
- 初めての前向き試験で抗EGFR抗体薬の信頼性が確実に! 進化を続ける切除不能・進行再発大腸がんの薬物療法
- 遺伝子変異と左右どちら側にがんがあるかが、薬剤選択の鍵を握る! 大腸がん薬物療法最前線
- 化学放射線と全身化学療法を術前に行うTNT療法が話題 進行下部直腸がん 手術しないで完治の可能性も!
- 肛門温存の期待高まる最新手術 下部直腸がんTaTME(経肛門的直腸間膜切除術)とは
- 大腸のAI内視鏡画像診断が進化中! 大腸がん診断がより確実に
- 患者さんによりやさしいロボット手術も登場 新しくなった大腸がんの手術と薬物療法


