渡辺亨チームが医療サポートする:再発大腸がん編
FOLFOX4療法で症状改善、転移巣は3カ月後に消失していた
白尾國昭さんのお話
*1 FOLFOX4の副作用
エルプラットは、特有の副作用として、冷たいものに誘発されて起こる知覚神経障害があります。これは、冷たいものにさわったときに手足がピリピリと電気が走るように痛むといった感覚を覚えるものです。水を飲んだときの口の中のピリピリした感じも同様のメカニズムによるものです。個人差もありますが、一般にはこれらの副作用もそれほど大きなものではありません。しかし、長く治療を続けていると神経症状が強くなる可能性があるので注意が必要です。
このほか、エルプラットには消化器系と血液に有害な作用を与えることがあり、FOLFOX4のように5-FU/ロイコボリンと併用することによって、これらの副作用の発生率が増大します。エルプラットと5-FU/ロイコボリン の併用投与でよく報告されている副作用は、倦怠感、下痢、嘔気、嘔吐などです。また血液の副作用として、白血球減少、好中球減少、血小板減少、貧血が見られます。
副作用としていろいろ種類はありますが、最も注意すべきものの1つは、アナフィラキシーショックと呼ばれるアレルギー反応です。これは血圧低下を伴うもので、時に致死的な場合もあります。もちろんめったに起こることではなく、治療前に十分チェックされます。
アナフィラキシーショックは投与から数分以内に起こる可能性があります。症状を緩和するため、エピネフリン、コルチコステロイド、抗ヒスタミン剤が使用されています。
| 種類 | 副作用発現頻度 | |
|---|---|---|
| 10%以上 | 5~10%未満 | |
| 精神神経系 | 頭痛 | 味覚異常 |
| 消化器 | 食欲不振(89.4%) 悪心(78.8%) 嘔吐(59.1%) 下痢(39.4%) 便秘 | 腹痛 |
| 腎臓 | 尿沈査異常 タンパク尿 | クレアチニン上昇 BUN上昇 尿ウロビリノーゲン異常 尿糖 |
| 肝臓 | AST(GOT)上昇(42.4%) ALT(GPT)上昇 ALP上昇 LDH上昇 ビリルビン上昇 | |
| 電解質 | 血清ナトリウム、カリウムの異常 | 血清クロール、カルシウムの異常 |
| 過敏症 | 発疹 | |
| 投与部位 | 注射部位反応 | |
| その他 | 疲労(43.9%) 発熱 アルブミン減少 CRP上昇 総タンパク減少 |
[FOLFOX4の副作用]
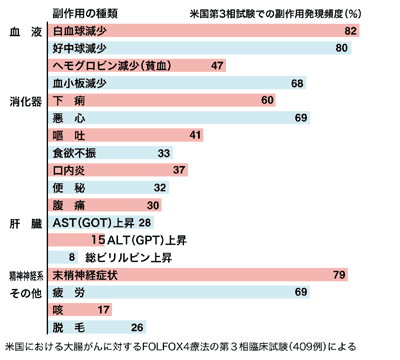
*2 エルプラットの禁忌例
エルプラットは、同剤または他の白金化合物に対するアレルギー歴がある患者に投与してはいけません。他の白金化合物と同様、過敏症およびアナフィラキシー性/類アナフィラキシー性反応が報告されています。また妊娠の可能性がある女性に対し、エルプラットよる治療期間中は妊娠を避けるように指導する必要があります。
*3 エルプラットの取り扱い経験
エルプラットは抗がん剤であるため、このような薬剤を取り扱った経験がある専門的知識と技術を持った医師の監督下で投与されなければなりません。治療や合併症の適切な管理は、適切な診断施設や治療施設がすぐに利用できる環境のもとではじめて可能となります。
ただし、がん専門病院でなければ、その医療施設がエルプラットの取り扱い経験があるかどうかについては、なかなか判断がつきません。通常、腫瘍内科医のいる病院ならエルプラットの治療を受けることができます。
*4 インフュージョンポンプ
シリコンで作った風船に薬液が入ったもので、風船が縮む力で薬が押し出され、24~48時間、持続的に一定量が静脈内に投与されます。
*5 治療効果の判定
抗がん剤治療では、どのような治療効果が現れているかを、きちんと判定していかなければなりません。一般の診療においては、「がんが小さくなった」とか「消えた」という表現をしますが、臨床試験での抗がん剤の効果判定法は上の表のように細かく分けて行っています。ですから、臨床でもこうした分類を参考にして治療方針が決定されます。検査は定期的に行っていきますが、表の中の「進行」という判定が出るまで抗がん剤治療を続けることがよいとされています。
| 1 | 完全寛解(CR=コンプリート・レスポンス) |
|---|---|
| 腫瘍がすべて消失し、その状態が4週間以上続いている場合 | |
| 2 | 部分寛解(PR=パーシャル・レスポンス) |
| 腫瘍の縮小率が50%以上で、新しい病変の出現が4週間以上ない場合 完全に治ったわけではないが、薬がよく効いている | |
| 3 | 不変(SD=ステイブル・ディジィーズ) |
| 腫瘍の大きさがほとんど変わらない場合(正確には、50%以上小さくもならず、25%以上大きくもならない場合)。がんは放置すればどんどん大きくなるので、大きさが変わらないのは、薬の効果があったことを意味している | |
| 4 | 進行(PD=プログレッシブ・ディジィーズ) |
| 腫瘍が25%以上大きくなった場合、もしくは別の場所に新たな腫瘍ができた場合 |
*6 FOLFOX4療法の治療期間
再発転移した大腸がんに対する抗がん剤治療は、がんが大きくならずに安定している限り、なるべく長く継続することがよいとされていて、場合によっては年単位で続ける方もおられます。
*7 抗がん剤の限界
1つひとつの抗がん剤はある期間投与を続けるうちに効かなくなってしまう宿命にあります。がん細胞が薬剤に抵抗力を持つためで、このことを薬剤耐性といいます。この段階では別の薬に切り替えなければなりません。
*8 今後期待できる大腸がんの抗がん剤
大腸がんのさらなる治療効果向上を目指して現在新しい薬剤の開発が試みられています。世界的にみると大腸がん治療の発展のスピードは目覚しく、現在日本で使えない有望な薬がいくつかあります。これらの薬が日本でも使えるようになれば、治療の選択肢が広がります。有効な薬を日本でも使用できるよう早期の国内承認が待たれます。
| 治療法(レジメン) | 患者数 | 奏効率 | 無再発生存期間 中央値(月) | 生存期間 中央値(月) |
|---|---|---|---|---|
| 5-FU/ロイコボリン | 226 | 21% | 4.3 | 12.6 |
| IFL(N9741) | 264 | 31% | 6.9 | 15 |
| FOLFOX(N9741) | 267 | 45% | 8.7 | 19.5 |
| FOLFIRI/FOLFOX | 109 | 56% | 8.6 | 21.5 |
| FOLFOX/FOLFIRI | 111 | 54% | 8 | 20.6 |
| IFL+アバスチン | 403 | 45% | 10.6 | 20.3 |
FOLFIRI=5-FU持続静注+ロイコボリン+イリノテカン
大腸がんで注目されている薬の1つは分子標的薬のアバスチン(一般名ベバシツマブ)です。アバスチンは、初めての「血管新生阻害剤」といわれています。この薬は細胞表面にあって、新しい血管を作るカギになるVEGF(血管内皮細胞増殖因子)を標的にして働きます。その結果、がん細胞に栄養を運ぶ血管が伸びていくのを抑えるために、がんの成長を邪魔するのです。また、アバスチンは他の抗がん剤をがんに届きやすくする働きもあると考えられています。現在標準治療となっているFOLFOX4療法に、アバスチンを追加することによって、その生存期間が約2カ月延びることが臨床試験で示されています。すでに欧米ではアバスチンが大腸がんに対して承認されていて、アメリカではFOLFOX4+アバスチンが標準治療になっていくと思われます。日本ではアバスチンは承認されておらず、現在臨床試験が進められているところです。
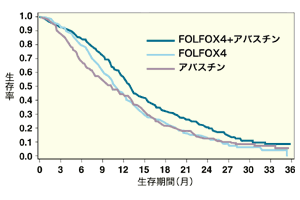
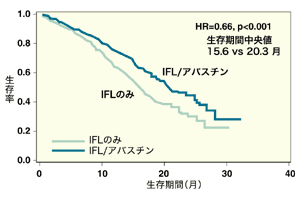
一方、ほかの薬が効かなくなった大腸がんに対して期待されているのが、アービタックス(一般名セツキシマブ)という薬です。この薬は細胞表面にあって細胞の異常増殖に関与しているEGFRというタンパクに結合して、増殖を邪魔するものです。イリノテカンに耐性ができている大腸がんに対して、アービタックスを組み合わせると、効果が高いといわれています。
同じカテゴリーの最新記事
- 切除可能な直腸がん試験結果に世界が注目も 日本の標準治療は「手術」で変わりなし
- ビタミンDの驚くべき効果がわかってきた 消化管がん手術後の再発・死亡リスクを大幅に減少
- 世界最大規模の画期的研究の一部解析結果が発表 大腸がんの術後補助療法の必要性をctDNAで判断する
- 初めての前向き試験で抗EGFR抗体薬の信頼性が確実に! 進化を続ける切除不能・進行再発大腸がんの薬物療法
- 遺伝子変異と左右どちら側にがんがあるかが、薬剤選択の鍵を握る! 大腸がん薬物療法最前線
- 化学放射線と全身化学療法を術前に行うTNT療法が話題 進行下部直腸がん 手術しないで完治の可能性も!
- 肛門温存の期待高まる最新手術 下部直腸がんTaTME(経肛門的直腸間膜切除術)とは
- 大腸のAI内視鏡画像診断が進化中! 大腸がん診断がより確実に
- 患者さんによりやさしいロボット手術も登場 新しくなった大腸がんの手術と薬物療法


