進行別 がん標準治療 治療の中心は外科手術。ただし、選択するのは患者自身
2期~3期
標準治療は外科手術
2期は、がんが大腸の壁を越えていてもリンパ節転移がないもの。リンパ節転移があると3期になります。そして、肝臓など他臓器に転移した状態が4期です。
この場合、標準的な治療は手術になります。手術にもいろいろな方法がありますが、基本的にはがんの病巣を、安全領域を見込んで切除し、周囲のリンパ節郭清を行い、他臓器への転移の有無を確認することになります。4期でも手術をするのか、と疑問に感じる人もいると思いますが、上野さんによると「正確なステージ分類は、手術で摘出した組織をみてわかるもの。明らかに内視鏡治療の対象でなければ、手術が基本になります。それによって、4期と判明することもあるので、4期の人でも手術をしていることが多い」といいます。
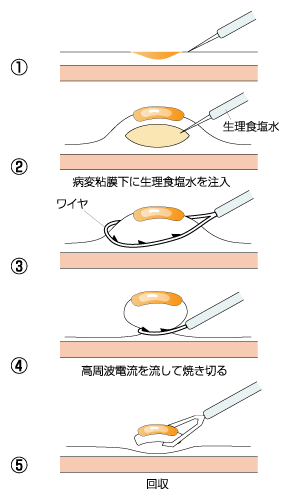
平べったいがん(表面型)やへこんだ形のがん(陥凹型)は
がんの下に生理食塩水を入れて盛り上がらせ、その根元に
ワイヤーを引っかけて、高周波電流を流して焼き切る。
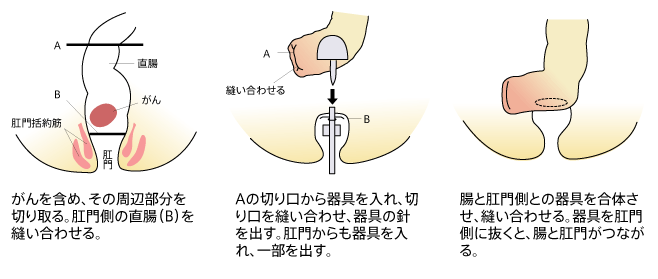
補助化学療法
再発防止の有効性がはっきりしているのは3期
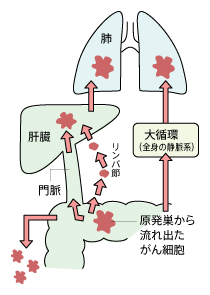
がん細胞が血管の中に入ると、
静脈から門脈を通って、肝臓、
さらに肺へと転移しやすい
1期の場合は、内視鏡で治療するにしても開腹手術をした場合でも、外科的な治療が終わればそれで治療は終了します。これで95パーセント以上の人は完治します。これが、2期、3期になると、術後の再発を防ぐ目的で、補助化学療法が行われることがあります。上野さんによると「はっきり補助化���療法が有効とされているのは、とくに3期」だそうです。
3期の場合は、これまでの臨床試験の結果、補助化学療法を実施することで、大腸がんで死ぬ可能性を30パーセントくらい減らせるとされています。これに対して、2期の場合は5年生存率81パーセントが補助化学療法を実施することで83パーセントぐらいに向上します。つまり、上乗せ効果は2パーセントほどということになります。
そのため、「化学療法には副作用もあります。したがって2期の場合、若い人ならば考えますが、高齢者には強いて化学療法は勧めていません。3期であれば一般的には補助化学療法を受けることを勧めますが、本人が希望しない、あるいは高齢で全身状態もあまりよくない、生命予後が5年未満と考えられるような場合は、まず行われないのがふつうです」と上野さん。
抗がん剤は、5-FUを中心にロイコボリンを加えた2剤併用療法がよく行われています。投与の方法もいろいろありますが、一般的には5日間の連続投与を4週間、あるいは5週間ごとに行います。または、週に1回ずつ6週間抗がん剤を投与し、2週間休むというサイクルを4回繰り返す方法もあります。外来通院で化学療法を受ける場合などは、週1回ペースの投与が行われることが多いそうです。 ただ、下痢や脱毛、全身のだるさなどの副作用もあります。
同じカテゴリーの最新記事
- 切除可能な直腸がん試験結果に世界が注目も 日本の標準治療は「手術」で変わりなし
- ビタミンDの驚くべき効果がわかってきた 消化管がん手術後の再発・死亡リスクを大幅に減少
- 世界最大規模の画期的研究の一部解析結果が発表 大腸がんの術後補助療法の必要性をctDNAで判断する
- 初めての前向き試験で抗EGFR抗体薬の信頼性が確実に! 進化を続ける切除不能・進行再発大腸がんの薬物療法
- 遺伝子変異と左右どちら側にがんがあるかが、薬剤選択の鍵を握る! 大腸がん薬物療法最前線
- 化学放射線と全身化学療法を術前に行うTNT療法が話題 進行下部直腸がん 手術しないで完治の可能性も!
- 肛門温存の期待高まる最新手術 下部直腸がんTaTME(経肛門的直腸間膜切除術)とは
- 大腸のAI内視鏡画像診断が進化中! 大腸がん診断がより確実に
- 患者さんによりやさしいロボット手術も登場 新しくなった大腸がんの手術と薬物療法


