渡辺亨チームが医療サポートする:大腸がん編
大腸がんが肝臓に転移しても、抗がん剤治療に希望がある
| 斉藤信子さんの経過 | |
| 2002年 4月25日 | 近所のクリニックで便潜血反応が陽性。 |
| 4月28日 | R病院消化器内科の内視鏡検査で「進行したS状結腸がん」発見。 |
| 5月20日 | R病院消化器外科へ入院。 |
| 5月21日 | 腹腔鏡手術で、S状結腸がんを摘出。 |
| 6月20日 | 病理検査の結果、3期のS状結腸がん。手術と術後補助抗がん剤療法を勧められる。 |
| 7月1日 | 5-FU+ロイコボリン療法を開始。6カ月後終了 |
| 2004年 3月15日 | 定期検査で肝機能の異常から転移発見 |
| 4月20日 | 肝転移に対する5-FU+ロイコボリン+カンプトの抗がん剤療法を開始 |
| 8月10日 | 肝転移巣が縮小 |
大腸がんを手術で摘出したけれども、その後しばらくしてから肝臓や肺に転移することがよくある。
その場合、どういう治療法が最適なのか。
ここに登場する斉藤信子さんがまさにその例。
手術という選択もあるが、彼女の場合は、手術ができないケースであったため、抗がん剤治療をすることになった。
残念ながら、肝臓に影が
斉藤信子さんは2002年5月21日、R病院消化器外科で腹腔鏡下のS状結腸がん摘出手術を受けた。以後の経過は良くて、病気前と変わらず食欲もあり、2年近くを快適に過ごしている。定期的に画像診断を行い、腫瘍マーカー(*1)などの血液検査をしていたが、異常は見つかっていなかった。
ところが、手術を受けてまる2年を迎えようとするころ、何か体がだるく感じられるようになった。最初は例年悩まされていた花粉症のせいかと思っていたが、時間が経つうち、だるさがひどくなり、食欲まで衰えてきたことから、「どうも花粉症だけではなさそうだ」と気づき始めた。
2004年3月15日、定期検査を受けた。その血液検査の結果を見て熊谷医師が告げる。
「GOT120、GPT35と高いし、LDH(血清乳酸脱水素酵素)も上がっていますね。腫瘍マーカーCEA(がん胎児性抗原)も132と高くなっています。エコーで見ましょう」
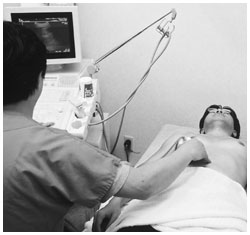
お腹にプローブを当てて超音波検査をしているシーン
熊谷医師は超音波検査の機器がある治療台へ信子さんをうながす。信子さんが診察台に横になると腹部にプローブが当てられた。
「肝臓に影がみられますね」
2年前、検査で結腸がんが見つかったときと同じように、医師の表情に緊張がうかがえる。
「��の臓器も調べる必要があるので、CT検査を受けていただきます」
熊谷医師は、看護師に信子さんをCT検査室に案内するよう指示した。
「再発かしら……」
信子さんは動揺し、不安が高まっていく。
CT撮影を済ませて、再び熊谷医師の待つ診察室に戻る。いつもは柔和な顔だが、今日は引きつっているように感じられる。 「残念ながら、肝転移が認められます。この黒っぽく見えるのががんです。全部で10個以上ありそうですね。大きいもので3センチくらいあるでしょう」
「ええっ」
信子さんは悲鳴をあげた。
「もう治ったと思っていたのに……。『がんは再発したらおしまい』っていいますが……」
居ても立ってもいられない思いで、信子さんは畳み掛ける。熊谷医師は丁寧な口調で答えていった。
「大腸がんは転移しやすいがんで、私たちが『もう治った』と思っていた患者さんでも、再発するケースがしばしば見られます(*2大腸がんの転移)。おっしゃるようにがんは一般に転移が見られた時点では、もう完治を望むことはできません。ただ、大腸がんは他の臓器がんに比べて再発した場合も、かなり延命される方が少なくありません」
| 肝機能 検査項目 | 正常値 | 数値の増減 | 内容の説明 |
|---|---|---|---|
| GOT (グルタミン酸オキサロ酢酸トランスアミナーゼ) | 5~40KU/dl | ↑肝障害、心筋梗塞 | 肝、筋細胞に存在する酵素。 GOT>GPT:心筋梗塞、アルコール性肝炎 |
| GPT (グルタミン酸ピルビン酸トランスアミナーゼ) | 5~30KU/dl | ↑肝障害 | 特に肝細胞に多い。肝細胞の変性・壊死に反応 GPT>GOT:ウィルス性肝炎 |
| γ-GTP | 50U以下 | ↑アルコール性肝障害、脂肪肝、慢性肝炎 | 蛋白分解酵素の1つ。アルコール性肝炎の早期発見に有効。 胆汁の通過障害でも上がる。 |
| LDH (乳酸脱水素酵素) | 50~400U | ↑急性肝炎、悪性貧血、急性心筋梗塞、がん | すべての組織に存在する酵素で、5種類の分画があり、それにより鑑別診断。 |
| LAP (ロイシンアミノペプチターゼ) | 30~70U | ↑胆汁の通過障害 | LAPも細胞に含まれている物質で胆汁に排泄される。 |
| TTT (チモール) | 5U以下 | ↑慢性肝炎以外に急性A型肝炎、高脂血症など | γ-グロブリンの上昇やアルブミンの低下で起きるこう質反応を調べる。TTTとZTTは共に肝臓の障害の程度を調べるが、肝臓が悪くないのに多少上回っている人が、特に女性に多い。 |
| ZTT (クンケル) | 4~12U | ↑慢性肝炎、肝硬変、慢性感染症 | |
| ALP (アルカリフォススファターゼ) | KK法3~12U 国際単位 80~240U | ↑胆汁の通過障害(黄疸)骨疾患、妊娠 | ALPは肝、腎、骨、胎盤に存在し、胆汁に排泄される。成長期の小児では高い。 |
| 総ビリルビン | 0.2~1.2mg/dl | ↑黄疸 | ビリルビンは胆汁に含まれている色素。赤血球中のヘモグロビンが壊れてできる。 赤血球が大量に壊れたり、胆汁の通過障害があると血管に入って黄疸になる。 |
| 直接ビリルビン | 0~1.0mg/dl | ↑胆石症、胆道がん、膵がん | |
| 間接ビリルビン | 0.2~0.9mg/dl | ↑急性肝炎、溶血性黄疸 | |
| ChE (コリンエステラーゼ) | 0.8~1.1 | ↑脂肪肝、肥満 ↓慢性肝炎、肝硬変 | ChEは肝臓で作られる酵素で、低下は肝障害が進んだことをあらわす。 |
肝転移は手術か、抗がん剤治療か
がん再発の告知にショックを受けた信子さんだったが、まもなく自分が置かれた状況を受け入れ始めた。熊谷医師に「これからどうしたらいいでしょうか?」と、治療法について聞いている。熊谷医師はCT画像を示しながら、こう話す。
「CTで検査すると転移は肝臓だけに限られているようです。切除可能な場合は、外科手術で取るのがベストですが(*3肝転移大腸がんの治療)、斉藤さんの場合は転移数が多いので、切除は難しいと思います。このようなケースでは、全身への抗がん剤療法がいいと思います。消化器内科の大田先生に連絡してありますので、このあと、消化器内科に寄ってください」
信子さんは、自分にはもう抗がん剤治療しかないと聞かされ、絶望的な気持ちになってしまった。いろいろな本を読んだが、そのいずれにも「消化器のがんは抗がん剤が効かない」と書かれていた。それに手術後補助抗がん剤療法を受けたとき、かなり激しい脱毛や吐き気が見られた。「自分は抗がん剤の副作用を受けやすいのでは」という心配もあった。
あれやこれやを考えると、いっそのことがん治療から逃げ出してしまいたいという気がしてくる。そんな不安や迷いをかかえたまま消化器内科の外来を訪れると、大腸内視鏡検査のとき以来会っていなかった大田医師が待っていた。
決してあきらめる必要はない
「先生、熊谷先生から新しい抗がん剤の治療を受けたほうがいいと聞いてきたのですが、本当に治るのですか? 副作用ばかりでつらい目にあうのなら、止めたいとも思うのですが」
信子さんは、いきなりこう切り出した。今日1日、突然何もかもが悪い流れになってしまい、ちょっと自暴自棄気味になっていた。大田医師は落ち着いた表情で説明を始めた。
「けっしてあきらめることはないと思います。確かに日本では、大腸がんについては、以前新しいお薬を臨床で使うための開発は遅れていました。ところが、法律が変わって治験が行いやすくなり、新しい抗がん剤治療を行えるようになってきたのです。現在はいろいろな可能性が出てきているのですから、ぜひ希望をもって治療に取り組んでください」
信子さんは、気持ちが鎮まってくるのを感じていた。そして、「そういえば、この先生の大腸内視鏡検査はとても上手だったわ。きっと患者のことを第一に考えてくれる先生に違いない」と考えていたのである。
次々に出てくる大腸がんに有効な抗がん剤
大田医師は、今後の治療方針について話し始める。

日進月歩で進む大腸がんの抗がん剤
「手術後には再発予防のために5-FUとロイコボリンによる抗がん剤治療を受けていただきましたが、最後に抗がん剤を投与してから1年以上たってからの再発ですので、一般的には、まだ5-FUが効く可能性があると考えられます。再発転移した大腸がんに対する抗がん剤は、以前は5-FUくらいしか有効とされるお薬がありませんでした。ところが、最近は、カンプト(もしくはトポテシン、一般名イリノテカン)や、まだ日本では使えませんがエロキサチン(一般名オキサリプラチン)という新しいお薬が登場して、進行大腸がんの治療成績が大きく向上しています(*4再発大腸がんの抗がん剤)。1990年代後半、欧米でカンプト(トポテシン)と5-FUを併用すると、大腸がんに対して高い抗がん力を示すことが証明されています。斉藤さんの場合は、5-FUとその作用を高めるロイコボリン、それにこのカンプト(トポテシン)を組み合わせた抗がん剤治療が、現在考えられる治療のベストです。残念ながら斉藤さんのがんは根治性がない状態で、吐き気、下痢などの副作用のある治療といわれていますが、治療がうまくいけば、またがんのことも忘れて生活できるようになると思います」
こうして信子さんの再発結腸がんに対するカンプト(トポテシン)+5-FU+ロイコボリンの抗がん剤治療が始まった。この治療は、4週間を1サイクルとして進められる。2サイクルが終わったころから、信子さんは食欲が回復し、体のだるさも少なくなっていった。
4サイクルの治療が終わった8月10日、大田医師は信子さんにCT画像を示しながら、うれしい報告をした。「肝臓の転移巣はすっかり小さくなっています。GOTは90まで下がり、肝機能は回復していますね。腫瘍マーカーCEAも88まで下がりました。よかったですね」
まるできつねにつままれたような顔をしている信子さん。なにしろ4カ月前にがん再発を聞かされたときは、もう自分の命はいくらもないと覚悟をしたくらいだ。抗がん剤の副作用も、想像していたほど厳しいものではなかったような気がするが、その結果がこんなに早く良い方向に出るとは考えていなかった。
「いずれ現在の治療は効かなくなるかもしれません。しかし、日本ではまもなくエロキサチン(*5)という抗がん剤が使えるようになる見通しがあります。このお薬も加えた治療法など、まだまだ可能性は広がっているのですから、これからもぜひ前向きに考えてください」
大田医師の話を聞きながら、新薬の恩恵を受けられた幸運を実感した信子さんは目に涙を浮かべていた。
同じカテゴリーの最新記事
- 切除可能な直腸がん試験結果に世界が注目も 日本の標準治療は「手術」で変わりなし
- ビタミンDの驚くべき効果がわかってきた 消化管がん手術後の再発・死亡リスクを大幅に減少
- 世界最大規模の画期的研究の一部解析結果が発表 大腸がんの術後補助療法の必要性をctDNAで判断する
- 初めての前向き試験で抗EGFR抗体薬の信頼性が確実に! 進化を続ける切除不能・進行再発大腸がんの薬物療法
- 遺伝子変異と左右どちら側にがんがあるかが、薬剤選択の鍵を握る! 大腸がん薬物療法最前線
- 化学放射線と全身化学療法を術前に行うTNT療法が話題 進行下部直腸がん 手術しないで完治の可能性も!
- 肛門温存の期待高まる最新手術 下部直腸がんTaTME(経肛門的直腸間膜切除術)とは
- 大腸のAI内視鏡画像診断が進化中! 大腸がん診断がより確実に
- 患者さんによりやさしいロボット手術も登場 新しくなった大腸がんの手術と薬物療法


