渡辺亨チームが医療サポートする:大腸がん編
便潜血反応検査を受ければ大腸がん死亡率が減少する
朴成和さんのお話
*1 便潜血反応検査
消化管で出血すると便の中に血液が混じりますが、少量なら目に見えません。わずかな赤血球成分であるヘモグロビンの化学反応で出血を見つけるのが便潜血反応検査です。この検査は、大腸がんの検診の代表的なものとなっていて、食事制限などの負担もなく、集団の中から、大腸がんの精密検査が必要な人を拾い上げるために最も有効な方法と考えられます。
ただし、大腸がんがあってもすべて便潜血反応で陽性になるわけではありません。陽性でも「大腸がんがある」とはいえず、陰性でも「大腸がんはない」といえないのです。便潜血陽性の早期がんは全早期がんの中の数パーセント以下で、進行がんでも3割程度です。
しかし、ヨーロッパでの大規模な研究による長期観察の報告により、経年での便潜血反応から、大腸がん死亡率が10~33パーセント減少することがわかっています。40歳を過ぎたら毎年この検診を受けることをお勧めします。
*2 大腸がんとは
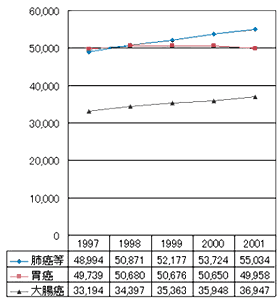
大腸は小腸のあとに続く消化管で、消化吸収された残りの腸内容物をため、水分を吸収しながら大便にする働きがあります。内部には多種、多量の細菌が住んでいて、大腸の働きを助けています。大腸は約2メートルの長さがあり、盲腸からはじまり、全体にクエスチョンマークのような形になっています。最初に上のほうに向かう部分が上行結腸、その次に横たわっている部分が横行結腸、次に下に向かう部分が下行結腸、さらにS字状に曲がっている部分がS状結腸、約15センチの真っすぐな部分が直腸で、最後の肛門括約筋のあるところが肛門管です。
大腸がんは消化器系のがんでは、胃がんに次いで多いがんです。もともと欧米人に多かったがんですが、日本人でも増加が目立つようになりました。現在毎年約8万人が罹患し、約3万5000人が死亡し、がん死亡者数では胃がん、肺がん、肝臓がんに次いで4番目に多く、2015年ごろには胃がんを抜くと予測されています。
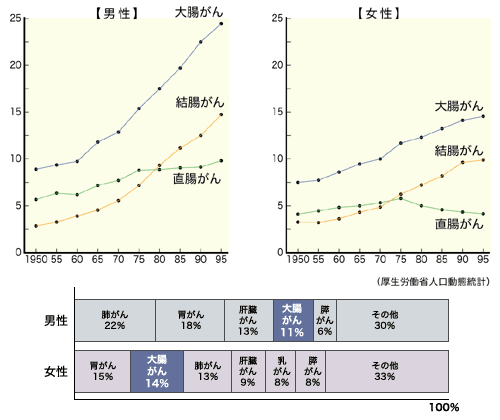
大腸がんにかかる年齢は60歳代がピークで70歳代、50歳代と続きますが、欧米と比べ、10歳ほど若い傾向があります。5~10パーセントの頻度で30歳代、40歳代の若年者に発生し、若年者大腸がんは家族や血縁者の中に多発する傾向があるとも言われています。
大腸がんは大腸粘膜のあるところではどこからでもがんができますが、約7割は、S状結腸と直腸に発生しています。
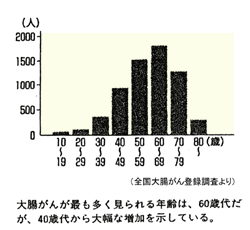
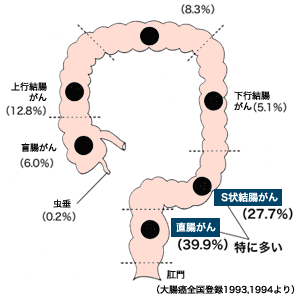
*3 大腸がんの自覚症状
大腸がんは、初期にはほとんど症状がなく、症状が現れてもがんに特徴的なものではないので、良性の疾患と見分けがつかないのが普通です。その症状は、血便、便が細くなる(便線細少)、残便感、腹痛、下痢と便秘の繰り返しなど排便に関するものが多く、貧血を起こすこともあります。自覚症状は、大腸のどこに、どの程度のがんができるかによって多少違いますが、S状結腸や直腸など出口に近いほど、便通異常が増えてきます。
大腸がんが進行すると、お腹が張っておならも出ないような腹痛に至ることもあります。さらに腸閉塞症状のために嘔吐などの症状が現れたり、肺や肝臓の腫瘤として大腸がんからの転移のほうが先に発見されることもあります。
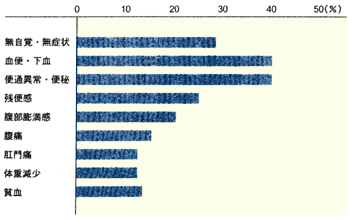
*4 大腸がんのリスクファクター
大腸がんの発生には、遺伝的因子よりも環境的因子の比重が大きいと考えられています。日本では大腸がんが1970年代から急増していますが、食生活の急激な欧米化が原因ではないかと考えられます。アメリカなどへ移住した日本人では、白人なみの頻度にまで増えることが観察されている一方、菜食主義者や、赤身肉の摂取量の少ない国や地域では発生率が低い傾向にあることがわかっているのです。
大腸がんは、赤身肉の摂取量の多い人にリスクが高いことが認められています。これは、動物性脂肪による細胞分裂促進作用や、動物性タンパクの加熱により生成される発がん物質などによるものと推定されています。肥満やアルコールの摂取も、大腸がんのリスクを上げることが示されています。一方、野菜類の摂取が、定期的な運動とともに、大腸がんの発生を抑制することが認められています。その他にビタミンD、カルシウム、葉酸などの摂取が大腸がんのリスクを下げるという報告もあります。
一方、古くから大腸がんの予防に有用だと考えられていた食物繊維については、最近の無作為化比較試験や大規模コホート研究では、「食物繊維を多く摂っていたグループにおいて、大腸がんのリスクが低かった」という知見は得られませんでした。
また、5パーセント前後の大腸がんは遺伝的素因で発症するとされており、血縁者の中に大腸がんにかかった人がいることは、大腸がんにかかりやすい危険因子となります。さらに、大腸ポリープになったことがある、長い間潰瘍性大腸炎にかかっている、治りにくい痔瘻があることなども危険因子であることが指摘されています。
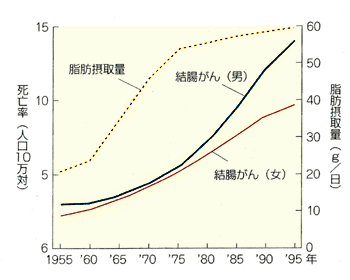
*5 大腸内視鏡検査
先端にカメラのついたファイバースコープを肛門から挿入して大腸の中を観察するのが大腸内視鏡検査です。盲腸まで全大腸をくまなく観察できる長い内視鏡のほか、S状結腸までを観察する短い内視鏡もあります。内視鏡検査は、微妙な色調の変化や、極めて小さなポリープまで発見することができ、専門医なら大腸内に進行がんがある場合、この方法によりほぼ100パーセント見つけることができます。検査を受けている人が直接モニターを見ながら医師の説明を聞くことができるのも特徴です。さらに、大腸内視鏡検査ではポリープの切除(内視鏡的ポリペクトミー)も可能です。大腸がんの疑いがあれば、直接組織を採り(生検)、病理検査によってがんであることが確定できます。
*6 早期結腸がんと進行結腸がん
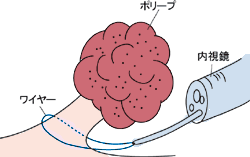
大腸の壁は内腔側から、粘膜、粘膜下層、筋層、漿膜下層、漿膜(外膜)という5つの層に分かれていますが、このうち、がんが粘膜内もしくは粘膜下層にとどまっているものを「早期結腸がん」、筋層以下にまで進んでいるものを「進行結腸がん」といいます。早期結腸がんのうちがんが粘膜内に留まったものをmがんといい、リンパ節転移は0パーセントで、大きくなければ肛門から内視鏡を入れて切除する内視鏡的ポリペクトミーで完治します。粘膜下層まで入っているものをsmがんといいリンパ節転移は10パーセント、固有筋層では25パーセント、漿膜を破ってしまうと40パーセントの転移があると考えられます。外科的な手術で切除可能な大腸がんは進行がんでも70~80パーセントは完治します。
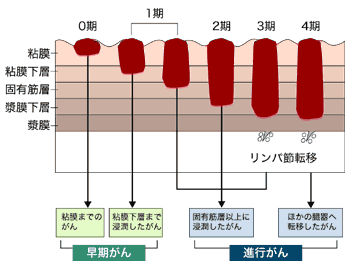
*7 大腸がんの広がり診断
大腸がんと診断がつけば、CT、MRI、超音波検査などの画像検査により原発巣での進みぐあいだけでなく、リンパ節転移や肝臓や肺、腹膜への転移の有無が調べられます。どの程度がんが拡がっているかによって治療法も異なります。ただし、リンパ節転移の程度などは、手術してみないと十分把握できないことがあります。
画像検査では最近、PET検査が注目されています。腫瘍マーカーの推移などから転移・再発が疑われますが、CT、MRIでも判断できない場合でも、PET検査で発見される場合があります。
同じカテゴリーの最新記事
- 切除可能な直腸がん試験結果に世界が注目も 日本の標準治療は「手術」で変わりなし
- ビタミンDの驚くべき効果がわかってきた 消化管がん手術後の再発・死亡リスクを大幅に減少
- 世界最大規模の画期的研究の一部解析結果が発表 大腸がんの術後補助療法の必要性をctDNAで判断する
- 初めての前向き試験で抗EGFR抗体薬の信頼性が確実に! 進化を続ける切除不能・進行再発大腸がんの薬物療法
- 遺伝子変異と左右どちら側にがんがあるかが、薬剤選択の鍵を握る! 大腸がん薬物療法最前線
- 化学放射線と全身化学療法を術前に行うTNT療法が話題 進行下部直腸がん 手術しないで完治の可能性も!
- 肛門温存の期待高まる最新手術 下部直腸がんTaTME(経肛門的直腸間膜切除術)とは
- 大腸のAI内視鏡画像診断が進化中! 大腸がん診断がより確実に
- 患者さんによりやさしいロボット手術も登場 新しくなった大腸がんの手術と薬物療法


