渡辺亨チームが医療サポートする:大腸がん編
大腸がんの治療に腹腔鏡手術を選択する根拠
高度な技術が必要な腹腔鏡手術
朴成和さんのお話
*1 結腸がんの治療
結腸がんは早い時期に発見すれば、内視鏡的切除や手術により完全に治すことができます。少し進行したがんでも手術可能な時期であれば、肝臓へ転移しても、手術により治癒が望めます。
結腸がんの手術は、結腸にあるがんの部分とともに上下へ10センチほどずつ離して腸管を切除します。
同時に周囲のリンパ節の切除(リンパ節郭清と呼ぶ)を行います。切除する結腸が長くても、術後の消化・吸収等の機能障害はほとんど起こりません。
しかし、発見が遅れれば、肺、肝臓、リンパ節や腹膜などに転移が起こります。こうした場合には、化学療法(抗がん剤治療)や放射線治療が行われます。
*2 開腹手術と腹腔鏡手術
結腸がんに対する腹腔鏡手術は1990年代前半から国内でも行われるようになり、腹腔鏡手術を施行する施設は徐々に増えてきています。開腹手術ではお腹を20センチくらいは切らなければなりませんが、腹腔鏡手術では普通は4カ所の穴を開けるだけですみます。ただし、がんを摘出するために真ん中に1カ所、4~6センチくらいの切開が必要です。
腹腔鏡手術は、まず炭酸ガスで腹部を膨らませて、1つの穴から内部を映し出す腹腔鏡というカメラを入れ、モニターを見ながら、別の穴から差し入れた手術器具で腸を切除し取り出すという手術を行います。開腹手術は2~3時間前後で行うことができますが、腹腔鏡手術はこれよりやや長めです。が、傷口が小さいので、術後の疼痛も少なく、術後7日前後で退院できます。入院費用も少なくてすみます。
また、大腸がんの腹腔鏡手術は、作業している部分がモニターに大きく映し出されるので細部まで把握でき、リンパ節を取り除くような細かい作業がやりやすいという面があります。一方、画面を見て行うので距離感がつかみにくく、触感もないというのが欠点で、狭い腹腔内の作業で臓器を傷つけたり、誤ってがんを切り裂き、ばらまく危険性もあります。ですから、腹腔鏡手術は、開腹手術と比較してある程度経験を積んだ専門医が行う必要があるといえるでしょう。
進行がんでも、一部のものは術後2~3年までは、腹腔鏡手術の生存率は開腹手術と同等と考えられています。現在、国内では進行がんに対する腹腔鏡手術と開腹手術のどちらがいいかという比較試験が行われています。
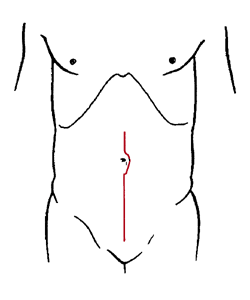
縦に20cmぐらいメスを入れる必要がある
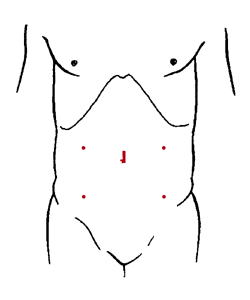
真ん中に小さな切開のほか、4カ所穴を開けるだけ
医療の標準化を進めるクリニカルパス
朴成和さんのお話
*3 クリニカルパス
クリニカルパスとは、疾患ごとに治療・検査やケアなどをタテ軸に、時間軸(日付)をヨコ軸に取って作った、診療スケジュール表のことです。このシステムは医療を同じ質、同じ手順で提供できるように考えられたもので、アメリカで始まり、日本には1990年代半ばに導入されました。現在では主に入院時に患者さんに手渡されるなど広く普及しています。
以前は同じ病院の中でも医師の経験や好みによって医療の内容が違うということが珍しくありませんでしたが、クリニカルパスを導入することによって標準化が可能になりました。疾患ごとに検査、治療、食事などを、どんなスケジュールで行うかをはっきり示されるので、患者さんは、その日どんな検査があって、いつ手術を受けて、いつ頃には退院できるかということがわかります。また、医療スタッフにとっても、どのような医療行為をいつ、誰が行うのか、患者さんへの説明はどのようにするか、ということが明確になるので、チームとしての医療サービスをスムーズに提供できるようになります。
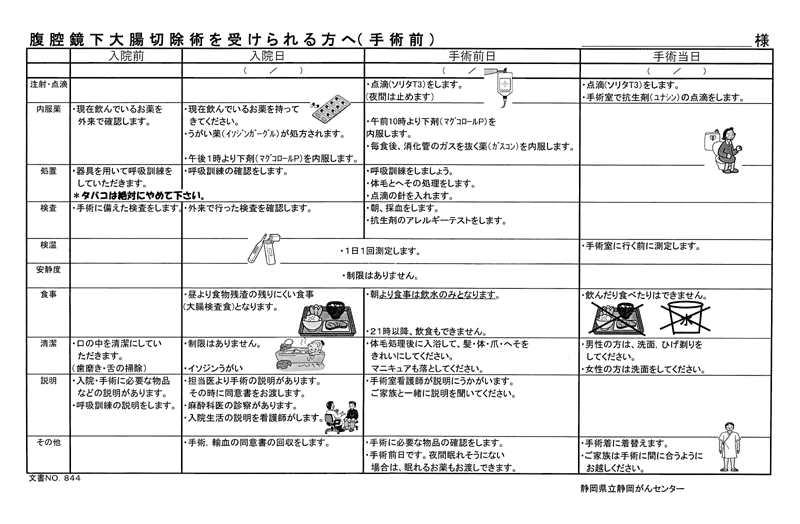
*4 所属リンパ節の郭清
結腸がんの手術では、早期がんであっても病変が粘膜筋板を越えて拡がっていれば、リンパ節転移の危険性があり、がんが深くなればなるほどリンパ節転移の率が高くなるため郭清と呼ばれる外科療法が必要となります。結腸がんの予後は、明らかに腫瘍の腸壁浸達度およびリンパ節転移の有無に関連しています。また諸研究から、リンパ節転移の数が予後に影響することがわかっています。1~3個のリンパ節転移にとどまる患者は、4個以上のリンパ節転移患者より、生存率は明らかに良好です。
肝臓、肺、腹膜などにも転移しやすい
朴成和さんのお話
*5 術後の検査
結腸がんは手術を受けた後に再発することもあります。術後は定期的に(3~6カ月の間隔)再発チェックのための検査を受ける必要があります。切除した部位に局所再発が起こることもありますが、肝臓、肺、腹膜などの臓器にも転移しやすいので、胸部X線検査、肝臓のCT、超音波検査、腫瘍マーカーCEAとCA19-9などの検査を行います。結腸がんは他のがんとは異なり、再発巣の状況によっては切除により完治も期待できます。
再発の8割以上は術後3年以内に発見されます。3年以降は半年に1度の検査で十分です。成長の遅い大腸がんもあるので5年間の追跡は必要です。5年以上再発しないことが完治の目安です。
*6 結腸がんのステージ分類
結腸がんには、Dukes(デュークス)分類とステージ分類が使われます。がんの大きさではなく、大腸の壁の中にがんがどの程度深く入っているか、及びリンパ節転移、遠隔転移の有無によって進行度が規定されています。
2つの分類にはわずかな違いがあるのみで、デュークスAは0、1期に、デュークスBは2期に、デュークスCは3期に、デュークスDは4期に相当するものと考えて差しつかえありません。デュークス分類は、国際的に広く用いられているものです。
| デュークス 分類 | デュークス A(95%) | がんが大腸壁内にとどまるもの |
|---|---|---|
| デュークス B(80%) | がんが大腸壁を貫くがリンパ節転移のないもの | |
| デュークス C(70%) | リンパ節転移のあるもの | |
| デュークス D(25%) | 腹膜、肝、肺などへの遠隔転移のあるもの |
| ステージ 分類 | 0期 | がんが粘膜にとどまるもの |
|---|---|---|
| 1期 | がんが大腸壁にとどまるもの | |
| 2期 | がんが大腸壁を越えているが、隣接臓器におよんでいないもの | |
| 3期 | がんが隣接臓器に浸潤しているか、リンパ節転移のあるもの | |
| 4期 | 腹膜、肝、肺などへの遠隔転移のあるもの |
*7 結腸がんの予後不良因子(再発リスク)
結腸がんの組織型には正常細胞に近い高分化がん、より悪性度の高い中分化がん、もっと悪性の低分化がんがあり、特殊なものとして未分化がんもあります。この順序で悪性度が増し、治る確率も低くなります。治りやすいほうに分類される高分化がんと中分化がんで全体の80パーセントを占めますが、食生活の欧米化の影響か、近年高分化がんが減って欧米に多い中分化がんが増えています。転移がある場合でも、高分化がんと中分化がんのほうが低分化がんより治りやすいことがわかっています。
*8 術後補助化学療法
結腸がんの手術後は再発予防の目的で、抗がん剤による補助化学療法が行われる場合があります。再発予防目的の抗がん剤の効果を確かめる研究が多数行われていて、欧米には有用性を示すデータが数々ありますが、現在の標準的な術後補助化学療法は、5-FUとロイコボリンの併用療法です。しかし、わが国には十分な効果が確認された研究はまだなく、標準的な術後補助化学療法はまだ定まっていません。結腸がんの術後には、現時点では5-FUとロイコボリンの併用療法を6カ月間行うことが妥当と考えられます。
同じカテゴリーの最新記事
- 切除可能な直腸がん試験結果に世界が注目も 日本の標準治療は「手術」で変わりなし
- ビタミンDの驚くべき効果がわかってきた 消化管がん手術後の再発・死亡リスクを大幅に減少
- 世界最大規模の画期的研究の一部解析結果が発表 大腸がんの術後補助療法の必要性をctDNAで判断する
- 初めての前向き試験で抗EGFR抗体薬の信頼性が確実に! 進化を続ける切除不能・進行再発大腸がんの薬物療法
- 遺伝子変異と左右どちら側にがんがあるかが、薬剤選択の鍵を握る! 大腸がん薬物療法最前線
- 化学放射線と全身化学療法を術前に行うTNT療法が話題 進行下部直腸がん 手術しないで完治の可能性も!
- 肛門温存の期待高まる最新手術 下部直腸がんTaTME(経肛門的直腸間膜切除術)とは
- 大腸のAI内視鏡画像診断が進化中! 大腸がん診断がより確実に
- 患者さんによりやさしいロボット手術も登場 新しくなった大腸がんの手術と薬物療法


