手術後の癒着防止材や腸閉塞を防ぐ薬が登場、患者さん自身の食生活の改善も肝心 消化器がん手術後の腸閉塞は、この対策で減らせる
注目される大建中湯の効果
術後の早期離床も腸閉塞の予防に効果があると船橋さんは言います。
「患者さんの中には、すぐにベッドから起き上がるのが怖いとか、痛いんじゃないかと躊躇する人もいます。しかし、長くベッドに寝たままでいると、むしろ腸管が異常な位置で癒着をきたすおそれがあります。現在では、術後の創痛は鎮痛剤によって十分除去ができるので、腸閉塞予防の観点からも早期離床を患者さんには勧めています」
薬による予防法としては、スムーズな排便を促すために緩下剤として酸化マグネシウムを処方することもありますが、最近注目されているのが漢方薬の「大建中湯」です。
山椒、人参、乾姜、膠飴の生薬で構成される漢方薬で、腸の蠕動が過度に亢進している場合にはそれを抑制し、蠕動が不活発なときには刺激を与えるというように、腸管運動のバランスをよくすることによって腸閉塞を予防・治療する薬です。
「腸管の蠕動が弱く、定期的な排便が見られない方、食後におなかが重く便秘傾向にある方には大建中湯を処方しています。大きい手術の後、長期間にわたる麻痺性の腸閉塞が見られた方にも予防的に服用していただくこともあります。このほか、大建中湯の薬理作用として腸管の血流増加作用、抗炎症作用などが認められており、癒着性腸閉塞の保存的治療や予防薬として大変興味深い薬剤です。大腸がんの開腹手術症例で、術後早期の大建中湯の投与によって腸閉塞の発症を抑え、入院期間も短縮できたとする報告もあります。現在、大腸がん術後の消化管機能異常に対する大建中湯の効果について臨床試験が進行中であり、その結果に期待したいと思っています」
異常を感じたら速やかに受診を
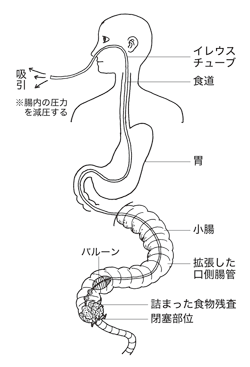
腸閉塞になったときの対応としては、速やかに受診することが大切。
「腸閉塞では、腸は蠕動によって細くなったところでも無理やり消化物を通そうとするので、過度の蠕動に伴って間欠的な痛みが現れます。おなか全体が張ってきたとか、苦しい、気持ち悪い、吐き気がするといった症状も重要なサインです。このような症状が出る前に、定期的な排便が見られなくなったとか、すぐにおなかが張る、食欲が落ちた、食事をするとすぐにおなかが痛くなるといった兆候が認められたときは、腸閉塞の可能性を考えて、医師の診察を受けることを勧めます」
腸閉塞は病気や手術の種類、手術の範囲によっても異なりますが、胃の手術後は注意が必要。とくに、胃を全摘すると、小腸を直接、食道につなげて食物のルートを造るため、口に入れた食物が直接、小腸内に入り、腸閉塞になりやすいのです。
血流障害が疑われない腸閉塞では、手術を行わない保存的治療が原則。通常はイレウスチューブ(あるいはロングチューブともいう)を鼻から入れて、閉塞部位の近くまで進めていき、閉塞部位の口側に溜まった腸の内容物を吸引すれば、腸閉塞がおさまることが多いようです。
「何らかの原因(多くは食物残渣)で腸に通過障害が起きると、腸管内を絶えず流れている消化液が狭くなった部位の口側に徐々に貯留し、これとともに狭窄した腸管に浮腫(むくみ)をきたします。この浮腫によって腸管の狭窄はさらに強くなり、腸閉塞は徐々に進行していきます。また、腸管内に溜まった消化液内では腸内細菌の繁殖が進み、やがて、異常に増殖した腸内細菌は腸管壁を通じて徐々に血液の中に入り、敗血症の状態へと進んでいきます。イレウスチューブは、口側に溜まった消化液を体外に吸引することで、腸管の浮腫を軽減し、腸閉塞の病態を改善に導く重要な役目を果たします」
しかし、チューブを入れて保存的に治療しても症状や所見がよくならない、という場合は手術になります。また、イレウスチューブによる治療中に、血流障害を疑わせる症状や所見が認められた場合には、保存的治療は中止して、すぐ手術が必要となります。手術では、血流障害を起こした箇所が壊死に陥っていれば、腸管の切除が必要となりますが、壊死を起こしていなければ、腸管の血流の回復を確認したうえで、癒着している部分だけを剥離して手術を終了します。
「ただし、せっかく腸閉塞を治す手術をしても、その手術が新たな癒着を生み、その癒着が原因で腸閉塞が再び起こる可能性があるため、腸閉塞の治療は難しいといえるでしょう。したがって、腸閉塞にならないように予防に努め、腸閉塞の場合にはできるだけ早期に保存的治療で治すのが望ましいですね」
腸管の浮腫改善を目的に、挿入したイレウスチューブから大建中湯を注入する方法も行われています。
腸閉塞を予防するために食事に気をつけよう
- 〇水を吸収して体内で膨らむ
- キノコ類、昆布
- 〇ガスが発生しやすくなる
- 炭酸飲料、豆類、イモ類、カニ、エビ、大根
- 〇便を固くする
- ご飯、餅、トウモロコシ
- 〇腸管を詰まりやすくする
- トマト、ワカメ、キャベツ、玄米、貝類
※消化器がんの術後の人は、上記の食品をとり過ぎないように注意する
術後の腸閉塞を起こさないためには、患者さん自身が生活習慣を見直すことも大切です。
「いちばん気をつけてほしいのは食事です。術後早期に起こる腸閉塞の場合、癒着が形成されやすくなってくる術後15~20日ころが危険といえるでしょう。そのころは食事も普通にするようになっているでしょうが、大食いや早食い、あるいは消化の悪いもの、刺激の強いもの、キノコ類や昆布のような水を吸って膨張するものを大量に食べたりするのはよくありません」
働き盛りの方では、日々の仕事の忙しさに追われて、つい短時間に大食いするということがあるので、とくに注意が必要です。逆に、お年寄りだと、歯が悪いために無意識に食べ物をよく噛まずに飲み込んでしまうことが多いので、東邦大学医療センター大森病院の外来では、患者さんには調理方法を工夫して食事を摂取するように指導しています。
「また、炭酸飲料、豆やイモ類、カニやエビ、大根などはガスを発生しやすくします。米飯、餅、トウモロコシなどは便を固くし、トマト、ワカメ、キャベツ、玄米、貝類などは腸管を詰まりやすくするため、摂取する際には注意が必要でしょう」
船橋さんは、このようにアドバイスしてくれました。
同じカテゴリーの最新記事
- 切除可能な直腸がん試験結果に世界が注目も 日本の標準治療は「手術」で変わりなし
- ビタミンDの驚くべき効果がわかってきた 消化管がん手術後の再発・死亡リスクを大幅に減少
- 世界最大規模の画期的研究の一部解析結果が発表 大腸がんの術後補助療法の必要性をctDNAで判断する
- 初めての前向き試験で抗EGFR抗体薬の信頼性が確実に! 進化を続ける切除不能・進行再発大腸がんの薬物療法
- 遺伝子変異と左右どちら側にがんがあるかが、薬剤選択の鍵を握る! 大腸がん薬物療法最前線
- 化学放射線と全身化学療法を術前に行うTNT療法が話題 進行下部直腸がん 手術しないで完治の可能性も!
- 肛門温存の期待高まる最新手術 下部直腸がんTaTME(経肛門的直腸間膜切除術)とは
- 大腸のAI内視鏡画像診断が進化中! 大腸がん診断がより確実に
- 患者さんによりやさしいロボット手術も登場 新しくなった大腸がんの手術と薬物療法


