正しい知識を持ち、納得して治療法を選択するために 切らなきゃいけないわけじゃない。食道がんの化学放射線療法
食道をとりたくないから
広大病院では、紹介状をもって「化学放射線療法」を受けようと放射線治療科を訪れた患者さんにも、必ず外科医の意見も聞くよう話しているという。
男性患者のAさん(69)は、胸部食道の中部を塞ぐような大きな隆起性の食道がんで、手術による切除も可能と考えられた。病期は2B期。権丈さんに言われて外科医の意見も聞いたが、「食道をとりたくない」と、自らが化学放射線療法を選択した。
放射線は1日2グレイずつ、週に5日、連続して照射した。1回の照射時間そのものはわずか3分程度なので、あっという間に毎日の放射線治療は終わる。計60グレイに達するまで6週間ほどかけて行った。
食道がんの放射線治療では飲み込み時の違和感や疼痛の出る場合があるが、Aさんの副作用は強くなく、照射皮膚に日焼けに似た症状が出る程度だった。
一方、抗がん剤は前述のランダと5-FUの2剤併用療法を行った。「フルドーズ(大用量)」といわれる処方で、初日だけ2剤を用いて、その後の4日間は5-FU単独で投与。その間、放射線は毎日2グレイを当て続け、5週目になって、もう1度同じ抗がん剤投与を行った。するとAさんの食道がんは、CR(肉眼的にはがんが消えた状態)に。2年後の現在も再発せず、元気に生活している。
「Aさんと同じ病期でも、鎖骨の上や裏側のリンパ節が転移によって大きくなったような場合は手術適応にならないことが多く、その場合にも『化学放射線療法』が行われます」
広大病院では、2期と3期の「化学放射線療法」において、CRは66パーセント、3年生存率は40パーセントになっている。
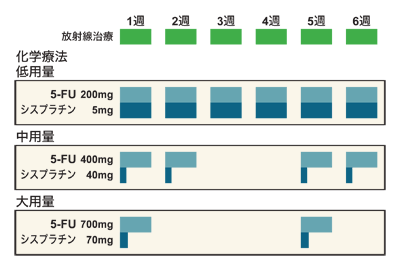
新剤導入が遅れている現状
国内の食道がん治療で一般的に使われている抗がん剤は、今のところ4種類しかない。広大病院では化学放射線療法の際には、ランダと5-FU、ネダプラチンと5-FUという3種類の抗がん剤で2パターンの治療を行っている。タキソテール(一般名ドセタキセル)を含む治療は、再発時に用いるセカンドラインという位置づけだ。
このほか、安全性と効果をみる第2相臨床試験に入っている薬剤が2種類ある。タキソール(一般名パクリタキセル)と5-FU系のTS-1(一般名テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム)である。しかし承認されるには、まだしばらく時間がかかりそうだ。
「今のところ、食道がんには分子標的薬もなく、肺がんや乳がん、大腸がんに比べて、新剤導入が遅れているのが現状です」
サルベージ手術の高リスク
食道がんについては、再発したときや化学放射線療法でCRに至らなかったときのサルベージ(救済)手術についても考えておくべきであろう。
国立がん研究センター中央病院の「化学放射線療法」101例のうち、再発や残存でサルベージ手術を行った症例は22例。そのうち14例成功とされている。
「2~3期で化学放射線療法を行ったときには、サルベージ治療がある程度避けられず、もし5年生存率が手術に匹敵するとしても、再発時に手術を受けて救済された方を含めてのことになるでしょう」と権丈さん。
国立がん研究センター中央病院の通常の手術における手術関連死は2パーセント未満だが、サルベージ手術まで含めると13パーセントに急増するとのことだ。
「放射線治療を終えてから時間が経つと組織が固くなって手術が難しくなり、合併症も増えてきます。また、照射線量や照射体積によってもサルベージ手術の難しさは変わります。そのため手術ができる人に化学放射線療法を行う場合には、サルベージ治療の可能性を考えて放射線量を50.4グレイに落とし、がんが残ればすぐに手術に入るという判断をしているところもあります」 サルベージ手術のリスクは高いわけだが、手術不能な3期(T4=周囲の臓器に腫瘍が食いこんだ状態)と4期では、放射線治療ガイドラインでも「化学放射線療法」が第1選択だ。
「4期は厳しいですが、5年生存率が10パーセントあり、決してあきらめてはいません」
治療前に頭頸部チェックを
「食道がんの治療に入る前の意外な盲点が、頭頸部のチェックです」と権丈さんは指摘する。
食道がんを治療する前に、胃がんを併発していないかどうかは内視鏡検査で確認されるが、口の中から食道までの間の咽頭部も食道と同じ食べ物の通り道のため、別のがんが併発している可能性が高いのだ。内視鏡検査だけではここまで調べきれないことがあるのだという。
「私たちの病院では、食道がん治療を始める前に必ず耳鼻咽喉科の診察も受けてもらいます」
また、化学放射線療法は治療期間が1カ月以上になるので、その間、いかに脱落者を出さないかも重要になるという。
「化学療法中の1週間は入院ですが、放射線治療だけの期間は通院になります。栄養状態の確認のため毎日の体重チェックはもちろん、食道がんの患者さんにはお酒や煙草が好きな人が多いため、禁酒禁煙の徹底が重要になってきます」
治療途中の飲酒は粘膜炎が悪化するため厳禁。煙草も、肺炎や粘膜炎リスクが高まるので絶対禁止だ。
「化学放射線療法で食道がんを治して、長生きされる方も多くおられます。治療後、食道がんの再発や転移に注意し続けることはもちろん大事ですが、食道がん体験者には胃がんや頭頸部がんなどが出てしまう割合も普通の人よりはるかに高いのです。2つ目のがんにも目を配りながら、その後の有意義な人生を送ってほしいと思っています」
同じカテゴリーの最新記事
- グラス1杯のビールで赤くなる人はとくに注意を! アルコールはがんの強力なリスクファクター
- ビタミンDの驚くべき効果がわかってきた 消化管がん手術後の再発・死亡リスクを大幅に減少
- 食道がんの薬物療法が大きく動いた! 『食道癌診療ガイドライン2022』の注目ポイント
- 放置せずに検査し、適切な治療を! 食道腺がんの要因になる逆流性食道炎
- 免疫チェックポイント阻害薬が薬物療法に変革をもたらした! 食道がん、キイトルーダが1次治療に加わる見込み
- 5年生存率を約2倍に改善! 食道がんの術後ペプチドワクチン療法
- 若手術者の養成が重要課題に 保険適用になった食道がんに対するダヴィンチ手術の現状
- ステージⅡとⅢの食道がんに放射線減量の化学放射線治療 食道がん治療に切らずに食道温存への期待
- 進行・再発食道がんに対する化学治療の最新知見 免疫チェックポイント阻害薬登場により前途が拓けてきた食道がんの化学療法


