「術後」よりも「術前」のほうが、5年生存率が良いという臨床試験結果も 転移を抑え、再発を防ぐ!? 食道がんの術前化学療法
抗がん剤が効けば5年生存率は約70パーセント
術前化学療法の効果については、当センターと大阪大学、近畿大学の3施設でまとめたデータがあります。
胸部食道扁平上皮がんでリンパ節転移のあった105人の5年生存率は、約45パーセントでした(表3)。
(リンパ節転移のあった胸部食道扁平上皮がん105例)]
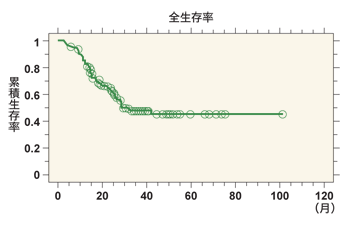
患者さんの中には、抗がん剤治療の効果が大きい人とそれほどではない人とがいます。このデータでは、CT検査で食道がんの断面積が半分以下になる「効いた人」は約40パーセントでした。
一方、当センターで術前化学療法を行った77人のデータによれば、「効いた人」の5年生存率は70パーセントにも達しています。「効いた人」の場合、手術で摘出したリンパ節の転移個数を調べると、平均2.2個でした。一方、「効かなかった人」はリンパ節転移が平均12個あり、5年生存率は30パーセントを切っています(表4)。
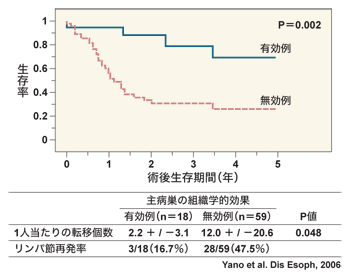
術前化学療法では、それほど重篤な副作用は出ていません。高度な白血球の減少のあった方、吐き気や消化器症状のあった方がともに約30パーセントです。腎障害はほとんどありません。
といっても、かなり毒性の強い抗がん剤治療を行いますので、その後に手術をすると、手術の合併症が増えないかと心配される方もおられるでしょう。
しかし先の105人は、全員が手術を受け、手術関連死はゼロでした。肺炎や縫合不全の割合は、抗がん剤治療なしで手術した人の場合と変わりませんでした。この結果から、術前化学療法は手術後の経過に悪影響を及ぼさないと考えています。
また、抗がん剤が効かなかった場合、手術をするまでの2カ月間にがんが進むのではないかと危惧される方もおられるでしょう。確かに、そのリスクはあります。抗がん剤が効かなくて、がんが進む頻度は約10パーセントあり、そのうち数パーセントの人は、肝転移が出てくるなど手術ができなくなります。
では、その人が抗がん剤治療をしないで手術していたら、肝転移していなかったかと言うと、必ずしもそうとは言えません。肝転移は2カ月前からすでにあり、2カ月間にがんが見える大きさになったというだけのことかもしれないからです。
PETが可能にした「効果判定」
抗がん剤治療がどれぐらい効いたのか、治療後の「効果判定」は非常に重要です。判定できなければ、再発の可能性の高い人が、痛い思いをして手術を受けることになります。
ところが、従来の検査では、細胞レベルでの抗がん剤の効果判定は、非常に難しいのです。CTや内視鏡では、がんがどれだけ縮小したかをチェックすることしかできません。CTで小さくなったように見えても、がんがしっかり残っている場合もあれば、あんまり小さくなっていないのに、がんはもうなくなり、結合組織に置き換わていることもあります。
抗がん剤が「効いた人」は、リンパ節転移の減った人ですが、これは手術でリンパ節を取ってみて、初めてわかることです。CTでは、微小なリンパ節転移は診断できません。
そこで今、注目されているのがPETスキャンです。PETのほうが従来の検査よりも、がん細胞の量を評価するのには適しています。PETでは、患者さんに注射した薬剤ががん組織に集まり、そこが光ります。がん細胞が他の組織に置き換わっていれば、光りません。
大阪大学の研究では、抗がん剤治療後のPET検査で原発巣が消えた人と残った人の間で、手術後の再発率に3割近い差がありました。
現在、当センターでは、抗がん剤治療の前後に、PETを必ず撮り、治療の効果を判断しています。そのデータをもとに、患者さんと手術をするかどうかを相談しています。PETは、放射線治療後の効果判定にも有効です。
課題は「効果予測法」の開発
今、私たちが抱えている最大の問題は、抗がん剤治療や放射線治療を行う前に効果予測ができないか、ということです。これがわかれば、抗がん剤治療を行うかどうかの、正しい選択ができます。
術前化学療法が「効いた人」では再発率が下がりますが、「効かなかった人」の再発率は、抗がん剤治療をしてもあまり変わりません。つまりムダな抗がん剤治療を受けることになります。
あらかじめ「効く人」と「効かない人」がわかれば、治療前にその効果を知り、1人ひとりの患者さんに合った治療ができるのではないか、と考えています。
この研究を私は大阪大学で続けてきました。食道がんでは、がん抑制遺伝子「p53」が突然変異を起こしている割合がかなりあります。この遺伝子に変異のあった人は、抗がん剤や放射線が効きにくく、がんが完全消失した人は1人もいませんでした。逆に、変異のない人のうち3割は、がんが完全消失するほどの効果(グレード3)が出ました。
ですから、あらかじめ内視鏡でがんの組織を一部採って遺伝子診断をし、p53の変異があるかどうかを調べれば、術前化学療法の効果がある程度予想できます。p53以外にも、同様のデータが集まってくれば、もう少し正確な予測ができるのではないかと、期待しています。
同じカテゴリーの最新記事
- グラス1杯のビールで赤くなる人はとくに注意を! アルコールはがんの強力なリスクファクター
- ビタミンDの驚くべき効果がわかってきた 消化管がん手術後の再発・死亡リスクを大幅に減少
- 食道がんの薬物療法が大きく動いた! 『食道癌診療ガイドライン2022』の注目ポイント
- 放置せずに検査し、適切な治療を! 食道腺がんの要因になる逆流性食道炎
- 免疫チェックポイント阻害薬が薬物療法に変革をもたらした! 食道がん、キイトルーダが1次治療に加わる見込み
- 5年生存率を約2倍に改善! 食道がんの術後ペプチドワクチン療法
- 若手術者の養成が重要課題に 保険適用になった食道がんに対するダヴィンチ手術の現状
- ステージⅡとⅢの食道がんに放射線減量の化学放射線治療 食道がん治療に切らずに食道温存への期待
- 進行・再発食道がんに対する化学治療の最新知見 免疫チェックポイント阻害薬登場により前途が拓けてきた食道がんの化学療法


